| ハーブ(香草、薬草)とは、主に温帯地方に産し、花や葉、茎、根などの部分を使用(利用)して、人々の暮らしに役立つ、香りのある植物をいいます。 古き良き物への郷愁と、本物への良さを見直そうとする運動がヒッピーやアーティストの間で広がり、日本でも自然食運動等から、健康食品や薫香、ハーブ(香草、薬草)、ポプリ等が再認識され始めました。 ハーブ(香草、薬草)の歴史は古く、古代ローマ、ギリシャの頃から、医薬品、香水、化粧品、食品などに使用(利用)され、殺菌や防腐の大きな役割を果たしていました。 |
|
| ハーブ(香草、薬草)の定義 | |
| 一般に、ラベンダー(ラヴェンダー)やローズマリー(マンネンロウ、まんねんろう)などのハーブ(香草、薬草)は、「香りのする植物=香草」、「薬効をもった植物=薬草」と認識されていると思いますが、少し詳しくハーブ(香草、薬草)の定義を紹介してみたいと思います。 「ハーブ大全」によると、「オックスフォード英語辞典」を引用して、ハーブ(香草、薬草)とは「葉、または茎と葉が、飲用、薬用に使われたり、においや香味が引用されたりする植物のこと」、「その成分が、食品や飲料の中に保存用香辛料または健康増進剤として添加される植物や、食品・飲料以外の製品に香水、化粧、洗浄の効能(効果、効用)を期待して使われる植物の全て」とあります。 次に、「ハーブの辞典」によると、聖書の創世記、第1章を導入に「当初ハーブは青草、つまり緑の草をさすことばであった。(中略)こうした雑草(グラス)と区別して人間の生活に役立つ草をハーブと呼ぶようになったのである」とあります。少々極端ですが、言い換えると、ハーブ(香草、薬草)とは「人間にとって役に立たない雑草を除く全ての植物」ともいえます。 しかし、少し曖昧なので、再び「ハーブ大全」から引用すると、「もともとヨーロッパの植物学は、薬用植物の研究に始まりました。(中略)ハーブとは本来『草』という意味ですが、当初は『草』はすなわち『雑草』であったわけです。時代は下がり、一般植物の研究も行われるようになってから、ハーブははっきりと『薬効を持った植物』を指すようになりました」とあります。 以上のことから、ハーブ(香草、薬草)とは「人間の生活に役立つ植物」の総称といえます。 しかし、ハーブ(香草、薬草)の定義は、国や学者によって様々ですので、あくまでも一つの解釈としてお考えください。 |
|
| 使い方(利用法、利用方法、活用法)例 | |
↑ローリエ(ローレル、月桂樹、ゲッケイジュ、ベイ)はスープ、シチューに  ↑レモングラスはハーブティー(ハーブ茶、お茶)に |
 ↑タイム(タチジャコウソウ)は肉料理、魚料理に  ↑ローズマリー(マンネンロウ、まんねんろう)は肉料理、魚料理に |
| ハーブ、スパイス&ポプリ、アロマセラピー(アロマテラピー)の専門店 ハーブ&アロマ花と香りの店 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-9-29第2プリンスビル608号 TEL&FAX:092-713-7459 営業時間 AM9:00〜PM6:00 店休日 日祝祭日(但し特別なイベントは除きます) |
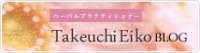

 ブログ
ブログ