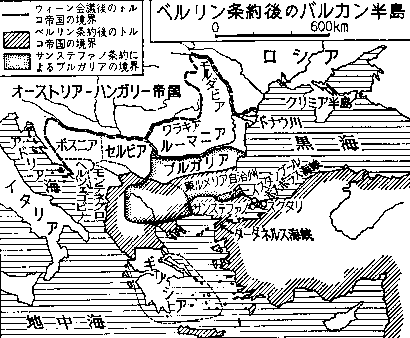| しかし,これらの諸民族はまだ自力で目的を達することができなかったので,かれらの運動はしばしば列強に利用された。そのころ列強は,トルコの衰退に乗じてトルコ領への進出をねらっていたが,とくにロシアは,穀物輸出の通路として,黒海からボスポラス・ダーダネルス両海峡の確保をはかって,しきりに南進策をとった。(バルカン半島の地名等はベルリン条約後のバルカン半島の図、参考 (新しいウィンドウを開きますので、適当に利用しやすい大きさと位置にしてご利用下さい。))イギリスはこれに対抗して,インドとの交通路の安全をはかろうとし,フランスはエジプトに勢力を扶植しようとしていた。ここに諸民族の運動と列強の利害関係が結びついて,国際間の鋭い対立がおこるようになった。これがいわゆる東方問題で,先のギリシアの独立も,そのあらわれであったが,その後エジプトとトルコが開戦すると,問題はさらに複雑になった。 |
|