50. タンク干し。
Ninjaに続き、900SSもタンク干しを行います。
しかし、900SSはタンク内にゼンダーユニットとフュエルポンプが入っていて、はずすのがめんどっちい。
なので、できるだけ空に近くなるまでガソリンを減らすのみにしました。
(フュエルポンプで吸い上げているので、適当に混ざった水は吸い上げられるので、空近くまでガソリンを
使えば、水も殆どなくなります。)
現在、ガソリンは、7L程度入っているので、燃費17Km/Lとして120㎞も走れば殆ど空になるはず。
そこで本日、暑い中、箱根までのツーリングとしました。
箱根の道の駅の往復でほぼ110㎞ですので、丁度良いかと。
ちゃきちゃき堂を出発し、西湘BP→箱根新道→箱根道の駅。
道の駅はさすがに涼しく、30分ほどゆっくり涼みました。
今日は気温が高かったのですが、箱根神社や芦ノ湖がすっきり見えました。
その帰り道、そろそろフュエルアラームランプ(900SSにはリザーブがないのでその代わりのランプが点灯します)
が点くと思っていたのですが、点きません。
結局家の近くのいつものガソリンスタンドに着いても点きませんでした。
ガソリンタンクを覗いても殆どガソリンは入っていません。
しょうがないので、ガソリンを入れてみると 15L入りました。
タンク容量は17.5Lですので、2.5L残っていたことになります。(フューエルアラームランプ故障?)
まあ箱根の登りや帰りの旧道で、ガソリンと水はブレンドされて水もガソリンと一緒に燃えたはずなので
これで良しとします。
次の時はフュエルフィルター交換も含め完全に空にして水抜きです。
2018/8/14
49. Power 2CT。
タイヤを取り換えて、初のツーリングに行きました。
朝早くちゃきちゃき堂を出発。R246で御殿場に行き、東名で帰宅するだいたい100㎞のルート。
順調にR246を走っていた時に、いつものあの症状がまたまた出ました。
下バンクのプラグかぶりによる失火。
しばらく走ると復活することもあるので、1気筒で様子を見ましたが、回復する様子もないので、
コンビニでプラグを交換することに。(そろそろK&Nフィルターの掃除しないといけませんね)
工具+予備プラグは常備しています。
コンビニのお客さんに見られながら(見守られながら?)カウルを外してプラグ交換。
交換後はいつものように絶好調。 御殿場で少し休んで、再出発。
やっぱり新品タイヤは安心です。
御殿場までの山道、東名を走った結果、以前のPowerより粘っこい感じですが、
車体が軽い900SSには、 直線、コーナー共に丁度良い感じの安定感になってます。
2CTは初めてですが、「あたり」 のタイヤでした。
2018/8/14
48. 足下、万全。
タイヤ、替えました。
本日朝からホイールを外し、タイヤ屋さんへ行きます。
しかし今朝は、8時ですでに29℃。
久しぶりに大汗かいてなんとかホイールを外してリーフに積み、出発。
タイヤ屋さんでの交換時間は30分。 コンビニで時間をつぶして引き取り、帰宅。
早速900SSに取り付けました。
やっぱ新しいタイヤは良いですね。
なんかオートバイに乗る気にさせてくれます。
これで、3台のオートバイすべてタイヤはOK。
いつでも、どんな速度でも、どこにでも行けます。
あとは、自転車のタイヤ替えればAll Clear です。
2018/7/14
47. 足下が危ない。
タイヤです。
オーナーの単身赴任終了時に交換したままです。
交換したのは2011年。
いくらPilot Powerとはいえ、限界をすでに3倍以上超えてます。
ここ数年は、乗る機会も、快飛ぶ機会も少なく、流して走るだけであまり気にもなりませんでした。
でも、限界。 だから交換です。
オートバイのタイヤはMichelin 1番、Dunlop 2番です。
ほかのタイヤにも浮気しましたが、やっぱりこの2つのメーカーがオーナーには合うようです。
しかし、今となっては900SSのリアは、Ninjaほどではありませんが、少し特殊なサイズです。
適合するのはMichelinではツーリング+スポーツのPower 2CT位しかありません。
ですので、本日 Power 2CTを予約。
来週交換です。
2018/7/8
46. フォークオイル交換、そして車検。
フロントフォークオイル交換の効果は、結構なもんでした。
少し硬くなりましたが、80km/h以上のコーナーでも「しっとり」していてバタつく様子もなく、ほんとにいい感じです。
上質な900SSになりました。
そして車検。
定期のオイル系の交換を行い、その他を確認してNinjaと一緒にユーザー車検。
日々ちゃんと整備していれば、なんとか車検は通ります。
ちなみに、今回は、自賠責+重量税+検査費用で2万円弱でした。
(書類は自分で書けば、代書屋さんへの3000円は無しになります。書くのは簡単です。)
また、よく車検検査前にテスター屋さん(事前に車検項目を有料で確認してくれるお店)に持っていく人がいますが、
まずは自分で整備して、それで車検ラインを通し、 それでダメだったら行くようにしたほうが良いです。
テスター屋さんに行くと、3000円以上かかります。
車検は、検査場にもよりますが、オーナーが車検をする湘南陸事は時間内であれば何回でも検査を受けられます。
(各車検場で違うかもしれません。確認してください。)
とにかく整備を理解して日々整備していればまず問題なく車検ラインでの検査は通ります。
自分の整備を信じてまずは、車検ラインを通してみることです。
頑張ってみてはどうですか。
後日、横浜のDuca専門店でタイミングベルトを交換しました。
交換したときに店長さんから、
「タイミングベルトは、お客さんの走行距離なら2年じゃもったいないかもね。」
と言われました。
次回は3年で交換してみますかね。
2018/4/8
45. やっとなんとか。
すっごーく気になっていた数年交換していないフロントフォークのオイル。
オイルの劣化により、相当性能ダウンしているのではないかーーーーー
なんて思いながら思い切って交換しました。
フロントフォークを外し、横浜の有名なドカッティショップへ持ち込み。
あくまで原点復帰目的ですので、純正レベルのオイルと量で交換をお願いしました。
2日で交換完了の連絡があり、本日引き取り。
シール関係の劣化もなかったようで、オイル交換のみの工賃でした。
さて、ノーマルの乗り心地はどんなもんでしょうか。
2017/3/20
44. ああああああ〜の後始末。
クラッチピストン、交換しました。
Riding Houseさんのものを購入し、取り換えです。
特に問題もなくすんなり交換でき、エア抜きもきっちり終わりました。
あとは温かくなる3月を待つだけです。
2017/2/25
43. 今年の春は。
今年の春は、ドカで旅に行こうと思っています。
Ninjaでは、九州まで2回往復してますが、ドカでの一番遠距離は諏訪湖。
オーナーのツーリングのセオリー通り、最小限の荷物をリアシートに括り付けて、
気の向くままに、色々行ってみますかね。
2017/2/19
42. そろそろ部品確保。
オーナーのドカ は、これまで思いの他壊れず(Ninjaよりも)、元気でしたが、
そろそろ、部品供給を考えないといけないようです。
今では、ワンオフで製作してもらえるショップもあり、古いバイクに乗っている者にとっては
随分楽になりましたが、やはりリーズナブルに乗るには、中古です。
車種限定のカウル、タンク、ハーネス、リレー、ワイヤーのうち、リレーとワイヤーは、現在も発売されて
いますが、 カウル、タンク、サスは新品(社外含め)があっても高すぎて手が出ません。
これらは良い状態の 中古を収集しておいたほうがいいようです。
ただこれって、多くの場合、部品取り車を買ったほうが効率的なことが多いですが。
2017/2/19
41. オイルホース交換 #2。
フロントとクラッチのホースの交換です。
フロントは、ブレーキマスターから2本出ていて左右のキャリパーに繋がっています。
まずはエア出しの要領で左右のキャリパーのブリードバルブからオイルを出します。
リザーブタンクのフルードがなくなったら、キャリパー側のホースを外し、フルードの流れ出しが
止まるまで放置。
流れ出しが止まったら、ブレーキマスター側を外します。
そして、新しいホースを取り付けますが、ここはぴったり。
またまたキャリパー側からシリンジでフルードを注入してまずは終了。
その後エア出しを根気よく行います。
思ったよりもスムースに完了しました。
さて最後のクラッチです。
これもまずリザーブタンクのフルードを追い出した後、ホースを外し、注射でフルード入れ。
あとは、エア抜きのみーーーーーーの筈でしたが、なんとエア抜きを行って出てくる
フルードに黒いゴミがーーーーーー。
あぁぁぁぁぁ〜。(落胆の声)
こっ、これはクラッチピストンのOリングの粉ーーーー。
そうです。Oリングの劣化によりボロボロになったゴムの破片。
クラッチレリーズは、購入当時から社外のピストン径が大きい(軽い)ものがついてました。
早速クラッチレリーズのメーカーに電話。
しかし、Oリングは「生産中止」とのこと。
新品買うと結構します。
ま、しゃあないですね。
20年オーバーのイタ車を1stバイクにしてるわけだし。
早速、部品を取り寄せて気持ちよく走れるようにします。
2017/2/19
40. オイルホース交換。
オーナーのドカは、丁稚 虎の生まれた年と同じ年式。
1995年です。
そう、22年経ってしまったということです。
そのため、樹脂製のいろんなものが劣化してきました。
その中で一番危ないのが、ブレーキホース。
峠や高速を走っているときに、ホースがパンクしてしまっては、最悪です。
ほんで、思い切ってホースを交換することにしました。
ACパフォーマンスの車種専用のフロント・リアブレーキ、クラッチ用のホース、ついでに
リザーブタンクのホースも購入。
本日、朝から写真を撮りに行って、帰宅して3時頃からゴソゴソと交換開始。
最初にリアブレーキですが、純正とは違い、キャリパー側のフィッティングが90°ではなく
45°位でその結果取り回しがギリギリ。何とか取り付けを終えてエア抜きです。
エアブリードバルブを上向きにするため、キャリパーを外し、まずはセオリー通りにリザーブタンク
にブレーキフルードを注ぎ、ブレーキペダルを踏みながらエアブリードバルブを開閉しながら、
キャリパーの中の古いオイルを出し切ります。
オイルが綺麗になってなったら、今度はキャリパーのブリードバルブにホースを介して
ブレーキフルードを注射器で押し込みます。(エアが入らないように注意)
そうすると、ブリーザータンクまでオイルが逆流し、交換完了
ちょっと乱暴なやり方なので、安全の保障はしかねますが、オーナーはキャリパーOH
の時とかは、このやり方です。
ここまでやって、時間切れ(夜の飲兵衛タイム)
来週、時間作ってフロントとクラッチのホースを交換する予定です。
だんだん復活してくるドカです
2017/2/12
39. クラッチ交換。
懸案だったクラッチをやっと交換できました。
ニュートラルでアイドリングすると「ガラガラー----」
そろそろやばいと思ってました。 22600km。
交換してもらったのは、横浜の有名なドカッティショップ。
なんとちょうどクラッチ交換キャンペーンをやっていて、部品代が3割引き。
クラッチのアウターとインナードラム、ディスクを交換。
本日修理が終わり、引き取りに。
すっごく愛想のいいオーナーの方にいろいろ聞き、
小一時間でそのお店を出ました。
クラッチ周りを交換した愛機。
40km以上の帰路を、ほんとに気持ちよく走れました。
空冷のドカは、整備されていると、振動も気持ちいいくらいしか出ないし、
4000rpm以上では振動も殆どなくなります。
そしてアクセルを捻った分だけ前に出る。
決して出すぎないし遅れない。
必要十分。
これが気持ちいい。
上質な乗り心地
いまだに900SSが好きな理由です。
2016/12/04
38. オイル交換。
夏の暑さのピークも過ぎたので、オイルを交換することに。
前回はアルファベット3文字のオイルを使ってみましたが、半年 500kmで
粘度も全くないシャバシャバになってしまいました。
こんなに粘度がなくなったのは、初めてです。
ということで、急遽これまで使っていた Motul 5100 に戻します。
フィルター交換はなしです。
アルファベット3文字のオイルは、どっかで作ったパチモンでしたかね。
2016/ 5/22
37. フュエルラインの交換。
あんまり乗らずに2年がたち、また車検。
Ninjaと同日に無事車検を通し、ちょっと真面目にメンテナンス開始。
と思いましたが、ちょっとフュエルホース系が気になりました。
。
900SSは、ダンドラキャブの常識で、フュエルポンプでガスを供給します。
更にそのフュエルポンプはタンクの中。
フュエルポンプでの圧送を考えると、ホースの劣化は、致命的です。
ほんでまずは、フュエルライン系を交換することにしました。
同時に、いつものタイミングベルト交換も行うことに。
ここいらのメンテは、残念ながら素人がやると危ないので、ショップにお任せです。
(タイミングベルト、フュエルポンプ式のフュエルホース交換は、さすがに自粛)
このメンテが終わったら、オイル交換とかボチボチやります。
2016/ 5/22
36. 久々の箱根。
車検も取り、タイミングベル、オイルも交換し、バッテリーも交換して全てOKのDucati。
本日、久しぶりに朝から箱根へ。
いつもどおりの西湘バイパスから箱根新道を通り、芦ノ湖へ。
いやー、楽しいです。
やっぱりオートバイは用途に合った車重が必要です。
峠ではどんなにPowerがあっても、軽くないと楽しくない。
オーナーにとっては、180kgがリミットでしょうか。
思い通りに振り回せるのが面白いですね。
ブレーキも充分利くし。
でもツーリングでは、車重がないと高速道路で風に振られて疲れます。
Ninjaは、250kg程度ですが、高速は本当に楽です。
(キャスターが27°っていうのもあるでしょうが)
Ninjaなら一日1000kmの高速ツーリングも辛くありません。
で、箱根の山を適当に流して、いい気分で写真撮影。

白樺湖に続いて芦ノ湖がバックの写真です。
何故か写真は湖が多いですね。
あっ、ヘルメットはAraiのRX7 RR5 です。
女将にお願いしてプレゼントでもらいました。
前回買ったRR4は 丁稚 虎 用になってしまい、RAM SZ3しかなかったので。
やっぱRX7はいいですね。
通気性もよいので、髪の毛への負担も少ないかと−−−−−−−−−−−。
夏は、何処に行こうかなぁー
2014/ 7/13
35. バッテリー 2個目。
電気系の薀蓄を思いっきり書いた後すぐですが、バッテリーが逝ってしまい
ました。
充電時間はかかりまくるは、やっと充電が終わって電圧を測ると 12.5V。
その状態で900SSに乗っけてセルボタンを押すと
「カチカチカチカチカチ------------」
リレーが悲鳴を上げます。
完全にバッテリー、逝っちゃってます。サルフェーションですかね。
ただ突然逝ってしまうのは、中華製の特徴でしょうか。(ACデルコは、中国生産)
そこでバッテリーをネットで検索。
調べると、中華製のバッテリーがいっぱい出てました。
その中で、オーナーは、ライズコーポレーションさんの「マキシマ ジェルタイプ」がちょっと
気になりました。
中華製ですが、1年保障。
販売元もしっかりしている。
早々に購入。(送料、代引き手数料込みで7000円)
で、届いたのがこれ。で、すぐに充電しないまま電圧チェック。


13.14V。 おっ、ばっちり?
早速900SSに乗せてエンジン始動。
セルボタンを押すと、事も無げに「ズドン、ドッドッドッド---」
セルモーターにアーシングした効果もあるのでしょうが、力強く始動しました。
その後電圧を見ると
アイドリング(1000rpm)で13〜14.17V, 4000rpmで14.3V。


発電機もOKでしょう。
ガルーダ製の1500rpmから充電するレギュレターを付けていますが、始動して電圧が
14V以上に上がると言うことは、MFバッテリー用として作られてはいないっちゅう
ことですね。 あーあ残念。
とにかく、初期充電をして交換完了です。
あとは、この中華製 ジェルバッテリーがどこまでもつか。
まあ、純正指定は安くても1万円オーバーですから、2年持てばいいかな。
2014/ 6/21
34. アーシングの結果とベルト交換
んで、暫らく乗ってみました。
結果は、あっけなくGood。
セルの回転は良くなるは、かぶりもなし。
低回転(3000rpm以下)でもちゃんとトルクが出でいます。
とにかくニコニコです。
ここで知ったかぶり。
やはり古いビックシリンダーのエンジンは、きっちり爆発させる事が必要。
そうすると、見る必要があるのは、まずは電装系。
プラグで強い火花を出す。 プラグから逆にたどると
① プラグ、プラグキャップ、ハイテンションコード
② コイル
③ バッテリー
ですが、オーナーはコイルの劣化に遭遇した事がありません。
(強化はBenlyで経験。 排気量もあって、改善はほんの少し)
なので、リフレッシュは、主に①と②(既に交換済み)
次に必要なのが、ちゃんとセルを回すこと。
これって結構できてません。
セルは、通常セルスイッチを押せば、勢いよく回ります。
ウッウウィンって言う状況なら、それは×。セルが回っていません。
セルをきっちり回すためには、
① セルモーター自体が元気。
② リレーが元気。
③ バッテリーが元気。
④ 配線が充分。
以上が必要です。
特に古いオートバイの場合、前述したように④があぶない。
なので、
セルモーター → クランクケース → フレーム → バッテリーから
セルモーター → バッテリー でアーシングを行ったわけです。
その結果、セルモーター → クランクケース → フレーム → バッテリー までの道のりを
甘く見てはいけないことが、判りました。
結構な抵抗のようです。
(やるならショップと相談しながらやってください。)
それで気をよくして、タイミングベルトの交換も実施。
ベルトの交換は、失敗したときのことを考え、前から、ショップにお願いしています。
部品代15000円、交換賃15000円 計30000円也(約です)
2年に1度必ず交換。唯一、お金がかかる部分です。
(数年前に比べてベルト代が倍になりました)
でもその結果、エンジンは絶好調。 文句なし。
空冷Lツイン900ccの80Ps程度ですが、フルにぶん回せる面白さがあります。
加えてシビアでピンポイントの操縦性は、はまった時は天国、ずれたら地獄。
−−−−−− さすが DUCATI −− 楽しい −−−−
2014/ 5/18
33. アーシング
アーシングもこれで3台目。
Ninjaはもともとアーシングがされていて、Benlyはオーナーが実施。
で色々やった結果、アーシングは気分的なものという結果です。
(オーナーが鈍感すぎて気づいていないのかもしれない)
でもこの改造は、少なくとも悪い方向には行かない改造です。
で、900SSに実施。
と言ってもセルモーターハウジングとバッテリーのマイナスを繋ぐだけ。
これだけでもセルの廻りが変わるはず。
さて、どうなりますか−−ね。
(真似しないでくださいね。)
2014/ 4/20
32. 車検!
またまた車検の時期になりました。
実は、昨年の11車検が切れていたのですが、車検を撮る暇も無く、結局4月7日に。
(ちなみにNinjaと同じ日です。)
車検は、Ninjaが午前中、900SSは午後から。
で、Ninjaの車検を済ませ、いったん帰宅し昼食。
その後仮ナンバーを取得。
少し時間があったので車検場での不具合を予測してバイクショップへ行き、コネクターを物色。
そして車検場に向かおうとしたとき−−−−−−。
でました。
セルボタンを押してもカチっとも何も言わないあの症状。
うーん。今日車検取らないとまた年休とって−−−−−それは何としても避けたい。
で考えると、スターターボタンを押してもカチっともウィンとも言わない−−−−−−。
セルに電気が行っていない。
とすれば、スイッチかスターターリレーが怪しい。
で、まずはスイッチにWD-40をスプレーし、10回くらいON-OFFを繰り返します。
でもだめ。
だとすると次はスターターリレー。
まずはスターターリレーの接触不良を考え、接続部分を弄ると、何のことはなく始動。
どうもリレーの接触不良のようです。
その後数回スターターボタンを押して始動しましたが、問題なし。
接触改善は後でやることにして、車検場へ。
手続きを済まして検査ラインに行くと、朝と同じように誰もいない状態ですぐに
検査開始。−−−−そして終了。
ちょっとライトの光量が心配でしたがなんとかOK。
(次は少し考えないといけないかもしれません。)
あっけなく検査完了で、またまたいつでもあの極上の走りが楽しめます。
あとは、懸案のタイミングベルト交換とクラッチの交換です。
(高いんですよね。)
2014/ 4/ 7
31. スターター。
この一ヶ月、腰痛・帰省で殆どオートバイに乗る時間がなく、何となく欲求不満でした。
んで今日、久々の箱根へと。
季節は既に秋。 メッシュのジャケットでは少し、肌寒い感じです。
いつものように箱根新道をちんたら登り、そこから旧道で降りてきます。
休憩は無しで西湘バイパスの登りのサービスエリアへ。
所要は1時間半。
コーヒーを飲んで、ゆっくりして、さて帰宅。
ところがセルが回りません。
イグニッションキーを回すと、フュエルポンプは回っているのですが、セルがうんともすんとも。
以前も休憩した後にセルが回らず、押し掛けしたことがあります。
でもそのときは駐車場から道に出るまで長い下り坂で、簡単に掛かりましたが、
今日は平坦地。
参った。
セルの位置か、噛み込みが悪いのかと思い、ギアを入れて少しゆすってみましたが、
エンジンはかからず。
しょうがない、久しぶりの押しがけです。
周りにいるオートバイに迷惑を掛けないように、駐車場の端まで900SSを押してスタンバイ。
気合を入れて10歩くらい走り飛び乗ります。
そしてクラッチを繋ぎます−−−−−ま、一回じゃ掛かりませんわね。
繰り返すこと4回。
見事エンジンが掛かりました。
押しがけは、通常の湿式クラッチであればギアを入れると押すのが重くなるので、
ニュートラルで押して飛び乗った後にギアを2or3速に入れてクラッチを繋ぎます。
でも、乾式クラッチの900SSでは、ギアを2速に入れたままでも殆ど抵抗がないので、
2速に入れてクラッチを切ったま押して飛び乗った後にクラッチを繋ぐだけ。
車重も軽いので、結構簡単です。
これがNinjaだったらと思うと、恐怖です。
帰宅後、確認してみましたが、何事もなかったようにエンジンが掛かります。
どうもギアを入れたままエンジンを切るとセルの咬み込みによって、この症状が出る
ようです。
エンジンを切るときにニュートラルにするようにして、しばらく様子を見ます。
教訓
古いオートバイの休憩は、下り坂のある場所に限る。
2013/ 9/22
30. フロントブレーキ。
フロントブレーキを揉み出ししていると、パッドピンが錆びていることに気が付きました。
そこで、パッドピンを新品に。
もちろんBremboの純正。
ステンレスの社外品が多く出ていますが、ステンレスとアルミは電食でよくない組み合わせ。
なので純正の鉄製のピンとしました。
1本850円。
こんなピンがーーーと思いながら揉み出ししてピン交換。
そして本日試乗。
なんと、ブレーキから「ゴッゴッ」という摺れる音。
止まって見ましたが、どこも干渉していません。
パッドを入れ替えてしまったため、どうも当たりが変わって音がしているようです。
と言うことは、ディスクもだいぶ磨耗しているのかと−−−−。
100kmほど走ると、殆ど音は消えました。
そろそろパッドも交換せにゃ。
2013/ 7/ 7
29. 電装系その次。
プラグキャップを交換し、いい気になっていましたが、整備しているときにハイテンションコードに
触ると、コードがカチカチ。
早速DS2輪館で、Kijima製のハイテンションコード 1m×2個購入。
12月に交換したキャップはそのままで、純正コイルからハイテンションコードを外して、交換。
交換は、簡単。 あっという間。
で、エンジン始動。
冬場は、バッテリーを満充電しても、セルをまわし始めは、「うぃん・うぃん・--」で、数回クランキング
なのですが、今回は「うぃん・うぃん・ズドドドドドドーーーー」であっけなく始動。
その後もアイドリングが安定しています。
やっぱ、20年近く経つと、コード、ホース系は交換ですね。
ちなみに、ハイテンションコードは、900SSの場合、1mでフロント、リア2本分足りました。
余った1本は、Benlyのハイテンションコード交換に使いました。
さて、残るはフュエル系のホース交換です。
(これが一番危ないかも)
2013/ 2/10
28. 電装系
最近は、調子よく走っていた900SSですが、冷え始めた最近はどうもフロントバンクが
かぶりやすい状態です。
もともと、キャブの調整が濃い方向で、空冷だし冷却も考えりゃまあいいかとそのままに
してました。
しかし、しばらくぶり(と言っても1ヶ月以上は放置していません)にエンジンを掛けようと
するとプラグがかぶり、結局プラグ交換。
まあ交換すると元気に回ってくれるのですが、なんか最近多発気味。
プラグがかぶるのですから、悪いところはプラグに近いところから
①プラグキャップ
②ハイテンションコード
③コイル
ですね。
と言うことで、今回プラグキャップをNGK製のものに交換。
当然抵抗入りのものですが、価格は2つ合わせて1200円くらい。
純正のプラグキャップをはずし、ハイテンションコードを1cm切断してNGKのキャップを接続。
エンジンをかけると----------- ウィン ウィン ズドドドドドドド とこれまでより元気に
始動、始動後も安定しています。
さすがNGKなのか、さすがの純正も17年も経つとどうしようもないのか。
古い外車は、電装系を取り替えることで見違えると言われますが、オーナーの900SSも
17年を経て、そんな時期になっているのかも知れません。
2012/12/23
27. 確認!
やっとのことで、メーターギアと右ハンドルバーのトラブルを解決し、今日は
その確認。
丁度、会社のオートバイ乗りの集まりでツーリングがあり、それに最初の少しだけ
参加し、修理状況を確認することにしました。
(本当はフル参加したかったんですけど寒くてーーー。)
スピードメーターは、針が全くぶれる(振れる)ことなく安定しています。
100km/hでも大丈夫。
ハンドルバーは、角度も丁度良く、OK。
更にメーターもグラグラすることなくしっかり取り付け出来てます。
タイヤも新しく、久しぶりに900SSでの楽しい時間が取れました。
ただ、あまりにも寒くて、チョコチョコ休みながらでしたが。
2012/3/4
26. トラブル対応完了
オークションで落札したハンドルバー他が、無事入手できました。
物は、オークションの写真とほぼ同じで、使い込まれたものです。
バーやクランプに塗装のはがれ、錆はあるもののリペア範囲内で、
曲がりはありません。
ペーパーで適当に錆を落とし、つや消しの黒スプレーで化粧しなおし。
乾く時間を使って、右カウル、フロントフェンダー、キャリパー、タイヤを外します。
(ここまで約20分)
殆ど問題なくばらし完了。
外れたナット部を見ると、雌ねじ部が錆びており、強くねじ込んだため、
この錆から破断したようです。 残念。

見ててもしょうがないので、そそくさと組直し。
ただ、ハンドルバーの位置合わせは、一応ノギスを使って左右をあわせます。
今度は、ハンドルを樹脂ハンマーで軽く叩いても動かない程度しか締めません。
時間にして、ほぼ1時間。
老後はバイクの修理ショップができそうになってきました。
2012/2/26
25. トラブル対応×2
ラッキーです。 メーターギアがありました!!。
メーターの取り付けブッシュとスピードメーターギアが届いたとのことで、モトコルセさんに
早速商品を引取りに行きました。
ブッシュは、必要数は3個でしたが、10個単位の受注ということで、1袋10個のブッシュと
スピードメーターギアを受け取りました。
帰宅後、900SSのカウルを取り外し、まずはメーターの取り付け。
メーターの取り付ける支柱は、エポキシパテで補強しています。
取り付け部にブッシュを嵌め込み、樹脂ナットで固定。
まあまあ上手くいきました。
続いてスピードメーターギアの交換です。
しかしここでどうせならと、錆が気になるハンドルバーの再塗装と、フォークアウターの錆、汚れ
取りも行おうと、フロント全ばらしを敢行。
まずはフロントスタンドでフロントを浮かし、ブレーキキャリパーを外します。
外したキャリパーは、軍手の中に入れ他の部位に傷をつけないようにガードします。
そしてフロントアクスルを抜き取ります。
フロントフォークは、三叉の下側のクランプボルト、ハンドルバー、上側のクランプボルトの順で緩め、
静かに下側に抜き取ります。
抜き取ったフォークはアウターに錆が少し出ており、またアクスル取り付け部の内側はオイルで
汚れていました。
それらを磨き、給脂すると少し綺麗になりました。
ハンドルバーは、適当にタオルマスキングをしてつや消しの黒に塗装。
そして、左・右とフォークの掃除も進み、三叉のトップ、ボトムのボルトを締め、取り付けていきます。
フォークが取り付いたところで問題のメーターギア。
タイヤを取り付け、アクスルシャフトを通そうとすると−−−−−− 通りません。
完全に入り口で引っ掛かっています。
??????
シャフト径とメーターギアの貫通穴径を確認すると、φ20で問題なし。
しかし、シャフトを通そうとすると、通りません。
そこでメーターギアの逆から通してみると−−−−−−するっと通ります。
????? そこでメーターギアのシャフトが入る側をよくよく見ると、なんとバリが内径側に出てます。
0.2mm程度。
さすがイタリア。
これくらいは組むときに自分でやれとのことでしょう。
すぐにサンドペーパーで入り口のバリを削り落とし、爪で引っ掛かりが無いことを確認した後、
グリスを薄く塗って取り付け完了。メーターの動作確認も終了しました。
そして、最後にハンドルの位置調整を完了させ、右のハンドルバーのクランプボルトを締め付けた時です。
ぱきっ
なにーっ。
通常のアルミ製のハンドルバーでは、フォークへの取り付けがすり割に明けられたねじ穴に
ボルト2本を通して締め付けますが、900SSのそれは鉄板の筒製で、締め付けのねじ穴は
その筒にナットを溶接で着けたような感じです。
そのナットが取れてしまったのです。
うおー です。 ショックです。
溶接で修理しようにも、多分取れる前に変形しているため、元には戻らない−−はず。
新しいハンドルバーを取り寄せようにも多分左右1セットで、またまた2週間。
それに小遣いもメーターギア購入で心もとない。
ショックで修理はそこで一旦終了。
そして、オークションとなりました。
探してみると、本当に偶然だと思いますが、900SSのSL(スーパーライト)に付いていた
ハンドルバーやスイッチ、クラッチマスター、スロットルグリップ、スロットルワイヤーが全部で3000円とのこと。
その場で落札しました。
ボルト締め付けの際、トルクレンチを使っていたのですが、取れてしまった理由は?
又来週、ホイール外してハンドル交換となりました。
2012/2/19
24. トラブル発生×2
先週、プラグキャップの状況を確認するために、近くを流していたときです。
スピードメーターの針が突然 ”ユラユラ”し始めました。
えーっ。で帰宅して確認。
900SSは、スピードメーターのワイヤー取り付け部が奥にあり、作業性が非常に悪いので
トップカウルを外し、メーターを取り外します。
しかし、この時点でまたトラブル発見。
メーターケースのボディマウント部3箇所のうち、1箇所が折れており、他の2箇所はメーターケースに
埋め込まれた金属部品(クッション材を取り付けてマウントするボルトが切ってあります)がナット
と一緒に共回りしています。
しょうがないのでクッション材を切断し、クッション材が付く部分をプライヤーで掴んでナットを回します。
その状態で、まずは順番に確認。
まず考えられるのは、メーターの針を押さえているダンパーの不良。
この場合、すぐに日本計器さんに修理をお願いするしかありません。
次にメーターワイヤーが引っかかりながら回っていること。この原因は
① メーターワイヤーが痛んでいる。(スプリング状のワイヤーの芯が曲がっている、切れている)
② フロントホイールにあるメーターギアが原因。(歯が欠けたりして回りが悪くなっている)
などが考えられます。
経験上、ワイヤーがだめなんだろーなーと思いながら、まず自分で確認できる①+②の確認。
メーターからワイヤーをはずし、タイヤを回転させてメーター側のワイヤーを見てみると、確かにワイヤーが
カクカク引っかかりながら回っています。
この時点でメーターではないことが判明。 −−− 安心
そこでまず①の確認。
フロントホイールにあるメーターギアからワイヤーを抜き取り芯を抜き出します。
確認しましたが異常な部分は無く、手で回しても引っかかりはありません。
?????じゃ、メーターギア? −−− ちょっと不安
恐る恐る②の確認。
ホイールをはずし、ホイールギアを外して清掃、確認−−−−−−
この時代のメーターギアは、スペーサーとなる部分は金属ですが、筐体は樹脂。
その樹脂が割れています。
中のホイールと共回りするスパイラルギアを回してみると、確かに引っかかりながら
回ります。 −−− 不安が現実へ。
うわー。 部品取れるかな。
すぐに車を飛ばしてモトコルセさんへ。
いつも良くしてくれる店員さんに割れたメーターギアを見てもらいました。
その店員さんによると、もともと筐体部分の樹脂が割れやすいこと、またホイールの
カラーがメーターギア側に抜けてくると、それに押されて更に割れやすくなるそうです。
筐体が割れると、ギア同士の軸間距離が広がり、噛み合いが浅くなるので歯欠け
も置きやすくなるとのこと。
またこの店員さんも900SSに他のオートバイの物が使えないか色々探したそうですが、
互換性のあるものは無かったそうです。
「部品取れるかなー」と、心もとないご返事。
−−− 目いっぱい不安。
メーターギアがもし生産中止で入らなければメーター交換ですが、ネットで探してみても
900SSに雰囲気の合う市販品はありません。
900SSのメーターはお気に入りです。拘ってます。
悩んでいると、以前FJのスピードメーターの修理をお願いした日本計器さんで機械式を
電気式にする改造も受けてくれることを思い出しました。
このVegriaのメーターが改造可能かどうかは解りませんが、手はそれしかありません。
ただ、そうなると改造+スピードセンサーでいくらかかることやら???。
お小遣いも少ない昨今です。何とかメーターギアを入手したい!!。
あることを祈りながら、注文を入れ、帰宅。
ついでに、メーターのケースも入手できるか聞いてみたところ、ケースでの部品は
無く、メーター本体ごとになる模様。(高そー)
帰宅後、メーターケースの修理(もしかしたら使わなくなるかもしれませんが。)を実施。
アセトンを流し、樹脂を溶かして再接着を狙います。
このやり方は、FJの割れたアンダーカウルで行いましたが、強度の高い接着剤で着けるより
綺麗で強力に修復できます。
また、ナットは最悪共回りしたときでも簡単に割って外すことができる樹脂ナットにします。
以上で本日の修理は終わり。


↑ ’95 オイルTemp付。 ↑ 折れた足の応急処置(メーター裏側)
今はただただお店からの良い連絡を祈りながら待ってます。
2012/2/4
23. やっぱり−−−
最近、片肺状態が頻発してました。
それも決まってフロント(ほぼ水平の)シリンダー。
エンジンはそれでもかかり、回転をあげると片肺状態が回復する−−−
プラグの火花は飛んでいる。
でもプラグを交換してもすぐに片肺。そんなことがちょくちょくありました。
古いオートバイに乗っている方々は、お解かりだと思いますが、こんな時
疑うべきはプラグキャップとコード。
既に16年経ったオートバイです。
ハイテンションコードもそろそろ交換時期。
プラグキャップを見ると、走行には問題ないレベルですが、ハイテンションコード
との取り付けが少しゆるい感じです。
キャップからハイテンションコードをはずして確認。
すると、キャップを押し込んでいた部分が結構開き気味で接触も疑わしい状態。
多分、片肺の原因はこれ。
本来なら、高性能のハイテンションコードをつけたいのですが、何処のメーカーのものが
良いかまだ調べてません。
なのでハイテンションコードを2cm程度切断し、キャップをねじ込んで再利用。
(900SSは、国産車と違いハイテンションコードに結構余裕があります。)
エンジンはそれから1発始動となりました。
ハイテンションコードは、10年以上経ったら著しく劣化するので交換したほうが良いそうです。
ハイテンションコードとキャップのセットについては、様々なメーカーから出ています。
書き込みの内容を整理すると、
① 低速回転での爆発力が上がる。高回転ではあまり効果なし。
② 4気筒より単気筒、2気筒のほうが効果がある。
③ シリンダーの排気量が大きいほど効果がある。
ということで、900SSでやらない手はなさそうです。
9000rpmまわすと壊れますってマニュアルに書いてあるし、80馬力そこそこ
なので、低・中回転命だし。
まずはNGKのものから取り付けてみよっかなっと。
2012/1/23
22. 来ました 車検です
購入4回目の車検。
今回はこれまでの車検と違う点が2つ
一つ目は、車検が切れていること。(本業が忙しく、車検にいけませんでした。)
もうひとつは、所有者変更(ディーラーからオーナーへ)を行うこと。
まずはHPで予約して書類の確認。
1. 車検証
2. 納税証明書
3.自賠責保険証
4. 定期点検記録簿
車検証と納税証明書は問題ありませんが、今回は車検切れ状態ですので、
自走で陸運事務所に行くオーナーは、仮ナンバーを取得する必要があります。
仮ナンバー取得には、まず自賠責保険(25ヶ月で15000円くらい)のみオートバイ屋
で加入し、その証書を持って役所へ行き、仮ナンバーを申請します。
取得料は750円。
そして代書屋へ。
ところがその途中、なんとフロントバンクの片肺が死にました。(プラグのかぶり)
ふかしても治らず、結局ちゃきちゃき堂に引き返し、プラグをはずして掃除。
気を取り直して、再度代書屋へ向かうと、今度はリアのブレーキが抜けました。
止まって見ると、なんとリアキャリパーのボルトが片方抜け落ち、キャリパーが
ぶら下がってました。
再度ちゃきちゃき堂へ帰還し、適合サイズのボルトで締め付け。
その他の部位の締め付けも確認し再々度、代書屋へ向かいました。
代書屋では、以下の書類を作ってもらいます。
5. 継続検査申請書
6. 自動車検査票
審査費 ( 1300円の収入印紙込み)
検査 ( 400円の収入印紙込み)
これで3000円くらいです。
ただし今回は、所有者変更の書類もあり、+1500円くらい。
車検場の事務所でまずは重量税の収入印紙を購入、用紙に貼り付けです。
7. 重量税納付( 5000円)
そして納税確認(納税証明書)を終わらせ、検査の申し込み窓口へ申請し、
書類を持って、オートバイで検査場へ。
検査開始。
しかーし、今回二輪用のテストコースは改修中。
自動車のラインへ並び、テストを受けます。
フロント、リアブレーキでOKをもらいましたが、スピードは4輪のコースのため
テストができず不要とのこと。
最後のライト。
ここに魔物が住んでおりました。
なんと、暗くて下向きとのこと。
不合格をもらった後テスター屋さんに行き、確認してもらいましたが、「暗い」とのこと。
テスター屋さんが言うには、「まずレンズと反射鏡が曇っているので、ヘッドライトをはずして
エアーで拭いて掃除し、現状のブルーバルブを通常の白色バルブにしたほうがいい」。
本日中に車検を通さなくてはいけないオーナーとしてはこの二つをすぐに実行。
その場を借りて、ライトの取り外しです。
まず苦労してヘッドライトを取り出し、エアーで掃除し、更にテスター屋さんで購入した白色の
H4のバルブに取替え、再度チェック。
なんと信じられないことに、明るさが3倍(何じゃこりゃ。)になりました。
光軸をあわせて再度陸事のテストを受け、無事合格。
光軸調整は8年前に行ったのみでしたが、まさかずれるとは思っていませんでした。
その後、車検証を添えて名義変更を行い、9年越しでオーナーの900SSとなりました。
2011/11/2
21. ちと、レストア+タイヤ交換。
なんと、FJやFZRのレストアに現をぬかしている間に、900SSの錆が酷くなりました。
ディスクローター、ホイール、フレームの塗装剥げと錆。
これはいけません。
気合を入れて、これまで培ったレストアの腕を生かして、綺麗にしていきたいと思っています。
DUCAについては、数年後にフレームやホイールの焼付け塗装を行う予定です。
なので今回は、どれだけ綺麗にお手製塗装が出来るか。
がんばります。!!
あと、タイヤが既にご臨終だったので、奮発してMICHELIN PILOT POWERを装着。
FZRにも同じものを同時交換。
お揃いになりました。
早速走りに出かけました。
慣らしという事もあり、のんびりでしたが、いやいやなかなかのタイヤです。
ケース自体はご臨終のD208より柔らかい感じですが、深くバンクさせても張り付いた
感じのコーナリング。(当然ちゃんと駆動を掛けなきゃだめですが。)
さすがMICHELIN、これから楽しみです。
2011/10/17
20. K&N エアフィルター
Ninjaに続き、900SSもK&Nのリプレイス用エアフィルターに交換しました。
(フィルターはK&Nが多いです)
通常は約1万円。(結構高い。)
ただ、 純正品を2回交換するとほぼ同価格になりますが。
フィルター系には結構神経を使うオーナーですが、専用の洗剤で
洗浄しながらちゃんと使うと、結構長持ちします。
ちなみに洗浄後きっちり乾かさないで給油すること、極端に
吸入抵抗が上がって、中速あたりで息継ぎします。
そのK&Nエアフィルターが、横浜の量販ショップでなんと2割引。
早速購入。
古いフィルターもまだ使えそうでしたが、外観では判らないのがフィルター。
もったいないとは思いながら、取り外してK&Nのリプレイスフィルターに
オイルを染み込ませて装着。
Ninjaもそうですが、交換しても、低速回転ではあまり効果が見られません。
ただ、Ducati では−−−−−−−
まず、始動時のバックファイヤーが増えます。温まるまでですが。
多分エアの流入能が上がるためだと思います。
走り出すと、中〜高回転へのつながりが良くなり、中高回転も少しだけ軽く
回る気がします。
ま、そんな程度です。
2011/07/15
19. 家の周りのツーリング
Ducatiにも暫く乗っていなかったので、昨夜から充電してちょっこっとツーリング。
目的は、
① 服飾系の学校に入った番頭の鈴用に女将が譲ったミシンの修理用ベルト購入。
② FJのバッテリーの振動防止用緩衝材の購入。
③ 鈴が学校で使うと言い張るコンパクトデジカメの購入。
と言うことで、近くのミシン屋さんとホームセンターに行き、問題もなくそれらを購入。
さて最後のコンパクトデジカメを買いに関東では大手の電気屋さんに行き、目的のカメラを
購入しました。
−−−− が、Ducatiでした。 それもシングルシートで、荷紐もありません。
ミシンの修理用のベルトと、緩衝材は何とかジャケットの中に入れれば帰れます。
でも、コンパクトデジカメは結構な荷物。
考えた挙句、お腹が季節外れのサンタクロースみたいになるのを覚悟で、ジャケットの下に
カメラを入れ、帰宅したのでありました。
とっても不恰好でした。
2011/05/22
18. バッテリー交換#2とオイル交換
プラグを買ってきました。
指定は、イリジウムですが、これまでイリジウムを着けても、結局2ヶ月で
だめになってしまったので、通常のプラグ。
左カウルを外し、プラグソケットを抜き、エアーでプラグ周りのごみを飛ばした後、
プラグ交換。
やっぱりキャブの濃い目のセッティングのせいで、カブリ気味になっています。
プラグを取替えて、さてエンジン始動。
あっけなく、掛かりました。
それも、心なしかいままでよりアイドリングが安定しているようです。
(多分気分的なものだと思いますが)
また、ついでにオイルとオイルフィルターも交換しました。(半年ぶり)
オイルはMOTUL 5100、フィルターは、K&Nです。
フィルターにK&Nを使うのは、フィルターの先にレンチで回せる四角い突起があるためです。
実は昔、他社のものを使ったとき、カップ状の取り外し治具では外せず、苦労した
ことがあります。(多分焼きついていた?)
カップ状の取り外し治具は、一回滑るとフィルター外周の8面形状が変形し、力が掛から
なくなります。
その点、K&Nなら最初からレンチで取り外しできます。
その分割高ですが、確実で安全に作業するには、このフィルターが一番だと思っています。
2011/04/09
17. バッテリー交換 #1
とうとう、バッテリーが駄目になりました。
あまり乗ってやれなかったのがいけなかったのだと思います。
バッテリーはシールドタイプではありましたが、買った当初から××12B−4で、
純正の××16AL−A2に比べて小さいのが付いてました。
最近では、フル充電しても「ウ−−ウィン。ウィン」みたいに、如何にも
「バッテリー元気ありません!!」状態でした。
そこで、またまたインターネット探しまくりの日々が続きます。
でも結局購入したのはACデルコ。
さすがに日本製は高く、でも知らないメーカー品は、タンク下にバッテリーを置く以上
使いたくないし。
到着後、××12B−4と交換すると、セルの回り方が全然違います。
どうせならと、トリクル充電器も買って、充電しまくれるように、コネクター取り付け。
 ← 見えます?カバー付です。
← 見えます?カバー付です。
これで、いつでも簡単に充電できます。
しかーし。
エンジンが掛からない。
またまたプラグかぶり??
オーナーのDucatiは、結構な濃い目にキャブをセッティングしてますので、始動失敗すると
プラグは濡れ濡れです。
来週までにプラグを買って再トライです。(ワクワク!!←これが既に病気)
2011/03/27
16. またまた車検です
購入後3回目の車検です。
GPZ1000RX購入以降、すべてユーザー車検をやってきてますが、やっぱり少し
不安なものです。
まずはHPで予約。
取り消し、変更も出来るので結構便利です。
そして書類の確認。
1. 車検証
2. 自賠責保険証
3. 納税証明書
いこれらはいつも車検書を入れているケースに入れてますので問題なし
そして
4. 定期点検記録簿
の作成です。
インターネットでダウンロードした定期点検記録簿をPrint out して、
準備は完了。
点検表に従って点検です。
ボルト・ナットの締め付けもサービスマニュアルを見ながら、トルクレンチで確認。
そうすると、いつも整備しているつもりでも、ブレーキキャリパーのボルトが
緩んでいたり、少しのオイル滲みが見つかったりします。
またタイヤもそろそろーーー。
でも一番の驚きは、その走行距離。
前回の車検から2年。なんと1000km走っていない。
遠乗りのツーリングができなかったこともありますが、少しさびしい状況です。
ここまでが、準備です。
さて、車検当日となりました。
年休を取っての車検です。
車検場に向かい、まずは代書屋へ。
代書屋で以下の書類を作ってもらいます。
5. 継続検査申請書
6. 自動車検査票
これで1500円くらいです。
ついでに
7. 自賠責保険(24ヶ月で13400円)
も更新です。
車検場の事務所でまずは重量税、審査・検査費の収入印紙を購入、
用紙に貼り付けです。
8. 重量税納付( 5000円)
9. 審査費 ( 1300円)
10. 検査 ( 400円)
そして納税確認(納税証明書)を終わらせ、検査の申し込み窓口へ。
その書類を持って、オートバイで検査場へ。
9:00からの検査ですが、時間を見ると5分前。でもなんと今回は、
一番乗り。
そして検査開始。
まずは、外観検査。検査官が状態、車体番号などを確認。
その後エンジンを掛けて方向指示器やヘッドライト、ブレーキランプ、
クラクションの確認です。
さて、次はライン検査です。
何回やっても緊張します。
いつもと同じ指示に従って無事完了。
車検は、事務所手続き、検査を含めて20分で終了です。
2009/10/10
15. そろそろ、頭が危ない #2
タイミングベルトを交換しました。
オートバイ屋さんに行って、交換です。
自前での交換も検討しましたが、どうもインパクトレンチが必要であること、
また、もしかの組み間違いを考えるとオートバイ屋さんでお願いしたほうが
得策です。
交換時間は約1時間。
交換総費用はまあ飲みにいったことを考えれば安いもんです。
(ただ、最近の水冷Ducatiでは5万前後かかるそうです)
オートバイ屋さんのお兄さんにも、
「車検ごとに変えたほうがいいですよ。あと、従業員でベルト交換後、
ベルトカバーを着けずエンジンを掛けっぱなしでウエスで車を拭いて
いたときウエスがベルトに巻き込まれて、エンジンがパーになったこともあります」
なんていわれると、やっぱオートバイ屋さんでの交換が安全です。
で、そのタイミングベルト交換中にちょっと横を見ると、大きな箱が幾つも
積み上げられており、その箱には
「デスモセディチ---」
なーんて書いてあって、オーナーはヨダレだらだら。
どんなんかなー、やっぱ早いんだろうなー。
が、どうせオーナーが買っても200馬力のうち、せいぜい使って100数馬力でしょう。
オートバイを飾り物にする趣味は無いので、ヨダレもすぐに乾きました。
やっぱりオーナーには900SSが丁度いいです。
まあまあの加速、決めなきゃおっとっとのコーナリング。
オーナーには楽しいオートバイです。
2009/1/1
14. そろそろ、頭が危ない
そうです。 前回タイミングベルトを変えて既に3年が経っていました。
まずいです。
距離でいくと12000kmあたりで交換が良いという情報が多いのですが、
最近乗る機会が少なくて、交換後、まだ3000km弱。
しかし、そこは樹脂製品。
経年劣化+停止時間大による硬化など、結構危ない可能性があります。
よって、交換といたします。
ヘッド壊れたら、オーナーに直す財力は今ありませんので---。
2008/12/11
13. 久しぶりの箱根
GWに、久しぶりに箱根へ行きました。
西湘BPが全線復旧したこともあり、その下見も兼ねて。
まずは西湘BP。
台風の影響で対面通行になっていた区間が、確かに再舗装され、
従来の2車線道路へ復旧しています。
西湘BPは、オーナーのオートバイの調子を見るテストコースで、
① 制限速度内での加減速(40⇔70km/h)
② 同速度でのギアチェンジ(2〜5速での70km/h走行)
などを行い、車体、エンジンの確認を行います。
そんなことしながら、料金所を抜けSAで休憩していると、
後から後から凄いオートバイが入ってきます。
Ducati、BM, 日本メーカーの最新型から、既にクラッシックの領域にある
ローレプ、Z1、CB750 CB750Fなどなど。
(あっ この前ヴァイルスいました)
どう見ても数百万かかっていそうなオートバイばかりです。
それらを横目で見ながら、SAを出発し箱根新道へ。
当日は曇り+箱根の山は靄に覆われていました。
こういう靄の日はお気に入りのターンパイクでも気持ちよく走れません。
900SSは、日本製のSSのように低速から高速までが楽しめるオートバイ
ではありません。
中速〜高速でグィーンと曲がるコーナーが得意です。
少なくともオーナーには。
だからほんとは、ターンパイクが良いのですが、こういう日は逆にストレス
が溜まります。
ということで安い箱根新道へ。
箱根新道は、入ってすぐのパーキングでのネズミ捕りが有名ですが、
当日は朝8時ということもあり、まだ制服の方々はいません。
900SSには少し退屈ですが、制限速度を一応守りながら登り、時々現れる
中〜高速コーナーを楽しみながら大観山へ。
大観山に着く頃は、周りに靄がたちこめ、気温も下がりました。
レストハウスには、ペアのDucati乗り、ソロのトライアンフ、SRなど10台近くの
オートバイが止まってました。
その中にオートバイを止め、お決まりの「なーんにも考えない一服」。
この贅沢な時間が、結構今の生活に大事な時間になってます。
2008/5/10
12. へたこいたぁ〜
暖かくなってきました。
久しぶりに、少し走ってみよっかナーということで、走りはじめました。
実は、寒い間にプラグをイリジウムに交換していました。
イリジウムと言えば、悪い評判を聞かないプラグ。
一本の値段も通常の3〜4倍。悪くちゃかないませんが。
わくわくしながら、スタート!
と・こ・ろ・が。
低速のトルクが全くありません。
クラッチを3000rpmで繋いでも、エンジンはストール寸前まで
回転が落ち、それからゆっくり加速。
家の周りを数kmくらいぐるぐる。何度やっても同じ。
やっぱり、イリジウムって古いオートバイには合わないのかなぁー
などと思いながら家に帰って、普通プラグへ交換しようとカウルを
外した瞬間。
「 へたこいた〜 」
なんと、フロントバンクのプラグキャップがぶらぶら。
そうです。 なんとシングルで走ってたのです。
なぜ外れたかわかりません。
キャップを取り付けたときのクリック感は、十分でした。
皆さん「1気筒死んでいたら、振動がすごくてわかるだろうがっ!」
って思ってるでしょ?
確かに、Ninjaなど、4気筒では1気筒でも死のうものなら、ごろごろと、
とんでもない振動が出ます。
ところが−−−です。 900SSは殆ど通常と変わらないのです。
(もともと振動が多いこともあり。)
アイドリングも安定しているし、ただ、トルクが125クラスに細った
感じになるのです。
ほんとに不思議なオートバイです。
キャップを取り付け、再度買い物へ。
あの、4000rpmからのトルクが戻ってきました。
ただ、それまでの生ガスがエキパイに溜まっていたため、結構な白煙を
少しの間吐いてましたが。
2008/3/16
11. トリクル充電器
とうとう、900SSのMaintenance Freeバッテリーも上がり気味になりました。
意を決して、まずは安売り広告調査。
冬はやっぱり、微弱電流でいつもフル充電状態を保ってくれる「トリクル」充電器。
調べると、デイト◆と、トートクラフ◆の2社から出ている模様。
次に、前からちょっと気になっている、トリクル+サルフェーション対応充電器。
ここでサルフェーションとはですがーーー
以下いろんなところから読みかじったことを書いてます。
専門家ではないので内容に不適切あればすみません。
サルフェーションとは、 バッテリー液中に溶解している硫酸鉛の粒子が結晶
になって、不環性(元に戻りにくい)硫酸鉛となる現象だそうです。
不環性硫酸鉛は電気を通しにくく、これが極板に堆積すると極板の反応面積が
減少して放充電能力(=容量)が低下するため、充電をしても回復しなくなります。
これを、解消してくれるのがパルス充電器です。
なぜ気になっていたかと言うと、開放型のNinjaのバテリー上がりが最近頻発
しており、このサルフェーションが起きている?とも思えるからです。
そこで、トリクル+パルス式充電器を調べましたがいずれも2万円オーバー。
そこで、オーナーは、Ninjaのバッテリーがもし回復しなければ新しいMFとする決意
を持ってトリクルのみの機能にしました。(8千円弱でした)
(MFだからサルフェーションが起きないわけではないのでしょうが)
もともとバッテリーの寿命は約2年だと思ってます。(経験上)
バテリーを無理して使って、意楽しみにしていたツーリングが台無しになっては
元も子もありません。
だから、オーナーは、バッテリーの交換を多分他の人たちよりこまめに交換してます。
MFバッテリーのメリットは
① 液ダレがない。 電解液がこぼれると、錆は起こすは、塗装は剥がす
はで大変です。
② 液補充の手間が不要 これ結構助かります。
補充液は安いのですが使い切れず、本数が増えます。
また、開放型って液の減り方が不規則で、気が付くと
半分位になって、劣化が進んでいることもあります。
③ 放電がゆっくり(?) オーナーの感覚ですが、普通の開放型より放電が遅い
ような気がします。
また、セルを回したときの元気も良い気がーーー。
ただ、いかんせん値段が高い。開放型の1.5倍近くです。
でも、その価値は十分あると思っています。
早速家に帰って充電してみました。
Ducatiは、ぎりぎりエンジンがかからないバッテリー容量となっていたのですが、約6時間
で、一発始動になりました。
来週は、Ninja の充電です。
バッテリーを買い換えるか否かはその次の週にわかるでしょう−−−−。
2008/1/27
10. 久々の
11月の終わり、久しぶりにY氏・T氏と900SSで箱根へ行きました。
例のごとく、西湘BPのSA集合。
珍しくというか、初めて集合一番乗りだったオーナーは、缶ジュースと
タバコで待つこと10分。
まずはSV1000のY氏到着。
その後、T氏がTDM900で到着と思いきや、なぜかY氏ではない誰かと
お話中。
手を上げてT氏に合図すると、そのお話し相手と2人でこちらへ。
なんと、久しぶりの参加メンバー増。
しかし、そのオートバイはSRX600。 オーナーも久しぶりに見せて頂きました。
状態は良く、調子も良さそうです。
とうとう、不人気ビッグツイン3台のグループが、ビッグシングルもその範疇に
入れてしまいました。
普通は、直4が仲間になる可能性が圧倒的に高いのですが
SRX600がお仲間になるあたり、このグループの特殊性が見えます。
それでも皆一応、それなり株式会社の管理職のはずなのですが−−−−。
次からは、Ninjaでは来れないグループになりそうです。
そうは言っても、新しいメンバーが入っていただけるのは嬉しいことです。
SAを後にして、向かうは亀石峠のドライブイン。
箱根新道から、十国峠を抜け、箱根スカイラインへ。
この日オーナーは、朝から何故か調子が悪く、体が動きません。
どうしてもワンテンポ遅れたり速かったり。
長年の経験で、こんな日は無理をせずちんたら走ることに決定。
無理して走って、怖い思いをすると次に走りに行く意欲が欠如するので
最近はそうしています。
ところが、T2氏がY氏、T1氏についていくではないですか。
いくらSRXの車重が軽いだ、ハンドリングがいいとは言っても
相手はTDMとSV。
倍以上の馬力と10年以上の年式差をもろともせず、
付いて行ってました。
T2氏うまいっ!
それを2〜3コーナー分見た後、のんびりツーリングで腹をくくった
オーナーは、久しぶりの景色をきょろきょろしながら堪能し、3人に
遅れながらもついていったのでした。
2007/12/02
9. 車検
さてさて、なんと購入後2回目の車検の時期がやってまいりました。
オーナーは、GPZ1000RX購入以降、すべてユーザー車検です。
以降、オーナーのやり方ですので、正確かどうかわかりませんが、参考まで。
まずは、検査日の予約。
最近は、HPで予約が出来るので安心、早く済ませられます。
続いて書類の整備。
1. 車検証(無きゃ乗れてません。)
2. 自賠責保険証(同上。)
以上2つは、乗車時に所持を義務付けられてます。
この2つは問題なし。続いて
3. 納税証明書
これが落とし穴だったりします。
その車検を受ける前に納税した証明書ですが、これが書類整理が悪いと
再交付。オーナーの場合、女将のまめさに助けられております。
と言うことでこれも問題なし。
以上の準備は、所要時間10分くらい。
さて、いよいよ第一関門の
4. 定期点検記録簿
の作成です。
定期点検記録簿は、車のメンテナンス記録簿や、インターネットに載ってますので
それを使用してます。
↓こんなのです。
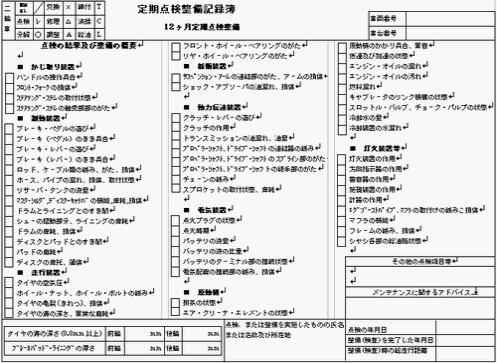
オーナーの場合、この点検にしたがって、まじめに点検を行います。
ユーザー車検は、手を抜く車検ではなく、お店でやってもらう点検を自分でやる
だけのことです。
だから、手を抜くのは × 。
ということで、3時間ほど掛けて、掃除、調整を含め点検、調整を行います。
その結果で、定期点検記録簿が、完成。
記入は、点検、分解、交換、修理、調整、締め付け、清掃、給油と、作業別に
確認記号が違うので、注意です。
また、シャフトドライブ、空水冷、ドラムブレーキの違いを間違わないように
記入します。
オーナーの場合、殆ど点検で、締め付け、清掃、給油が1〜2個です。
で、ここからがオーナーの根性の無いところで、車検場に行く前に、
5. 継続検査申請書
6. 自動車検査票
については、検査場近くの代書屋さんで作成してもらいます。
そのときついでに
7.自賠責保険(2万円くらい)
の継続加入も済ませます。
代書費用は検査費用の印紙代込みで 2500円くらいで、記入間違いが
無いことを考えると、まあまあです。
さて、これらの書類をクリアボックスに入れて、車検場へと向かいます。
オーナーの地区は湘南自動車検査登録所で、近くにあります。
まずは、事務所へ行って、納税確認と書類確認です。
それが済んだら、重量税を納付し、継続審査申請書にその印紙を
貼り付けます。
8. 重量税納付書(当然支払い有 5000円)
以上で書類の準備はすべて完了。
その書類を持って、検査場へ。
まずは、外観検査。
検査では、移動したりライト点けたりするので、オーナーは検査が終わるまで
エンジンを掛けっぱなしにします。
係員の人がオイル漏れ、改造箇所を細かく見られますが、大抵は大丈夫。
車体確認後、係員の人が前に立ち、
「ライト上向きに点けけてください」(ライトはこの後点けっぱなし)
「ウィンカー点けてください。 右、左」
「ホーン鳴らしてください」
その確認後後ろに回り、
「ウィンカー点けてください。 右、左」
「フロントブレーキ掛けてください」
「リアブレーキ掛けてください」
以上の指示をしてくれるので、その通りに操作します。
その後、車体番号確認と、ハンドル幅のみ計測して終了。
OKでした。(オーナーのハンドルはノーマルです。)
さて、次はどきどきのライン検査です。
何回やっても緊張します。
まずは、排ガス検査ですが、オーナーのオートバイは95年式のため、
検査は無し。
排ガス検査場所をそのまま素通りして検査ラインの前に行きます。
以下、掲示板の表示、手順に違いがあるかもしれませんが、
大体の流れを書いてみます。
検査ラインの上には、電光掲示板があり、
「フロントタイヤをローラーに乗せてください」
の表示が出ています。
前に進みローラーにフロントタイヤを乗せ、ニュートラルにした後、
フットスイッチを踏みます。
そうすると、電光掲示板に「スピードメーター確認」の文字が。
その後、ローラーが回り始めます。
スピードメーターが40km/hになったら踏んでいたフットスイッチ
から足を離します。
そうすると「スピードメーターOK」の掲示。
続いて、「ブレーキ確認」
ローラーにフロントタイヤを乗せたまま、フロントブレーキの確認です。
ローラーが回り始めるので、多少ハンドルを押さえていると、
「フロント、リアブレーキを掛けてください」と表示が出ます。
確認するのは、フロントブレーキですが、飛び出すこともあるので、
リアも一緒に掛けます。 思いっきりです。
そうすると「フロントブレーキOK」です。
続いて、「リアタイヤをローラーに乗せてください」と表示されます。
乗せると「ブレーキ確認」の文字が出ます。
その後、ローラーが回り始め、掲示板に
「フロント、リアブレーキを掛けてください」と表示が出たら、またまた
両方のブレーキを鬼のように掛けます。
そしたら「リアブレーキOK」です。
リアブレーキの点検が終わると掲示板に、
「前に進んでください。」と表示されます。
検査の最後、ライトの確認です。
フロントタイヤを停止ラインに合わせ、停止させます。
その後、光軸検査機が横から張り出してきて、光軸確認。
「光軸(ライト)OK」が出ればラインから出て、検査結果結果を
プリントする機械に検査表を入れて、検査結果を記入します。
何とか今回も1発OKでした。
その検査表を持って、また事務所へ戻ると、そこで車検証と
ステッカーがもらえます。
そのステッカーを貼って、車検はすべて終了。
検査で落ちやすいのは、ライトです。
結構、光軸は走ることで狂っており、オーナーの前に車検をやっていた
オートバイ屋さんもライト×になってました。
また以前、RXで1回目の車検はOKだったのに、2回目に検査官から
「これ輸出用のライトですね」と指摘を受けました。
結局、RXを購入したショップに騙されたのですが、それを言っても
理解するような賢いショップではないので、その頃行っていた別の
ショップにライトを注文し、翌週に再度検査を受けたことがあります。
光軸は狂うものです。
もし光軸が×でも、検査予約時間内であれば再検査をしてもらえるので、
速攻で近くのテスター屋さんで光軸調整をしてもらい(3000円)再テストです。
前回のNinjaが光軸×でテスター屋さんのお世話になりました。
検査は、書類の提出などを含め、通常1時間あれば十分です。
これで、通常6万円かかる車検が、28千円で済みます。
年休を取って32千円のバイトをしたと思えば、儲けた気分倍増です。
さてさて、来年の3月はNinjaの車検。
がんばらねば。
2007/10/02
8. メーターマウント#2
メンテナンス記録6で書いたメーターマウントの折れの修理状況ですが、
接着剤が良かったのか、その後問題は、起きてません。
最近の接着剤の進化には驚きますが、オーナーのようなセルフメンテナンス派には
うれしいことです。
2007/08/16
7. バッテリー
最近、3週間ほど900SSに乗れませんでした。
バッテリーがちょっと心配で、オートバイ小屋の中で始動。
やはりバッテリーは上がり気味で、やっとのことで始動しました。
900SSは、バッテリーが上がって、始動時のセルの回転が弱いと、いわゆる
アフターファイヤーで、マフラーからびっくりするような 「パーン」という爆音
(破裂音)が出ます。
気筒あたりの容積が大きく、シングルプラグのため、バッテリーが上がった時
の燃焼のしにくさはしょうがないことですが、結構近所迷惑です。
プラグを3000kmで交換してはいますが、やはりバッテリーが上がると起きます。
そのため、セルの回りが悪いときは、住宅から50mくらい離れた場所まで押して
エンジン始動。
結構、ご近所に気を使うオートバイです。
2007/07/15
6. メーターマウント#1
本日、ちょっとメンテしようかと思い、900SSを倉庫から出し、まずは掃除を
していたのですがーーーー。
なんと、メーターが、ぐらぐら。
確認してみると、メーターケースのマウント部分が折れていました。
どおりで最近高速走行中にメーターがよく揺れるなーと思っていました。
メーターのケースは表向きはスポンジでまとめたような見栄えですが、
フレームがプラスチックで、それをフロントカウルのフレームへラバーマウントしています。
早速、超強力接着剤をホームセンターに買いに行きました。
耐衝撃性に強く、プラスチックに使える接着剤を購入し、早速接着してみました。
接着時間は48時間とのこと。
来週の土日で確認します。
2007/05/05
5. Mmmmm
本日、静岡の寸又峡へ行って参りました。
朝8時に集合し、例のごとく国道を使って。
そこで感じたことは、やはり900SSでは、低速のワインディングは辛いという事。
もうどうしようもありません。
ただただ我慢のツーリングとなります。
でも、たまにある中速以上の部分では、SSの本領発揮。
道路に貼り付くようなとてもとても気持ちの良いコーナリングが出来ます。
しかし、そろそろ2万km目前。
クラッチ、タペットetc---- いろいろ気になります。
ということで、GWの終わりにショップに持ち込み、相談してみます。
2007/04/30
4. カスタム
900SSは、頭の写真でお分かりのように殆ど改造をしておりません。
理由は、オリジナルを出来るだけ守りたいがためです。
DUCATI用の改造パーツは、他の日本車のものに比べてそれほど高価
と言うこともなく、ネットで探せば今でも結構な改造パーツもあります。
また、詳細の標準SPECを調べてみましたが出力などHPによって違ったり、
よく断定できません。
よって、オーナーのSSの多分普通と違う部分は、下の表の通りです。
エンジン系 |
サイレンサー | ライディングハウス チタン S/O |
| クラッチピストン | モトコルセ | |
電装系
|
バッテリー |
MFバッテリー(現在純正の開放式) |
レギュレター |
ガルーダ製(1500rpmから充電) |
これ以外は、ノーマルです。
上記変更パーツのインプレッションですが、
① ライディングハウス チタン S/O

音は非常に気に入っています。あと酸化変色も。
音質は乾き過ぎず、音量は多少ありますが嫌な音では
ありません。(そうは言っても早朝は、住宅から離て始動が基本)
ノーマルに比べ3000rpm付近でのトルクが落ちますが、5000rpm
以上の吹けあがりは良くなります。
しかし、ノーマルでは出ないアフターファイヤーが「ポンッポンッポンッ」。
しょうがなく、アイドリングの回転数をいじって1000→1200rpm
(あくまでメーター読みです)にしたところ、殆どなくなりました。
② MFバッテリー
メンテナンスが楽です。(それだけ)
規定の16ではなく、12になっているので、多少の軽量化?
③ レギュレター

縦のリブの付いた四角い物体↑
この年式の純正レギュレターは、聞くところによると3000rpm以下では
充電しないとか?(あくまで聞いた話)
確かに、3000rpm付近でずっと走っても、セルの回り方からして、
あまり充電はしてないような気がします。
交換は、30分もあれば完了しますが、コネクターの防水が忘れがち。
配線図どおりに行っただけですが、今のところ問題なし。
これまで街乗りだけでは充分にチャージしていなかったわけですが、
付けた後は街乗り30分くらいをこなした2週間後にちゃんとセルが回り
一発始動します。(いろいろな条件が重なっていますが。)
これまで取り付けた(取り付けられていた)部品は、幸運にも性能的にはずれ
は無く、それなりの効果を出しています。
SSのメンテは、このように基本的に、悪くなったところ、心配なところ、不足を
感じるところにだけ行っています。
ただ最近気になっているところは、フレーム。
ぽつぽつと錆びが出始めており、12年落ちということを考えるとそろそろ
再塗装を考える必要ありです。
2007/01/06
3. Duca 褒め
900SSを購入してから2年半経ちました。
特別、長い距離でもなく、平均的な距離を走っていると思います。
その中で感じたのはやはり走る環境を選ぶオートバイであること。
一番楽しいステージは、中高速コーナーのあるステージです。
低速コーナーでは、そのエンジンの特性(3000rpm以下はダメ)
や、加速性能で勝負になりません。
また、ミッションが高速寄りで、3000rpm6速でなんと90km/h、
4速でも70km/hに 達してしまいます。
よって街中では4速以上のギアには殆ど入りません。
さらに、ハンドル切れ角が少なく、NinjaのつもりでUターンしようとすれば
切り替えし増か、最悪こけてしまいます。
南関東で走るなら、オーナーが楽しいのは伊豆スカあたりのみです。
操作に対して少しの狂いも無くラインが変わる。
だから失敗すると曲がらなかったり、曲がりすぎる。
直線では殆どのリッタークラスに追いつけない。
でもコーナーへの進入(減速)、コーナリングスピードで追いつける場合が殆ど。
そのときのコーナリング中の地面に吸い付くような上質感。
ちゃんと荷重をコントロール出来たときの話ですが。
でもその後の直線では必ず抜かれ、また最初からやり直し。
でも、楽しい。 やみつきです。
たかがエンジン出力86PS。
こちらでコントロールしなければ、ただの遅いオートバイですが、
オートバイに乗せられてしまう日本のSSには無い感覚です。
そんなどーしょうもないDucatiですが一回は乗ってみては?。
(別にDucatiの廻し者ではありませんが。)
2006/12/06
2. 覚悟
イタ車は良く壊れるし、修理代が高く、道楽者の乗り物、なんて言われます。
Ducatiに乗ってると知った途端、放蕩親父を見るような目になります。
Ducatiの維持費は高いか安いか。
乗っている人は、「そう高くは無い」と言っているようです。
確かに壊れなければ、維持費は日本車と同じ位です。
オイルも、特別指定されているわけではありませんし。
また、乾式クラッチもスリッパー式にすれば、エンブレも穏やかになり,
エンジン、駆動系への負担も減ります。
日本車でもオーバーホールを2万キロごとに行う人もいることを考えると、
平均すれば差は無いのかも。
し・か・し
注意しなきゃいけないのは、やっぱりイタ車であること。
ネックはタイミングベルト。
これが破断するとシリンダー、ヘッド、ピストン等総交換で数十万コースです。
(こういうところに、耐久性の無いベルトを使う所がイタ車らしい。)
でも、2年に1回くらい(車検時)に交換していれば、ほぼ大丈夫と聞きました。
(オーナーの年式の900SSだと、部品代+交換賃で2万円弱ですが、水冷になると
5万円位だそうです。)
その位のメンテナンスで、何事も無く10万km近く走る人もいるようです。
その他は当たり外れ。神様に託しましょう。
いくらイタリア人の仕事(職人技の意味だったと思います)とはいえ、そこは人。
やっぱり出てしまいます。
あれだけ品質を問い改善を行う日本の自動車会社ですらあるじゃないですか。
しょうがないときっぱりあきらめましょう。
それでもDucatiに乗りたい。それも調子のいい当たりのDucati。
さてどうやって手に入れるか。
あるショップの人から、
「1万km走ったDucatiなら、最初から調子がいいか不具合は完治したものが多い。
逆に走行が少ない場合は、何かしら問題を抱えていることがある。
あんなオートバイ、調子が悪かったら、手放すでしょ?」
って聞いたことがあります。 御尤もです。
オーナーは、最初から95年式を探してましたので、新車には目もくれませんでした。
試乗はしませんでしたが、信頼できるショップでしたし、もし試乗しても良し悪しは
判断できません。
結局そのショップの「これ調子いい出物ですね」の一言で、購入を決意。
今となっては、それが当たりのDucatiを探せた理由だと思います。
Ducatiの新車の維持費は運で決まります。
Ducatiの中古の維持費はショップとの信頼関係です。
2006/12/02
1. 購入
2004年4月、それまで2年間探しつづけた ’95 Ducati900SS を購入。
’95に拘った理由は、丁稚 虎へ譲るため。
’95は、虎の生まれた年です。
2年間、ショップを探し回ったにも拘らず、見つかるときはあっけないもんです。
何故か行かなかったちゃきちゃき堂に一番近いショップで、店員さんから一言
「ありますよ」。
1週間 考え、購入しました。
走行12000km、フルカウル 赤 。
特に改造した所は無く、唯一ライディングハウスのチタンスリップオンが付いてました。
このSSは、丁稚の虎に譲る予定ですので、大幅な改造はしません。
できるだけオリジナルを守る。 完調を維持する。
このSS、クラッチが、ヘッドが---と世間で言われる割には、これまで2年半の間
(その間6000km走行)、調子を崩したのは、バッテリー上がりと、プラグかぶり1回、
そしてバックファイヤー?防止のアイドリング調整のみ。
なぜか、もう一台の中古Ninjaより手間がかからないのです。-----不思議。
この2年、ショップでの修理は、調子を見てもらうためについでにお願いした
オイル交換だけ。
(オイルフィルターが外れず、お願いしました)
日常整備も、車検もほとんど自分でやっております。
一応走ってますので、あまり間違ってはいないのかと勝手に思い込んでいます。
(ただし、定期的にはショップへ行き、軽く診断はしてもらってます。)
それではこれまで、行ったメンテナンスについて。
(注意:もしかしたら間違ったことをしてるかもしれませんので、やってみようと
思われた方はショップやマニュアルで確認してから行ってくださいね。)
① 準備
参考書::Ducati 600,620,750&900 2-valve V-twins
Hayns Motorcycle Service Repair manual

有名な本です。全部英語です。大変です。
購入の動機は、各部位の締め付けトルクを知りたかったから。
下手してねじ切りでもすれば、涙ものです。
工具 :KTC :必要工具(6角レンチ、ラチェット+ボックスレンチ、他)
?メーカー :オイルフィルターレンチ、リアメンテナンススタンド、エアゲージ、トルクレンチ
こんなところでしょうか。
あと、エアコンプレッサーもあれば便利です。(ごみ飛ばし、エアー入れに)
ちゃきちゃき堂秘密兵器→
② 乗車前
・ タイヤ圧確認 当然ですけど。
・ 各部オイル漏れ確認
フロントフォーク この年式はSHOWA製で、少し安心。
エンジン周り オイルにじみ、漏れはなし。
にじみそうなところを拭き上げてにじみを
見つけやすくしています。
エンジンオイル量の確認は、直立状態で。
・ ボルト類の緩み、ガタ 一度だけ、ステップボルトが緩んでました。
それ以外は、緩んではいません。
締め付けは、プラスチック部分以外は全て
トルクレンチを使用してます。
・ 音 空冷Ducatiのエンジン音を聞いた人は
びっくりしますよね。
「壊れてるの?」といわれたことも。
とにかくドカドカ ガラガラ うるさいのですが、
どんな音が良いか悪いか判らないため、
たまにショップへ行って確認してもらいます。
(これが定期診断)
③ エンジンオイル、フィルター交換
エンジンオイルは、6ヶ月、もしくは3000kmで交換しています。
フィルターは、オイル交換2回に1回行っています。 純正品です。
オイルはMOTUL 300V 15W-50。 これが一番の贅沢。
交換は、ショートツーリングから帰った後に行います。
特に注意することはありませんが、オイルレベルの確認は数回エンジン
を掛けて、確認しながら調整します。
困るのは、ドレンプラグに使用するワッシャ。
特殊形状で、通常のショップでは、手に入りません。
ショップで分けてもらうのも、1個10円(らしい)で言いにくくて−−。
今度は、一度に20枚買おうと思っています。(それでも200円----)
④ プラグ交換
購入後3000km走った頃、始動性が悪化しました。
それまでは、ほぼセル1発で始動していましたが、だんだんセル回数が増加。
最初はバッテリーの充電不足が原因と思い、かからないときは充電してました。
その時、ふとプラグを見てみると、なんとプラグが真っ黒。(はずかし)
多少、ガスを濃くしていることもありますが、やはり街乗りでは辛いようです。
すぐに買い置きのプラグと交換したところ、1発始動となりました。
また、驚いたのは3000rpm付近でのトルク改善。
明らかにトルクが増え、2500rpmでも走れるようになりました。
3000km毎にプラグ交換としました。
プラグは要注意です。
④ ブレーキキャリパー掃除(あくまで私流ですが。)
1年に1回程度行っております。
ブレーキキャリパーをはずし、パッドをぬいた後、中性洗剤+歯ブラシで無心に洗う。
このときブレーキキャリパーを引出すキャリパーツール(プライヤーの逆)が便利です。
洗浄後は、水洗い→エア水飛ばし→拭上げ→ピストンへの潤滑→組付け。
ここで注意するのは、レバー(ペダル)を手ごたえが出るまで何度も握る
(踏む)ことを忘れないこと。
ブレーキキャリパーを取り付ける際にピストンは必要以上に戻っており、そのまま
走り出したらブレーキは利きません。(これでよくぶつかったりする)
ご注意ください。
⑤ ブレーキオイル交換
昔から1年〜2年に一度交換してます。
特別な思い入れや経験があるわけではありませんが、フルードが水分を
吸いやすいことを考えるとこのくらいの周期で交換かなと思っています。
1台(3箇所)分のオイル交換を行うと、次の次の日に握力が---。(歳か!)
⑥ タイミングベルト
車検時に交換(1回/2年)
こればっかりは、手を抜くわけには行きません。
下手すると腰上全交換ですので、ショップ任せです。
⑦ 車検
ユーザー車検の手続き、その方法は色々なHPを参考に。
昨年行った車検では、車検前にライディングハウスのサイレンサーを
純正に戻したのみ。
その他はすべて、上記の日常メンテで通ってしまいました。
以上が通常私が行っているメンテナンスです。 −− 普通でしょ。−−−
ただし、いつ迄もその状態が続く理由もなく、メンテナンスの道をまっしぐら。
2006/11/30



 ←芦ノ湖にて
←芦ノ湖にて