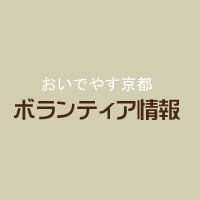おいでやす京都ボランティア情報はボランティアに携わってきたサイト管理者の情報発信のページ。ボランティアに興味ある方に、またボランティア活動を通じて知り合った方に、活動を知ってもらったり、楽しんでもらうサイトです。
僕の知ってるボランティアの起原
かつて大英帝国は、インドをはじめとして世界各地に植民地を持っていました。そこを統治するための軍隊に人手が足りなくなり、大英帝国は軍隊に志願兵を募集しました。
人々は彼らのことを『ボランティア』と呼びました。
やがてイギリス産業革命が始まり、農村から都市へ向かう人々の大移動が起こると、農村は荒廃し各地に強盗や”こそ泥”が出没するようになり、住民たちは村を守るため自主的に自警団を作るようになりました。
人々はその自警団のことを『ボランティア』と呼びました。
都市が膨張する中で、貧しい人違が集まって暮らす場所、スラム街が生まれました。
オックスフォード大学などの学生が、そのスラム街の真中に家を借りて住むようになり、そこから救貧活動が活発に行われるようになったそうです。そんな学生達のことも『ボランティア』と呼びました。
日本ではボランティアと言う言葉は存在しませんでしたが、関東大震災が起きた当時には、4年前の阪神大震災の時と同じく、学生を中心にたくさんのボランティア活動がなされたそうです。
当時は陸上の交通手段は壊滅状態、関東から脱出するには海から逃げるしかなかったそうです。
そうした人たちが中継地点の神戸港に着くと、学生達が炊き出しをして出迎え、被災者を車で神戸駅まで送るなどされていたそうです。
その後も民間の自主的な組織がたくさん活動していたらしく、東京の下町でも貧しい人達の住む地域に学生が家を借り、大学の教授に頼んで来てもらい市民大学を開く、ということも行われていたそうです。
しかし、日本が戦争に向けてひたすら走っていた時代、昭和初期に制定された国家総動員法によって、そんな組織もすべて国の枠組みに組み込まれ、そこからはみ出した民間組織は、反政府組織、危険思想の持ち主として、特高や警察などから弾圧を受けて消滅していきました。
戦後復活したところもありましたが、こうして日本の市民による自主的な活動組織は大きな打撃を受けてしまいました。
終戦後、財閥は解体されましたが、国家総動員法によって作られた国の官僚システムは温存され、戦後の復興期に効率的な資源の再配分をするのに有効でした。
つい最近まで「日本の政治家は三流だけれども、官僚が優秀だから大丈夫」などともてはやされた時期もありましたが、それがただの幻想だと気づくのに時間はかかりませんでしたね。
まさにおごれる平家、久しからずです。(記:サイト管理者)