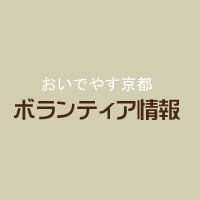おいでやす京都ボランティア情報はボランティアに携わってきたサイト管理者の情報発信のページ。ボランティアに興味ある方に、またボランティア活動を通じて知り合った方に、活動を知ってもらったり、楽しんでもらうサイトです。
メンバーさんとの関わりを考える
1996年5月22日(水)午後10時半~12時半、FV事務局での話し合いを終えた後、北白川の王将で遅い食事をとりながら、微笑、中川、久保、太田の4人で、フリートーキングをしました。(一場面を再現すると…)
中川英夫:FV事務局(社会人) 久保利隆:京都大学 大学院生
微笑美佳子:施設職員(就職1年目) 太田恵子:京都外大
- 中川
- 「みんなの会にはあまりきてないメンバーさんなんやけど、みんなの会で子供扱いされて、いややったというたはるらしい。」
- 太田
- 「え、そんな事言うたはるメンバーさんがいやはるんですか。誰ですか、いや、私誰がそんな風にゆうたはるのか知りたい。」
- 中川
- 「ぼくも本人から励みに自分の気持ちとか、そのときの様子とか書いてもらいたいと思うんやけど、名前は出さずに匿名にして欲しいというたはるねん。ぼく自身はそのメンバーさんのことを子供扱いした記憶はないのやけど、久しぶりに来たみんなの会のときも、一人でぽつんとしてるのが目についたから、何度かそばに行って話しかけた。ぼくがとった行動の中でそんな風に感じる態度があったのか、担当カウンセラーの人の態度がそのメンバーさんのプライドを傷つけたのか、詳しいことはわからない。いまのFVの限界というか、みんなの会をする前日とかに、みんなで集まってケース・スタディが出来れば、一人ひとりのメンバーさんにどう接すればいいかとか言う話もできるけど、今みたいに当日きて何もわからないままメンバーさんについたりしていると、周りの人の接し方とか見て何となく幼児扱いするようなこともあるかもしれない。」
- 微笑
- 「メンバーさんよりも年下のカウンセラーがつくこともあるし」
- 久保
- 「ぼくはずーと疑問に思ってるのですけれども、例えば新人のリーダーとか、まだなんの人間関係も出来ていないメンバーさんに対して、○○ちゃんと話しかけるとか、はたから見て子供扱いしてるように見えるような態度にでるとか、基本的にそれは良くないことだと思うんです。
障害者の人と一緒に街に出ると、社会の人達からの冷たい視線を感じることがあるじゃないですか。実社会の中では障害者という事で軽んじられる風潮があるでしょう。僕たち自身がそういった言葉使いをすることで障害者の人の立場を引き下げるようなことになっちゃあいかんと思うです。僕たちは常に障害者の人の立場を引き上げるように考えて行動するべきじゃあないでしょうか。」 - 太田
- 「引き上げるとか言う考え方自体が差別的と違いますか。メンバーさんを赤ちゃんのように扱ったり、軽く見るのは良くないですけど、メンバーさんとリーダーの関係が一番大切で、社会の人がそれを見てどう感じるかという事は気にしなくてもいいんじゃないですか。社会の人の方が間違った考え方をしているのだから。」
- 微笑
- 「私も学生の頃は久保さんのような考え方も持っていましたけど、今年から福祉施設の職員をするようになって、今はそんな風には考えてません。メンバーさんによっては幼児的な話しかけが必要な人もいるんです。赤ちゃんに対しては幼児言葉というのがあるじゃないですか。赤ちゃんにも普通に話しかけたらいいかというと、赤ちゃんの間はその方が理解しやすい、コミュニケーションが取りやすいからそうするんですよね、障害者の場合もそういうレベルまでしか発達していない人もいるんですよ。いままで○○ちゃんと言われてきて、きゅうに言われ方を変えたら理解できないとか、パニックになる人もいるんです。変えて行くには何年も時間をかけて取り組みをしていく必要があるので、思いつきみたいにそういうことをするのは良くない場合もあるんです。学生なんかは2~3年で卒業したら就職してどこかへ行ってしまうこともあるから、安易にそういうとりくみをすると良くないと思います。
- 久保
- 「いやあ、なんか納得いかんなあ。」
- 中川
- 「三つのパターンがあると思うねんな。①身体的に重度のハンディを持っている人。②身体的にも精神的にもハンディのある、重度重複障害と言われる人。③年を取って呆け老人のようになった人。 ①の場合は年相応の接し方をするべきですよね。③の場合もその方がぼけていたとしても、基本的にそう接するべきだと思うんです。ぼける前は普通に生きてきやはったんやし。あっちの世界とこっちの世界を行ったり来たりしたはるんやし。」
- 微笑
- 「ぼけたお年寄りというのは、ずっとぼけた状態のままじゃなくて、普通の状態に戻ることもあるんですよね、だから子供扱いするような接し方をすると、ひどくプライドを傷つけることがあるので、ちゃんと接するべきです。」
- 中川
- 「②の場合にどうするかなんやけど、微笑ちゃんも、久保さんもどちらも正しいと思うねん。メンバーさんの理解しやすい接し方をするというのもそのとおりやし、20年、30年、その人なりに同じように生きてきたんやし、年相応の接し方をするべきやというのも正しい。『メンバーさんの可能性を信じて』ということをよく言うわけやけど、“こんな事は出来ひん”と決めつけてることも多い。例えばあるメンバーさんにある取り組みをしたとして、半年間はただ混乱するだけかもしれない、でも、1年取り組んだら、3年取り組んだら、出来るようになる。理解できるようになるかもわからん。ただ混乱するだけで、終わるかもしれない。とりあえず大切なことは、みんなでそういった話し合いを繰り返ししていけるような機会をつくってゆくべきやね。」
- 久保
- 「家庭訪問に行かしてもらってる○○さんでも、励みに載っていた以前の家庭訪問記録を読んでみると、今と違って、前向きに取り組みをしていたのがわかる。そのときには出来るようになっていたことが、家庭訪問に行けなくなって、そのままになってる間に、もっとひどい状態に戻ってしまった。そういったことも確かにあるんですね。それだからといって、取り組みをせずに、ただ一緒に遊んでお互いに楽しかったらいいと言うよりは、それでも何かしらの事をした方がいいと思いますけどね…。」
こんな感じで話に熱中するうち閉店。他にお客さんは誰もいなくなっていた。
いつも前向きな気持ちを忘れずに、毎日を過ごしたいと思います。
グループワークの手法を使った勉強会ならみんなの意見を出しやすいんじゃないかという意見もあります。みんなで前向きな意見を出し合って、楽しく、有意義な活動に盛り上げていきたいですね。