豊倉が大学院博士課程に進学したのは1961年4月で、それまでの修士課程在籍2年間に晶析工学基礎として行った過飽和溶液特性とその溶液の中に静置された結晶の成長現象の研究は晶析現象を学習する上では成果があった。そこでは、結晶の成長現象を制禦するのに有効な操作因子を対象に、文献調査や実験的研究を通して検討し、それらを整理した纏めに基づいた、化学工業プロセスの生産工程で妥当な工業晶析操作法の検討を可能にした。そのことを今にして思い直してみると、当時明らかになっていた晶析現象や理論を、工業晶析装置・操作の改善や発展に適用出来る範囲の把握に有効であったが、 大学院入学時に城塚先生から与えられた工業晶析装置の設計に適用できる設計理論提出に向けての前段研究成果としては薄氷を踏む思いであって、それは設計理論の研究に慎重に適用した。
当時の工業晶析現象の研究成果は、かって故桐栄先生が云われていた物理化学の領域における研究成果であって、その適用できる対象は狭く、特定製品の生産に限定されることが多くて種々の晶析操作全般に適用できる化学工学理論として考えるにはまだ多くの研究が必要であった。この段階の工業晶析装置、操作の設計はそれぞれの産業で個々に経験したことを基にさらに工夫重ねて改善してきた過去の経験で体得したknow-how の積み重ねによって行われていた。従って、このようなknow-howの蓄積のない場合の装置・操作の設計を行うことは難しかった。そのような状況を打破して、液相から付加価値の高い結晶製品を必要にして充分な量生産出来るようにすることは化学工業の発展に必要であると城塚先生はお考えになって、晶析装置設計理論の提出を豊倉の博士論文テーマに与えて下さったと思えた。・・城塚先生は1958年に出版された改訂第2版化学工学便覧を豊倉に見せながら、単位操作の各章には設計法の項目はあるが晶析にはない。早稲田で晶析装置設計理論を提出して化学工学便覧に晶析装置設計法に関する項を設けられるようにしようでないかと云われたことを今でも鮮明に覚えている。
このような状況下では晶析操作の目的をどのような結晶製品の生産を対象に するのか決めることは容易でなかった。当時を振り返ると、晶析操作は重要な単位操作であるが、工業晶析現象は化学工学の書物には殆ど記述がなく、実際の工業晶析装置においても何が起こっているかも分かり難くて、晶析研究を行うのは止めた方がよいと云われていた国立大学の著名な先生のお名前も複数聞いたことがあった。その一方で、晶析は20世紀の前半に報告された化学工学で有名なMIT Reportに、将来の化学工業の発展に極めて重要な単位操作であると云われたようであったが、第2次世界大戦が終わっても晶析研究はなかなか活発にはならなかった。そのような状況の中でも国内では、東京大学の宮内先生は昭和20年代の後半に晶析基礎研究を行っておられ、また、東京工業大学の藤田研究室では、昭和30年代前半に谷本先生が第一、第二過溶解度や回分冷却晶析法の研究成果を発表されていた。この頃の化学工学分野における主な晶析研究は結晶成長現象を対象にしたものが比較的多かったが、晶析装置の設計に関する研究は、米国アラバマ州にあったTVA公社肥料総合研究所のP.Muller & W.C.Saemanは1947年にCEPに連続流動層型晶析装置の解析を発表し、また1950年代にはAIChEに連続晶析装置内結晶粒径分布の理論的解析も発表するようになっていた。またヨーロッパではBransomが同じ頃連続晶析装置内における結晶粒径分布の解析を行っていた。
2)大学院博士課程の晶析研究;
2・1) 結晶成長速度に関する研究;
工業晶析晶析装置内の結晶成長速度は、装置内に懸濁する結晶粒径と結晶の生産速度を増大させる観点から研究した。この研究で対象にした系や製品結晶の特性について特殊なものを除くと、工業晶析装置内は多数の結晶が懸濁する結晶スラリー状態の成長速度が重要であると考え、しかも、所望粒径に成長するまでの結晶は結晶破砕など起こり難いような操作状態で可能な限り早い結晶成長速度が期待できるような操作条件を決める研究に焦点を合わせて行った。実験そのものは晶析装置設計理論を工業晶析装置設計に適用する時の確認実験と同時にデータを取得する方法で行った。また、晶析装置内の結晶が懸濁するスラリー溶液に城塚先生が長年研究を行って来られた脈動を付与した時の結晶成長速度への影響も調べ、実験範囲では結晶成長速度を増大するデータを取得して、早稲田大学理工学研究所報告24号、22,(1963)に発表した。
2・2)晶析装置設計理論の研究;
装置設計理論は当面生産しなければならない特定の結晶製品を対象にする場合と広く多種類の結晶生産の対象になる一般的な晶析装置設計理論がある。米国で晶析装置設計理論を研究したW.C.Saeman,は、豊倉が1966~68年に留学したAlabama,州のTVA Fertilizer Development Center で肥料生産工程における晶析プロセス開発を行い、その解析を纏めた論文を上記CEPの1947年に発表していた。しかし、その解析結果はそのままではプラントの実測データと一致せず、そのプラントデータの整理法を提出し、それによる工業晶析装置の設計法を発表した。この当時の様子は、旭硝子研究所の八幡屋正氏が1958年6月に化学工学専門視察団の一員として40日間のアメリカ訪問団に参加された際、ワシントンでの解散後NewYorkで単独にW.C.Saemanに会われて1時間ほど話をされて来られたそうです。この時の話は豊倉の退職記念として1999年3月に出版した「二十一世紀への贈り物 C-PMT」のp.19に寄稿いただいた「晶析のあけぼの」の中に記述してある。豊倉が八幡屋氏にお目に掛かったのは、1961年秋、八幡屋氏が早稲田大学に城塚先生を訪ねて来られた時だった。 当時、豊倉はTVA留学が決まっていたので、城塚先生から教授室に呼ばれて八幡屋氏に初めて御挨拶した。その時八幡屋さんは、TVA訪問時のことを思い出され、「とても良いところだから楽しんで研究してらっしゃい。私も時間があればもう一度ゆっくり行って来たいですね。」と云われたことがあった。以降40年余八幡屋氏には親しくしていただいて晶析の話を良く伺いました。また、元日産化学常務取締役を務められた故小久保先輩は八幡屋氏が1958年に行った訪米帰朝講演を聴いた時、Saemanが理論展開をして提出した設計理論式によって、晶析装置設計は出来るかと尋ねたが、八幡屋氏は明快な返事をされなかったとの話を故小久保さんから聞いたことはあって、晶析装置設計の難しさを教えられたことがあった。
豊倉は、このような状況下で、晶析装置設計理論に基づく工業晶析装置の設計法の研究法を始めた。そこでは、海外誌に発表されていた、工業晶析装置の動向とそこで討議されていた工業結晶製品の特徴を整理して、工業晶析装置で生産される結晶は、比較的粒径の揃った所望粒径の結晶を所定量生産することが重要であることを改めて認識した。また、製品結晶の品質は、結晶を生成する過飽和溶液中に存在する不純物や溶媒、操作温度や過飽和度の影響を大きく受けても、装置スケールアップの影響を受けない場合があって、そのような場合には小型実験装置によるテストで所望製品結晶を生産できる操作条件を決めると、それと同じ条件で同一形式の工業晶析装置を操業することによって所望製品結晶を工業生産出来ると考えた。このような考え方で晶析装置操作法を設計するのに、城塚先生は晶析操作は拡散操作の範疇で考えられるのでガス吸収装置等と同様にHTU × NTU法や理論段数法によって、晶析装置高さを算出できる筈だから考えてみるようにとご指導を受けた。
一方、1960年代の工業晶析装置は20世紀前半に開発されたKrystal-Oslo型と米国Swenson社が20世紀半ばに開発したDTB型が世界で広く使用されるようになっていた。これらの装置は、比較的粒径の揃った粗粒結晶生産するに適した装置であったので、これからも広く採用されると考えてこれらの装置設計理論の提出を研究した。その一方、撹拌槽は構造が簡単で扱い易く、多くのプロセスで使用されており、それを晶析装置として使用した装置の設計法も提出した。
3)連続分級層型晶析装置設計法(Krystal-Oslo型、C.E.C. Crystallizer;
参考文献6;連続式分級層型晶析装置の塔高算出法について、化学工学29巻、9号、698(1996)
参考文献7;連続式円錐形分級層型晶析装置の設計法、同誌、30巻、9号、833,
参考文献A;晶析工学の進歩 P.261~292 1992)早稲田大学豊倉研究室
参考文献B;晶析装置および操作の設計法 ?~?;ケミカルエンジニヤリング (4)p.55,(1966),(5)p41,(6)p.62,(7)p.77,(8)p.42, ( 1966)
本項で扱う晶析装置設計法の詳細は上記参考文献に発表しているので、関係式の誘導、図・表についてはここでは省略して、この研究の本質的な部分の理解をしやすいように概要の記述のみ行う。特にその詳細に関心のある諸氏は参考文献を参照していただきたい。尚、そこに記述している内容について疑問の有る諸氏は、直接豊倉にお尋ね下さい。
3・1 ) 連続分級層型モデル晶析装置の概要;
連続分級層型モデル晶析装置は工業晶析装置の概要を理解しやすいように単純化したもので、装置の形状・装置内の流動状態は理解し易いが、工業装置のそのものと見なしてよい場合もあるが、時として同一視することはできない場合がしばしばある。後者の場合、そのずれが許容範囲を超えると工業装置や操作法を修正して製品結晶が許容範囲に入るようにようにするか、モデルを変更して別の理論の提出をしなければならない。その意味では、ここで提出する理論は、晶析装置設計理論体系確立の一里塚であって、新理論を提出することによって明らかになった新しい課題の発掘とさらに進んだ理論体系構築を示唆するものと考えて研究を続ける。
ここで対象にする工業化モデル晶析装置の主要部分は、装置上部に設置される所定過飽和度の溶液を調整する調整槽とこの系内に添加された種結晶が所望粒径の結晶に成長するまで成長する晶析装置本体とに分けて考えた。
調整槽からの溶液は循環パイプを通して晶析装置本体の底部に供給され、装置本体内を上方に向かって上昇する。その時この溶液は、本体内の結晶を流動層の流動特性に従って流動状態を保ちつつ、溶液過飽和度の低下に相当した溶質量を成長させる。ここで、円筒形状の晶析装置本体を垂直設置すると、装置内を上昇する溶液の空塔速度は装置本体内を通してほぼ一定と考えられるので、本体内の高さ方向の底部からの位置によって決まる結晶の懸濁密度と結晶粒径も流動層の流動特性式を満足する数値になる。ここで晶析装置本体を上昇する溶液の過飽和度は、本体底部は溶液調整槽と同じと考えられるが、装置本体内を上昇するにつれて低下するので、装置本体内に懸濁する結晶の成長速度は、装置底部の結晶は最大で、底部から上方に離れるに従って減少する。したがって、この操作を続けると、装置底部に懸濁する結晶粒径が所望に達したところで、その結晶を取り出すようにすると、底部から取り出された結晶量に応じて、本体内の結晶は徐々に降下する。この操作で装置内に懸濁する結晶が成長する量だけ底部から結晶を排出すると、装置内結晶の懸濁状態や装置内溶液の流動状態は一定な定常状態に保つようになる。その時の懸濁スラリーのそっくり包み込むような装置を設計し、その状態を安定させるような操作条件で操作出来れば、、所望粒径の結晶を所定量生産できる晶析装置は設計できたことになる。
3・2 ) 標記モデル工業晶析装置設計式の提出;
ここで対象にするモデル工業晶析装置は、上記参考文献6に引用されてるSaemanやPulleyの論文等で扱われていたモデル装置(1950年頃一般的に扱われていたモデル)と対比して次のように考えた。まず、本研究では装置高さzの推算式を対象にして、製品結晶や種晶の粒径は所定値で均一と想定したが、装置本体内の塔頂部の溶液濃度については、過去の文献では脱過飽和が進み、ほぼ操作温度の飽和溶液になっているとして扱われていたのに対して豊倉は、装置塔頂部溶液が飽和溶液になるためには、溶液は長時間晶析装置本体内に滞留する必要がり、多くの場合現実的でないため塔部溶液の過飽和度をΔC2として考えることにした。
このように連続分級層型モデル晶析装置を新しく設定し、城塚先生のご指導を踏まえて、ガス吸収装置設計式と同様にして晶析装置本体微小塔高さ dz 当たりの物質収支を取って次式(参考文献6の式(3))を得た。この式は晶析装置内任意位置で着目した dz 高さの円筒における、単位時間当たりの物資収支を次式のように表現したもので、詳細は参考文献を参照いただきたい。
(製品結晶個数に基づいて算出した結晶量の増加)=(|溶液中の溶存溶質量の減少|)=(結晶成長現象による懸濁結晶の成長結晶量) (3)
この式(3)の第3項にある結晶成長速度は、溶液本体内より結晶周辺への溶質拡散現象と成長する結晶表面における結晶成長現象の直列機構を考え、それぞれの物質移動係数や表面晶析速度係数をKD, KRで表すと装置高さzは参考文献6の式(27)となる。
z=H.CG.U. × N.T.U. (27)
ここで、H.CG.U. は式(9)であり、
H.CG.U.=H.T.U. + H.SR.U. (9)
ここで、N.T.U. およびH.T.U. , H.SR.U.は参考文献6の式(11) , (7), (8)となる。 一方、KDおよび流動層の流動特性式として参考文献6の式(13),(14)を適用すると H.T.U.は式(21)より算出できる。
H.T,U.=A1 × C.F.D. (21)
ここで、A1,およびC.F.D.はそれぞれ、参考文献6の式(22),(23)で表される。ここで、C.F.D. は、無次元粒径(y1)= (製品結晶粒径)/(種晶粒径) および 無次元過飽和度(φ) = 塔底過飽和度)/(塔頂過飽和度) にて算出されるが、参考文献6のFig.3の線図にて容易に求まられる。
一方、H.SR.U.は参考文献6の式(24)にて、A2およびC.F.SR.より算出され、それらはそれぞれ式(25)、(26)にて示されている。ここで、C,F.SR.は、C.F.D. 同様無次元粒径(y1)および 無次元過飽和度(φ)によってFig.4にて容易に求めることができる。
3・3 ) 連続式分級層型晶析装置による塩素酸ナトリウム系実験データの検討;
小形連続式分級層型晶析装置における定常操作時の晶析実験データは参考文献6のTable 1に示してある。このデータと化学工学29巻2号、122(1965)に発表した同系の結晶成長速度データを式(9)に適用して、晶析装置内結晶流動層高さを算出しても、実験操作時の流動層高さと一致しなかった。それは、装置内に形成された結晶流動層を構成している懸濁して結晶と流動層の流動特性式を測定した時の粒径分布と異なっており、その上流動層内には大きな循環流が形成されるのが観察されたが、そのうえ、塔頂に近い流動層部には比較的結晶懸濁密の小さい整流部分が存在し、それらを総合的に考えるとモデル装置で想定した結晶懸濁状態は、装置本体部分部分のそれと異なっており、現段階では、この推算値を実験装置のデータにそのまま適用できるようにするには多くの実験・研究を重ねる必要があると考えた。そこで、式(9)をさらに変形して誘導した参考文献6の式(28)より小型連続式分級層型装置データの検討を行った。そこでは、この式(28)をさらにデータの整理に適用しやすいように、結晶成長速度が拡散段階支配と結晶表面段階支配に分けて式(29),(30)を誘導した。常温における易溶溶液からの結晶成長実験では、溶質の拡散段階が支配的に関与することが多いので、Table 1のデータ整理に、式(29)を適用し易いように表示にすると式(33)となる。
(塔高z) = (設計定数α*)(生産結晶量)(生産結晶粒径の4/3剰)(C.F.D.)lnφ/ΔC1 (y1 の13/3剰) (33)
ここで、Φ、ΔC1、y1 はそれぞれΔC1 /ΔC2 、塔底部溶液過飽和度、塔頂部 結晶粒径に対する塔底部無次元結晶粒径である。
式(33)を用いて参考文献6のTable 1 のデータを整理するとFig.7の点綴となり、原点通過の直線で表すことが出来た。そこで、その勾配より設計定数α*求めた。 また、小久保らは円筒形分級層型晶析装置を用いて硫酸アンモニウム系の実験を行い、化学工学28巻2号,p.138(1964)にその実験データを発表している。そのデータを式(33)にて、同様な整理をすると、参考文献6のFig.9に示すような相関を得て、設計定数も求めることができた。
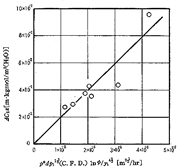 |
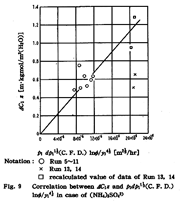 |
| Fig.7 Correlation between ΔC1z and P1*dP11・1/3(C.F.D.)lnφ/y14・1/3 in case of NaClO3 (大きく) |
Fig.9 Correlation between ΔC1z and P1dP11・1/3(C.F.D.)lnφ/y14・1/3 in case of (NH4)2SO42 (大きく) |
4)連続混合型モデル晶析装置の設計法・・Conveying type:連続運搬層型モデル晶析装置およびWell Mixed type:連続完全混合型モデル晶析装置設計法;
3)では、連続流動層型モデル晶析装置の設計法を研究し、A x C.F.C.で晶析装置高さを算出する設計式を提出した。この設計式で重要なA および C.F.C.はそれぞれ、以下の特性を持っているもので、晶析装置設計を容易にした。
Aは、装置形式や操作条件を包括した設計常数、結晶形状係数、装置内許容最大過飽和度、生産結晶量、製品結晶粒径より算出される数値で、個々の装置設計時に規定され決められるもの。
C.F.C.は、装置形式によって規定される無次元晶析操作因子で、装置内の無次元結晶粒径、無次元操作過飽和度、時には装置内無次元結晶密度等で決まる、系や生産量、製品結晶粒径の絶対値関係ない数値で、既に線図化されており、それにて容易に求めることが出来る。
そこで、標記連続混合型モデル晶析装置の設計式を連続流動層型モデル晶析装置の設計式同様、A x C.F.Cで表示するように研究し、Conveying type: 連続運搬層型モデル晶析装置およびWell Mixed type: 連続完全混合型モデル晶析装置それぞれに対して下記参考論文8 および11に発表した。
参考文献8;連続式撹拌層型晶析装置の設計法、化学工学30巻、9号、p.833 (1966)
参考文献11; Design of Continuous Crystallizers, C.E.P. Symposium Series, Vol. 67, No.110, 145, (1973)
これらの論文で提出した装置設計式:
Conveying type: 連続運搬層型晶析装置容積の算出に対して、参考文献11の式(6)をA CBVに、また 式(7) を ( CFC ) CBV に対して提出し、その結果装置容積V’ の算出式を式(8)に示した。
V’=ACBV s × (CFC)CBV (8)
また、参考文献11にA CBF として式(11)を、また ( CFC ) CBFとして式(12)を算出しており、それより装置内溶液循環流量Fの算出式として、式(10)を提出した。
F=ACBV × (CFC)CBF (10)
従って、装置断面積Sおよび高さZの算出式としてそれぞれ、式(13),(14)を示した。
S=F / G Gは空塔速度 (13)
Z=V’ / S (14)
連続完全混合型モデル晶析装置設計法は、装置内の結晶スラリーを均一状態であると設定すると、装置に出入りする結晶数バランス式から算出される結晶モード径と装置内溶液過飽和度を基準にした無次元結晶粒径および無次元過飽和度を考えることが出来る。この無次元値を基準に溶液過飽和度および結晶粒径を議論すると、ここで対象にしたモデル晶析装置においても、上記A x (CFC)形式で纏めた晶析装置設計式を誘導できた。その詳細は、参考文献8に発表した。ここで、参考文献として提示した論文内容は城塚先生のご指導を受けて城塚研究室で行ったものです。城塚先生は、常に学内で研究した成果は報文や解説記事として発表するようにご指導下さった。後者の活動は博士課程最終年度になってから始まった。
5)むすび ;
tc-pmtホームページに、今年の一月以降城塚先生を偲ぶ特集を始め、城塚先生をご存じの他大学の先生方や企業のトップの方々、卒業生等から城塚先生の思い出や、それと関連した私ども弟子達に対する励ましの言葉など頂きました。特に、卒業生から寄稿された記事を読むと、その卒業生と一緒に過ごした研究室時代のことが思い出され、忘れ始めていたことも思い出して、私が化学工学会から学会賞を受賞した時にそれまでの晶析研究を纏めて出版した「晶析工学の進歩」、早稲田大学を退職した時に研究室卒業生が出版した「二十一世紀への贈り物C-PMT」改めて開き直し、城塚先生からご指導いただいたご教訓の深さをしみじみと思い出しています。
私が、物心ついた頃には、中華事変は可成り進んでいたようで、昭和初期の不景気から脱して世の中に明るさが見えたように思えて子供心にも恵まれた時代に育ったようにも感じました。しかし、第二次世界大戦から戦後に掛けての混乱期を何とか切り抜け、大学を卒業した昭和30年代には、日本社会に明るさが蘇ってきて就職も急に好転して日本国中が二桁成長に沸きかえった。当時の欧米先進国の経済成長は一桁の安定成長を続けていて、日本の好況は何時まで続くか一瞬不安を感じることもあったが、借金をしてもそれを返済するときには貨幣価値が変わるので、借金をしない人は馬鹿だとそれが当たり前に思える時代であった。
人は誰しも、その人の生まれ育った境遇や環境によってそれぞれ異なった人生観を持つようになり、その上でその人の道を歩んで一生を過ごす。その過程は人によって異なったものであるが、その人生における区切りになると思う時期に過去を振り返り、その経験を踏まえて未来・将来に新しい可能性が見える次の道を選んで、新しい修行を始める階段を登り始めることは大切である。しかし、その道は紆余曲折があって、時には立ち止まって過去を振り返り、状況に応じて軌道修正をしながら前進することも必要である。
豊倉は、早稲田大学大学院に進学し、城塚研究室の末席に加えて頂いた時、人生の最も大切なこまが回り始めたように思える。それは、Chemical Engineering Scienceに根幹をおいた人間社会の発展に貢献するChemical Engineering Technologyの構築であった。1959年4月は、城塚先生から晶析装置の設計理論を提出して、化学工学便覧に晶析装置設計の項を設けるようにしようと冗談?を云われて頂いた研究課題への取り組みが始まった大切な時期であった。今から思うと、最初に発表した晶析装置設計理論の論文の中で提案した無次元因子(C.F.D.)は1963年初夏の夜、自宅の机の上で運良く誘導出来たもので、具体的な研究成果への起点であった。この無次元因子は博士論文で纏めた連続晶析装置設計理論の全てに適用でき、1965年の化学工学協会関東支部主催の最近の化学工学講習会で講演した時、この講習会の担当幹事をしていた味の素の技術者から、晶析装置設計理論には、変わった纏め方がありますねと、興味をもって云われたのが初めての意見であった。この研究を始めて45年、寝ても覚めても晶析の夢を見続けているが、城塚先生から戴いた大切な結晶核はまだまだ成長させなければならないと思っている。