(山崎 康夫)
|
略歴 |
|
|
|
1981年 |
早稲田大学理工学部応用化学科卒 |
|
|
1986年 |
早稲田大学大学院理工学研究科博士課程修了(工学博士) |
|
|
1985年 |
早稲田大学助手 |
|
|
1987年 |
日本化学工業株式会社入社 研究開発本部 |
|
|
1990年 |
愛知工場 |
|
|
1993年 |
生産管理部 |
|
|
1996年 |
情報システム部 |
|
|
1998年 |
社団法人日本粉体工業技術協会晶析分科会 代表幹事 |
|
|
1999年 |
生産技術部付課長 |
|
|
2000年 |
情報化推進室長 |
|
|
2005年 |
執行役員 技術推進本部長兼技術推進部長兼品質管理部長 |
|
|
2006年 |
執行役員 技術推進本部長兼品質管理部長 |
|
「 tc-pmtの3周年を祝う 」
豊倉先生、tc-pmtのホームページ、開設3周年おめでとうございます。
私は、1981年に学部を卒業してから助手を退職(1987年)するまで豊倉研究室のOB会の運営を担当しておりました。日本化学工業に入社してから数年間は燐酸の精製晶析を研究し1989年にハワイで開催された第3回Pacifichemなどで発表するなど、細々と晶析研究を続けておりました。(今になってみるとこの研究は当社の重要製品の販売に寄与しているようですが。)
豊倉先生が、1992年に化学工学会賞を受賞されその記念会のための組織(会長棚橋純一氏)がそのまま継続し、先生の退職記念会につながっています。
豊倉先生が退職される直前に、日本粉体工業技術協会に晶析分科会を設立するコーディネータに就任され、前記国際会議の際に「時期をみて社会貢献をする必要を感じています」という一言から分科会の代表幹事を拝命しています。
その分科会の設立から5年目に開催した「工業晶析国際シンポジウム」(幕張メッセ、2002)の会場で第一回のC-PMTの会合を行い、1年余のOBを交えた議論の末に、本ホームページ、tc-pmtが設置されました。
というわけで、私が本HPに関わっている事情を概説しましたが、豊倉研究室以外の一部の方々からは、「山崎君が豊倉先生のフォローをするだろう」と申し付けられているのもその理由であります。
以前の私の寄稿にご紹介したように、その後、2003年5月には、C-PMTの会のホームページ、
www.c-pmt.netが設置されていますが、OBによる運営は実現できていません。2006年の5月に若手?有志が再結成され、運営開始する計画をしていますので、今後の活動が期待されています。
2007年の正月に先生から「当初から3年をめどにHPを運営してきた。そこで、これまでの3年間を総括して今後の計画をたてたい。」とのお話があったので、この機会にいままでに卒業生が投稿されてきたものを再度拝読することにしました。
tc-pmtのホームページの解析
どの寄稿も興味深く、また豊倉先生がコンパクトながら細かく記述された前文も味わいがあることを再認識しました。大雑把に(機械的ですが)分類してみると、下表のようになりました。(複数選択あり。豊倉先生・奥様の寄稿文も含む。)
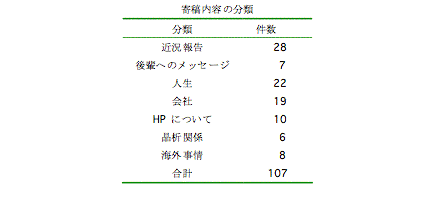
先生からの依頼が、「近況報告など」となっていると思われますので、それが多いのは当然ですが、卒業から現在まで(表には「人生」と表記)に関するものが多いようです。「会社」に関する愚痴とかがあるのかなと思いましたが、そうではなく積極的な内容がほとんどでした。興味深いのは、「海外事情」に関するものがかなりあるような気がしていましたが意外にも8件でした。開始当初、晶析に関するものがある程度よせられるのかと思われた方も多かったのですが、空けてみると6件で、豊倉先生と私のものを除くと少なかったようでした。
3年間どのように継続されてきたのかというと、次図の通りです。
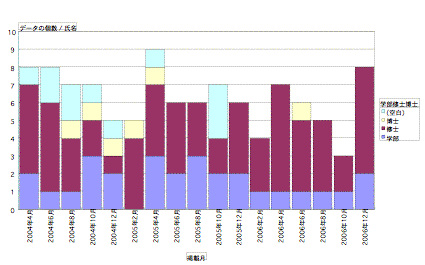
1回当たり平均6件で、少ないときには3件、多いときでも9件と均等に構成されていました。文章量はまちまちですので、件数だけではそのバランスについては語れないのは明らかです。この表では、青色が学部卒、エンジ色が修士修了、クリーム色が博士修了です。これもまた絶妙のバランスになっていることが分ります。なお、寄稿数の割合は次表の通りです。
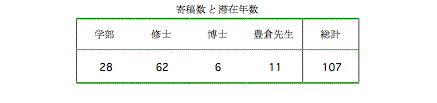
卒業人数は、学部2:修士1の比率で寄稿数の比率はその逆ですから、学部卒の方にもう少し寄稿していただければと思います。
各卒業年度の方々からどの程度寄稿しているのかは、次図に示します。
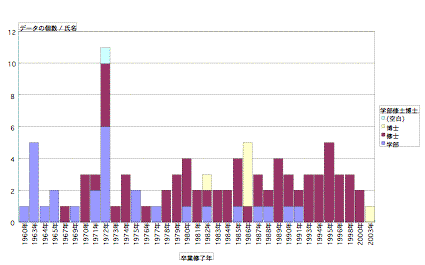
この表では、寄稿のない卒業年度は表示されていませんが、よくみると8割以上の卒業年度の方々から寄稿されていることが分ります。この表は、前表と同じく滞在年数がパラメータとなっています。
各年度1〜2名が寄稿していただいていますが、複数寄稿されているのは一部の方だけでした。また、複数寄稿されている方の年代はどこかに偏ることなしにばらついていることも分ります。
今後の方向性
いままでの寄稿を改めて拝読し分析してみますと、内容のある有意義なものが多く、今後も数年間継続していく価値があるのではないかと強く感じます。
各卒業年度のうちの1〜2名が寄稿していただいておりますが、また寄稿していただいていない方も多いようです。そういった方に寄稿をお願いすることができればよいように思います。例えば、すでに寄稿された方などに連絡役になっていただきお願いすることもよいのではないでしょうか。特に、学部卒の方の寄稿を期待したいと思います。また、すでに寄稿されている方の大半は、1回のみです。2周目以降複数の寄稿をお願いしてもよいのではないでしょうか。
内容も、「近況報告」に限らずに、従来にない新ジャンルの寄稿が期待されているでしょう。 連載されている方もいらっしゃるようですから、これも参考にしていただくとして、複数の方で話題をつないでいくというのもよいのではないでしょうか?
晶析についての寄稿ですが、せっかく「世界の豊倉」研究室のOB会なのですから、もう少し多くてもいいのかもしれませんね。研究発表をするわけではないのですから、抽象的でもよいわけで、情報交換の場になればと願っています。
運営の案ですが、今まで豊倉先生(とお嬢さん)が築き上げてきたものをそっくり真似するのはできそうもありませんので、上記のように、寄稿依頼の仕組みを創るところからはじめたらいかがでしょうか。それから、Webへのアップロードなどは持ち回りで担当すればできないことはないと思います。しかしながら、それぞれの寄稿の前文、紹介文については、当面、豊倉先生にお願いするしかないように思われます。
豊倉先生と同じ頻度と件数を前提とするならば、もう一回りということで、さらに3年間を目途にするというのは如何でしょうか?
以上、今後の取り組みについてご提案しますので、各位の積極的な参画を期待いたします。
top
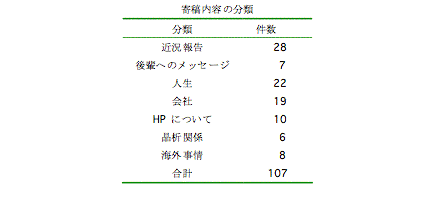
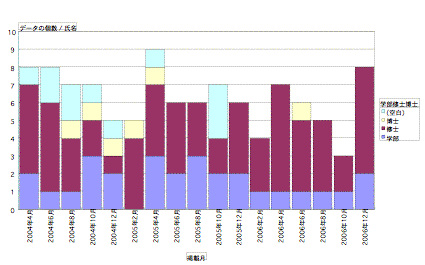
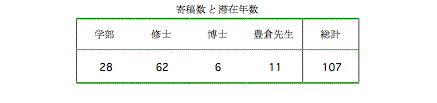
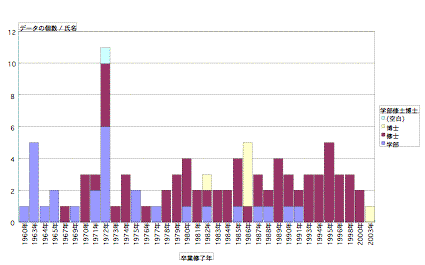
![]()