・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(小川 弘)
略歴
勤務:菱日エンジニアリング(株)研究開発部嘱託 (三菱重工業(株)横浜研究所 顧問)
学歴:早稲田大学第一理工学部応用化学科(化学工学コース)昭和39年(1964)3月学部卒業
職暦:昭和39年(1964) 4月1日 三菱重工業(株)長崎研究所入社
逆浸透法による海水淡水化プラントの開発研究に従事。10T/DパイロットP.
昭和46年(1971)10月1日 同社 広島研究所へ転任
排煙脱硝装置(SCR)の開発研究に参加、事業化成功。(三菱重工のシェア50%)
昭和61年(1986) 6月1日 同社 横浜研究所へ転任
ごみ焼却炉の排ガス処理装置の開発研究及びダイオキシン対策研究に従事。
平成 8年(1996) 10月1日 菱日エンジニアリング(株)に移籍、現在に至る。
ダイオキシン類分析事業及び三菱重工・横浜研究所の研究支援
その他:・1987〜1996 厚生省(現環境省)/(財)廃棄物研究財団:「有害廃棄物(含むダイオキシン類)処理に関するプロジェクト研究」協力(企業)委員
・1997〜2003 厚生省(現環境省)/(財)廃棄物研究財団:「有害廃棄物(含むダイオキシン類)の測定分析法に関する研究」 (幹事会社)協力委員
・ 2000〜2000 環境省委託研究:(財)日本環境衛生センター「ダイオキシン類の簡易測定法に関する技術検討会」(H12〜15) 検討委員
・日本化学試験所認定機構(JCLA) ISO17025技術審査委員(ダイオキシン類測定分析)
研究発表
(1)Chemosphere,Vol.18,Nos.9/10,pp 1785-1797,PCDDs & PCDFs FROM THE MSW INCINERATOR(1989)
(2)Chemosphere,Vol.32,Nos.1,pp 151-157,DIOXIN REDUCTION BY SULFUR COMPONENT ADDITION(1996)
解説
(3)日本エネルギー学会誌、第76巻、第10号、p.950-962、総説ダイオキシン抑制燃焼技術(1997)
(4)Journal of the Society of Inorganic Materials,Japan 7,57-65,解説ダイオキシン類の抑制燃焼技術モ(2000)
著書(一部の執筆担当)
(5)「燃焼生成物の発生と抑制技術」 監修 新井紀男、発行(株)テクノシステム(1997)
執筆担当:第11章 廃棄物排焼 第3節 塩素等のハロゲン化合物の発生と抑制技術
(6)「燃焼圏の新しい燃焼工学」 監修 本田尚士、発行 (株)フジ・テクノシステム(1999)
執筆担当:第4章 廃棄物燃焼のエンジニアリング 第9節 ダイオキシン抑制燃焼技術
(7)「日本の大気汚染の歴史」 編集 大気環境学会、発行 公害健康被害補償予防協会(2000)
執筆担当:第6章 大気汚染制御技術の開発< 6.11.企業における大気汚染対策 7.廃棄物焼却技術
(以上)
ダイオキシン問題へのかかわり
小川 弘
昭和39年に三菱重工業(株)に入社し、長崎研究所に7年6ヶ月、広島研究所に14年8ヶ月、そして昭和61年6月に(出身地は横須賀ですが) 横浜に帰ってきて19年経ちました。小生が横浜研究所に転任した当時、横浜製作所は大手ごみ焼却炉メーカですから、ダイオキシン(DXNs)問題に対応したのですが、DXNs分析結果が思うように得られませんでしたので、自分で分析するようになった次第です。平成8年10月からは三菱重工を卒業し、横浜研究所のダイオキシン分析実施部門を担当している関連会社(菱日エンジニアリング)で働いていますが、三菱重工からの分析依頼だけでは、食べられないので外部からの分析依頼をうけて来ました。ところが、分析業者の過当競争で分析費用の価格破壊が起こり、真面目で正直な会社は赤字になる状況になってしまいました。
小生は化学工学卒のつもりですので、積極的に化学分析をやりたいとは思っていなかったのですが、三菱重工では分析と縁が切れなかった様です。昭和40年代の後半、広島研究所で脱硝触媒の開発研究を進めるのに触媒の組成分析を依頼したのですが、当時研究の主流は排煙脱硫装置開発で、乾式脱硝研究の分析はなかなかやってもらえませんでした。そこで自分で分析したら、化学係長(三菱重工の中国地区の化学分析責任者)にさせられ、昭和53年8月〜昭和57年3月の間、化学分析の変革に努めました。横浜研究所に移っても、まずDXNs分析に着手しましたし、三菱重工最後の3年間(平成5〜8年)は、分析化学小研究室室長(三菱重工全体の分析技術取りまとめ)でした。
横浜研究所でDXNs対策研究を進める都合上、DXNs分析をやりだした1986年当時は、国公立の公害研究所(数年後には皆メ環境モ研究所に名称変更された)では、労働組合からメそんな危険な物の分析などとんでもない。モと一機関(現(財)日本品質保証機構)以外は分析できず、民間会社でも三菱重工を入れて4社しか分析できませんでした。以来10年間、DXNs対策研究のために、DXNs分析を続けた結果、分析分野でも認められたようで、平成12年から16年3月まで環境省の委託研究/日本環境衛生センター「ダイオキシン類簡易測定法技術検討会」の検討委員に任命され、一応メ先生(学識経験者)モの仲間入りを果たしました。
国公立の環境研究所の多くがDXNs分析を始めたのは、平成11年(1999)「ダイオキシン対策関係閣僚会議」で策定されたダイオキシン対策推進基本指針モ(指針にDXNs分析技術の研修機関の設置等が示された)が発表された以降です。DXNs分析は指導的立場にある公的研究所よりも民間の分析会社(約20社)が先行する逆転状態になっていました。
DXNs分析者の安全確保についてはJISや環境省の測定分析マニュアルに記載されていますが、食料油に混ぜて食さない限り、人は消化・吸収出来ないので比較的取扱いは容易です。取扱うDXNs量は、溶剤に抽出するまでは、一般家庭の台所よりは多いがホテルの厨房よりはずーと少ない。抽出後は内部標準物質として13C12-2,3,7,8-PCDDs/DFsを加えるのでDXNs量は増加しますか溶剤に溶けた状態で密閉された容器に入っています。PCDDs/DFsはカラムクロマトや濃縮操作でも気化しませんから、呼吸から被爆する恐れはありません。しかし、DXNsよりも溶剤に注意して、ドラフト内作業にするとか、保護具を着用する等の防御が必要です。
大体、ダイオキシンを地上最強の毒物モと称した先人が悪いのですが、ごみ焼却炉で発生するDXNs(PCDDs/DFs & Co-PCBs)は廃棄物燃焼におけるメ非意図的生成物モです。有機物が燃焼する時に、塩素(塩ビである必要はない。食塩でよい)存在すると、濃度は燃焼条件で変わるが、DXNsが発生する。その時、硫黄が存在するとDXNsの生成を阻害する。私はDXNsの燃焼抑制試験では、模擬ごみとして「大鋸屑+塩ビ粉末」を使っていました。木材を燃やすとDXNsが容易に発生します。
1990年頃のダイオキシン国際シンポジウムにおいて、米国EPAの人は「米国の大気中PCDDs/DFsの1/3は森林火災からくる。」と、カナダEPAの人は「カナダの大気中PCDDs/DFsの1/2は森林火災からくる。」と言ったとのことです。(1995年USEPAのPCDDs/DFs発生源台帳では4位6.9%と発表された。) 薪を燃やすことは、人類誕生の時からやっていることですから、人間は燃焼で生成したDXNsと接して進化してきたはずです。
7〜8年前から環境試料(大気、河川水、海水、底質、水生生物、土壌)中DXNs分析も手がけていますが、「省庁の縦割り体制」を強く感じています。例えば、農地土壌や農地からの流入がある河川水では農薬(CNP、PCP)由来のダイオキシン類が検出されるが、農水省に遠慮してか、環境省からは公式に発表していないようです。また、環境省は、やはり農水省に遠慮してか、魚の可食部を分析し、「水生生物」としており、汚染原因がPCBであるとことも公式には発表していない。しかし、行政官は発表しなくとも、国公立研究所の研究者(公務員)は学会等で4〜5年前から発表を始めましたので、DXNs関連の研究者の間では常識になりました。
小生も7〜8年前から講演ではダイオキシン類汚染の真実を説明する様にしています。講演の前刷りは長過ぎるので環境汚染の部分を付けました。結論としては、ダイオキシン類の人への暴露は、95%以上が食品経由ですから、自治体のごみ焼却炉からのダイオキシン類排出濃度を削減しても、ダイオキシン類摂取量が短期的に低減されないことは当然です。食品中ダイオキシン類は主に、1960〜80 年の間、多量に環境中に放出されたPCP(ペンタクロロフェノール)とCNP(クロロニトロフェン)等の農薬中不純物であるPCDDs/DFsと製品PCBの漏洩によるCo-PCBsから来ていると推定されている。
なお、ダイオキシン類汚染の最大の被害者は我々世代の息子や娘(1965〜1975生)で、最近はその40%まで低減しました。残された問題は保管だけ義務付けたPCBの処理ですが、近々本格的な処理ができる段階になりました。
以上、DXNs分析についての日頃の憤懣を書きましたが、私の専門はDXNsの燃焼抑制技術ですから、DXNsの環境汚染には予防処置に貢献したにすぎません。いまだに、皆様の非科学的な恐怖心に支えられて、DXNsで報酬を貰っていると思うと、心苦しい限りです。2年前から年金受給者ですが、今年度も週2日(火、木)勤務していますので、DXNs、POPs(残留性有機有害物質)、環境ホルモン(内分泌攪乱化学物質)等でお問い合わせ等がありましたら、気楽にご連絡下さい。
[勤務先住所]
〒236−8515 横浜市金沢区幸浦 1−8−1 三菱重工・工作棟1F 菱研開
TEL:(045)776−7536 FAX:(045)776−7539
E-mail:Hiroshi_Ogawa@r.ydmw.mhi.co.jp
[自宅住所]
〒242−0006 神奈川県大和市南林間 6−31−18
TEL:(046)272−7587 FAX:(046)272−7587
E-mail:ogawa_1640@yahoo.co.jp (以上)
ダイオキシン類排出規制の効果と環境汚染
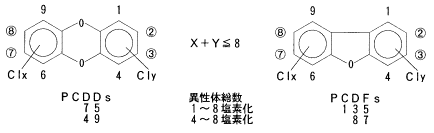
図1 ダイオキシン類(PCDDs&PCDFs)
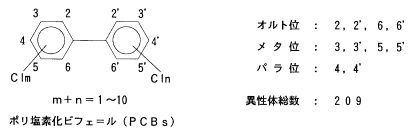
図2 ポリ塩素化ビフェニル(PCBs)
表1 PCDDs/PCDFs及びCo−PCBsの毒性等価係数(TEF)
|
PCDDs/PCDFs
|
Co−PCBs
|
|
〔PCDDs〕
|
I−TEF
WHO'88
|
WHO-TEF
1998
|
〔Non−ortho Co−PCBs〕
|
TEF by
S.Safe
|
WHO-TEF
1998
|
|
2,3,7,8−T4CDD
|
1
|
1
|
*3,4,4',5−T4CB (# 81)
|
−
|
0.0001
|
|
*1,2,3,7,8−P5CDD
|
0.5
|
1
|
*3,3',4,4'−T4CB (# 77)
|
0.01
|
0.0001
|
|
1,2,3,4,7,8−H6CDD
|
0.1
|
0.1
|
*3,3',4,4',5−P5CB (#126)
|
0.1
|
0.1
|
|
1,2,3,6,7,8−H6CDD
|
0.1
|
0.1
|
*3,3',4,4',5,5'−H6CB (#169)
|
0.05
|
0.01
|
|
1,2,3,7,8,9−H6CDD
|
0.1
|
0.1
|
|
|
|
|
1,2,3,4,6,7,8−H7CDD
|
0.01
|
0.01
|
|
|
|
|
*1,2,3,4,6,7,8,9−O8CDD
|
0.001
|
0.0001
|
|
|
|
|
〔PCDFs〕
|
I−TEF
WHO'88
|
WHO-TEF
1998
|
〔Mono−ortho Co−PCBs〕
|
TEF by
S.Safe
|
WHO-TEF
1998
|
|
2,3,7,8−T4CDF
|
0.1
|
0.1
|
*2',3,4,4',5−P5CB (#123)
|
0.001
|
0.0001
|
|
1,2,3,7,8−P5CDF
|
0.05
|
0.05
|
*2,3',4,4',5−P5CB (#118)
|
0.001
|
0.0001
|
|
2,3,4,7,8−P5CDF
|
0.5
|
0.5
|
*2,3,3',4,4'−P5CB (#105)
|
0.001
|
0.0001
|
|
1,2,3,4,7,8−H6CDF
|
0.1
|
0.1
|
*2,3,4,4',5−P5CB (#114)
|
0.001
|
0.0005
|
|
1,2,3,6,7,8−H6CDF
|
0.1
|
0.1
|
*2,3',4,4',5,5'−H6CB (#167)
|
0.001
|
0.00001
|
|
1,2,3,7,8,9−H6CDF
|
0.1
|
0.1
|
*2,3,3',4,4',5−H6CB (#156)
|
0.001
|
0.0005
|
|
2,3,4,6,7,8−H6CDF
|
0.1
|
0.1
|
*2,3,3',4,4',5'−H6CB (#157)
|
0.001
|
0.0005
|
|
1,2,3,4,6,7,8−H7CDF
|
0.01
|
0.01
|
*2,3,3',4,4',5,5'−H7CB (#189)
|
0.001
|
0.0001
|
|
1,2,3,4,7,8,9−H7CDF
|
0.01
|
0.01
|
|
|
|
|
*1,2,3,4,6,7,8,9−O8CDF
|
0.001
|
0.0001
|
|
|
|
*:TEF変更のあったもの
1.ダイオキシン類排出規制の効果
平成11年3月30日に「ダイオキシン対策関係閣僚会議」で策定されたメダイオキシン対策推進基本指針モでは、「今後4年以内に全国のダイオキシン類の排出総量を平成9年に比べ約9割削減する。」と、メ削減計画モにおいては、「平成14年度末のダイオキシン類の削減目標量を843〜891g-TEQ」(平成9年の推計排出量に比して88.2〜88.5%減)と定めている。
排出イベントリーは平成9〜14年の各年の排出量について整備し、改めて推計を行った結果を表2に示した。1) 排出総量は年々減少し、平成15年は、平成9年から約95%減少し、376〜404 g-TEQとなっている。これら削減目標と平成15年の推定排出量とを比較すると、目標を下回っており、削減目標は達成されたと評価される。
表2 ダイオキシン類の排出量の目録(排出イベントリー)[概要]
|
発生源
|
排出量[g-TEQ/年]
|
|
平成9年
|
平成10年
|
平成12年
|
平成14年
|
平成15年
|
削減目標量**
|
|
1.大気への排出
|
|
|
|
|
|
|
|
一般廃棄物焼却施設
|
5,000
|
1,550
|
1,019
|
370
|
71
|
310
|
|
産業廃棄物焼却施設
|
1,500
|
1,100
|
555
|
265
|
74
|
200
|
|
小型廃棄物焼却炉等
|
700〜1,153
|
700〜1,153
|
544〜675
|
112〜135
|
73〜98
|
66〜112
|
|
火葬場*
|
2.1〜4.6
|
2.2〜4.8
|
2.2〜4.8
|
2.2〜4.9
|
2.3〜5.1
|
|
|
産業系発生源
|
|
|
|
|
|
|
|
製鋼用電気炉
|
228.5
|
139.9
|
131.1
|
94.8
|
80.3
|
130.3
|
|
鉄鋼業焼結工程
|
135
|
113.8
|
69.8
|
51.1
|
35.7
|
93.2
|
|
亜鉛回収施設
|
47.4
|
25.4
|
26.5
|
14.7
|
5.5
|
13.8
|
|
アルミニウムスクラップ溶解施設
|
30.7
|
28.8
|
22.2
|
16.2
|
17.4
|
11.8
|
|
その他の業種
|
21.8
|
20.9
|
14.2
|
13.6
|
13.3
|
15
|
|
タバコの煙*
|
0.1〜0.2
|
0.1〜0.2
|
0.1〜0.2
|
0.1〜0.2
|
0.1〜0.2
|
|
|
自動車排出ガス*
|
1.4
|
1.4
|
1.4
|
1.4
|
1.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.水への排出
|
|
|
|
|
|
|
|
一般廃棄物焼却施設
|
0.044
|
0.044
|
0.035
|
0.008
|
0.004
|
|
|
産業廃棄物焼却施設
|
5.27
|
5.27
|
2.47
|
0.856
|
0.599
|
|
|
産業系発生源
|
6.14
|
5.67
|
4.80
|
0.99
|
0.73
|
|
|
下水道終末処理施設
|
1.09
|
1.09
|
1.09
|
0.505
|
0.540
|
|
|
共同排水処理施設
|
0.126
|
0.126
|
0.126
|
0.208
|
0.203
|
|
|
最終処分場*
|
0.093
|
0.093
|
0.056
|
0.021
|
0.020
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(その他:*印の計)
|
3.7〜6.3
|
3.8〜6.5
|
3.8〜6.5
|
3.8〜6.7
|
3.8〜6.7
|
3〜5
|
|
合 計
|
7,680〜8,135
|
3,695〜4,151
|
2,394〜2,528
|
944〜970
|
376〜404
|
843〜891
|
|
|
内,水への排出
|
12.77
|
12.30
|
8.57
|
2.58
|
2.10
|
|
|
対平成9年削減割合(%)
|
−
|
49.0〜51.9
|
68.8〜68.9
|
87.7〜88.1
|
95.0〜95.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**:削減目標量は水への排出分を含めた値
2.ダイオキシン類の耐容一日摂取量(TDI)
|
摂取ルート
|
平成9年度
|
平成10年度
|
|
pg-TEQ/kgbw/日
|
(%)
|
pg-TEQ/kgbw/日
|
(%)
|
|
食品
|
魚介類*
|
1.51
|
( 58.1)
|
1.41
|
( 67.5)
|
|
肉・卵
|
0.42
|
( 16.2)
|
0.31
|
( 14.8)
|
|
乳・乳製品
|
0.19
|
( 7.3)
|
0.17
|
( 8.1)
|
|
有色野菜
|
0.10
|
( 3.8)
|
0.03
|
( 1.4)
|
|
米
|
0.024
|
( 0.9)
|
0.001
|
( 0.0)
|
|
その他
|
0.17
|
( 6.5)
|
0.08
|
( 3.8)
|
|
食品 小計
|
2.41
|
( 92.7)
|
2.00
|
( 95.7)
|
|
環境
|
大気
|
0.17
|
( 6.5)
|
0.07
|
( 3.3)
|
|
土壌
|
0.02
|
( 0.8)
|
0.02
|
( 1.0)
|
|
合計
|
2.60
|
(100.0)
|
2.09
|
(100.0)
|
*:厚生省データにより魚介類の摂取重量は、1日当たり平均 100g であり、そのうち外海魚が3/4、内海魚(内海、
内湾魚及び沿岸魚)が1/4を占めると想定する。
表4 食品からのダイオキシン類1人1日摂取量の全国平均年次推移
|
|
平成10年度
|
平成11年度
|
平成12年度
|
平成13年度
|
平成14年度
|
|
1人1日摂取量
[pg-TEQ/kgbw/日]
|
2.01
|
2.25
|
1.45
|
1.63
|
1.49
|
|
(1.22〜2.77)
|
(1.19〜7.01)
|
(0.84〜2.01)
|
(0.67〜3.40)
|
(0.57〜3.40)
|
3.ダイオキシン類の人体汚染
ダイオキシン類は脂溶性であるため、人間はメダイオキシン類を溶解しているモ油脂を食することにより、摂取し、その大部分は脂肪に蓄積されて体内にとどまる(半減期は約7年)と考えられている。皮下脂肪が母乳になるため、母乳中ダイオキシン類濃度を測定し、人のダイオキシン類蓄積量を総合的に解析する試みが、主に欧米でなされてきた。
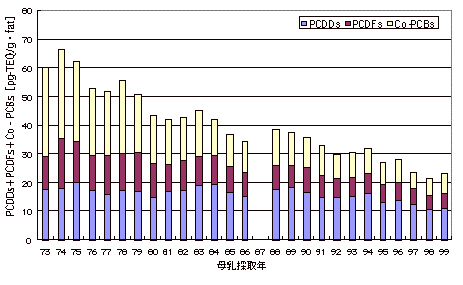
我が国においても、母乳中ダイオキシン類の経年変化をみるため、大阪府公衆衛生研究所において凍結保存している1973年〜1996年の凍結保存母乳を、各年ごとに等量ずつ混合した均一混合物(各年1検体)として、ダイオキシン類濃度を測定し、図3を得た。5)
図3 大阪府における母乳中ダイオキシン類の推移
・1970〜75年の間、人へのダイオキシン類汚染が最大(約60 pg-TEQ/g fat)となり、以後、減少傾向が最近1998年頃(20〜25 pg-TEQ/g fat)まで継続している。
・母乳中ダイオキシン類の減少傾向は、先進工業国に共通して見られ、メ人のダイオキシン類汚染モが先進工業国では同一の原因から来ていることを示唆している。
4.ダイオキシン類の環境汚染
ダイオキシン類の摂取は、表3から、我が国では魚介類経由の割合が多いことが分かっている。水質・底質中のダイオキシン類が、食物連鎖による生物濃縮によって魚介類に濃縮され、最終低的に人間に摂取される。それら環境媒体中のダイオキシン類異性体データはダイオキシン類の由来を反映すると考えられるので、益永らは東京湾と霞ケ浦流域で採取した堆積物と土壌のダイオキシン濃度デ−タを主成分分析分析で解析した。6)その結果、 CNP等の農薬由来のダイオキシン類がまだ多量に農地に残存していることが明かになった。そこで、過去のダイオキシン放出の実態を明らかにするため、農家の倉庫に残された農薬を探し求め、農薬及び製品PCB中ダイオキシン類(PCDDs/PCDFs & Co-PCBs)濃度と年間使用量のデータから積算して得られた放出量の経年変化を図4に示した。7)
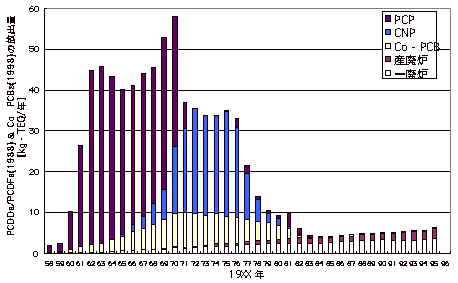
図4 日本におけるダイオキシン類放出量の経年変化
日本における人へのダイオキシン類(PCDDs/PCDFs & Co-PCBs)汚染は、下記のような状況であった、と推測される。
・ 環境中に拡散したダイオキシン類は、食品を経由して、人に摂取された。即ち、PCDDs/PCDFsは主に農薬中不純物から、Co-PCBsは漏洩した製品PCBから、生物濃縮・食物連鎖を経て、人に摂取されたと推定される。
・ 1970〜75年の間、人へのダイオキシン類汚染が最大(約60 pg-TEQ/g fat)となり、以後、減少傾向が現在(20〜25 pg-TEQ/g fat)まで継続している。
・ 1985年以降、PCDDs/PCDFsは廃棄物焼却炉からの放出が主体となったが、1998年からはダイオキシン規制等により放出量は減少に転じた。
5.おわりに
ダイオキシン類の排出規制が平成9年12月1日から開始され、またダイオキシン類による環境汚染についても調査・研究が進み、下記のようなことが明らかになった。
(1)ダイオキシン類の主要な排出源と考えられていた廃棄物焼却炉のダイオキシン類抑制対策が進展し、暫定基準が廃止後の平成15年には、日本のダイオキシン類排出総量が平成9年から95%減少し、政府の削減計画(平成9年に比べて約9割削減する)を達成した。
(2)ダイオキシン類の人への暴露は、95%以上が食品経由であることから、廃棄物焼却炉からの排出濃度を削減しても、日本人のダイオキシン類の摂取量が低減されることはない。即ち、ダイオキシン類排出規制は予防的な対策であったことを意味する。
(3)食品中ダイオキシン類は主に、1960〜80年の間、多量に環境中に放出されたPCPとCNP等の農薬中不純物であるPCDDs/DFsと製品PCBの漏洩によるCo-PCBsから、生物濃縮・食物連鎖を経て、人に摂取されたと推定される。
(4)人へのダイオキシン類汚染は1970〜75年の間に最高(約60 pg-TEQ/g fat)となり、以後、減少し、現在は欧米諸国と同程度の20〜25 pg-TEQ/g fat、最高値の約40%までになっている。
なお、PCBは、長年にわたり保管されているため、漏洩の危険性が増大していたが、平成13年6月に、国はPCB廃棄物処理特別措置法を制定し、平成28年までに処理する制度を作った。これにより、環境事業団(平成16年4月からは日本環境安全事業株式会社)が、処理施設を(全国5ヵ所に)設置し、本年から本格的に処理事業を行うことになった。8)
[参考文献]
1)環境省:環境管理局報告書/水環境部報告書,メダイオキシン類の排出量の目録(排出イベントリー)(平成16年9月)(2004)
2)厚生省:平成9年度食品中のダイオキシン類等汚染実態調査報告について平成10年10月28日(1998)
3)環境庁:関係省庁共通パンフレットダイオキシン類モ,p.9〜10(1999)
4)厚生労働省食品安全部:メ平成14年度食品からのダイオキシン類一日摂取量調査等の調査結果について,平成16年3月16日、厚生労働省ホームページ(2004)
5)厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課:メ平成9〜11年厚生科学「母乳中のダイオキシン類濃度等に関する調査研究」の総括についてモ,厚生労働省ホームページ 平成12年12月28日(2000)
6)益永,中西,桜井,小倉:第7回環境化学討論会講演要旨集,5, p.20〜21(1998)
7)益永,中西:朝日新聞,平成11年3月5日(1999)
8) 日本環境安全事業株式会社JESCO:PCB廃棄物処理事業,JESCOモHP URL:http://www.jesconet.co.jp/,(2005) (以上)
![]()
![]()
![]()