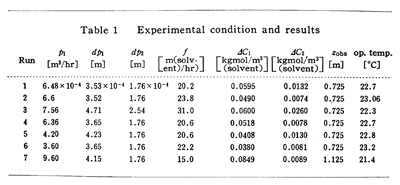1)はじめに :
2009B5-1,1では20世紀前半に提案されたKrystal-Oslo型晶析装置およびSaemanが提出した晶析装置設計理論の概要を扱った。その内容を受けて2009B6-1,1では、成長型連続晶析装置を再検討してその装置の特徴を理解し易く、尚かつ均一粗粒結晶の生産に適し、工業的に広く稼働していた連続式円筒分級層型晶析装置を対象にした設計理論を扱った。この理論の提出は、オリジナルに考案されたモデル晶析装置および操作法を検討して、そこで対象にした晶析装置内の結晶懸濁状態や過飽和溶液の流動特性を、Krystal-Oslo型晶析装置特性を理解しやすいように示した理想モデル装置にて研究して比較的簡単に連続晶析装置設計理論を提出した。そこでは、装置設計に使用される結晶成長速度やその装置で生産される製品結晶等、晶析装置設計理論の研究で検討対象になる全てのものは、研究段階で扱いやすいような理想モデルで示されるものであったが、それはあくまでも工業晶析装置の設計法を確立するための経過段階で設定されて研究されたものであった。今回対象にした2009B7-1,1の記事は、この理想モデル装置を対象に提出した塔高Zの算出式を使用した晶析装置本体の塔高算出法を扱ったもので、簡便に塔高を算出するための設計定数αを提出した。次に、ここで対象にした連続式円筒分級層型晶析実験装置を立ち上げ、そのテスト装置を稼働させて取得したデータより設計定数の算出法を検討した。それより、この方法で設計した工業晶析装置の妥当性も検討して、工業晶析装置設計法提出に向かって歩み出した。
2)連続式分級層型晶析装置の塔高算出
09B6-1,1で誘導した塔高Zの算出式は式(27)で表される。「この式の詳細は(参考文献1・・晶析工学の進歩のp.295)の式(27)(あるいは参考文献2・・化学工学29巻9号、p、697(1965))の式(27)・・を参照して下さい。」
Z = H.CG.U. x N.T.U. (27)
晶析装置の設計式をこのように表現したのは、城塚先生のご指導を受けて、豊倉が研究 を行って提出したのははじめてであった。当時の拡散単位操作の設計理論は、H,T,U, x N.T.U.の概念で体系化されていた関係で、多くの化学工学系研究者・技術者からそれ なりの反響はあった。しかし、充填塔などで代表される拡散操作系装置では高さ方向に 充填材による不規則な分布が無視できると考えられる場合にこの式の意味はあったが、 分級層型晶析装置で懸濁する結晶粒径は高さ方向に分布があり、H.CG.Uを通常の H.T.U.のように考えることは出来なかった。そこで、晶析操作におけるH.CG.U.の物 理的な意味を考えると、結晶製品を規定する結晶粒径および結晶の生産速度を所望値に 維持できるように操作することは必要で、そのような特性値を維持できる結晶を生産で きる最大操作過飽和度、結晶の成長速度を規定する拡散段階の物質移動係数KD(また は拡散係数によって表示できる)および結晶表面における結晶成長速度係数KR 、その 他溶液・固体結晶の物性等があり、それらを除外すると装置内溶液の最大・最小過飽和 度比 φおよび装置内塔底、塔頂部に懸濁する結晶の最大と最小粒径比 y1、装置内塔 頂の結晶懸濁密度(1− e)で表される無次晶析操作特性因子(C.F.D.)および(C.F.SR.) となる。そこで、晶析装置塔高の算出を容易にするために、対象とする系の結晶成長速 度を拡散段階律速と表面晶析段階律速のそれぞれに分けて考えるとそれらは式(29)、 (30)となる。
拡散段階律速結晶成長速度の場合 :
Z = ( αD ) f’(種晶粒径の13/3剰)(C.F.D.)lnφ/ ΔC1 (29)
表面晶析段階律速結晶成長速度の場合
Z = ( αR )f’(種晶粒径の4剰)(C.F.SR.)lnφ/ ΔC1 (30)
ここで、(αD )および (αR )は所望結晶製品を生産する晶析装置塔高を推算決定するための設計定数である。この設計定数に含まれる特性値は参考文献に掲載されてる式(27)と比較すると明らかなように系の物性値のみで表される特性値であるので、操作条件や装置形式・操作法が同じ晶析装置において取得された数値は、スケールアップの影響を殆ど受けないと考えている。
・・・・・・・・一般的に考えると、晶析装置の装置特性も他操作の化学装置同様スケールアップの影響を受けると考えられるが、晶析操作において安定した結晶製品が生産されるような操作条件は一般に狭く、通常そのような結晶製品が生産されるばあいは、装置全体がこの狭い操作範囲に収まっている場合である。しかも、装置内に懸濁している結晶は急激に変化するような流動状態では、結晶破砕等の複雑な現象が起こり易く、そのため、晶析操作に精通した技術者は装置内の結晶スラリーを穏やかな流動状態で操作するように心掛けており、装置のスケールアップの影響は受けないように操作されることが多い。・・・・・・・・
一方、小型晶析装置で結晶を生成させ、ほぼ定常状態とみなせる結晶得られる時、そのような結晶が生成したような操作条件下で得られたデータから算出された設計定数を用いると、多くの場合スケールアップの影響は殆ど受けない。しかし、装置形式の異なる装置や操作条件の大幅に異なる操作で得られる結晶粒径分布や個々の結晶に着目すると析出結晶の物性値が大幅に異なることがある。特に結晶粒径分布が異なる場合、その分布を持った結晶を表す代表粒径はどのように決めて測定したものかをよく確認して設計定数を算出し、その定数が目的製品結晶を生産する装置の設計に適用してよいことを検討してから設計に入る必要がある。
工業晶析操作で対象になる結晶の成長現象は、結晶周辺溶液内の結晶析出成分の拡散現象が律速になる場合と成長する結晶表面に拡散してきた結晶析出成分が、成長する結晶格子への配列になる表面晶析現象が律速になる場合、およびこの両段階の律速寄与がほぼ同程度になる場合がある。一般に溶解度の大きい系の結晶成長現象では拡散段階が律速となる傾向があり、それとは反対に溶解度の小さい系では表面晶析段階が律速になる場合がある。また、操作温度が高い場合は拡散段階が律速になる傾向があり、融液がそのまま結晶化して成長する場合は、結晶が析出する時に発生する結晶化熱を効率的に除去することが晶析速度に影響することがある。連続分級流動層型晶析装置の塔高を算出する場合、式(29)および(30)の双方の式を用いて設計定数( αD )および( αR )を求め, その数値の散らばりの小さい方の式を使用して塔高を算出しなければならない、その実例は化学工学37巻4号、416(1973)に故青山吉雄氏と豊倉が連名で発表した論文「分級層型晶析装置による硫酸ナトリウムの晶析ーパイロットデータより工業装置へのスケールアップ」に実際に行った計算結果も示されている。
3)連続円筒分級層型パイロットプラントによる塩素酸ナトリウム実験と実験結果 :
朋子さんへ・・・今回は出来れば晶析工学の進歩 p296のFig.6 ・・実験装置図とTable 1 のExperimental condition and resultsの各1枚 および p.297 のFig.7、の1枚の計3枚です。その内p.296の2枚は、3 )章の適当な所に, p.297 のFig.7、の1枚は4 )章の適当な個所に入れてください。仕上げる時はここの括弧内をすべて削除してください
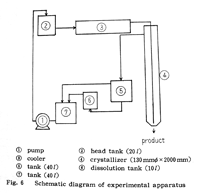 |
| Fig.6 Schematic diagram of experimental apparatus(大きく) |
実験に用いた分級層型装置およびそのフローの概要はFig.6に示す。Fig.中![]() で示された晶析装置本体は垂直円筒管で、貯槽タンク
で示された晶析装置本体は垂直円筒管で、貯槽タンク![]() の所定濃度・温度に調整された塩素酸ナトリウム水溶液は循環ポンプ
の所定濃度・温度に調整された塩素酸ナトリウム水溶液は循環ポンプ![]() にてヘッドタンク
にてヘッドタンク![]() 、熱交換器
、熱交換器![]() 晶析装置本体
晶析装置本体![]() を通過して系内を循環するように操作した。この溶液流は熱交換器で所定の過飽和溶液になるように調整され、晶析装置本体内の下降管を通って装置本体底部に供給され、そこより下降管と装置本体壁間の空間部分を上昇して塔頂部より溢流してタンク
を通過して系内を循環するように操作した。この溶液流は熱交換器で所定の過飽和溶液になるように調整され、晶析装置本体内の下降管を通って装置本体底部に供給され、そこより下降管と装置本体壁間の空間部分を上昇して塔頂部より溢流してタンク![]() に戻した。この晶析装置本体より溢流した溶液は温度を適度に上昇させ、装置本体内での結晶成長による濃度低下を殆ど無視できるように溶液中に懸濁している微小結晶を溶解して補償操作を行った。また、実験を開始前には、種晶として操作中に塔頂より供給する微結晶を充分な量篩い分けして、定常操作に備えた。
に戻した。この晶析装置本体より溢流した溶液は温度を適度に上昇させ、装置本体内での結晶成長による濃度低下を殆ど無視できるように溶液中に懸濁している微小結晶を溶解して補償操作を行った。また、実験を開始前には、種晶として操作中に塔頂より供給する微結晶を充分な量篩い分けして、定常操作に備えた。
実験は貯槽タンクの溶液をポンプ![]() によって循環し、系内各所の温度が安定晶析操作可能と判断できるように安定した段階で溶液の循環流路のバイパスバルブを開いて晶析装置本体への溶液供給を一時停止して種晶を装置底部に供給した。この時供給した結晶量は、その操作で定常になった時に予想される装置内懸濁量の約1/5程度であった。この所定量の結晶を供給した段階で、晶析装置本体への溶液流入を徐々に増やして、晶析装置本体内の底部に入れた結晶を穏やかに流動させた。この時、本体内の結晶の流動状態を注意深く観察しながら、バイパスバルブを徐々に締めて晶析装置本体への溶液流入を開始した。この時装置底部に沈積していた結晶堆積表面がほぼ水平面を保ちながら徐々に上昇するように注意しながら、溶液流量を静かに増大させた。このように操作して溶液流量を当初の設定値に近づけ、結晶の流動層高がほぼ実験開始前に設定した高さになったところで晶析装置本体へ供給する溶液流速を一定値に固定した。それ以降は装置内に形成された流動層高は装置内に懸濁する結晶成長量に応じて緩やかに上昇を続けた。このような操作が安定した段階で、本体内の結晶流動層高さが一定に保たれるように装置底部のバルブを間歇的に開いて結晶を取り出し、その結晶スラリーを恒温槽中に静置したメスシリンダー中に入れ、結晶抜きだし時間に対する結晶堆積量を測定した。その実測値をグラフ用紙に点綴すると、実験当初は緩やかな上昇曲線を描いて上昇を続けたが、その曲線の勾配は次第に大きくなり、次第に一本の直線に収束した。その直線が充分収束したと判断された段階で、この直線の勾配よりその実験テストの結晶生産速度を決定して、実験を終了した。この実験終了段階で装置本体内の流動層上部および底部の溶液、および結晶を採取し、溶液濃度および結晶の粒径分布を実測した、この一連のテストで得られた実験結果はTable 1 に示す。
によって循環し、系内各所の温度が安定晶析操作可能と判断できるように安定した段階で溶液の循環流路のバイパスバルブを開いて晶析装置本体への溶液供給を一時停止して種晶を装置底部に供給した。この時供給した結晶量は、その操作で定常になった時に予想される装置内懸濁量の約1/5程度であった。この所定量の結晶を供給した段階で、晶析装置本体への溶液流入を徐々に増やして、晶析装置本体内の底部に入れた結晶を穏やかに流動させた。この時、本体内の結晶の流動状態を注意深く観察しながら、バイパスバルブを徐々に締めて晶析装置本体への溶液流入を開始した。この時装置底部に沈積していた結晶堆積表面がほぼ水平面を保ちながら徐々に上昇するように注意しながら、溶液流量を静かに増大させた。このように操作して溶液流量を当初の設定値に近づけ、結晶の流動層高がほぼ実験開始前に設定した高さになったところで晶析装置本体へ供給する溶液流速を一定値に固定した。それ以降は装置内に形成された流動層高は装置内に懸濁する結晶成長量に応じて緩やかに上昇を続けた。このような操作が安定した段階で、本体内の結晶流動層高さが一定に保たれるように装置底部のバルブを間歇的に開いて結晶を取り出し、その結晶スラリーを恒温槽中に静置したメスシリンダー中に入れ、結晶抜きだし時間に対する結晶堆積量を測定した。その実測値をグラフ用紙に点綴すると、実験当初は緩やかな上昇曲線を描いて上昇を続けたが、その曲線の勾配は次第に大きくなり、次第に一本の直線に収束した。その直線が充分収束したと判断された段階で、この直線の勾配よりその実験テストの結晶生産速度を決定して、実験を終了した。この実験終了段階で装置本体内の流動層上部および底部の溶液、および結晶を採取し、溶液濃度および結晶の粒径分布を実測した、この一連のテストで得られた実験結果はTable 1 に示す。
・・・この実験で採取した結晶スラリーは恒温槽中に静置したメスシリンダー中に蓄積させたが、それは実験操作中にスラリー温度が変化することによって採取した結晶が成長したり、溶解したりするのを避けるために行ったもので、実験室の温度変化に注意して対応を取った。また、本実験系では別に200リットルの溶液貯槽タンクを用意し、そこに充分な量の供給溶液を事前に調整して、実験進行中の溶液濃度減少の影響を無視できるように操作した。ここでは、操作中に起こるかも知れない万一の場合に対しても予想される範囲で対応出来るように事前に用意しておいた。本実験では製品結晶と種晶結晶の粒径はそれぞれモード径にて表示したが、この実験においては定常操作時のデータを実測したが、そのため、装置内より製品結晶として抜き出し結晶数に相当した種結晶数として、製品結晶量の(種晶粒径/製品粒径)の3剰倍の種晶を間歇的に装置上部より供給した。しかし、装置内に形成される結晶流動層上部には殆ど結晶の確認できないような透明溶液ゾーンが存在していて、添加種晶は装置内に形成している結晶流動層に吸収されるものもあると考えられたが、また一部の種晶は装置から溢流される溶液に流されて装置本体から排出されると思われた。一般の工業操作では、このような種添加を行いながら操作されることは稀で、多くの場合装置内で自然発生的に生成される2次核などによって自動的に供給されると考えられている。その検討は後日、2次核発生現象の研究を行った後で行う予定である。
4)塩素酸ナトリウム実験:データからの円筒分級層型晶析装置塔高の算出 :
豊倉らが別に行った実験では、塩素酸ナトリウムの結晶成長速度は結晶周辺の溶液流動の影響を受けていたので、この系の結晶成長速度は拡散段階支配の可能性は大きいと考え、式(29)より得られる式 (29)’
(αD )= f’(種晶粒径の13/3剰)(C.F.D.)lnφ / ΔC1・ Z (29)’
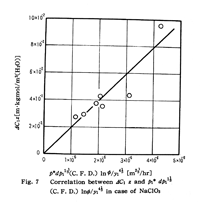 |
| Fig.7 Correlation between..... 大きく) |
を用いてTable1の各実験ランデータより f’(種晶粒径の13/3剰)(C.F.D.)lnφおよび ΔC1・Z を算出して、Fig.7のグラフに点綴した。この点綴は式(29)および(29)’ が適用できると考えると原点通過の直線で表されることになり。その直線の勾配より連続式分級層型晶析装置塔高を算出する設計定数(αD)は次式となった。
(αD )= 2.0 x 10の4剰 [ kmol・hr/ mの4/3剰・mの3剰(H2O)]
この数値を式(29)に代入すると所望塩素酸ナトリウム結晶を所定量生産する連続円筒分級層型晶析装置の結晶流動層高は算出出来る。
5)むすび
今回は前号の記事(2009B6-1)で紹介した早稲田大学で提出した晶析装置設計理論を検証するため、研究室に立ち上げた連続円筒流動層型晶析装置で実測した塩素酸ナトリウム晶析実験データの整理に適用した結果を纏めた記事です。豊倉はここに記述した経過を辿って研究を進めることが出来たことは大学工学部に席を置いて研究した者として本当に恵まれたと痛感している。その一方で城塚先生にお掛けしたご苦労を最近になってやっと少し分かるようになった気がします。大学研究の使命は広く世の中の発展に貢献できる理論を提出し、それを発展させることによってその研究の意義を高めることと思い研究を続けてきた。幸い、大学院に入学して、丸4年を経過した年の春、無次元過飽和度・無次元粒径に基づく晶析操作特性因子を提出出来て、20世紀前半に提出されたKrystal-Oslo型晶析装置によって代表された連続円筒流動層型晶析装置設計理論の骨子を提出した。その時業者に発注した連続晶析実験装置も完成し、そこで提出した設計理論を適用して実測データを纏めて、同装置の塔高算出法を提出出来た。
この一連の研究では、連続円筒流動層型晶析実験装置で実測したデータの整理法等も提出できたが、まだ、工業装置の設計に実際使用できるか否か確認することは出来なかった。しかし、この時期は日本化学工業の発展期に当たり、日本の造船企業は化学装置の製造を活発に始めた時期と重なり、欧米プラントメーカーから将来有望な化学産業における生産技術の日本への移転が始められた時期で、晶析装置はその一つとして着目された。これらの日本企業の中には晶析装置のパイロットプラントを建設して、その技術開発を自力で始めるところもあった。これらの企業技術者の中には早稲田大学で提出した晶析装置設計理論を学んで、自社晶析技術の開発を行うところも出てきた。これら日本企業の動きによって、早稲田大学の晶析研究は産業界のニーズに応えることも視野において、これら生産技術の発展に貢献する工学晶析基礎理論の確立についての研究を進め、その経験を生かして、1966年12月から1968年12月に掛けての欧米留学を行った。次号以降に、その渡米までに行った晶析研究活動を中心に紹介する。