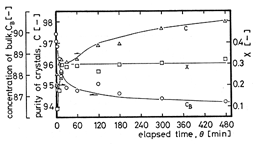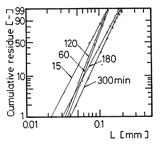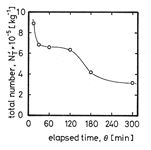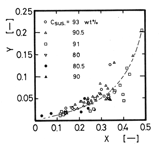前号では1969年に研究を開始いたナフタレンー安息臭酸からのナフタレンの精製晶析に関する研究成果を紹介したが、当時は晶析による精製分離法に対する化学工業界の認識は未だ低く、それをどのように発展させるかは研究室の課題であった。この分野の研究については、アメリカの帰国後、城塚先生から意味深いお話し、「自分の研究分野で成果を上げることは重要なことであるが、その(晶析)分野の全ての研究課題で成果を独占してはならない。研究を発展させるためには日本国内の晶析研究を独占して、他の研究者の研究意欲をそぐようにしては結果的にはグループの発展、日本の晶析グループの発展にはならないから心して活動するように」を伺ったことがあった。この内容は当時二つの意味「一つは研究課題そのものについてであり、もう一つは日本国内を複数の地区に分けてその全てにおいて」であった。豊倉が研究を開始した頃の晶析分野のメインテーマは「早く晶析装置の設計法を確立せよ」と言われていて、(1970年代に当時米国・Swenson社晶析担当のBennetからそれはAmbitiousで不可能だというような手紙をもらったことがある。)晶析に関心のある研究者はその命題に何らかの成果を出すことを目標に研究していた。その様な状況下で早稲田グループは他の研究者に先駆けて、幸運にもある程度の成果を上げ得たので、豊倉はこれからの晶析研究の課題は晶析法による精製分離法であろうと云っていた。しかし、豊倉はこの研究課題に対して一歩引いた気持ちで、研究室で博士課程を目指す学生に精製晶析の研究をするように進めたが、豊倉自身は日本の研究が沈滞するように感じた時はそれなり大学院学生に協力して研究をするように心掛けていた。
1970年代の後半には、日本国内では学会主催や業者による講習会の開催が頻繁に行われていて、晶析は化学工学系の新しい分野の単位操作として日本各地で頻繁にテーマにされ、豊倉は講師として招かれた。このような講習会では、企業技術者の困っている問題についてしばしば質問を受けたが、その中に大手の石油精製企業の技術者からスイスのタンクメーカーが開発したMWB精製晶析装置についての意見を求められたことがあった。実は、その時豊倉はこの晶析装置のことを知らなかったので、どうゆうものか企業技術者に教えてもらった。その時、話を聞くとそれは豊倉研究室で1969年始めたスケール状精製晶析装置を工業化したようなもので、1974年にAIChE National Meetingで豊倉が発表したデータに基づいて意見を述べたことがあった。その講習会の時には豊倉が1980年5月から早稲田大学在外研究員としてヨーロッパに4ヶ月出張する予定の話をしたら、是非その装置についても様子を調べて欲しいと云われたことがあった。豊倉はその後予定通りヨーロッパに出張したが、その出発前に既に親しくなっていたイギリス、University College LondonのMullin教授にヨーロッパ滞在中にヨーロッパの晶析研究の活発な企業を訪問したいにで紹介して欲しいと尋ねたら、その中にスイス、BucksにあるMWB社があり、訪問することが出来た。
1980年7月初め、スイス東部BucksにあるMWB社を一人で訪問した。当日は午前中にBucks駅に汽車で着く話をしておいたので、Buchs駅のホームにあるベンチに座って待っていると、初対面のMr.Oskar Fischerがニコニコしながら現れ、Prof.Toyokuraかと聞かれた。この時、この国は日本人が来ると云うだけで簡単にホームの上で会えるのがと不思議に思いながら、劇的な面会をした。後で聞いた話だが、彼の奥さんは日本人で、日本には10年くらい駐在したことがあったようで、日本のことは良く知っていた。MWB社は駅前にあり、歩いて数分のところにあった。そこでは、形どおりMWB精製晶析装置の説明を聞かされ、この装置が如何に優れた装置であるか基本原理に基づいて説明してくれた。その説明が蒸留塔と外見が同じであったせいか、多くの化学系の技術者は蒸留塔を知っているためか、この装置を蒸留塔と対比しながら説明された。そのため、豊倉は、早稲田大学で独自に晶析研究をしており、その研究成果に基づいてこの装置内の現象を考えると、晶析は蒸留操作と異なると言って1976年のAIChE Symposium Seriesに発表したデータに基づいて豊倉の考えを説明した。その中で、豊倉らが提出した結晶中からの不純物拡散モデルを説明し、実際の操作では発汗現象が起こるので精製効率はそれよりさらによくなるので、MWB社のデータは充分信頼するに値するとも伝えた。その時、Oskarは自分はセースエンジニヤーなので学問的なことは発言を控えるが、実は、この技術の発明者であるMr.Saxerは現在出張中で、今日の3時過ぎに帰社するので技術的討論はそれからにしてくれと言われて、隣駅Sargansの丘の上にある昔、ローマの砦であったレストランに案内されて昼食を取った。
ゆっくり食事をしてから時間を見計らって、眼下にあるSargans駅にMr. Saxerが乗った汽車が到着するのに合わせて行き、そこでMr.Saxerを拾って本社の会議室に帰って技術討論を再開した。そこでの議論では、Mr. Saxerは発汗操作の効果を既に経験していたように豊倉の解釈に賛成し、討議は順調に進んだ。この訪問以降豊倉はMWB社とは親しい関係が出来、その後、Sulzer Chem. Tech社と合併してもその関係は継続して今日に至っている。
2)スケール状晶析法と多結晶懸濁晶析法とによる精製晶析法の検討:
1980年9月、ヨーロッパ滞在4ヶ月の在外研究終了後、豊倉研究室でこれまで行ってきたスケール状晶析法による精製晶析法とは別に、通常の懸濁多結晶系の精製晶析操作法の研究を行うことにした。そこで、工業晶析装置の選定を考えた時に必要な工業操作条件に対するそれぞれの晶析操作の特徴を検討する。
i )工業晶析装置・操作法選定の必要条件とスケール状結晶生成操作法の特徴:
工業装置選定の必要条件は、選定された装置は対象とする系に対して安定操作をすることが容易で、しかも工業装置として要求される必要量の精製製品を生産するのが可能なようにスケールアップすることが簡単に出来、その上、設備建設費および運転費が安価で所望製品を安価に生産できることである。スケール状晶析装置は先月号(2006B-1,3)の実験装置(詳細はオリジナル文献のAIChE Symp. Series, vol.72, Nov.153, p.53(1976)に示した装置図を参照)に示したものを工業操作しやすいように製作した装置で、その主要部分はように円筒管内部に所定温度の冷媒を流し、それによってその円筒管外側表面に沿って濡れ壁状に流下する融液を冷却し、円筒管外部表面にスケール状に所望結晶を析出させるものである。所定量の結晶が析出したところで被精製融液および冷媒の供給を停止し、供給融液の未晶析流体を所定のタンク貯槽に集める。その段階で冷媒を加熱媒体に切り替え、円筒管外表面に析出したスケール状結晶を融解してその純度の対応した貯槽タンクに収納する。この時融解融液は供給原料融液に対して純度がよく、通常それを数回程度繰り返すことによって所望濃度の精製融液を得ることが出来る。この切り替え直後に融解した初期融液の中には結晶中に包含された不純物が濃縮された融液が優先的に包含されており、それを分別することによって製品側に収納する融液純度を大幅に向上することが出来る。このような操作上の工夫をすることによって、一回の晶析操作による製品純度は著しく向上し、精製コストの低減を図ることが可能になることがある。その操作法においては、融液が過飽和状態になるところは装置本体内の結晶を析出させる部分のみであり、操作中に結晶の析出によって融液の流動を閉塞させる箇所がない。そのため、結晶の析出速度を速くするために冷媒温度を低くしても結晶析出による閉塞の心配は殆どない。また、この操作では、製品は結晶を融解して融液として取り出し・輸送するので製品分離にための濾別操作も不要で、配管中の閉塞もなく安定操作に適した装置と考えることが出来る。装置の処理量に対応したスケールアップは円筒晶析管の長さは2種類に規格化しており、実質的にはその本数を変えることによって、比較容易に行うことが出来る。その結果この装置は大型装置が立ち上げられており、広く世界中の工場で使用されるようになっている。
ii )多結晶懸濁形式晶析装置による精製晶析法:
通常の晶析法では多結晶懸濁形式の晶析装置が広く用いられており、その意味ではその形式の装置が広く用いられている。それは、通常の晶析法に精通している企業技術者は晶析操作特有の難しさに対する問題は解決済みとの判断による。その操作法では、装置内に懸濁している結晶表面積の広さが結晶の成長速度、言い換えると結晶の生産速度を大きくしている。従って、操作過飽和度を大きく取れない場合には多結晶懸濁系が有利である。しかも、その操作で所望純度の粒状結晶を生産する場合はこの操作法は明らかに有利である。しかし、その純度が不十分な場合には晶析装置内操作法を工夫するか、晶析装置より結晶を取り出した段階で、別の開発されたピュリファイヤーを使用しなければならない。このピュリファイヤーについても、基本的な現象は豊倉研究室で研究されており、それについての検討は次の項で扱うが、最近の工業装置は化学工学便覧等でも紹介されてるので、必要であればそれらを参照して欲しい。
3)ベンゼンーシクロヘキサン融液系からの精製ベンゼン結晶の晶析:
前号(2006B-1,3 晶析法による分離法(1))では常温より高い温度で操作されるナフタレンー安息香酸融液よりナフタレンの精製晶析を対象に研究を行ったが、ここではほぼ室温付近で操作されるベンゼンーシクロヘキサン融液系からの精製ベンゼン結晶の晶析を対象に研究を行った。このような融液系の晶析(溶媒晶析)では、系に多量存在する第1成分が晶析対象になるが、通常の晶析で対象にする溶媒に溶存している溶質の晶析は後の「(4) その他の精製晶析 」で扱う。通常の晶析操作では液相中の析出成分は成長結晶表面への析出成分の拡散現象と結晶表面で結晶格子に析出成分が配列する結晶表面現象が直列機構で起こっていると考えられている。しかし、融液晶析では析出成分が成長結晶周辺に充分存在するので析出成分の成長結晶表面への拡散現象は他の現象に比して早く進むことが多く、晶析現象が早く進むために晶析熱による特有な現象が起こりやすい。通常の溶質晶析では熱拡散速度は物質拡散速度より遙かに早いので、このような現象が見られにくく、この現象について充分気を付ける必要がある。
豊倉研究室におけるこの種の融液晶析は1981年に大学院博士課程前期に進学した山崎さんの研究が中心であり、その主な成果は「晶析工学の進歩(1992年出版):pp.458~488」に原著論文コピーが掲載されている。それらは下記タイトルで表示記号は6・2・g〜d で示されているので、必要に応じて参照されたい。
| 6・2・d: | 「回分式撹拌槽によるベンゼンーシクロヘキサンよりのベンゼン結晶粒子群の生成」(山崎康夫ら;化学工学論文集、12卷5号、610(1986) |
| 6・2・e: | 「連続式MSMPR型晶析装置によるベンゼンーシクロヘキサン混合融液よりのベンゼン結晶純度」(山崎康夫ら;早稲田大学理工学研究所報告、第111集、29,(1985 |
| 6・2・f: | 「撹拌槽中での成長、溶解させたベンゼン結晶の純度と粒径分布」(山崎康夫ら;化学工学シンポジウムシリーズ7、53 (1984) |
| 6・2・g: | ” Purification of crystallized organic substances by pore diffusion in Crystal” ( yamazaki,Y. et al ; Ind. Crystallization, ’84, 37 (1984) Elsevier Science Pub. |
3−1) 回分式撹拌槽におけるベンゼンーシクロヘキサンよりのベンゼン結晶粒子群の生成(6・2・d参照)
山崎らは、多結晶懸濁融液系内のベンゼン結晶の挙動を明らかにするため、小型撹拌槽内における晶析実験を行った。その槽内に懸濁するベンゼン結晶の懸濁量・純度および融液中のベンゼン濃度等の操作時間に対する変化をFig.1に、その時の懸濁ベンゼン結晶粒径分布の変化をFig.2 に示す。
山崎らは、多結晶懸濁融液系内のベンゼン結晶の挙動を明らかにするため、小型撹拌槽内における晶析実験を行った。その槽内に懸濁するベンゼン結晶の懸濁量・純度および融液中のベンゼン濃度等の操作時間に対する変化をFig.1に、その時の懸濁ベンゼン結晶粒径分布の変化をFig.2 に示す。
3−2)連続式MSMPR型晶析装置におけるベンゼンーシクロヘキサン混合融液かりのベンゼン結晶純度 ( 6・2・e &f参照)
大容量処理が対象なる工業プロセスでは、連続溶媒晶析操作が重要であり、定常状態の連続晶析装置内に懸濁している結晶析出量とその結晶中の不純物濃度の関係を求めるために小型連続晶析装置を用いて実験を行った。そこでは連続操作開始後装置内スラリーの懸濁密度は、徐々に増加したが、滞留時間の1〜2倍程度で最大値に達し、その後は減少して、7滞留以上になるとほぼ一定値に安定した。この一定値になったところで、操作はほぼ定常状態になったと見なし、装置内の懸濁スラリー重量当たりの懸濁結晶重量比X(無次元)と装置内懸濁スラリー中に含まれる不純物量と懸濁結晶量当たりに含まれる不純物量との比Y(不純物はシクロヘキサン)を両対数点綴をするとFig.4となる。Fig.中に示したCSUSは百分比で表したスラリー中の溶媒濃度(ここではベンゼン濃度)で、このXとYとの関係は精製に用いた原料融液の溶媒濃度が80〜93%の範囲で一本の曲線で表されることを示した。
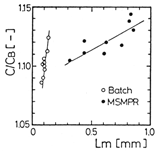 大きく |
3−3)室温付近の溶媒晶析法の総括(6・2・d〜gおよび6・2・h参照)
晶析工学の進歩(1992年に発刊)に収録した溶媒晶析に関する研究は装置内おける結晶生成に関するものと、生成した結晶の純度向上を目的にしたものがあり、山崎さんが行った研究は前者が主であった。また、山崎さんは6・2・gの研究で、村田さんらが行ったナフタレンー安息香酸融液よりのナフタレンスケール状晶析研究で検討した包含母液の挙動を考慮した晶析機構を検討している。一般的に、多晶懸濁系晶析操作では2核発生を無視出来ない。そこで発生した結晶核は成長している結晶に付着し、それが結晶中への不純物濃度の増加に関与する理論的展開を行い、実験結果と比較している(6・2・h参照)。
通常の晶析操作では、生成する結晶粒径は大きい結晶の方が純度の高い結晶が生成されると云われている。6・2・hの研究では、ベンゼンーシクロヘキサン系融液晶析で析出した平均粒径0.2mm程度の結晶群の純度は濾別直後は97%ぐらいであったが、その平均粒径を1mm程度に成長させると99%の結晶に純度を上昇させることができた。ここでの純度低下は結晶表面に付着している母液によると考え、濾紙等で丁寧に拭き取ると平均粒径0.3?以下の結晶では99.95%純度の結晶を生成することが出来た。しかし、結晶粒径がこの粒径より増大すると結晶純度は粒径とは逆に低下し、平均粒径0.8mm程度の結晶では、結晶純度は99.75%ぐらいに低下した。この純度低下は懸濁結晶によって発生した2次核の付着に基づくものでないかと考えている。このテストで装置内の懸濁結晶がベービー結晶を産めるマザー結晶の最小粒径は0.3mm近傍であろうと推察している。
山崎さんは一連の結晶精製に関する研究で、結晶の部分融解操作を行うと、結晶中の無次元不純物量(I/Io ;I は任意時間の結晶中の不純物量, Ioは部分溶解テスト開始時の結晶中の不純物量)を無次元溶媒結晶量(M/M o ;Mは任意時間の結晶量、Mo はテスト開始時の結晶量)に対して両対数グラフで直線上に点綴されることを見出した。その後、豊倉が早稲田大学を退職直前に研究室で世話した現在ダイセル化学工業の新井工場に勤務している高島さんが、この研究を引継いで一連の研究を行った。その結果、種々の実験条件で測定された測定値はそれぞれ、テストサンプルに固有の2本の直線上に点綴され、融解初期のテスト結果は、M/Moの僅かな減少に対してI/Io の減少量は大きく直線的に減少した。しかし、その勾配はそれぞれのサンプルで異なり、結晶の生成条件や部分融解の操作法の影響は受けるようであったが、その勾配や無次元不純物量の到達点がどのように決まるかは未だ明らかになっていない。 しかし、M/MoとI/Io によって決まる操作線の勾配が最大になり、しかもI/Ioが最小になるような操作法を決めることが重要なこと分かる。この操作線はI/Ioの最小値付近で45度の勾配の平行線に変わった。この勾配45度の操作線上を移動する操作を継続しても結晶純度は変化しなくなり、この操作は終了しなければならないことも明らかにした。このことによって理想的な操作法を描くことは出来るようになっているが、未だこの関係は理論的に説明できていない。これを追求することによって種々の新しい現象が見出されるのでないかと期待している。
4)その他の晶析法による精製分離法:
気体・液体・固体三態の存在域を示す相図は構成成分の組成と温度・圧力によって表示される。地球上の生活を考えると大気圧下で営まれており、通常の場合は圧力は大気圧でほぼ一定とみなされ、実際にはそのように考えて操作されることは多い。1970年代に神戸製鋼所の守時氏は数千気圧以下の範囲で操作圧を変化させ、特定組成の結晶を工業的に生成する圧力晶析操作法を開発した。1980年代に、豊倉は守時氏と共同研究を行い、ベンゼンーシクロヘキサン系をモデルとして一連の基礎研究を行った。その研究成果は「晶析工学の進歩」pp.489~510に掲載した。その要点を整理すると、
- 液相に一気に高圧を付与することによって液相中に1次結晶核を発生させ、それを成長させることによって短時間に多量の結晶を析出することができる。
- 圧力容器内の析出結晶はその容器に接続した配管内バブルを操作して僅かに減圧することによってその配管接続口に設置した金属メッシュを通して残留融液を装置外に排出することが出来、装置内で析出した結晶を融液から分離することができる。
- 装置内より残留融液を排出するために、装置内の高圧力を低下させる操作によって、析出結晶を部分的に融解し、それにて発汗操作を自然発生的に起こすことが出来る。そのため、析出結晶中に包含されている不純物濃度の高い未晶析融液を選択的に排出でき、高純度結晶を精製分離することができる。
- 高圧付与による晶析操作では、液体の非圧縮性より融液内の過飽和度を比較的均一にしかも短時間に付与することが出来、他の操作法と異なる高純度結晶を析出することが出来る可能性がある。
この高圧付与による圧力晶析法は、守時氏の努力で世界に先駆けて工業化に成功した日本のオリジナルな操作法であり、世界各国の晶析研究者から着目されている。この技術はLarson教授によってアメリカACT (Association of Crystallization Technology ) の会議でも正式議題に取り上げられ討議している。
通常の溶質晶析法においても、生成結晶は高純度物質になりやすい特徴があり、基礎研究分野において精製法として古くから用いられてきた。これらの分野の結晶化は高純度物質の精製を目的にしており、工業操作のように多量の製品結晶を低コストで精製する制約は殆どなかった。化学工業界等で対象にする精製操作では低コストで精製することが極めて重要であり、再結晶を繰り返して製品結晶純度の向上を図る操作法を選定することは期待出来ない。そのため工業操作特有な精製晶析法の開発研究が行われている。この操作法でも、結晶中に不純物が入る機構を考え、その機構に対応した精製操作法を考案・開発しなければならない。その機構と対応においては一部のケースでは成果が上げられているが、まだ、その体系化が出来た状態にはなっていない。ここでは、成果のあった2、3の例を紹介する。
これらの操作法は既に報告されてる理学的基礎研究成果によって定性的な提案はできるものであるが、工業装置内では装置特有の操作因子の影響があり、定量的関係を明らかにして工業装置の生産技術を確立するためには、これらの状況を充分把握してその装置に適合した開発研究をする必要がある。(1).媒晶剤のように結晶特定面への親和力の大きい物質が溶液中に存在する場合;不純物が成 長している結晶表面に付着して媒晶作用が顕著になるのは操作過飽和度が小さくなり、結晶成長速度がある値より小さい時に表れることがある。 このような場合操作過飽和度を大きくして結晶成長速度を速くすると、成長した結晶中の不純物量が減少することがある。これは、成長している結晶面に作用する媒晶剤と成長に寄与する析出物質の競合作用の大小に起因するのでないかと考えている。
(2).装置内懸濁結晶表面に不純物の結晶核が発生し、それが成長して結晶中の不純物量が増 大する場合;これは、結晶表面上で不純物結晶が不均一核化現象を起こすためで、その核発生を阻止することが必要である。その場合結晶表面に接している溶液中の不純物濃度を低下させることが有効であり、この晶析系母液の物性値がこの系の溶媒物性値と異なる時、溶媒の供給法を工夫することによって不純物結晶の核発生を阻止できる。ラセミ溶液からの連続優先晶析操作でこの操作法は有効である。
(3).成長結晶表面に微結晶の付着などが起こり、それが原因で所望結晶中に母液が包含され 易くなり、結晶中の不純物混在量が増大する場合;この場合は溶媒添加や未飽和原料溶液を間欠的に供給し、周期的に装置内溶液を未飽和状態にすることによって過剰微結晶を溶解し、97〜98%製品結晶の純度を99%アップに改善して、スペックをパスしたことがある。この場合、装置内の粗粒結晶も未飽和状態にした時部分的に溶解するが、微結晶の溶解が進んだ段階で装置内の過飽和状態を回復すると部分溶解した結晶の溶解部分の修復成長は早く、あたかも溶解操作がなかったような粒径結晶の製品を生産できる。
また、蔗糖水溶液などの場合、操作過飽和度の大きい状態で操作すると母液中の水分は結晶化してシャーベック状になる。この多量の氷結晶を懸濁した蔗糖母液はさらに冷却されると母液中の水分は周囲氷結晶の成長に費やされ、その濃度は操作温度の飽和濃度近くまで濃縮される。この濃縮された母液を含むシャーベック状のスラリーより母液を取り出すと濃縮蔗糖溶液を生産できる。ここで分離された氷を融解すると純度の高い水を精製することも可能である。此の操作は果物ジュールの濃縮にも適用でき、冷熱エネルギーの回収を工夫するとによって省エネルギー濃縮技術に発展することが期待されている。この研究は山崎さんの一連の溶媒晶析研究の一部として研究されており、その成果は「晶析工学の進歩(1992)pp.511~515」に掲載している。
5)むすび
溶媒晶析をこのHPで扱ったのは初めてです。研究室内の事情があって本文中にも書きましたが、研究の進捗状況は豊倉研究室の研究課題としては順調に進んだとは言い得なかったかもしれないと思いる。しかし、そのために他の晶析研究分野の研究課題進捗状況と対比しながら研究を進めることが出来、結果的には豊倉が行った他の晶析研究課題と多少異なって、晶析工学の本質を考えながら研究を進める余裕があった気もする。その一方で、溶媒晶析だけ考えても手の付いてない研究課題が多いことを今更のように追い立てられる気も感じている。研究者が進めようと思う研究課題は研究者を取り巻く環境の変化につれて流動的であるが、10年30年先の世界の動きを想像しながら研究を進め、未来のある日に過去を振り返った時、納得出来るような成果を上げられればと思っている。