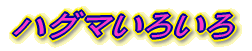
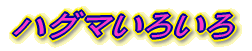

キッコウハグマ
|
埼玉県熊谷市は関東平野の真っ只中にあり、山らしい山は無く、最高峰が観音山と呼ばれる97mの古墳程度の山で、周囲の土地より僅か40m程度高いに過ぎないが、麓の竜泉寺の寺社林になっている為、開発や乱獲から免れ昔の里山の風情がそのまま残っている。 |
 |
 |
 |
オクモミジハグマ
| 一方、コウヤボウキ、カシワバハグマのコウヤボウキ属は十本前後の頭花を付けているのでいっそう箒(ほおき)やハタキの先の感じが強い。 高野山では竹箒を使うと大蛇が乗り移り災いを招くとして竹箒を使わず、その代用として高野山の付近で自生していた植物を使って作ったのがコウヤボウキ(高野箒)で、製品名が転じて植物名になった。 草本のように見えるがキク科の低木である。 昔は玉箒とも呼ばれ、新年の最初の初子の日、宮中ではこのコウヤボウキで作られた玉箒が授けられたとされ、大伴家持に次の一首がある。 「初春の 初子の今日の 玉箒 手に取るからに ゆらく玉の緒」。 |
 |
 |
 |
コウヤボウキ
|
カシワバハグマは葉が柏(かしわ)の形をしているのでカシワバハグマの名があるが、モミジハグマ属ではなく、コウヤボウキ属で頭花の数も写真のように10本程ある。 |
 |
 |
カシワバハグマ
|
モミジハグマ、キッコウハグマとコウヤボウキ、カシワバハグマは属は異なるが、同じキク科の花で、秋の観音山を彩る。 |