|
|
| |||||||||
|
|
現代管球の最終形・TVから送信機用途まで
| |||||||||
|
水平偏向 |
|
B/Wダブラ220v用: xDQ6・xBQ6〜 300/600mA用: 25E5・xBB14・xGB7〜 初期カラ−用: xCL5〜 中期カラ−用: xDQ5〜 大型カラ−用: xJS6・xKD6 | ||||||||
|
B/WT用 黎明期 |
|
| ||||||||
|
6BG6-G RCA
Ep=700V/20W、Sg2=350V/3.2W 6L6系の送信管807をオクタルベースに換え水平偏向出力管へ換装したもの。 |
6BG6-G 東芝 技術情報
無線と実験(昭和30年) | |||||||||
|
6BQ6族
220V
|
|
| ||||||||
|
6BQ6GT(ZENITHとSYLVANIA)
Ep=550V/11W、Sg2=175V/2.5W |
6BQ6GTB(RCA)
Ep=600V/11W、Sg2=200V/2.5W | |||||||||
|
| ||||||||||
|
左から6G-B6 6本/ 右25E5/12B-B14 (東芝製) Ep=600V/11W、Sg2=200V/2.5W 左から 3本目以降は多品種(12G−B3等)の量産化のために部材が共通化されている。従ってバービアンスなどの仕様は25E5に近いもの(gm=10000以上)と思われる。
| ||||||||||
|
xDQ6系 |
|
| ||||||||
|
6/12DQ6A(写真は日立製) Ep=770V/18W、Sg2=220V/3.6W |
12DQ6(頭頂部)
| |||||||||
|
25E5系 |
|
| ||||||||
|
25E5 (英フィリプス) Ep=250V/11W、Sg2=250V/5W 英フィリプス製。バルブ頭頂部にブリテンと書かれている。KT88などど同様に、頭頂部にゲッタ−飛散防止兼用雲母板がある。 |
25E5 (SYLVANIA) シルバニアブランドだが made in japan。 | |||||||||
|
カラーTV用 米国系 |
|
| ||||||||
|
6CB5 Ep=700V/23W、Sg2=200V/3.6W 6550Cや6GB8の原型になった。 |
6CD6GA/6CB5 Ep=700V/20W、Sg2=175V/3W 6CD6は6CB5と6CL5の中間。 | |||||||||
|
|
| |||||||||
|
6CL5 (GE後期) Ep=700V/25W、Sg2=200V/4W このタイプの見分け方はグリッドではなく、スクリーンに放熱器があるのが特徴。日本製にはないタイプ。 オクタルベース |
| |||||||||
|
マグノ−バル |
|
| ||||||||
|
6JS6A (東芝) Ep=990V/28W、Sg2=190V/5.5W 写真は八重洲FT101Sの終段管のもの。
|
6JS6A (底面ステム)
雲母スリットや形状、電極材質は最終段階にきている。 | |||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
6KD6 Ep=990V/33W、Sg2=200V/5W | 6JS6/6KD6 | |||||||||
|
垂直偏向 |
|
| ||||||||
|
9RA6/6RA6(6.3V 0.9A) Ep=550V/10W
gm=8500 rp=1.75k μ=15 |
9RA6(TOP)
電極構造から純3極管であることがわかる。 | |||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
左 6BM8/50MBM/16A8/8B8 Pen
Ep=550V/7W
Sg=550V/1.8W |
18GV8(18V 0.3A 松下) Pen
Ep=250V/7W
Sg=250V/2W オーディオ用としても6BM8をさらに適正化している。仕様上は使ってみたくなる球である。 ただ外観的にみると3極管部が異常に小さくプレート損失は0.5Wしかない。 | |||||||||
|
|
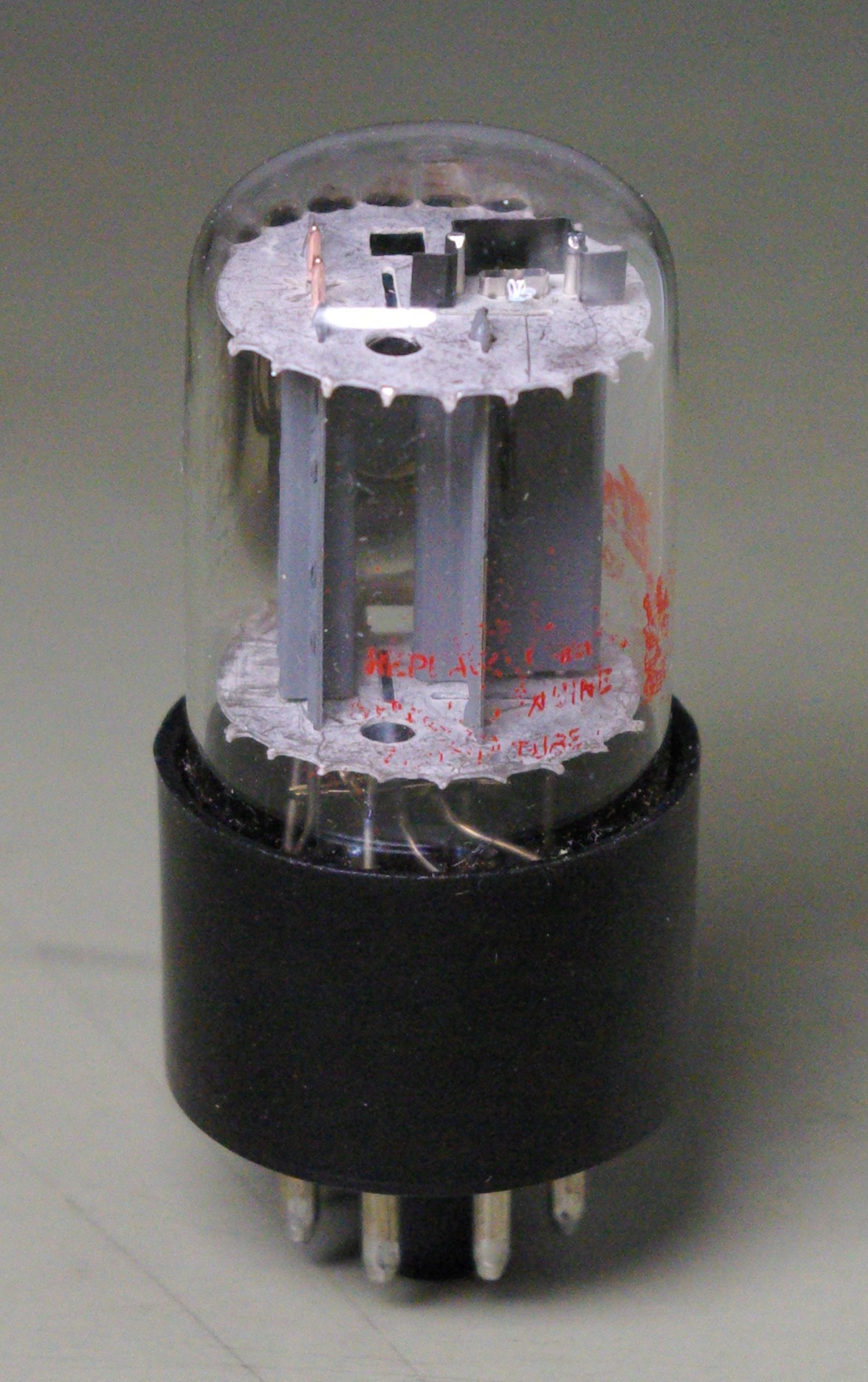
| |||||||||
|
6LU8(GE) Pen
Ep=400V/14W
Sg=300V/2.5W |
13EM7(ZENITH) 13V/0.45A Tri1
Ep=330V/1.5W μ=64 gm=1600 rp=40K
| |||||||||