手動掲示板3
質問・感想などをお寄せください。
手動なので掲載されるまでに数日かかります。
って要するにメールフォームなんですけど。
ロボの変形基地
変形合体ロボの玩具には基地がセットで付いてくる時代がありました。
ガオガイガーのスーパーミニプラでベイタワー基地やオービットベースを期待したのですが…
基地の玩具は需要が限られるのかな。
Re:ロボの変形基地
基地の玩具の需要はどうなのか…私個人のことを言えば、人型に変形する物を除いて基地の玩具にはあまり興味がなかったです。
ベイタワー基地はいかにも玩具化前提のギミック満載アイテムで、結構人気ありそうに思えますが。登場するロボットの数が多いために外されたのではないでしょうか。
スーパーミニプラでは『バイオマン』のバイオドラゴン(基地ではないですが)などはラインナップされてますね。ロボットと絡めて遊べるという点は大きいかもしれません。
アイアンギアー
既に一覧に掲載されてますけどクリックしたら見つかりません状態。
11/30公開予定という事でよろしいでしょうか?
Re:アイアンギアー
すみません。仮に作ったたものをうっかりアップしてしまいました。
製作は順調ですので、11/30公開で大丈夫と思います。
Re:アイアンギアー
艦首にあたる箇所がWMでそのまま爪先となるのはスムーズに変形出来そうで良いですね。(本家だと内側への収納が難しそうなので)
それにしても腕部のブリッジは格闘戦時は大変だろうなぁ。
惑星ゾラの住人ならバイタリティあるから大丈夫そうだけど。
Re:Re:アイアンギアー
ランドシップ時は爪先があるのになぜウォーカーマシンになる時わざわざ引っ込めるのか、全くもって理解に苦しみます。逆ならまだわかるのですが。
腕や足に乗ってる人の安全性の問題は、変形合体ロボットの永遠の課題ですね。本編でも「主砲(←足先)にも人がいるんだよ」などと不穏当なセリフが飛び交ってました。
ロボットじゃない合体メカ
今年で50周年を迎えたアSFアニメ
ゼロテスター
50周年なので玩具などの関連グッズが
出そうですが、流石に無理か。
1号メカは、簡単な合体構造で
印象が残ります。
Re:ロボットじゃない合体メカ
今後「50周年作品」が目白押しになりそう。
テスター1号は飛行機3体合体の最良のバランスを示したと思います。キングビアルなど後の多くのメカが同じ合体パターンを採用してますね。
デザイン面ではマーク1の大きすぎるキャノピーがアイコンになっていてシンプルながら存在感があります。
テスター2号のナポレオンフィッシュみたいなフォルムも独創的で、今の感覚でも新鮮に感じます。
Re:ロボットじゃない合体メカ
『ゼロテスター』のテスター機。
『無敵超人ザンボット3』のキング・ビアル。
どちらも、宮武一貴(スタジオぬえ)のデザインですね。
出展:『宮武一貴 デザイン集』幻冬舎,『宮武一貴 画集』HOBBY JAPAN
Re:Re:ロボットじゃない合体メカ
そうでしたか。同じ合体パターンなのも納得ですね。
調べてみたところ、ウィキペディアに「デザインはスタジオぬえが担当。合体のパターンは『ゼロテスター』のテスター1号機を参考にしている」とはっきり書いてありました。
しかしキングビアルがぬえの作品とは意外な気もします。宮武氏にしては箱っぽいというか、ゼロテスターに比べてデザイン力が後退してるのでは?
ザブングルとギャリア
かなりアレンジされたザブングルと元デザイン寄りのギャリア。
その中間的デザインのブラッカリィがどうなるか気になるところです。
Re:ザブングルとギャリア
変形合体を重視してアレンジする、というコンセプトでやっているので、変形合体しないブラッカリィを取り上げようとは考えもしませんでした。デザインだけをいじるのはどうも乗り気がしない。
しかしブラッカリィに変形合体機構を加える、という方向なら描けそうな気がします。検討してみます。
2体に分離させるとしたら、下半身メカは飛行機と車両の中間になるのか? ホバータンクのような感じでしょうか。
なぜ...?
ギャリーウィルの銃座の席って露出してませんでしたよね…?
Re:なぜ…?
私は理屈でデザインを考えることが多いのですが、この部分は特に明確な理由はありません。フィーリングの問題です。
なんとなくこの方がザブングルの世界にマッチしていると感じたからです。
合体するとむき出しでなくなる点も面白いと思います。
ソーグレーダー
ロボ小説知らないものばかりです。
ありがとうございます。
僕も設定画目的です。
勇者シリーズ最新作ソーグレーダーのWEB連載が始まりましたね。どうでしょうか。
勇者物はロボ時の簡略化が激しいのが気になりますが、新作は喜ばしいです。できればTVがよかったですが。
合体、パワーアップの方式はトランスフォーマーVのスターセイバーが元らしいですが(しゃべるのも)、ガンダムも変形させたりと、トランス〜はやはり偉大ですね。
Re:ソーグレーダー
主人公メカがキッチンカーというのは新しい。パワーアップ用メカは何なんでしょう。トレーラーではなさそうですね。
バーンガーンのバーンと同じで合体後はソーグは全く露出しないのか、など色々気になります。
勇者シリーズのメカでよくある、キャノピーがパカッと割れたりキャタピラが折れたりする変形が私は嫌いなのですが、今回も操縦席の存在を無視した変形で、そこは残念。
まずはWEB漫画という体裁ですが、おもちゃを出す予定はあるんでしょうか。TVアニメがないと厳しいですよねえ。
グレンダイザーUで浮かんだアイデア
グレンダイザーとドッキングするスペイザー。
ダブルスペイザーとマリンスペイザーとドリルスペイザーが合体して、スペイザーに成るのはどうでしょうか。
グレンダイザーのリメイクでは、主にスペイザーで工夫するようなので。
Re:グレンダイザーUで浮かんだアイデア
実はそういうアイディアをすでに考えてました。
グレンダイザー本体のリデザインの方向が定まらないためなかなか進まないのです。
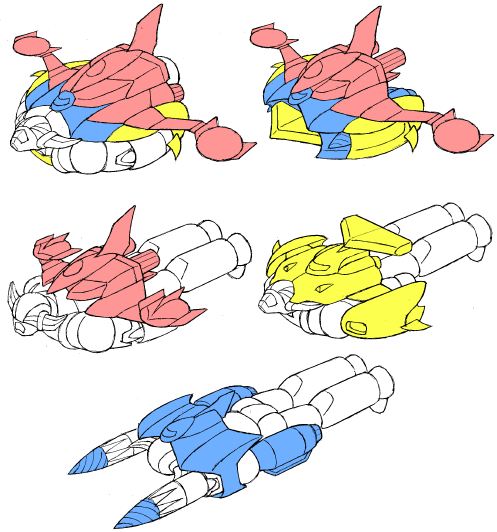
あとは、全機合体の「グレートグレンダイザー」をやるかどうかですね。
『U』のデザインは旧作とほぼ同じですね。懐かし派の海外スポンサーの要望なんでしょうけど、もうちょっと冒険して欲しかったです。
グレンダイザーUで浮かんだアイデア2
冒険か…
じゃ、グレンダイザー本体にコズモスペシャルスペイザーを混ぜてみるのはどうでしょうか。
ある意味で冒険になると思います。
Re:グレンダイザーUで浮かんだアイデア2
企画段階ではそういった挑戦的なデザイン案もあったに違いない。でも上の方の決定で、ディテールをいじっただけの無難なものが選ばれてしまう(あくまでも私の想像です)。そういう守りの姿勢をもどかしく思うのです。
私としては、ライディーンとゴッドライディーンぐらい違うものにして欲しかったですね。
ついでに言うとマジンガーZも何度もリメイクされてますが、もっと元デザインから離れた大胆なものが出てこないかと思うんですよ。
小説
小説に出てくるロボットも好きです。
ガイアギア
未来放浪ガルディーン
深海大戦
ブルバスター
お気に入りは聖刻1092の操兵です。
フォーザバレルのガンボーイってのもありましたね。
恥ずかしながらどれも読んだことありませんが。
以前戦国鍋TV、戦国炒飯TVというバラエティー番組内で戦国ロボというアニメパートがありまして、 合体変形なんでもござれのロボットが出てきます。動画も検索できますのでお時間あるときにでも。
僕が個人的に好きな変形機構は胴体から頭がにょきっと出てくるところです。
ザブングルとかバルディオスとか。
演出的にもかっこいいと思います。
が、これだと胴体内カラッポですよね。
いろんなメカとか詰まってなきゃいけないと思うんですけど。
Re:小説
私もロボット小説は知ってはいても読んだことはないですねえ。
そういうの見つけたらまず巻末に設定画が載っているかどうかチェックするのが習い性です。
メカデザインが好みだったのが『凶兵器ヴァン・ヴィール』。ただしそれは雑誌連載時の話で、書籍では別のデザインになってしまいました。なぜ?
『アース・リバース』。これは舞台設定が面白い。
『歩兵型戦闘車両ダブルオー』。ロボットが不恰好ということが何度も強調される。
『機龍警察』。デザイン不詳だったのが漫画化で明確になりました(漫画版も読んではいません)。そのうちアニメ化?
戦国武将がロボットで戦うのではなく、戦国武将がロボットなのが面白いですね。では誰が操縦しているのかということになるんですが。
私は中がカラッポになる変形は避けたいと思っているので、頭・拳・上腕・腿が生えるパターンを使わないようにしています。代わりに「装甲がスライドする」というパターンをよく使います。
頭が胴体から出て空いた空間を別のパーツで埋めるという手もあります。下から2号機の機種が刺さって頭が押し出される、とか。
勇者ライディーンの武器
ライディーンの武器ですが、
ダブル・ゴッドブレーカー
ダブル・ゴッドブロック
ダブル・ゴッドブーメラン
ダブル・ゴッドゴーガン
が出来るように左右対称にするのは
どうでしょう。
左右反転の問題が解決できそうなので。
Re:勇者ライディーンの武器
「左右反転の問題が解決」って意味がよくわかりませんが…。
ダブル・ゴッドゴーガンについて一言いわせてもらうと、片手では弓が引けませんがな。
勇者ライディーンの武器2
勇者ライディーンのアニメは左右が時々反転してしまう場面がありましたので、ライディーンの腕に付く武器のデザインを左右対称に出来ないかなと。
Re:勇者ライディーンの武器2
昔のアニメはコスト節減ために同じセルを使い回すことがよくありました。全く同じでは何だから左右反転させて使うことも多かったですね。
ライディーンのそれは単なるミスなのか、非対称だとわかった上で節約のためにあえてやっていたのか、どうなんでしょう。
武器を減らさずに左右対称デザインにできれば作画も助かり商業的にもマイナスにならず合理的なようですが、ちょっとためらいを感じます。
左右の武器が違い腕の形が微妙に違がっている点は、ライディーンのデザイン上の味になってると思うんですよ。その味をなくしてしまうのは寂しいなあ、と。
お城が変形するロボットといえば
お城が変形するロボットといえば
ゆるきゃらのお城ロボ
http://graphmary.com/oshirorobo.html
超城合体タメノブーンV
https://www.city.hirosaki.aomori.jp/tamenoboon5/
がありますね。
Re:お城が変形するロボットといえば
知らない城ロボがまだまだあるんですね。
>お城ロボ
何といっても高下駄がすごい。これは変形はしないのかな…と思いきや、走行モードになるんですね。
>タメノブーンV
合体前のメカが、戦車型などもあって多彩なのがいいですね。
合体システムを考えてあるのか融合みたいな感じなのか気になります。
下のスレで言ってた見つからない企画はこれか…? 登場した時期もそれらしいし。でも何かイメージが違う気がするんですよ。
昔話
昔は玩具オリジナルの変形ロボットが結構ありましたね。
鍵が変形するキーロボット、将棋の駒が変形するショーギロボ(本家はショーギウォーズ)
カップ麺から〜のテレコマ戦士どんぶりマン
ロボトライってのもありました。
雑誌Bクラブに載せるためだけに書かれた究極合身フィフティンガー。
お城ネタがあったので、城郭合体オシロボッツなるものを見ました。
いつも丁寧なご返答ありがとうございます。
Re:昔話
腕時計がロボットになったり、変形する意味ないよなあという感じのものも色々とありましたね。
特に私の記憶に残っているのは「ダイノゾーン」です。半透明+メタルのデザインが斬新でした。1体を除いて変形は面白くないんですが。
オシロボッツは例によって初めて知りました。普段積極的に情報収集してないんで、この掲示板に新情報を寄せていただけるのはありがたいです。
ホームページを見てみましたが、各ロボットのキャラ分けがしっかりできているのが好印象です。
お城が変形するロボットの企画ってすでにあったような気がするのですが何だったかなあ。
Re 昔話
ダイノゾーンはCMがかっこよかったです。
城ロボですが、無敵将軍かと思いましたが、鋼鉄城アイアン・キャッスルのアイアンオカザキじゃないでしょうか。
ついでですが、
ハコダテ観光ガイド イカール星人襲来中
留萌管内合体ロボ オロロン8
留萌管内合体機獣 オロロンロボメビウス
も面白いですよ。町おこしなんでしょうか。
ご参考にしていただけたらなによりです。
Re:Re 昔話
「アイアンオカザキ」は町おこし企画じゃなくて小説が先にあったんですね。これは珍しい例ですね。
純粋にロボット物作品として作られただけあって、本気のデザインですね。町おこしロボの素人っぽさも好きですけど。
「城郭合体オシロボッツ」と同じような、日本各地の実在のお城が変形する企画を以前見たような気がするんですが、ネットで探してもそれらしいものは見つかりません。一ヶ所の城だけのならあるんですが。もしかして個人のサイトか何かだったのか? せっかく色々と調べていただいたのにあいまいで申し訳ない。
ビッグダイエックス
遅ればせながらビッグダイエックスを拝見させて頂きました。
そう云えばメインスポンサーだった今はなきタカトクトイスから電撃合身版が発売されましたが劇中にはなかったトリプルアタッカーからの変形ギミックはブレインダーはブースター部分がバックパックになったりジャンボデ(ィ)ーは劇中と異なったのですがレッグスターの方がほぼ劇中通りでしたね。
電撃合身版とスタンダードの中間のDX版もあり、劇中未登場のオリジナルフォームのエックスファイターへの変形ギミックも搭載されました。
Re:ビッグダイエックス
アレンジするにあたってタカトク版は取り入れるつもりはなかったのですが、頭メカを大きくとか乗り物らしくとか、結果的に同じような方向性になりましたね。
エックスファイターと違って人型からの変形はしないものの、3体が合体した飛行メカを作るとい案もありました。うまくまとまりませんでしたが。
劇中の通りの変形合体をするおもちゃって、当時出たんでしょうか。逆にそっちが気になります。
最近ネオゲッターが流行っています
これというのも某アニメの主題歌の一部とネオゲッター対真ゲッターの主題歌の一部のリズムがほぼ同じだからなのですよ。だからこの際ネオゲッターのデザインと同作版真ゲッターのデザインをリメイクしてほしいと思っています。最近のシリーズの真ゲッター3は頭や胸が青くない上、明かされているゲットマシンの形状も大分違うようです。
Re:最近ネオゲッターが流行っています
ネオゲッターのデザインは過去作のミックスで、ネオ独自の特徴というものがなくて面白くないですねー。
アレンジするとしたら號でやったのと同じく、背中に来る機体の一部を胴体に移してバックパックを小さくするという方向でいくと思います。
真ゲッター3の色が違うって、「黄色い」という意味かと思ってしまいました。
黄色いのは『真(チェンジ!!)』版でしたね。
『真ネオ』版は胸が白で頭だけが黄色。なんでこんな妙な配色にしたのか理解に苦しみます。
ゲッターシリーズのアレンジではありがちなことですが、ベアー号が何がメインかわからない半端なカラーリングになってしまいそうです。
Re:Re:最近ネオゲッターが流行っています
チェンゲ版もいいですね。あくまでネオゲ版を提案したのは流行り故で、だったらチェンゲ版がいいと思います
Re:Re:Re:最近ネオゲッターが流行っています
チェンゲ版の、ほぼ黄色い真ゲッター3にほぼ白い真ゲッター2。これはほんとに困ってしまいます。
色を変えるためだけの変形(パネル反転など)はなるべく使いたくないんですよね。
「ダイナミックチェンジ 真ゲッターロボ」では、チェンゲ版と称しながら3の後部を赤と白、2の脚を赤にするということをやってます。
時にはこういう大胆さも必要ですね。
ところで、『ネオ』は『真(チェンジ!!)』より後の作品なんですね。真ゲッター3を一旦黄色にしたのにまた白っぽいのに戻したのか。
このシルエットは…
初めて投稿させていただきます。
いつも楽しく、そして参考にさせていただいております。
今回の予告のシルエットはもしかしてスーパーマリオラマのアレでしょうか?
自分自身でもアレンジを考えていましたので発表が楽しみです。
予告見ました
おお、もしやこれは、
銀河の海へ船を乗り出すやつ
ですか。
だとすると
操縦席が移動するシーンが
好きでした。
新たなシルエット
新しく出ていたシルエットですが
?I-ボンバーのビッグ.ダイエックスにしか見えないのですがどうでしょうか?
まとめてお返事
初めての方もそうでない方も今後ともよろしく。
3機とも元とはだいぶ違う形になってるので今回はそう簡単にはわからないだろうと踏んだのですが、あっさり見破られてしまいした。皆さんさすがです。頭メカの突起が決め手でしょうか。
シルエットを見ればおおよその傾向はつかめると思いますが、頭メカは他機と比べて小すぎるので担当する部分を増やして大型化、あとは各機を、人体パーツそのままのデザインなのを航空メカらくしています。
ところで、スーパーマリオラマと聞いて今話題の兄弟の関連かと思う人多いでしょうね。
Re:まとめてお返事
僕はレッグスターで分かりました。
双胴の乗り物になる変形って実は
あまりなかったり。
戦隊メカなどは左右くっついてひとつの
車っぽくなってます。
ライブロボの足、アクアドルフィンが二匹のイルカが並んでいるへんちくりんな乗り物になるので、一瞬ライブロボかとも思いました。
おっしゃる通り頭部ブレインダーにしては大きいなと思いましたが、そういう思惑があったのですね。
前から考えていたのですが、ビッグダイエックスのようなロボ正面か分離時に機体上面になるものは、
合体後コクピットはどうなるのでしょうか。
キュウレンオーの頭みたいにななめ軸で回転
するんですかね。
まあ、そんなこと考えちゃいけないのでしょうが。
Re:Re:まとめてお返事
言われてみれば確かに、脚メカが双胴になっている例は思い浮かばない(強いて挙げればカイラガーか)ですね。膝から下だけだったらくっつけるしかないし、股関節でつながっていたらそこを機首にしますものね。
ちなみにこのビッグダイエックスは、股関節を広げて左右の脚をさらに離しています。全翼機のような感じにしたかったので。
ゲッターロボ(初代)は合体後のコクピットが上向きのままという設定だったのが、途中からゲッター1の時のイーグル号のコクピットが頭部に移動して前を向くようになりました。
他の上向きで合体するロボットの場合も、作中でそういう描写がなくても合体時にシートが回転してるんだろうなと何となく想像しながら見てました。
コクピット内は人工重力があるので上向きのままでOK、なんていう例もありました。
城に変形するロボといえば
SKY x STUDIOから「RPG伝説ヘポイ」ドラゴン・キャッスルが出たことで思い出したのですが、当時の「RPG伝説ヘポイ」玩具で完全なる城に変形するものが少なかった気がしました。
デザイン的にも簡単そうだけど、変形できるか疑問でしたし。
Re:城に変形するロボといえば
かなりマイナーな作品というイメージですが、今になっておもちゃが発売されるということはそれなりに人気があったんでしょうね。
もしかして城に変形するおもちゃは、少ないというより無かったのではないでしょうか。
作中ではキャッスルたちは一度封印を解かれたら城には戻らない(たぶん)し、城状態の時は色が土色、描画もあっさりした感じで、印象が薄いですよね。商品化する意思が初めからなかったと推定されます。
変形させるとしたら、やっぱりは色が大問題ですね。そこは無視するしかないか。
シン・ユニバースロボ
今日職場の休憩時間でネットニュースを見たらシン・ゴジラやシン・エヴァ。シン・ウルトラマンにシン・仮面ライダーのシン・ジャパニーズヒーローユニバースが合体した「S.J.H.U.PROJECT シン・ユニバースロボ」の発売が発表されました。
https://p-bandai.jp/item/item-1000191755/
SMPの「タツノコ合体 タイムボカンロボ」共々最初知った時は正直合体ロボのバーゲンセールだなと思いましたが再版が決定した「超合体キングロボ ミッキー&フレンズ」以来奇抜合体を出してく(れ)るバンダイってすごい会社だと改めて実感しました。
Re:シン・ユニバースロボ
私はこの手の有名キャラ・メカ合体ロボの類はあまり好きじゃないです。
こうゆうのって本来ファンがパロディとしてやっていたことですよね。それをメーカーが先回りしてやってしまうのは、そりゃプロの技とコストが注ぎこまれているから文句がつけようがない仕上がりなんだけど、何か釈然としないものを感じるんですよ。例えて言えば公園が潰されてオシャレなビルが建ちました、周辺の街は賑わったけどそれでいいの?みたいな…
あと野暮を承知で言ってしまうと、この手のロボって往々にして、合体後の姿がまとまりに欠けるという難点があるんですよね。腕なら腕のデザインになってなくて合体前の姿が生々しく残っていて、そこを変形の工夫で(なんなら合体前の姿を少し変えて)うまく処理できないものかと思うのです。
ガムロック
密閉型コクピットで最小モデルは
夢源起動ガムロックだと思います。
最近知りました。
ボトムズやメガゾーンよりも小さいです。
ダイバロンとかアイゼンボーグ号とか、昔の主人公機はなぜか凶悪なデザインですね。
トゲトゲにドリルに電ノコに。
Re:ガムロック
こんながロボがあったとは、またしても初めて知りました。
「有人丸」という感じですね。
私の「小さいロボット志向」を猛烈に刺激します。
こんな体型のメカが主人公機とはテレビアニメなら快挙だと思ったのですが、基本おもちゃだけの企画のようですね。
支援メカと合体して大型で高頭身のロボットになるようで、そんなものは出さずに最後までちんちくりんなままで戦ってほしいところです。
トゲトゲ等は、子供にもわかりやすい強さの表現だったんだと思います。
だんだん使われなくなったのは、兵器としてリアルじゃないという理由なんでしょうか。
今のロボットの武装はビームガンにミサイルに…と決まり切ったものばかりでつまらないなあ、と感じる昨今です。
Re Re;ガムロック
なかなか面白いですよね。
見つけたときは、こんな方法があったか、と思いました。グレンラガンのラガンやバトルスキッパーよりも”ロボ”してると思います。実物モデルは走行モード(アニメパートでは、歩行時は後ろのタイヤが上がり、足が少し伸びている。)のようですが、パイロットより全高が低いので、これより小さいものは、そうそうないと思います。
最近のテレビアニメはカードバトルや異世界ものばかりなので、何と戦うかは別として、ロボが活躍する作品を久しぶりに見たいです。ガンダム以外で。
Re:Re Re;ガムロック
有人機を小型化していくと体型が不自然になる問題を、SDにすることで解決したのは画期的なアイディアだと思います。SDロボに人が乗ること自体あまりなかったし。
小型化するにしてもデザインとの兼ね合いで2m強ぐらいで手を打ちそうなところ、多少不恰好になってもさらに限界まで突き詰めた姿勢も支持したいです。
気になるのは尻重なスタイル。そうでないと走行ができませんが、1/1モデルはともかくおもちゃは走る必要あるんでしょうか。走れなくてもその分かっこよくするという選択もあったんじゃないかと思うんですが。
バトルスキッパーがロボしてないのは当時のおもちゃ技術の限界ですね。
3つのマシンが1つになる超合体サンゴッドV
サンゴッド1は大空を飛べ
サンゴッド2は大地を駆けろ
サンゴッド3は干潮時を狙って 波打ち際をゆけ
2つのマシンが1つになって 超合体サンゴッドV!
必然的に1台あまるサンゴッド3
2つのマシンが1つになるのも良し。
3つのマシンが1つになるのも有りだと思います。
Re:3つのマシンが1つになる超合体サンゴッドV
こんながロボがあったとは初めて知りました。
合体時に余るなら、サンゴッド3が丸ごと楯になるというのはどうでしょうか。楯の真ん中から首が生えているというシュールなデザインです。
で、本体は楯で守られるのだが3のコクピットは無防備で危険、という設定。
もう一つ案を考えました。
余計者と思われていた3には実は重要な役割があった。
ロボの上半身にも下半身にも変形できて、1・2のどちらかが破損した場合に代わりに合体することができるのだ。
ただしその合体形態は弱い、あるいはカッコ悪い、という欠点がある。
ダイバロンの隠れたフォームといえば
構造的に考えてもガンタンクのような形態しか思いつきませんが。
上半身はダイバロンで、下半身はバクシーンのまま。
Re:ダイバロンの隠れたフォームといえば
やっぱりそうなってしまいますか。アレンジ版だと「正座」という感じになりそう。
大型飛行メカにするにはバクシーンを後ろ向きにして、合体部を180°ひねったら…とか考えてみたんですがあまりうまくいきそうにないですねえ。
ダイバロンの隠れたフォーム?
「完全なる変形」のダイバロンを拝見させて頂きました。
このダイバロンってどことなく中間形態にもなれそうな雰囲気がしますが実は86年刊行のテレマガヒーロー大全集で初めて知った時ZZガンダムを思い出してしまったのでその発想に辿りつきました(命名:バロンフォートレス)。
Re:ダイバロンの隠れたフォーム?
ZZガンダムからの発想ということは、3体がほぼ無変形で合体して大型飛行メカになるわけですね。
そういった「おまけ」を描くこともありますが今回はそこまでは思いつかなかったです。
中間形態ならばフォートレスから分離せずにダイバロンに変形、となりますが…ダイバロンと同じ合体箇所でフォートレス合体できるかどうかが問題です。私のアレンジ版だと難しいかなあ。組み替え合体なら色々なパターンが想像できますね。
ダイバロン...合体後のトブーンのコックピットって危険じゃないでしょうか?
Re:
ヒーローなので平気です。
これがダイバロン!
とんでも変形合体の中で
納得が出来る形でダイバロンが
完成しましたね。
でも、
とんでも変形合体がまだまだ沢山あるのが
ある意味で怖いです。
Re:これがダイバロン!
ダイバロンの変形でどこがとんでもかと言ったら歯車ですね。
合体後は膝の両側と腰に分散しているものが、合体前は本体の前方に1まとまりになっている。
まともな方法では完全変形化はまず無理でしょう。
とんでも変形合体でまだ取り上げていないものというと何でしょうね。『アクマイザー3』のザイダベック号が思い浮かびます(あと合体バイクも)。
今後取り上げる可能性は限りなく低いですが。
Re: Re:
オモロイドが新しく発売されましたがパッケージがデジタル絵になってしまいました。やはり昔の手書きイラストのほうが好きです。
ホビージャパン別冊のブラスティーは今でも読み返しています。そういえばモデルグラフィクス誌で以前強襲バクライオーという連載がありましたが、いつの間にかフェードアウトしたような。3機合体3形態のしっかりとした設定を見たかったです。
最近Amazonでタンサー5を見ました。母艦のビッグタンサーをはじめ、登場する3メカ、スカイ、ランド、アクアタンサーも立派な変形メカですね。にしても、やはりミニチュア特撮は心躍ります。 特撮メカはアイゼン1号2号が一番好きです。おもちゃは先端からドリルが出るのがかっこよかったです。劇中その描写はないのですが。YouTubeで新撮パートが見れますね。またああいう長方形キャタピラメカの活躍する特撮番組を見たいものです。
アニメシンカリオンの変形シーンをよく見ると、けっこういろんなとこが縮んでいます。プラレールではなく実車を変形させていますから、それでプロポーションを合わせているのだと思います。
Re:Re: Re:
オモロイドのパッケージは昔のと同じ人が描いているらしいです。ということはその人が自分の作業をデジタル化していなかったら、今回も手描きのパッケージだった可能性もありますね。でもやっぱり今の時代、特にシンプルな画風の場合は手描きではデジタルに比べてアピール力が弱いような気がします。
『バクライオー』は主人公メカのデザインがどうにも時代遅れな感じがして好きじゃなかったです。リアル寄りの内容ともマッチしてないし。と思いつつ調べてみたら「再始動」という話も 。デザインはどうなるんでしょうか。
『タンサー5』のメカは人型にならないので関心が薄かったのですが、「ワンタッチ変形」がイデオンのおもちゃに引き継がれている(同じメーカーなので)と後で知りました。だから乗物から別タイプの乗物へというパターンになったんですね。そこは興味深いところです。
シンカリオンはおもちゃはプラレール型、アニメではリアルな列車なんですね。ギャグアニメでもないのにプラレール型の列車が走ってたらそりゃ変ですよね。十数年後には、超合金魂みたいな企画でリアルな列車から変形するおもちゃが出るかもしれません。
こんにちは、Keidaです。
遅ればせながら、ご報告します。
ちょっとパソコンの調子が悪くて。
もうすぐ、送っていただいたメールにお返事するつもりです。
私は、あなたがダルタニュスの作品を更新することを決めたことをとてもうれしく思っています。この作品は、あなたの最高の作品の一つであり、それに値するものだと思います。これからは、未来のロボットです。
あなたとアイデアを交換するのは楽しいことでしたが、あなたが成し遂げたことは、すべてあなたの素晴らしい技術によるものです。あなたは本当に恵まれていて、才能がありますね。
ダルタニュスのページで私の名前を見ることができて光栄です。
そしてこれからも、あなたの素晴らしい作品で私たちを驚かせてください。
Re:
先日のメールでも書きましたが、「武器」のアイディアを検討し始めた当初は、ページを新たに加えるほどの内容にはならないでのはと思っていました。
それがYuri様の助力もあっていつの間にかこんなにアイテムが増え、満足のいくページを作ることができました。自分でも驚いています。
本体の絵も描き直すことになったのは当然として、実は変形パターンも一部変える必要が出てきて、予想外に手こずりました。
ともあれ無事完成してひと安心です。
昔のゲームはパッケージが手書きイラストで豪華で綺麗したね。全然違うキャラが書いてあったり、沙羅曼蛇の蛇とかいつ出てくるんだよと思ってました。
変形メカといえばフォーメーションZとかテグザーとか、最近ブラスティーが商品化されましたが、ホビージャパン版のほうも好きでした。
ザボーガーはとても好きな作品です。子供でも無理と分かっていても胴からタイヤがでてくるシーンをとても興奮して見ていました。
ザボーガーを語るうえであのタイヤ収納は外せない要素となっていますが、そう考えると、ウィナルド?Uの変形は秀逸ですね。張り出した胸も妙にかっこよかったし、背中に乗るというのも斬新でした。
Re:
昔のゲームの画面ってドットの粗いシンプルなものでしたから「画面ではこんなだけど本当はこういうイメージなんで脳内で補完してね!」とパッケージでアピールしていたんだと思います。今ではゲーム画面自体がその辺の下手なイラストよりも緻密で美麗なものになっていて、そんな必要もなくなったんでしょうね。プラモデルでも最近は、箱絵より側面の完成写真の方がカッコイイんじゃないか、と感じることがあります。
ブラスティーはホビージャパンの企画が元祖だと思ってました。ゲームが先にあったんですね。
ザボーガー(に限らず昔の特撮の)の変形シーンはその部分だけのアップになるから、タイヤと胴体の関係性が曖昧なんですよ。もうちょっと引いて見せてくれよ〜と当時思ってました。
ウィナルドⅡ世は後輪が無変形で出しっぱなしなんですよね。でもそれほど目立たないようにうまくできてます。背中に乗れるようシートのクッション部分が回転するのが芸コマ。
昔ゲームの変形メカ
昔ゲームの変形メカは変形できるか疑問だったのですが、2023年の玩具技術なら可能な気がします。
特にナイトストライカーのインターグレイXsiは車からロボに変形するだけでなく、コックピットからバイクが出るギミックなどありますから。
Re:昔ゲームの変形メカ
私、ゲームにはまったく疎くいもので、変形メカの出てくるゲームといっても『スーパーロボット大戦』ぐらいしか思いつかないです(変形しないロボットの出てくるゲームならいくらか知ってます)。
インターグレイXsiは名前は知らなかったけどどこかで見たような気はします。調べてみたら変形するモデルが出てますね。もともと割と無理なく変形できそうなデザインだと思いますよ。
マシンドルフィン
ロボ形態の時の股関節は大河原邦男の重甲侍鬼に似ていますね
デトネイターオーガンのエクテアーマーとか
ブルージェンダーのアーマーシュライクとか
足突っ込む系のロボは尻餅ついたら膝折れそうです
ロボコンサイクルとか昔の特撮は平気で街中走ってましたよね
中に人が入ってたんでしょうか
ロボ丸もバッテンバイクに乗ってましたし
この手の実走着ぐるみを最後に見たのは
もりもりぼっくんの救急九太郎だと思います
確か後期のOPでビル街を疾走してたと記憶してます
Re:マシンドルフィン
ロボットの股間に操縦者の脚が入っている例は少数ながらありますが、腰幅が広くなったりして不恰好なので主人公メカにはしにくいですね。私のマシンドルフィンの場合は、腿の内側を削って腰幅を減らす、その部分を前アーマーで隠すという対策を取りました。
重甲侍鬼は腰幅は広いのに腿とスネをずらしてつなぐことで自然なプロポーションに見せており、この発想にはうならされたものです。
エクテアーマーはロボットの腿に、アーマーシュライクは股間に操縦者の脚を入れるタイプで、方式が違いますね。アーマーシュライクは脚の入る部分を2つに分けることで小さく見せているのが新しかったと思います。
マシンドルフィンは毎回道路の上を移動するシーンが出てきましたが、路面を走るのではなく合成で宙に浮いているというものでしたね(クルマの意味がないし、道路の上である必然性もない…)。地上を走るシーンもわずかにあったように思いますがあれはミニチュアを使ってたんでしょうね。
実走着ぐるみの例としては、『仮面ライダーBLACK RX』の敵怪人で下半身が車両になってるのがいました。でも疾走するシーンはなかったような気がします。
明けましておめでとうございます。
ガ・キーンを見て、特にこの太腿に脚部を収納して車輪にする機構に、とてもインスピレーションを掻き立てられました。 この機構は、バイクに変形するロボに応用すれば、かさばる車輪部分を、女性型ロボであっても体内(太腿)にも納められそうで凄く良いと感じました。
女性的体型を維持したまま車輪を体内に格納するだけなら他の変形機構もありますが、そういったものは大抵が車輪が小さくなりがちか脚部などが巨大なので。ガ・キーンの機構なら、女性的なプロポーションを維持したまま、素体以外のパーツに頼らずタイヤ部分を処理できそうで大変面白いです。
Re:明けましておめでとうございます。
お久しぶりです。
これはなかなか考えさせられるご意見ですね。
私はこれまで乗り物に変形するメカを考える時、タイヤやキャタピラを分割・変形させないという方針でやってきました。そこをいじったら負けだという気持ちがあるんですよ。
例えばザボーガーのタイヤを折り畳んでから本体に収納しスマートなプロポーションを達成したとして、賞賛されるのか。むしろ反則と言われそうです。
ではこのガ・キーンの場合はなぜ自分的にOKなのか、を検討してみました。
とりあえずの結論として「タイヤが収納されるのでなく別の物として表に出ている、ディテールの比較から人型の時タイヤがどこにあるかわかる」というあたりがポイントと思われます。
この問題は今後も研究していきたいと思います。
あけましておめでとうございます
久しぶりになりますが書き込みさせて頂きます。(長文で失礼いたします。)
・ゴッドライディーン
元祖のライディーンの変形で無茶な部分(特に腕のガワ)を玩具で変形可能にアレンジした(あと若干ガブスレイ)印象だったゴッドライディーン、それを更に武器の大型化と鳥脚との共有化でスマートにされていたのとゴッドボイスの展開がお見事でした。腕の武器がちょっとウィングガンダムEW版のイメージにも感じました(自分としてはライディーンの変形を突き詰めるとウィングガンダムの変形になるのかなと思っております)
・ビスマルク
こっちもガワの処理が特徴、しかしこっちは収納せずマントにするという大胆設定。なんなら機首もフードを背中に下ろした事にしてしまえばOK?と思いましたが、見事に収納する形にされているのが流石でした(構造がダイレオンぽい?)。さらに3機に分離及びオルガニックフォーメーションも両立させているのが更に見事な設計でした。
(ロードレオンて当時見た時にレーシングカーっぽくない(どっちかというとボレット3号)と思ったなぁ。)
・グレートファイブ
やはりジャイロの機首を拳側に持ってきましたか。色が黒になったという事はブラックがジャイロ、ピンクがドリル担当?
ギャラクシーロボも変形のアレンジが破綻なくしかも体型がマッシブで均整がとれているのが良かったのと、分割なしで2体合体しているのが圧巻。
この次はいよいよ戦隊初のグレート合体ロボに挑戦されるのでしょうか。その際は牛とサイのパーツ処理がどうなるのか楽しみです。
・ガ・キーン
元々のトンデモ設定(二人が操縦席から飛び出してぐるぐる回った軌道がコアパーツになる)を解決しているのが素晴らしい。タイヤの変形、大車輪アタックとバリアントアンカー、特にプライザーの脚がハンドル握っている腕に見える所が見事です。
予告のマシンは一応知っているのですが、番組見てなかったので詳細知らないんです。ロボットは玩具オリジナルって事位。バイクロッサーも(多分放映時間が平日夕方だった為)
Re:あけましておめでとうございます
今年もよろしくお付き合いお願いします。
>ゴッドライディーン
言われてみれば脚の変形がガブスレイに似てますね。これは意外な発見です。
ウィングガンダムの変形は、無変形の本体に大きなパーツを足して飛行メカに見せるというやり方で、変形メカとしてはライディーンより退行しているというのが私の印象です。
>ビスマルク
機首が頭をカバーする程度の大きさなら謎の余計なパーツで済ませることもできるけど、大きすぎるんですよね。
ビスマルクは元々は実写特撮の企画だったせいか、メカがアニメ作品の中では異質な感じがします。ロードレオンも特撮っぽいデザイン、なのか?
ボレット3号とはマニアック。スタジオぬえの本で知ってますがアニメでは見た記憶がないです。
>グレートファイブ
メカのの色を変えたのに合わせて5人の戦士の構成も「赤青黄白黒」という想定です。
ギャラクシーロボは積み上げてきたデザインの進歩が一挙に崩壊したかのようなセンスで、こんなん出すくらいなら無理に2号ロボ出さんでも…などと当時思ったものです。
スーパーライブロボについては目下構想をを進めていますが、ライブボクサーがデザイン・変形とも大きく変わることになりそうです。
>ガ・キーン
>元々のトンデモ設定を解決している
これはデザイン面でコアパーツを大きく目立つようにしたいというところから発展していったアイディアです。
>プライザーの脚がハンドル握っている腕に見える
プライザーとマイティーでバリアントカーを構成するとなると分量が足りず小さくなってしまうので、バリアントカーを大きく、ガキーン本体を小さく見せるための工夫です。ビスマルクで人馬形態(これは自慢できる出来ではありませんが)を描いたことがヒントになりました。