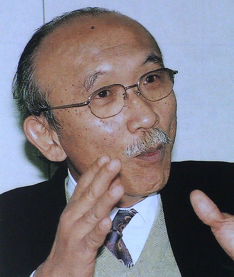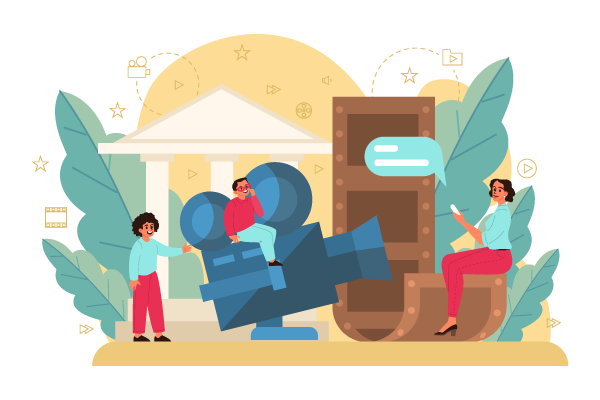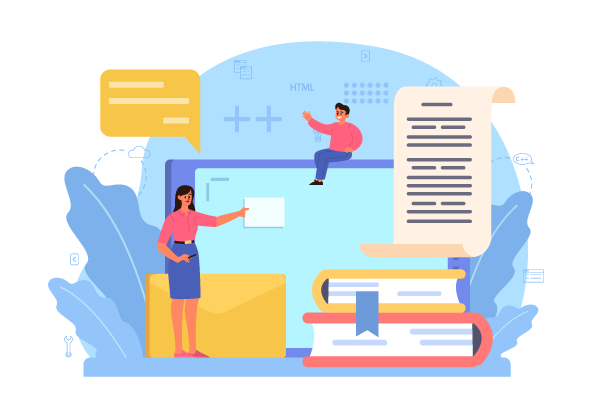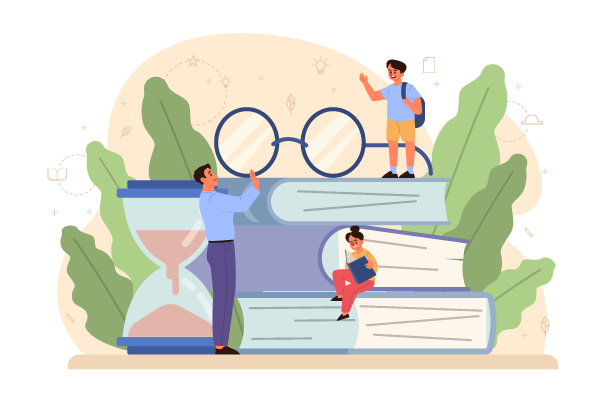数学教育研究所は、日本における数学教育の発展に取り組む場として設立されました。算数から高等数学まで幅広い領域を対象に研究を行い、とくに生徒の理解を深めるための実践的な指導法の開発に重点を置いています。活動は計算技術の指導にとどまらず、数学的思考力や問題解決能力を養うことを目的としており、その成果は教育者や研究者に広がり、日本各地の教育現場に新しい視点をもたらしています。
研究所の理念や設立当初の背景については、2000年4月にまとめられた「設立趣意書」に詳しく記されています。ここでは、その全文を掲載します。
設立趣意書の全文を表示する
明治以後、日本の教育は欧米先進国に追いつけ追い越せの旗印のもと、教師が生徒に多くの知識を効率よく伝達するために集団一斉の教授スタイルをとり続けてきた。その結果、多くの国民が平均的に高い水準の教養を持ち、近代産業を支える技術力を維持することができたという事実は否定できない。
しかし、一億総中流意識の時代となり、個性尊重が叫ばれ、産業構造が変化し、日本では「物」が作られなくなり、情報やサービスが経済活動の中心になってきた現代では、額に汗して生きることを避け、少しでも楽をしようという風潮が世の中を支配しつつあるように思われる。
個性尊重とは言いながら、今の若者はほとんど同じ人間に見える。持ち物も、衣服も、趣味も、話題も似ている。もちろん外見上だけのことかも知れないが、しかし内面的にも個性豊とも思えない。
親は、子供がよい大学に進むことを熱望し、小さい頃から「塾通い」をさせて知識の詰め込みに走る。しかもその結果はペーパーテストの点数という尺度で測られ、子供の心を痛めつける結果となっている。
多くの子供が毎日、詰め込みの教育をされた結果、新しいことを学ぶうれしさ、楽しさではなく、できるだけ勉強から遠ざかろうとする気持ちが大きくなってくる。中学校や小学校の学級崩壊という事象も、学校が子供たちにとって、息苦しい場所になっていることが原因の一端をしめているのであろう。
もちろん、現在の学校教育の混乱の原因は、複雑で、根も深く、簡単に改善はできないであろうが、我々は理論ではなく、実践できることから始めて、少しでも改善の方向を見つけていかなくてはならないと考える。
これまでの伝統的な教育は「教え込みの教育」「暗記中心の教育」であった。
しかも教師から生徒への一方通行の伝達であった。これは大学受験が主にペーパーテストで行われているという現状からすれば、当然とられるべき道であろう。しかし大学に入学するだけが目標となり、大学入学と同時に、目標を失うものも多いという現状を考えれば、我々は、大学入学後も、社会人となっても、自ら進んで研究課題をもち、勉強を継続するような人間を育成しなくてはならない。
学習には、「覚えること」「訓練すること」と「発表すること」「鑑賞すること」「作ること」が備わっていなくてはならない。
さらにこれらの学習は「受け身学習」ではなく、「能動的学習」でなければいけない。これまでの教育では、「覚えること」「訓練すること」だけが、「させられている」という「受け身学習」として存在したことを反省しなくてはならない。
知識の詰め込みだけではなく、実験や観察を通じて、新しいものを自ら感じ取り、議論し、発表して、さらに高度な課題を自ら見つけて追求していくという、学問本来が持っている「おもしろさ」を体験することが重要である。総合学習というものも、本来のねらいはここにある。しかし「「総合学習」ではどういうことを教えればよいのでしょう。」という疑問が教員の中にあるらしいが、この質問自体がすでに的はずれな質問であると言わざるを得ない。なぜなら「総合学習」のねらいは、教えることではないからである。
数学教育も、「発表すること」「鑑賞すること」「作ること」を学習の中に取り入れる必要がある。
これまでのように、教科書と黒板とチョークだけの世界では実現困難であったことが、テクノロジーを使用すると可能になるのである。
そこで、清風高校数学教育研究所では、新しい数学教育観に立って、テクノロジーを道具として利用して、生徒が能動的に「作る」「実験する」「発見する」「発表する」「議論する」数学学習を実践し、その結果を広く教育界に広め、同時に多くの仲間と共同して、新しい教材を開発することを目的として活動を開始する。
以上 2000年4月 設立趣意書より