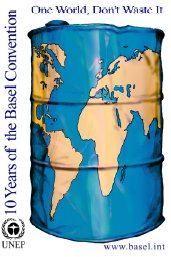|
僶乕僛儖丒傾僋僔儑儞丒僱僢僩儚乕僋乮BAN乯曬崘彂 2006擭11寧8擔 擔杮僼傿儕僺儞宱嵪楢実嫤掕乮JPEPA乯 擔杮偺傾僕傾偵偍偗傞桳奞攑婞暔杅堈偺帺桼壔峔憐偺戞堦曕 忣曬尮丗JPEPA as a Step in Japan's Greater Plan to Liberalize Hazardous Waste Trade in Asia 8 November 2006 Basel Action Network http://www.ban.org/library/JPEPA_report.pdf http://ban.org/library/JPEPA_Report_BAN_FINAL_29_Aug_071.pdf 栿丗埨娫丂晲丂乮壔妛暔幙栤戣巗柉尋媶夛乯 http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/ 宖嵹擔丗2006擭11寧10擔 峏怴擔丗2006擭11寧14擔 偙偺儁乕僕傊偺儕儞僋丗 http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/basel/JPEA/JPEPA_Report_BAN.html 1. 偼偠傔偵
丂娭惻揚攑偺栚昗偲偝傟偰偄傞攑婞暔偺懡偔偼丄偦偺杅堈偼丄乭桳奞攑婞暔偺崙嫬傪墇偊傞堏摦媦傃偦偺張暘偺婯惂偵娭偡傞僶乕僛儖忦栺偺壓偵尩奿偵娗棟偝傟傞傋偒偲偝傟傞崙嵺揑偵巜掕偝傟偨攑婞暔偱偁傞丅擔杮偲僼傿儕僺儞偺憃曽偲傕偵僶乕僛儖忦栺偺掲栺崙偱偁傞丅摨忦栺偼掲栺崙偵桳奞攑婞暔偺崙嫬傪墇偊傞堏摦傪嵟彫偲偡傞媊柋傪壽偟丄摨忦栺偱僇僶乕偝傟傞攑婞暔傪帺崙撪偱張棟偡傞傛偆媮傔偰偄傞丅偝傜偵僶乕僛儖忦栺偼偳偺傛偆側攑婞暔偺桝擖傕嬛巭偡傞偲偄偆掲栺崙偺庡尃傪擣傔偰偄傞丅偟偐偟丄僶乕僛儖忦栺偦傟帺恎偼丄愭恑崙偲奐敪搑忋崙娫偺攑婞暔杅堈傪尩枾偵偼嬛巭偟偰偄側偄偲偄偆偙偲傪擣幆偡傞偙偲偑廳梫偱偁傞丅僶乕僛儖忦栺廋惓忦崁偼敪岠偵昁梫側悢偺崙偵傛傝斸弝偝傟傟偽偦傟偑幚尰偡傞乮栿拲1乯丅 丂1995擭丄僼傿儕僺儞傕擔杮傕嶲壛偟偨戞3夞僶乕僛儖忦栺掲栺崙夛媍偼僶乕僛儖忦栺傪廋惓偡傞寛媍 III/1傪嵦戰偟偨偑丄偦傟偼偳偺傛偆側棟桼偑偁偭偰傕丄OECD乛EU偺壛柨崙媦傃儕僸僥儞僔儏僞僀儞乮Annex VII乯偼偦傟傜埲奜偺彅崙偵懳偟偰慡偰偺桳奞攑婞暔偺桝弌傪姰慡偵嬛巭偡傞傕偺偱偁傞丅擔杮偼 Annex VII乮OECD 壛柨崙乯偺儕僗僩崙偱偁傝丄僼傿儕僺儞偼偦傟傜埲奜偺崙偱偁傞丅偙偺嬛巭廋惓忦崁偼奐敪搑忋崙偵傛偭偰挿傜偔懸朷偝傟憗婜偺敪岠偑媮傔傜傟偰偄偨丅擔杮傕僼傿儕僺儞傕傑偩僶乕僛儖嬛巭廋惓傪斸弝偟偰偄側偄偑丄僼傿儕僺儞偼桳奞攑婞暔偺晹暘揑桝擖嬛巭傪偟偰偄傞偙偲偱抦傜傟偰偄傞[1]丅擔杮偼丄傾儊儕僇傗僇僫僟側偳堦埇傝偺愭恑崙偲摨偠偔僶乕僛儖忦栺廋惓忦崁傪斸弝偡傞堄恾偼側偔丄幚嵺偵偼偦偺栚揑傪懝側偆傛偆愊嬌揑偵摦偄偰偄傞丅JPEPA 偺庢慻偼偙偺愴棯偺堦梼偱偁傞偲変乆偼尒偰偄傞丅 丂偙偺擔斾宱嵪嫤掕乮JPEPA乯偑挷報偝傟偰埲棃丄僼傿儕僺儞偲擔杮偺惌晎摉嬊偼娭惻揚攑僾儘僌儔儉偵攑婞暔傪娷傔傞偙偲偼扨偵帠柋揑側偙偲偱偁傝丄僶乕僛儖忦栺傗僼傿儕僺儞偺崙撪朄傪柍岠偵偡傞傕偺偱偼側偄偲孞傝曉偟庡挘偟偰偄傞丅 丂乭桳奞攑婞暔偵懳偟偰偼廫暘側埨慡嶔偑偁傞乭偲僼傿儕僺儞捠彜挿姱僼傽價儔偼弎傋偨丅乭摨嫤掕偵娷傑傟偰偄傞崁栚偺傂偲偮偼丄変乆偑婋尟側桳奞攑婞暔偲屇傇傕偺偱偁傞丅偦傟偼慡偰傪娷傓杅堈偺拞偺堦晹偱偁傝丄偦偺偙偲偼変乆偑偦傟傜傪変偑崙偵桝弌偡傞偙偲傪嫋偡偲偄偆堄枴偱偼側偄丅攑婞暔忦崁偼偦傟埲忋偺壗傕偺偱傕側偄[2]丅乭 丂摨條偵丄擔杮戝巊娰偼師偺傛偆側惡柧傪敪昞偟偨丅 丂乭擔杮惌晎偼僶乕僛儖忦栺偵婎偯偔朄揑榞慻傒傪妋棫偟偰偍傝丄尩奿側桝弌擖娗棟傪幚巤偟偰偄傞偺偱丄傕偟丄偦偺傛偆側崙偺惌晎偑偦偺傛偆側桝弌傪彸擣偟側偄尷傝丄僼傿儕僺儞傪娷傓懠偺崙偵懳偟偰偳偺傛偆側桳奞偱婋尟側攑婞暔傕桝弌偡傞偙偲傪嫋偝側偄丅乭 丂偙偺惡柧偺屻敿晹偼偁傞偙偲傪弎傋偰偄側偄偲偄偆揰偱廳梫偱偁傞丅偦傟偼丄擔杮偼丄僼傿儕僺儞枖偼偦偺懠偺偳偺傛偆側奐敪搑忋崙偵懳偟偰傕丄僶乕僛儖忦栺廋惓嬛巭忦崁媦傃僶乕僛儖忦栺堦斒媊柋偵偟偨偑偭偰丄桳奞攑婞暔偺桝弌傪偟側偄偲弎傋偰偄側偄丅傓偟傠搑忋崙偼偦偺傛偆側桝弌傪彸擣偟側偔偰偼側傜側偄偲偄偆偙偲偵棷堄偟偰偄傞丅擔斾宱嵪嫤掕乮JPEPA乯偑敪岠偡傟偽丄擔杮偼僼傿儕僺儞偼偦偺傛偆側桝弌傪乭彸擣偟側偔偰偼側傜側偄乭偲庡挘偡傞偱偁傠偆偲峫偊傜傟傞丅 丂偙偺曬崘彂偺拞偱丄変乆偼桳奞攑婞暔偺娭惻掅尭傪娷傔傞偙偲偼扨偵帠柋揑側偙偲偱傕側偔丄杅堈岎徛偺億乕僇乕丒僎乕儉偵偍偗傞庢傞偵懌傜側偄暃嶻暔偱傕側偄偲偄偆偙偲傪徹柧偡傞丅偦傟偼朄揑偵廳梫側摦偒偱偁傝丄幚嵺丄悽奅偺僠僃僗丒僎乕儉偱擔杮偵傛偭偰尰嵼墘偠傜傟偰偄傞寁夋揑側愴棯偺堦梼偱偁傞丅偙偺僎乕儉偺寁夋偼丄桳奞攑婞暔偺崙嫬傪墇偊傞堏摦傪嵟彫偵偟丄偦偺杅堈傪尩奿偵娗棟偡傞偲偄偆僶乕僛儖忦栺偺媊柋傪暍偡偙偲偱偁傞丅 媟拲1丗 丂僶乕僛儖忦栺僂僃僽僒僀僩偱曬崘偝傟偰偄傞傛偆偵丗乭堦斒揑惌嶔偲偟偰媦傃僶乕僛儖忦栺偲桳奞暔幙媦傃婋尟側妀攑婞暔娗棟朄1990丄暿柤丄嫟榓崙朄6969偵婎偯偒丄DAO29偺戞VII復24愡媦傃25愡乮RA6969偺幚巤婯懃媦傃婯惂乯偱掕媊偝傟偰偄傞傛偆偵丄攑婞暔偺桝擖偼摨崙偵傛偭偰嫋壜偝傟側偄丅偟偐偟丄RA6969丄偦偺幚巤婯懃偲婯惂媦傃偺屻偵懕偔攑婞暔偺桝擖娗棟偺偨傔偺彅巜椷壓偱掕媊偝傟偰偄傞桳奞暔幙傪娷傓暔幙偺桝擖偼丄夞廂丄儕僒僀僋儕儞僌媦傃嵞張棟偺栚揑偵懳偟丄帠慜偺彂柺偵傛傞挿姱偺彸擣偑偁傞応崌偵尷傝嫋壜偝傟傞偐傕偟傟側偄丅DAO 94-28 偼丄撪晹偱嫋壜偝傟傞偲偄偆儀乕僗偱椺奜乮儕僒僀僋儕儞僌偺偨傔偺桳奞攑婞暔桝擖乯傪儕僗僩偟偰偄傞丅偦偺儕僗僩偼採埬偝傟偨娭惻掅尭偲偼偄偐側傞曽朄偵偍偄偰傕懳墳偟偰偄側偄丅偦偺儕僗僩偼壓婰偱擖庤偱偒傞丅 http://www.emb.gov.ph/laws/toxic%20substances%20and%20hazardous%20wastes/dao94-28.pdf 媟拲2丗Official: Enough safeguards vs toxic waste http://www.manilastandardtoday.com/?page=politics6_oct26_2006 栿拲1丗 僶乕僛儖忦栺偵偮偄偰 僶乕僛儖嬛巭椷丂寛媍 III/1 2. 僶乕僛儖忦栺偵斀懳偟攑婞暔杅堈偺帺桼壔傪媮傔傞擔杮偺悽奅揑側僉儍儞儁乕儞 丂僶乕僛儖嬛巭廋惓忦崁偑嵦戰偝傟偰埲棃丄擔杮偼丄JUSCANZ 乮僕儏乕僗僇儞僘乯偲偟偰抦傟傜傟傞奜岎僌儖乕僾乮擔杮丄傾儊儕僇丄娯崙丄僇僫僟丄僆乕僗僩儔儕傾丄僯儏乕僕儔儞僪乯偺彅崙偲偲傕偵僶乕僛儖嬛巭廋惓忦崁傪斸弝偡傞偙偲傪慾傫偱偒偨丅幚嵺丄擔杮偼桳奞攑婞暔偺崙嫬傪墇偊傞堏摦傪嵟彫偵偡傞偙偲偵娭偡傞僶乕僛儖忦栺偺媊柋偵偮偄偰丄摿偵僶乕僛儖嬛巭廋惓忦崁偵偮偄偰丄偳偺崙傛傝傕嫮偄寵埆姶傪帵偟偰偒偨丅 丂擔杮偼尰嵼丄攑婞暔杅堈傪嵟彫壔偡傞偨傔偺僶乕僛儖忦栺偺媊柋傪愽傝敳偗丄庛懱壔偟丄懝側偆偨傔偵條乆側愴慄偱嵟傕愊嬌揑偵妶摦偟偰偄傞崙偱偁傞丅埲壓偱柧傜偐偵偝傟傞傛偆偵丄JPEPA 攑婞暔杅堈忦崁偼扨弮偵岎徛帪偺帠柋揑側柤巆偲偄偆傛偆側傕偺偱偼側偄丅偦偆偱偼側偔偰丄偦傟傜偼傾僕傾堟撪攑婞暔杅堈寁夋偵岦偗偨傂偲偮偺戝偒側愴棯偺堦晹偱偁傞丅幚嵺丄擔杮偼丄桳奞攑婞暔偺乭娐嫬偵揔愗側娗棟乭媦傃乭攑婞暔儕僒僀僋儕儞僌乭傪嫮壔偡傞偲偄偆僼儕傪偟偦傟傪岥幚偲偟偰丄擔杮偼僶乕僛儖忦栺偺斖埻傪弅彫偟攑婞暔杅堈傪懀恑偡傞偨傔偵偄偔偮偐偺慜慄偱旕忢側搘椡傪暐偭偰偄傞丅 丂乭娐嫬偵揔愗側乭丄乭儕僒僀僋儕儞僌乭丄僉儍僷僔僥傿丒價儖僨傿儞僌乭丄偁傞偄偼乭俁俼倱乭偲尵偆傛偆側僌儕乕儞偱愊嬌揑側尵梩偱堄恾傪塀偡傗傝曽偼丄帺崙偱攑婞暔張棟偵愑擟傪帩偮傛傝傓偟傠偦傟傜傪桝弌偟偨偄偲朷傓崙乆偵傛偭偰偲傜傟偰偒偨丄偦傟帺懱偼怴偟偔傕側偄愴棯偱偁傞丅崙嵺揑側攑婞暔庢堷偑1980擭戙屻敿偵悽奅揑偵柧傜偐偵偝傟旕擄偝傟偰埲棃丄桝弌崙傗桝弌嬈幰偼攑婞暔桝弌傪惓摉壔偡傞偨傔偵丄偙偺乭僌儕乕儞乭偲偄偆尵梩傪棙梡偟丄桝擖崙偺棙塿偵側傞偲庡挘偟偨丅 丂怴偟偄偙偲偼丄摨偠榑徹偺懀恑偵岦偗偰擔杮偵傛偭偰傕偨傜偝傟傞岻柇偝偲搳帒偺儗儀儖偱偁傞丅斵傜偼丄夁嫀偵僶乕僛儖忦栺偵偍偄偰婞媝偝傟枖偼怣梡偝傟側偐偭偨偙傟傜偺庡挘傪幚尰偡傞偨傔偵怴偨側応傗忦栺傪幚嵺偵嶌傝弌偟偰偄偨丅擔杮偼丄搰崙偱偁傝戝検偺攑婞暔傪抲偄偰偍偔偨傔偵棙梡偱偒傞埨偄搚抧偑慡偔晄懌偟偰偄傞偑丄堦恖摉偨傝偺攑婞暔攔弌検傪恀寱偵尭傜偡偙偲傪懹偭偰偒偨偺偱丄懠偺JUSCANZ 彅崙傛傝傕偙偺僉儍儞儁乕儞偵娭偟偰擬怱偱偁傞偲怣偠傜傟偰偄傞丅 柧傜偐偵側偭偨擔杮偺僉儍儞儁乕儞偵偍偗傞 JPEPA 偺栶妱 丂攑婞暔杅堈傪悇恑偟傛偆偲偡傞擔杮惌晎偺愴棯偼丄惌晎宯尋媶婡娭偱偁傞嵿抍朄恖抧媴娐嫬愴棯尋媶婡娭乮IGES)偐傜弌斉偝傟偨惌嶔暥彂亀崙嵺儕僒僀僋儖摿嬫偲傾僕傾堟撪僱僢僩儚乕僋偺峔抸亁[3]偵旕忢偵偁偐傜偝傑偵弎傋傜傟偰偄傞丅JPEPA 偺栶妱偲愴棯偺攚宨偼丄攑婞暔杅堈傪梕堈偵偡傞偨傔偺擔杮偺惵幨恀偲屇傇偙偲偑偱偒傞偙偺暥彂偐傜堷梡偟偨師偺暥復偑柧傜偐偵偟偰偄傞丅乮傾儞僟乕儔僀儞偼嫮挷偡傞偨傔偵壛偊傜傟偨乯 丂乭偙偙偱変乆偑採埬偡傞惌嶔偼丄娐嫬揑丒宱嵪揑偵揔惓側儕僒僀僋儖帒尮偺崙嵺巗応偺宍惉懀恑傪栚揑偲偟偰偄傞丅乭 丂乭奺崙偵乽崙嵺儕僒僀僋儖摿嬫乿傪愝抲偡傞丅奺摿嬫偼丄巜掕峘榩偲巜掕岺嬈抧堟偐傜峔惉偝傟傞丅巜掕峘榩偱偼丄擣掕婇嬈娫偵尷偭偰儕僒僀僋儖帒尮偺崙嵺庢堷傪擣傔傞丅乭 丂乭偙偺惌嶔傪岠壥揑偵幚巤偡傞偨傔偵偼丄壗傜偐偺崙嵺揑崌堄傪庢傝偮偗傞昁梫偑偁傞丅嶲壛崙偼丄捠娭庤懕偒偵娭偡傞嵶偐側婯懃丒婯掕傗丄儕僒僀僋儖帒尮偺庢埖偄丒張棟偵娭偡傞帠崁偵崌堄偟側偗傟偽側傜側偄丅偦偺屻丄崙嵺儕僒僀僋儖摿嬫偺僱僢僩儚乕僋傪峔抸偡傞丅乭 丂JPEPA 偼丄偙偺惌嶔傪岠壥揑偵幚巤偡傞偨傔偵偙偙偵採埬偝傟偰偄傞乭崙嵺揑崌堄乭側偺偐丠 丂乭杮採埬偺棙揰偺傂偲偮偼丄彨棃偺杮奿揑側崌堄偵岦偗偨戞堦曕偲偟偰丄僷僀儘僢僩揑偵崙丒抧堟傪尷掕偟偙偺惂搙傪摫擖偱偒傞揰偵偁傞丅乭 丂僼傿儕僺儞偼擔杮偵傛傝戞堦曕偲偟偰偺僷僀儘僢僩僾儘僕僃僋僩偺傂偲偮偲尒傜傟偰偄傞偺偐丠 丂乭儕僒僀僋儖帒尮偺崙嵺棳捠偵偼丄娭惻棪偑崅偄丄旕娭惻忈暻偑偁傞偲偄偭偨悢乆偺忈暻偑偁傞丅偙偆偟偨忈暻偺偣偄偱丄攑婞暔傪儕僒僀僋儖帒尮偵曄偊傞僠儍儞僗偑朩偘傜傟偰偒偨丅偙偙偵採尵偡傞惌嶔傪幚巤偡傞偙偲偵傛傝丄儕僒僀僋儖帒尮偺庢堷偑崙嵺儕僒僀僋儖摿嬫撪偺擣掕婇嬈娫偱峴傢傟傞尷傝偵偍偄偰丄偙偺傛偆側忈暻偺娚榓傪捈愙揑偵峴偆偙偲偑偱偒傞丅乭 丂柧傜偐偵娭惻忈暻偺娚榓乮JPEPA乯偼傛偔寁夋偝傟庱旜堦娧偟偨愴棯偺堦晹偱偁傞丅師偵偙偺惌嶔暥彂偼旕娭惻杅堈忈暻乮偡側傢偪丄僶乕僛儖忦栺偺杅堈娗棟偲嬛巭乯偺偙偲傪尵偭偰偄傞丅 丂乭桳奞攑婞暔偺桝弌擖偼僶乕僛儖忦栺乮1989擭嵦戰乯偵傛偭偰婯惂偝傟偰偄傞丅忦栺偱偼丄捠夁崙傪娷傓慡偰偺崙偺彸擣偑媊柋偯偗傜傟偰偄傞偨傔丄桝弌擖庤懕偒偵挿偄帪娫偑偐偐傞丅偙偺庤懕偒偑儕僒僀僋儖帒尮偺崙嵺庢堷偵偍偄偰忈奞偲側偭偰偄偨丅偟偐偟丄崙嵺儕僒僀僋儖摿嬫偵偼傛傝娙慺壔偝傟偨庤懕偒偑摫擖偝傟傞偨傔丄偙偺栤戣傕旔偗傜傟傞丅乭 丂偙偙偱偙偺惌嶔暥彂偼柧妋偵擔杮惌晎偺僶乕僛儖忦栺媦傃僶乕僛儖嬛巭廋惓偺栚昗偲尨懃偵懳偡傞婎杮揑側寵埆姶傪偁傜傢偵偟偰偄傞丅僶乕僛儖忦栺偼丄乭儕僒僀僋儕儞僌乭偩偗偑僶乕僛儖忦栺偲僶乕僛儖嬛巭偺媊柋傪壥偨偝側偔偰傕傛偄偙偲偺朄揑惓摉惈偺崻嫆偲側傝摼傞偲偄偆傛偆側偙偲偼嫋偝側偄丅掲栺崙偼儕僒僀僋儖嶌嬈偼嵟廔張暘偲偟偰恀偵懡偔偺婋奞傪傕偨傜偡壜擻惈偑偁傝丄傛傝庛偄宱嵪椡偵晄嬒峵偵儕僗僋偲婋奞傪媦傏偟斵傜偐傜彜嬈揑偵嶏庢偟偰偄傞偙偲偵懳偡傞塀傟柂偲偟偰梕堈偵巊梡偝傟傞偲偄偆偙偲傪擣幆偟偰偄傞偺偱丄偙偺嬛巭廋惓偼偳偺傛偆側棟桼偑偁傠偆偲桳奞攑婞暔傪柧敀偵偦偟偰堄恾揑偵嬛巭偟偰偄傞丅嵟屻偵丄偙偺惌嶔暥彂偼偦偺寁夋傪幚巤偡傞偨傔偵擇偮偺拰偐傜側傞愴棯傪嫮挷偟偰偄傞丅偙偺愴棯偺戞堦偺拰偼 JPEPA 偺傛偆側擇崙娫帺桼杅堈嫤掕偺妶梡偡傞偙偲偱偁傞丅 丂乭1999 / 2000擭埲崀丄傾僕傾懢暯梞抧堟偱偼抧堟撪丒擇崙娫偺帺桼杅堈嫤掕乮俥俿俙乯偑媫寖偵奼戝偟偰偄傞丅偙偆偟偨擇崙娫丒抧堟撪杅堈嫤掕傪傔偖傞摦偒偼丄嬤偄彨棃搶傾僕傾嫟摨懱愝棫偵偮側偑傞偲婜懸偝傟傞丅崙嫬傪墇偊偨儕僒僀僋儖帒尮偺巗応奼戝偼丄偙偺傛偆側堟撪偵偍偗傞杅堈丒搳帒偺帺桼壔偺堦娐偲偟偰傕懆偊傜傟傞丅乭 丂幚嵺偵丄帺桼杅堈嫤掕偼梊尒壜擻偱偁偭偨偐傕偟傟側偄偑丄梊尒壜擻偱側偐偭偨偙偲乮妋偐偵僼傿儕僺儞偺柉廜偵傛偭偰偱偼側偄乯丄枖偼偳偺傛偆側曽朄偱傕旔偗傞偙偲偑偱偒側偐偭偨偙偲丄枖偼悽奅杅堈婡娭乮WTO乯偵傛偭偰婯掕偝傟側偐偭偨偙偲偼丄崙嫬傪墇偊偨儕僒僀僋儖帒尮偺巗応奼戝偱偁傝丄偙傟偼偁偨偐傕傂偲偮偺扨弮側彜昳偺傛偆偵桳奞攑婞暔偺帺桼壔傪沀嬋偵昞尰偡傞傕偺偱偁傞丅擔杮偑宱嵪揑掞峈椡偺庛偄強偵攑婞暔傪棳偟崬偙偲偑嫋偝傟偨帪戙偵帪寁傪媡栠傝偝偣傞偲偄偆惌帯揑栚昗傪扴偆偱偁傠偆偲偄偆偙偲偼梊尒偱偒側偐偭偨丅 丂偙偺惌嶔偺攚宨傪尒傞偲丄JPEPA偱偺杅堈帺桼壔偼丄尰嵼偺悽奅偺朄揑媦傃椣棟揑婯斖偵斀偟偰桳奞攑婞暔媦傃偦偺懠偺攑婞暔偺杅堈偵崙嫬傪奐曻偟丄愭恑崙偐傜奐敪搑忋崙傊偺攑婞暔偺棳傟傪嫋偡挿婜揑偱戝婯柾側愴棯偵偍偗傞怺椂墦杁偺堦晹偱偁傞傛偆偵尒偊傞丅 丂乭儕僒僀僋儖帒尮丒嵞惗惢昳偺杅堈懀恑慬抲偵偮偄偰丄巜掕峘榩偱僷僀儘僢僩揑偵摫擖偟丄偦偺岠壥傪妋擣偟偨忋偱丄摿掕偺帺桼杅堈嫤掕偺拞偵惙傝偙傓偙偲傕壜擻偱偁傞丅乭 丂偙偺惌嶔暥彂偺乭壜擻偱偁傞乮could be乯乭偼傑偩丄尰嵼偺 JPEPA 偺尰幚偵傛偭偰抲偒姺傢偭偰偄側偄丅 媟拲3丗崙嵺儕僒僀僋儖摿嬫偲傾僕傾堟撪僱僢僩儚乕僋偺峔抸 http://enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload/261/attach/LTP-05-006.pdf乮擔杮岅斉乯 http://www.iges.or.jp/en/pub/pdf/policybrief/001.pdf乮塸岅斉乯 擔杮偺俁俼僀僯僔傾僥傿僽
丂偙偺柤慜偼丄傕偪傠傫嬁偒偑傛偄偑丄側偤擔杮偑偙偺僀僯僔傾僥傿僽偵僶乕僛儖忦栺傪庢傝崬傑側偐偭偨偺偐偼偦偙偱弎傋傜傟偰偄傞栚昗傪棟夝偡傟偽偡偖偵暘傞偙偲偱偁傞丅俁俼僀僯僔傾僥傿僽偺庡梫側栚昗偺堦偮偼師偺傛偆偵弎傋傜傟偰偄傞丅乮栿拲2乯 丂乭婛懚偺娐嫬媦傃杅堈忋偺媊柋媦傃榞慻傒偲惍崌惈偺偲傟偨宍偱丄嵞惗棙梡丄嵞惗嶻偺偨傔偺暔昳丒尨椏丄嵞惗棙梡丒嵞惗嶻偝傟偨惢昳媦傃傛傝僋儕乕儞偱岠棪揑側媄弍偺崙嵺揑側棳捠偵懳偡傞忈暻傪掅尭偡傞丅乭 丂乭嵞惗棙梡丄嵞惗嶻偺偨傔偺暔昳丒尨椏乭偼崙嵺揑側掕媊偱偼乭攑婞暔偱偁傝丄攑婞暔偵偲偭偰偺棳捠偺忈暻偺嵟傕柧敀側椺偼丄傑偝偵丄僶乕僛儖忦栺丄僶乕僛儖嬛巭廋惓忦崁丄偦偟偰僶乕僛儖忦栺偑擣傔偰偄傞奺崙偺桝擖嬛巭椷偱偁傞丅NGOs 偲僶乕僛儖忦栺掲栺崙偵傛傞尩偟偄斀懳偵捈柺偟偰丄擔杮偼偦偺昞尰傪婔暘榓傜偘偨偑丄搰崙擔杮偱敪惗偡傞攑婞暔偺嶳傪傾僕傾偺椬崙偵傕偭偰峴偔偙偲偱攑婞暔栤戣偺抧堟揑乭夝寛乭傪恾傠偆偲偡傞擔杮偺堄恾偼偦偺傑傑巆偭偰偄傞偙偲偼柧傜偐偱偁傞丅擔杮偼偙偺堄恾傪岥摉偨傝偺傛偄昞尰偵偡傞偨傔偵丄乭儕僒僀僋儕儞僌乭丄俁俼倱乭丄乭帺桼杅堈乭丄乭僉儍僷僔僥傿丒價儖僨傿儞僌乭丄偦偟偰乭娐嫬偵揔惓側娗棟乭摍偺尵梩傪巊偭偰偄傞丅2006擭3寧偵搶嫗偱奐嵜偝傟偨傾僕傾抧堟俁俼s夛媍乮栿拲3乯偵偍偗傞媍挿僒儅儕乕偱師偺傛偆偵姪崘偟偰偄傞[4]丅 丂乭摟柧惈偲捛愓壜擻惈傪帩偭偨桳奞攑婞暔傪娷傓儕僒僀僋儖帒尮偺偨傔偺抧堟巗応傪妋棫偡傞偙偲丟帺桼杅堈嫤掕乮FTAs乯傪娷傫偱丄桝弌崙偲桝擖崙偺娫偺俁俼娭楢嫟摨傪峔抸偡傞偙偲丟崙乛嫟摨懱偺拞偱憡懳揑側棙揰乮偨偲偊偽丄媄弍揑擻椡丄楯摥椡妋曐丄巗応傊偺傾僋僙僗乯偺偁傞強偵搳帒偡傞俁俼惌嶔傪揥奐偡傞偙偲乭 丂擔杮偺攑婞暔傪張棟偡傞偨傔偵僼傿儕僺儞傪棙梡偡傞偲偄偆乭憡懳揑側棙揰乭偼丄楯摥椡偲搚抧戙偑偼傞偐偵埨偄僼傿儕僺儞偼丄擔杮偵斾傋偼傞偐偵埨偔攑婞暔張棟傪幚尰偡傞偙偲偑偱偒傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅偦偙偱弎傋傜傟偰偄側偄偙偲偼丄僐僗僩偺奜晹壔偺挿婜揑側塭嬁偲偄偆憡懳揑側寚揰偱偁傞丅尵偄姺偊傟偽丄擔杮偼丄挿婜揑側愑擟丄儕僗僋丄怑嬈揑寬峃栤戣丄媦傃丄巆熢偺張暘傗儕僒僀僋儖憖嬈偐傜偺攔弌塭嬁傪娷傫偱桳奞攑婞暔偺張暘乛儕僒僀僋儕儞僌偵傛傞崙搚偺媇惖偐傜摝傟傞偙偲偑偱偒傞偲尵偆偙偲偱偁傞丅慡偰偺奜晹僐僗僩偑寁嶼偝傟偨帪偵偼娫堘偄側偔丄偙傟傜偺慬抲偼擔杮偵偼宱嵪揑偵桳棙偱偁傝丄僼傿儕僺儞偵偼傑偝偵晄棙偱偁傞丅BAN偼擔杮偺俁俼僀僯僔傾僥傿僽傪乭桳奞暔幙杅堈偺壖柺乭偲屇傫偱偄傞[5]丅 栿拲2丗俁俼僀僯僔傾僥傿僽妕椈夛崌 娐嫬徣僀僔儏乕儁乕僷乕乛壽戣嘦 崙嵺棳捠偵懳偡傞忈暻偺掅尭 http://www.env.go.jp/recycle/3r/outline/issues_paper.pdf 栿拲3丗傾僕傾懢暯梞娐嫬奐敪僼僅乕儔儉戞2僼僃乕僘乮APFED II乯愱栧壠夛崌丂2006擭3寧5擔奐嵜乯 http://www.iges.or.jp/jp/ltp/activity05.html 媟拲4丗APFED Expert Meeting on the 3Rs in Asia March 5, 2006 Tokyo, Japan Draft Co-chairs乫 Summary http://www.iges.or.jp/en/ltp/pdf/activity05/summary.pdf 媟拲5丗The 3R Initiative: A Mask for Toxic Trade? http://www.ban.org/Library/briefingp9_april2006.pdf 擔杮偼桳奞攑婞慏偵懳偡傞僶乕僛儖忦栺偺尃尷偺庛懱壔傪恾偭偰偄傞
丂擔杮偼丄嫮椡側悽奅偺塣桝嶻嬈傪戙曎偟偰丄僲儖僂僃乕丄僀儞僪丄僊儕僔儍丄媦傃傾儊儕僇偲偲傕偵 僶乕僛儖忦栺偼攑慏偵揔梡偝傟側偄偟揔梡偡傋偒偱側偄偲擬怱偵庡挘偟偨丅擔杮偼偐偮偰僶乕僛儖忦栺夛媍偱丄嶲壛崙偑慏敃偵娭偟偰僶乕僛儖懱惂傪嫮壔偡傞曽岦傪朷傫偩庢慻傪慾巭偡傞忋偱庡摫揑側栶妱傪壥偨偟偨丅偦偟偰嵞傃丄乭venue shopping乭偺愴弍傪梡偄偰丄擔杮偼婛懚偺僶乕僛儖忦栺傛傝偼傞偐偵嶻嬈奅傛傝偺崙嵺奀帠婡娭乮IMO乯傊偺摴傪摜傒屌傔丄摨婡娭偑桳奞暔幙傪娷傓慏敃偺奐敪搑忋崙傊偺桝弌傪朩偘側偄慏敃夝懱偵娭偡傞戙懼忦傪嶌傞傛偆摥偒偐偗偨[6]丅 丂擔杮偑岎徛偵偍偄偰巜摫揑栶妱傪壥偨偟偨IMO忦栺埬乮draft乯偼丄僶乕僛儖忦栺偱偼攑婞暔惗惉幰偵壽偣傜傟偰偄傞愑擟傪崙嵺揑偵媡揮偝偣丄慡偰偺愑擟傪偦偺攑婞暔慏傪桝擖偟偨崙偵壽偡傕偺偱偁傞[7]丅摨忦栺偼尰嵼嵟廔寛掕偝傟傛偆偲偟偰偟偰偍傝丄嵟嬤偺10寧偵峴傢傟偨IMO夛媍偵偍偄偰擔杮偼僲儖僂僃乕丄僪僀僣媦傃傾儊儕僇偲偲傕偵丄僶乕僛儖忦栺偑栚揑偲偟偰偄傞悽奅偺桳奞攑婞慏偺奐敪搑忋崙傊偺晄嬒峵側攑婞傪杊偖偙偲偵偼傎偲傫偳栶偵棫偨側偄嵟掅尷偺偙偲亅乭僌儕乕儞丒僂僅僢僔儞僌乭偵偲偳傔傞偙偲傪妋幚偵偡傞偨傔偵庡摫揑偵摥偄偨[8]丅
丂僶乕僛儖忦栺偑慏敃傪庢傝埖偆偙偲傪朩偘傞暲乆側傜偸搘椡傪偟偰偄傞擔杮偺嵟戝偺娭怱偼丄嫮椡側奀塣嬈奅偺偨傔偵尰忬傪堐帩偡傞偙偲丄偡側傢偪丄慏偑偦偺惗柦傪廔偊偰攑慏偵側傞偲偒偵僐僗僩傪敪惗偝偣偢偵揝嵽偐傜旕忢偵棙塿偺忋偑傞廂妌乮墌乯傪摼傞偙偲偱偁傞丅擔杮偺峌惃偼傑偨丄夵慞偝傟偨媄弍偵傛偭偰岥摉偨傝傛偔偝傟偨攑婞暔杅堈偺帺桼壔偼丄挿婜揑側擔杮媦傃懠偺愭恑崙偺攑婞暔婋婡傪夝寛偡傞偨傔偺庤抜偱偁傞偲偡傞尒夝偲姰慡偵庱旜堦娧偟偰偄傞丅尵偄姺偊傟偽丄奐敪搑忋崙偵変乆偺攑婞暔傪梌偊丄斵傜偵変乆偺媄弍傪攧傝丄偦偟偰偦傟傪乭俁俼乭丄乭娐嫬偵揔惓側娗棟乭丄乭崙嵺儕僒僀僋儖摿嬫乭丄偦偟偰乭僉儍僷僔僥傿丒價儖僨傿儞僌乭偲屇傇丅偙傟偼僶乕僛儖忦栺偑弶傔偐傜夞旔偟傛偆偲偟偰偄偨寢枛丄偡側傢偪奐敪搑忋崙偑丄愭恑崙偺朙偐側愳偺巟棳偐傜棳傟弌傞墭傟偨悈傪曋棙偵娗棟偡傞栶傪妱傝摉偰傜傟傞悽奅丄偄傢偽攑婞暔怉柉抧庡媊偲偱傕屇傇偙偲偑偱偒傞悽奅偐傕偐傕偟傟側偄 媟拲6丗IMO偺 venue shopping偲僶乕僛儖忦栺棧傟偵偮偄偰偺徻嵶 http://www.ban.org/Library/briefingp5_april2006.pdf 媟拲7丗丂偙偺僪儔僼僩偺姰慡側斸敾 http://www.ban.org/Library/IMO_Draft_Convention_CritiqueFINAL.pdf 媟拲8丗丂慏敃夝懱偵娭偡傞NGO僾儔僢僩僼僅乕儉偺僾儗僗儕儕乕僗 http://www.ban.org/ban_news/2006/061013_ship_scrapping_immoral.html BAN 桳奞攑婞暔僯儏乕僗丂2006擭10寧13擔乛慏敃夝懱偵娭偡傞恖尃丒娐嫬抍懱僾儔僢僩僼僅乕儉丂僾儗僗儕儕乕僗丂慏敃夝懱偵娭偡傞IMO忦栺埬偼椣棟偵傕偲傞乮摉尋媶夛栿乯 http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/basel/BAN/06_10_13_Draft_IMO_Treaty 媟拲9丗Brief Outline of the Seminar on "Establishing the Global Framework in Ship Recycling https://www.maritimejapan.com/JSC/maritimejapan.nsf/v_welcome1_e /8E03989BC45813A9802571EE005701B8 3. 擔杮偐傜桝弌偝傟偨桳奞攑婞暔偼偡偱偵偁傆傟弌偰偄傞 丂尰嵼偼奐敪搑忋崙偵桳奞攑婞暔傪桝弌偟偰偄側偄偲偡傞擔杮惌晎偺庡挘偵傕偐偐傢傜偢丄幚嵺偵偼擔杮偲偄偆崙偼傎偙傠傃偐傜攑婞暔傪暚弌偟偰偍傝丄奐敪搑忋崙偵岦偗偰桳奞攑婞暔偑桝弌偝傟傞偙偲傪杊偖偙偲偑偱偒側偄崙側偺偱偁傞丅偡偱偵BAN偲僌儕乕儞僺乕僗偼擔杮偐傜偺戝検偺攑婞暔丄偦偟偰偁傞傕偺偼桳奞攑婞暔丄偑忋奀偺撿偵埵抲偡傞戜廈乮Taizhou乯[10]側偳偺拞崙偺峘偵晄朄偵憲傝崬傑傟丄偦偙偐傜埆柤崅偄揹巕攑婞暔張棟抧堟偱偁傞峀搶徣偺婱涀(Guiyu)[11]偵塣傃崬傑傟偰張棟偝傟傞偙偲傪曬崘偟偨丅偙傟傜偺桝弌偵娭偡傞嵟傕峀斖側曬崘彂偑2001擭媦傃2004擭偵幚巤偝傟偨BAN偺尰抧挷嵏偵傛偭偰嶌惉偝傟偨偑丄変乆偼偙傟傜偺桝弌偑崱擔偱偼峴傢傟偰偄側偄偲怣偢傞棟桼傪帩偭偰偄側偄丅
丂2005擭10寧偵BAN偼揹巕婡婍僗僋儔僢僾偺悽奅攑婞暔杅堈偺尰忬傪尒傞偨傔偵傾僼儕僇偺僫僀僕僃儕傾丄儔僑僗傪朘傟偨偑丄偦偙偱丄嵞巊梡偺偨傔偵桝弌偝傟偨偲偄偆怗傟崬傒偺擔杮惢帺摦幵偲揹巕婡婍僗僋儔僢僾傪尒偨丅偟偐偟桝擖偝傟傞傕偦傟傜偺75亾偼巊梡偡傞偙偲偑偱偒偢丄偦傟傜偼幖抧傗摴楬増偄偺僑儈幪偰応偵搳婞偝傟丄擔忢揑偵擱傗偝傟偰偄偨[12]丅
丂1999擭丄擔杮偺桳尷夛幮僯僢僜乕乮撊栘導乯偑屆巻偲婾偭偰戝検偺堛椕攑婞暔偲壠掚偛傒傪124敔偺僐儞僥僫乕偵媗傔偰僼傿儕僺儞偵桝弌偟偨乮栿拲4)丅摉帪丄偁傞僼傿儕僺儞偺怴暦偼師偺傛偆偵曬崘偟偰偄傞丅乭変乆偼僌儘乕僶儕僛乕僔儑儞偵偼巀惉偩偑丄傑偝偐偦傟偑壠掚僑儈傗戝検偺嫲傜偔揱愼惈傪帩偮桳奞僑儈偺桝弌偺僌儘乕僶儕僛乕僔儑儞傪娷傓偲偼憐憸傕偟側偐偭偨[13]丅 丂1994擭丄擔杮偺憿慏夛幮偱偁傞忢愇憿慏姅幃夛幮乮Tsuneishi Heavy Industries Inc.,乯偼僼傿儕僺儞偺僙僽搰偵嶻嬈僝乕儞偱偁傞惣僙僽嶻嬈岞墍乮West Cebu Industrial Park (WCIP)乯傪奐敪偟偨乮栿拲5乯丅尰抧偺夛幮偑忢愇憿慏偲宊栺偟丄憿慏強傪憖嬈偟偰偄傞丅忢愇憿慏偑WCIP偵搳帒偟偨棟桼偼丄摨搰偼斾妑揑婯惂偑娚偔丄埨偄楯摥椡偑妋曐偱偒傞偐傜偱偁傞偲怣偠傜傟偰偄傞丅偦偙偱偼丄尰抧偺斀懳偑婲偒傞傑偱偺悢擭娫丄墭愼傪杊巭偡傞桳岠側慬抲傕偲傜偢偵奀拞偱慏傪夝懱偟偰偄偨[14]丅 丂師偵擔杮偺奀塣嬈奅偼僀儞僪傊偺慏偺桝弌傪懀恑偡傞偙偲傪媮傔偨丅埆柤崅偄慏敃夝懱奀娸傾儔儞偺撿丄僺僷僶僼(Pipavav)峘偵擔杮偺帒嬥墖彆偵傛傝寶愝偝傟偨尰戙揑側慏敃夝懱巤愝偑偁傞偑丄偦偙偵偼擔杮偺棙屓怱偑側偄傢偗偱偼側偄丅尰戙揑側奜梞慏偺桳撆側揾憰偺壓偵偼朙晉側揝嵽偑杽傑偭偰偄傞偑丄擔杮偱偼崅偄楯摥捓嬥丄尩偟偄娐嫬婯惂丄媦傃巆熢傗傾僗儀僗僩傪杽傔傞梡抧偺尭彮偺偨傔偵丄慏敃夝懱偼旕忢偵崅偔側偭偨丅偟偐偟丄崱擔傑偱丄擔杮偵傛傝帒嬥嫙梌偝傟偨偙偺巤愝偼堦惽偺慏傕夝懱偟偰偍傜偢丄奐敪搑忋崙傊偺愭恑揑媄弍巟墖偲偟偰偆傢傋傪忺傞堦曽偱丄攑婞暔悇恑傊偺擔杮偺娭怱偺僔儞儃儖偲偟偰偦偙偵偁傞丅擔杮偑強桳偡傞慏偑枹偩偵夝懱偝傟偰偄傞傾儔儞偺夝懱尰応偱媄弍揑夵慞偑側偝傟偰傕丄偦傟偼傗偼傝帺崙撪張棟偲宱嵪揑庛幰偵懳偡傞攑婞暔偺晄嬒峵側晧扴偺杊巭傪媮傔傞娐嫬惓媊乮environmental justice乯偵懳偡傞晭怞偱偁傞[15]丅 栿拲4丗僯僢僜乕晄朄搳婞偵偮偄偰 http://www.jsdi.or.jp/~y_ide/010515fuho_niso.htm 栿拲5丗Tsuneishi Heavy Industries Inc., http://www.tsuneishi-rd.co.jp/company/thi.shtml 媟拲10丗GREENPEACE-BASEL ACTION NETWORK / Key findings from Taizhou Field Investigation http://www.ban.org/Library/Taizhou_E-waste_Research_Report.pdf 媟拲11丗Exporting Harm: The High-Tech Trashing of Asia http://www.ban.org/E-waste/technotrashfinalcomp.pdf 媟拲12丗Digital Dump: Exporting Re-use and Abuse to Africa http://www.ban.org/Library/TheDigitalDump.pdf 媟拲13丗PHILIPPINES: TOUGH TALK ON WASTE SHIPMENT WITH JAPAN http://www.ban.org/ban_news/philippines.html 媟拲14丗Japanese shipbreaking breaks workers in the Philippines http://www.jca.apc.org/joshrc/english/14-2.html 媟拲15丗Pipavav, a modern scrap yard waiting for orders http://www.greenpeaceweb.org/shipbreak/travelreport_pipavav.asp 4. 僶乕僛儖忦栺偑梫媮偟偰偄傞偙偲
丂慡偰偺攑婞暔偵偮偄偰帺桼杅堈傪嫋偡偙偲傪媮傔傞擔杮偲傾儊儕僇偺尒曽偲偼懳徠揑偵丄1980擭戙屻敿偵峀傑偭偨攑婞暔杅堈偺昿敪偵懳墳偟偰悽奅偺僐儈儏僯僥傿偼僶乕僛儖忦栺傪嶌傝弌偟偰戙懼揑側傾僾儘乕僠傪偲偭偨丅僶乕僛儖忦栺偼丄奐敪搑忋崙偑愭恑崙偺攑婞暔娗棟偺僐僗僩憹戝偵傛偭偰宱嵪揑掞峈椡偑嵟傕庛偄宱楬偵棳傟崬傓攑婞暔桝弌偵偝傜偝傟傞偙偲傪杊偖傛偆峔憐偝傟偨丅 丂攑婞暔偺崙嫬傪墇偊傞堏摦傪娗棟偡傞崙嵺揑側慬抲傪梫媮偟偨偺偼傾僼儕僇彅崙偵棪偄傜傟偨奐敪搑忋崙偱偁傝丄崙楢娐嫬寁夋乮UNEP乯偑懳墳偟偨丅幚嵺丄1988擭偵僼傿儕僺儞偼忋堾媍堳僄僪僈儖僪丒傾儞僈儔偲儅僯儞僞儖丒僞儅僲偵傛傝採埬偝傟偨僼傿儕僺儞偱偺妀枖偼桳奞攑婞暔偺桝擖丄曐娗媦傃桝憲傪嬛巭偡傞朄埬傪枮応堦抳偱嵦戰偟偨丅偦偺帪丄僼傿儕僺儞偺媍堳傜偼崙嵺揑側攑婞暔杅堈傪乭嬌埆旕摴側傗傝曽乭偲屇傫偩[16]丅 丂奐敪搑忋崙偼偳偺傛偆側棟桼偑偁傠偆偲愭恑崙偐傜搑忋崙傊偺桳奞攑婞暔偺姰慡嬛巭傪媮傔偨丅偟偐偟丄傾儊儕僇偺傛偆側崙偑庛懱壔傪偼偐傝崙嵺揑岎徛偱崌堄偼嵟彫岞攞悢偲側偭偨偺偱丄嵟廔揑偵偼1989擭偵彁柤偝傟偨僶乕僛儖忦栺偼傎偲傫偳偺奐敪搑忋崙偵偲偭偰偼幐朷偡傞撪梕偱偁偭偨丅僌儕乕儞僺乕僗傗傾僼儕僇彅崙偼偙偺忦栺傪斊嵾峴堊偲偄傢傟傞傋偒攑婞暔杅堈傪崌朄壔偡傞傕偺偱偁傞偲旕擄偟偨丅摉弶偺忦栺偼撿嬌戝棨傪彍偔悽奅偺偳偙偵傕桳奞攑婞暔傪桝弌偱偒側偄偲偡傞傪姰慡嬛巭偱偼側偐偭偨偺偱丄偦偺栺懇傪壥偨偡偙偲偑偱偒側偐偭偨偑丄偦傟偱傕旕忢偵廳梫側尨懃傪娷傓榞慻傒傪愝掕偟偨丅偙傟傜偺尨懃偼偙偺忦栺偺堦斒媊柋偺拞偵尒傞偙偲偑偱偒傞丅
丂摨忦栺偺巆傝偺晹暘偼丄崙壠娫偺忣曬揱払偲嫋壜傪傕偭偰杅堈傪峴偆偙偲偑偱偒傞傛偆捠抦偲摨堄偺巇慻傒傪婯掕偟偰偄傞偑丄僶乕僛儖忦栺偺栚昗丄尨懃丄媦傃儊僢僙乕僕偼柧妋偱偁傞丅偡側傢偪丄攑婞暔偼扨偵彜昳偱偼側偔丄傓偟傠乭椙偄傕偺乭傛傝傕乭埆偄傕偺乭偲傒側偝傟丄偦偺崻尮偱嵟彫壔偝傟丄偦偺杅堈偼摿偵宱嵪揑庛幰偵岦偗傜傟傞偲偒偵偼摿暿偺娗棟偑峴傢傟傞傋偒偱偁傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅 丂僶乕僛儖忦栺偑1992擭偵敪岠偟偰偡偖屻偵丄掲栺崙偼丄摿偵奐敪搑忋崙偼丄愭恑崙偐傜奐敪搑忋崙傊偺桝弌傪慡柺揑偵嬛巭偡傞妶摦傪奐巒偟偨丅戞1夛丄戞2夞丄媦傃戞3夞掲栺崙夛媍乮COPs乯偵偍偄偰丄嬛巭寛媍偑 I/22丄II/12 丄 III/1 [17]丄乮栿拲6乯 偲偟偰偦傟偧傟嵦戰偝傟偨丅偙傟傜偼丄掲栺崙偱偁傞奺崙偼偼偙傟傜偺掲栺崙偺寛媍傪幚巤偡傞偙偲傪堄枴偡傞偺偱丄旕忢偵廳梫偱偁傞丅斶偟偄偙偲偵丄僼傿儕僺儞偲擔杮偼偙傟傜偺寛媍傪斸弝偟偰偍傜偢丄偦偺偙偲偑 JPEPA 嫤掕偺忦崁傪壜擻偵偟丄幚嵺偵婋尟側堄枴傪帩偮偙偲偵側傞丅僶乕僛儖忦栺偲寛媍偺庯巪偼壓婰偺昞偵帵偝傟傞丅 媟拲16丗 The International Trade in Wastes: A Greenpeace Inventory, 1990. 媟拲17丗偙傟傜偺庡梫側寛媍偼壓婰偵偰尒傞偙偲偑偱偒傞丅 http://www.ban.org/main/about_Basel_Ban.html http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/basel/Basel_Decision_2.html 僶乕僛儖嬛巭椷丂寛媍 III/1乮摉尋媶夛栿乯 http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/basel/Basel_Decision_3.html
丂忋婰偺昞偵尒傜傟傞傛偆偵丄擔杮偲僼傿儕僺儞偼宱嵪揑摦婡偵傛傞攑婞暔偺桝弌傪傛傝椙偔娗棟偟丄帪偵偼嬌埆旕摴側傗傝曽傪嬛巭偡傞偲偄偆悽奅偺僐儈儏僯僥傿偺婅朷偲懌暲傒傪姰慡偵偦傠偊偰偄傞傢偗偱偼側偄丅偦偺拞偱嵟傕尠挊側偙偲偼僶乕僛儖嬛巭廋惓忦崁偺斸弝偲幚巤偱偁傞丅 丂偡偱偵62偐崙偑廋惓忦崁傪斸弝偟偰偍傝丄傾僕傾抧堟偱偼拞崙丄儅儗乕僔傾丄僀儞僪僱僔傾丄僽儖僱僀丄媦傃僗儕儔儞僇偑娷傑傟傞偑丄僼傿儕僺儞偼傑偩斸弝偟偰偄側偄丅堦曽丄擔杮偼廋惓忦崁偵斀懳偟偰偄傞偙偲偱抦傜傟偰偄傞丅偦傟偵傕偐偐傢傜偢丄椉崙偼僶乕僛儖掲栺崙偐傜斸弝偡傞傛偆懀偝傟偰偄傞偺偱丄椉崙偵埑椡傪偐偗傞偙偲偑廳梫偱偁傞丅愭恑崙偱偺攑婞暔張棟僐僗僩偺崅摣丄奐敪搑忋崙偺宱嵪揑側梸媮丄桳奞攑婞暔偺憹戝丄悽奅揑側晉偺晄暯摍側偳偺崙嵺揑側攑婞暔杅堈偺悇恑椡偼丄崱擔偼埲慜偵斾傋偼傞偐偵怺崗偱偁傞丅 丂2006擭8寧偵儓乕儘僢僷偐傜偺桳奞側愇桘壔妛宯攑婞暔傪傂偲慏暘庴偗庢傝10恖偺巰幰偲僐乕僩僕儃傾乕儖惌晎偺撪妕憤帿怑傪傕偨傜偟偨嵟嬤偺僐乕僩僕儃傾乕儖偱偺斶寑丄巊梡嵪傒徚旓幰惢昳偺傛偆側戝検側攑婞暔偺堏摦丄榁媭壔偟偨奜梞慏偺桝弌側偳偼丄悽奅偺桳奞攑婞暔杅堈偺娗棟偺嫮壔偺昁梫惈傪徹柧偡傞尰嵼偺帠椺埲奜偺側偵傕偺偱傕側偄丅 5. JPEPA 偺攑婞暔娭惻嶍尭偼堄枴偑側偄偺偐丠 丂乭[嫤掕拞偵]娷傑傟傞崁栚偺傂偲偮偼変乆偑桳奞攑婞暔偲屇傇傕偺偱偁傞丅偦傟偼慡偰崬傒偺杅堈偺堦晹偱偁傝丄偦傟偼斵傜偑変乆偵攑婞暔傪桝弌偡傞偙偲傪嫋偡偲偄偆偙偲傪堄枴偟側偄丅[攑婞暔忦崁偼]偦傟埲奜偺壗傪傕堄枴偟側偄丅亅亅僼傿儕僺儞捠彜挿姱僺乕僞乕丒僼傽價儕傾[18] 丂JPEPA 偺岎徛偵摉偭偨僼傿儕僺儞惌晎偺戙昞偼偦偺岎徛偺夁掱偱丄娭惻嶍尭僾儘僌儔儉偵攑婞暔傪娷傔傞偙偲偼尰幚偲娭楢偺偁傞偙偲偱側偔丄扨偵帠柋揑側偙偲偱偁傝丄崙撪朄傗僶乕僛儖忦栺傪柍岠偵偡傞傕偺偱偼側偄偲孞傝曉偟庡挘偟偨丅偙傟傜偺惡柧偼巆擮側偑傜帠幚偱偼側偄丅 丂忦栺偼堦扷斸弝偝傟傞偲崙撪朄偲摨摍偲側傞丅僶乕僛儖忦栺偦傟帺恎偼擔杮偱傕僼傿儕僺儞偱傕崙撪朄偲偟偰幚巤偝傟偰偄傞偑丄1989擭偺僶乕僛儖忦栺偼桳奞攑婞暔偺桝弌傪嬛偠偰偍傜偢丄扨偵桝弌偝偣側偄傛偆偵偟偰偄傞偩偗偱偁傞偙偲傪棟夝偟側偔偰偼側傜側偄丅愭恑崙偐傜奐敪搑忋崙傊偺攑婞暔搳婞偺悽奅揑側僎乕儉傪嬛偠偰偄傞偺偼丄僼傿儕僺儞偼傑偩偵斸弝偟偰偍傜偢丄擔杮偼斸弝偺堄恾偑慡偔側偄1995擭僶乕僛儖忦栺嬛巭廋惓忦崁偱偁傞丅偝傜偵丄僼傿儕僺儞偺崙撪朄偼儕僒僀僋儕儞僌偺偨傔偺桳奞攑婞暔偺桝擖偼尩枾偵偼嬛巭偟偰偍傜偢丄扨偵嫋壜惂偵偟偰偄傞偩偗偱偁傞丅偦偺忋丄僶乕僛儖嬛巭廋惓忦崁傪娷傫偩僶乕僛儖忦栺偼乮偦傟偑敪岠偡傞偲偄偆慜採偱乯丄JPEPA 傛傝忋埵偵埵抲偟丄偨偲偊偙偺擇崙娫嫤掕偑敪岠偟偰傕偦傟傪柍岠偵偡傞偲偄偆曐徹偼偳偙偵傕側偄偲偄偆偙偲偵棷堄偟側偔偰偼側傜側偄丅 丂朄棩偵柕弬偑偁傞偲偒偵偼丄JPEPA偺傛偆側怴偨側忦栺偵彁柤偡傞慜偵偦偺傛偆側柕弬傪杊偖偨傔偺庢慻偵傑偢拝庤偟側偔偰偼側傜側偄丅柧傜偐偵偙偺偙偲偼側偝傟偰偍傜偢丄偦偺棟桼偼幙偝傟側偔偰偼側傜側偄丅撪嵼偡傞柕弬偼嵸敾偱惓摉惈偑憟傢傟傞傋偒傕偺偱偁傞丅偦偟偰幚嵺偵嵸敾嵐懣偵側偭偨応崌偵偼丄朄掛偼嵟傕怴偟偔嵟傕嬶懱揑側嫤掕偺曽偑屆偔偰堦斒揑側嫤掕偵彑傞偲嵸掕偡傞偱偁傠偆丅杮審偺応崌丄JPEPA偼丄杅堈偺惂尷枖偼嬛巭偲偄偆峫偊曽偲柧傜偐偵柕弬偟偰杅堈傪懀恑偡傞偨傔偵柧妋偵偝傟偨旕忢偵摿掕側攑婞暔偺棳傟傪娷傓嵟傕怴偟偄嫤掕偱偁傞丅JPEPA 偵攑婞暔杅堈帺桼壔偺忦崁傪娷傔傞偙偲偺棟桼偼扨偵岎徛偺嶔棯偱偁傞偲弎傋傜傟偰偄傞偩偗偱偁傞丅 丂乭傕偟丄変乆偑偦偆偟側偗傟偽丄変乆偼懼傢傝偺傕偺傪採埬偡傞傛偆嫮偄傜傟偨偱偁傠偆丅偦傟偼岎徛愴棯偱偁傞[19]乭 丂乭億乕僇乕丒僎乕儉偺傛偆偵丄嫮偄僾儗乕儎乕偼僄乕僗傪塀偡偨傔偵嵟傕庛偄僇乕僪傪嵟弶偵尒偣傞乭偲僼傽價儔偼弎傋偨丅乭変乆偺僄乕僗偺僇乕僪偼変乆偑庣傝偨偄偲朷傓惉壥偱偁傞丅乭[20] --- 僼傿儕僺儞捠彜挿姱丂僺乕僞乕丒僼傽價儔 丂偟偐偟丄偦偺傛偆側偙偲偺庡挘偵媈媊偑採婲偝傟偨帪偵丄僼傿儕僺儞偺娐嫬摉嬊偺堦晹偵幚嵺偵斀懳偺堄尒偑偁偭偨偑丄擔杮偑偦傟傪巆偡傛偆庡挘偟偨偺偱斵傜偼偙偺晄夣側柕弬偟偨暥尵傪嶍彍偡傞偙偲偼偱偒側偐偭偨偲偄偆偙偲偑柧傜偐偵偝傟偨丅 丂僼傿儕僺儞娐嫬暃挿姱僨儈僩儕僆 L. 僀僌僫僔僆偼僼傿儕僺儞丒僨僀儕乕丒僀儞僋儚僀傾乕巻偵丄娐嫬摉嬊偼丄崙撪媦傃崙嵺揑側朄偼偙傟傜偺暔偵娭偡傞岎徛傪嬛偠偰偄傞偺偱丄攑婞暔偵娭偡傞岎徛偼乭柍塿乭偱偁傞偲捠嶻摉嬊偐傜崘偘傜傟偨偲弎傋偨丅偟偐偟斵偼丄乭埾擟帠崁乮Terms of Reference乯偼偡偱偵擔杮偵傛偭偰嶌惉偝傟偰偍傝乭丄僼傿儕僺儞偼偦傟偱傕摨崙偺朄棩傪幚巤偡傞偙偲偑偱偒傞偲崘偘傜傟偨丅 丂乭JPEPA 偼乭慡偰偐柍偐偺懨嫤傪嫋偝側偄嫤掕埬偱偁傝丄傕偟変乆偑11,300 偺暔昳偺傂偲偮偐擇偮偵摨堄偟側偗傟偽丄偙偺嫤掕埬偼側偄傕偺偲側傞偲崘偘傜傟偨丅乭[21] --- 娐嫬暃挿姱僀僌僫僔僆 丂悽奅杅堈婡娭乮WTO乯偼丄擇崙娫嫤掕偵100亾偺娭惻揚攑傪傪媮傔偰偄傞偲傎偺傔偐偡恖乆傕偄傞丅偟偐偟丄僼傿儕僺儞巻偐傜僀儞僞價儏乕傪庴偗偨僼傿儕僺儞崙嵺杅堈偺愱栧壠偱偁傞曎岇巑僕僃儖儈乕 I. 僇僣僪儔偵傛傟偽丄偙傟傕傑偨婾傝偱偁傞丅 乭帺桼杅堈嫤掕乮FTA乯拞偱暔昳偺慡偰偺娭惻偑僇僶乕偝傟丄堷偒壓偘傜傟傞昁梫偑偁傞尵偆偙偲傕傑偨惓偟偔側偄乭偲僇僣僪儔偼弎傋偨丅 丂悽奅杅堈婡娭乮WTO乯偺儖乕儖偑幚嵺偵尵偭偰偄傞偙偲偼丄掲栺崙偼乭幚幙揑偵慡偰偺杅堈乮substantially all trade乯乭傪FTA偵娷傔側偔偰偼側傜側偄偲偄偆偙偲偱偁傝丄乭慡偰偺杅堈乮all trade乯偱偼側偄偲僇僣僪儔偼愢柧偟偨丅 丂偝傜偵丄懡崙娫僶乕僛儖忦栺偑攑婞暔杅堈偵忈暻傪愝偗傞傛偆媮傔偰偄傞帪偵丄攑婞暔偑尩枾側暔昳偲傒側偡偙偲偑偱偒傞偺偐偳偆偐偵娭偟偰挊偟偔偁偄傑偄偝偑巆傞丅偙偺擇偮偺忦栺丄僶乕僛儖偲 WTO 偺拞偵撪嵼偡傞偙偺濨枂偝偲柕弬偼枹偩偵夝寛偝傟偰偄側偄丅懡偔偺恖乆偼丄WTO 儖乕儖偐傜懡崙娫娐嫬嫤掕乮MEA乯娭楢杅堈忦崁傪彍奜偡傞偙偲偵巀惉偟偰偄傞丅 丂幚嵺偵丄攑婞暔傪娷傔傞偙偲偵偼堄枴偑側偔丄僶乕僛儖忦栺偺媊柋丄僶乕僛儖嬛巭廋惓忦崁丄媦傃僼傿儕僺儞偺崙撪朄偵偍偗傞桝擖嬛巭偲柕弬偟偰偄傞偺偵丄偙傟傜偺攑婞暔偑嫤掕偵娷傑傟側偔偰偼側傜側偄愢摼椡偺偁傞棟桼偼尒偮偐傜側偄丅 丂偝傜偵埆偄偙偲偵偼丄JPEPA 偑僶乕僛儖忦栺偺媊柋丄嵟廔揑偵偼僶乕僛儖嬛巭忦崁偺幚巤丄媦傃僼傿儕僺儞偺崙撪朄偵塭嬁傪梌偊側偄枖偼懝側偆偙偲偼側偄偲偡傞庡挘偼丄恀幚偱偼側偄偲偄偆偙偲偱偁傞丅幚嵺偵丄偙偺嫤掕偼丄僼傿儕僺儞偲偦偺懠偺彅崙偺帩懕壜擻惈偺偨傔偵彨棃丄夡柵揑側寢壥傪傕偨傜偡偙偲偑偁傝偊傞丅 僇僣僪儔偼丄僼傿儕僺儞丒僀儞僋儚僀傾乕巻偺婰帠偺拞偱惌晎偺庡挘傪梫栺偟丄惌晎偺榑棟傪乭娫堘偭偰偍傝揑奜傟側傕偺乭偲屇傫偩丅斵偼丄JPEPA 偼幚嵺偵忦栺偱偁傝丄僼傿儕僺儞偺朄惂搙偺壓偺忦栺偼崙撪朄婯偲摨摍側傕偺偲偟偰僼傿儕僺儞偺朄棩偺堦晹偲偟偰偲偟偰埖傢傟傞偲弎傋偨丅JPEPA 偑敪岠偝傟傟偽丄偦傟偲柕弬偡傞埲慜偺朄棩偼柍岠偵側傞偲僇僣僪儔偼弎傋偨[22]丅 側偤丄攑婞暔杅堈帺桼壔忦崁偑娷傑傟偰偄傞偺偐丠 丂尰嵼丄攑婞暔帺桼壔忦崁偑擔杮懁岎徛幰偺嫮偄梫媮偵傛傞傕偺偱偁傞偙偲偑偼柧傜偐偵偝傟偨丅攑婞暔忦崁偼丄慡晹枖偼柍偺懨嫤偺側偄嫤掕偺堦晹偲偟偰僼傿儕僺儞偺堛椕夘岇幰傜偑擔杮偱摥偔偨傔偺楯摥忦崁偺戙彏偲偟偰庴偗擖傟傜傟偨丅偟偨偑偭偰丄偙傟傜偺攑婞暔杅堈忦崁偼擔杮懁偵偲偭偰偼旕忢偵廳梫偱偁傞偙偲偼柧傜偐偱偁傝丄擔杮偼丄僼傿儕僺儞偵偍偗傞彨棃偺攑婞暔桝擖婯惂偲嬛巭偺庢慻傪暍偡偙偲偵側傝摼傞慜椺傪嶌傝忋偘傞偨傔偵擔杮偺旕忢偵戝偒側宱嵪揑尃椡傪偦偺椬恖偵嫮梫偟傛偆偲偟偰偄傞傛偆偵尒偊傞丅 丂乭変乆偵偲偭偰 JPEPA 偱嵟傕廳梫側崁栚偼丄変乆偺奀奜偺楯摥幰偺廇嬈丄偡側傢偪変乆偺堛椕楯摥幰偑擔杮偱廇嬈偡傞偙偲傪壜擻偵偡傞杅堈偱偁傝丄偦偺偙偲偼僼傿儕僺儞偵偲偭偰旕忢偵廳梫偱偁傞丅偦偙偱変乆偵偲偭偰偺栤戣偼師偺傛偆偵側傞丅変乆偼変乆偺棫応偵屌幏偡傞偙偲偵傛傝丄変乆偺堛椕夘岇楯摥幰傗偦偺懠偺楯摥幰媦傃惗嶻幰偵桳塿偱偁傞擔杮偲偺嫤掕傪寢偽側偄偺偐丠丂偁傞偄偼丄DTI [擔杮偲岎徛傪峴偭偰偄傞僼傿儕僺儞捠彜徣] 偵擟偣傞偐丠乭丂[21] --- 娐嫬暃挿姱僀僌僫僔僆 丂忋弎偺戞2愡偱専徹偟偨傛偆偵丄傾僕傾偵偍偗傞攑婞暔杅堈帺桼壔偺偨傔偺擔杮惌晎偺惌嶔偺惵幨恀偱偁傞偲尒傞偙偲偑偱偒傞抧媴娐嫬愴棯尋媶婡娭乮IGES)偐傜弌斉偝傟偨惌嶔暥彂亀崙嵺儕僒僀僋儖摿嬫偲傾僕傾堟撪僱僢僩儚乕僋偺峔抸亁偲堦抳偟偰丄擔杮偼僼傿儕僺儞偲偺帺桼杅堈嫤掕乮FTA乯傪桳奞攑婞暔偺帺桼杅堈偵懳偡傞僶乕僛儖偺嵲偺愇慻傒傪曵偡偨傔偵棙梡偟偰偄傞丅 JPEA 偼 WTO 偲僶乕僛儖偺懳棫傪婅偭偰偄傞傛偆偵尒偊傞 丂偙偺偙偲偼丄僶乕僛儖嬛巭廋惓忦崁偺幚巤偵傛傝彨棃攑婞暔桝擖傪嬛巭偟傛偆偲偡傞僼傿儕僺儞偵偲偭偰旕忢偵尰幚揑側寽擮偱偁傞偺傒側傜偢丄WTO 偲僶乕僛儖偺懳棫傊偺摴傪奐偔傕偺偱偁傝丄娐嫬惓媊乮environmental justice乯偺彅尨懃傊偺悽奅揑側塭嬁偼攋夡揑側傕偺偲側傞偱偁傠偆丅幚嵺偵 JPEPA 偺杅堈帺桼壔偼丄WTO 偵傛傞僶乕僛儖忦栺傊偺堎媍怽偟棫偰偑尰幚偲側傝彑偰傞偲偄偆丄彮側偔偲傕岎徛幰傜偺堦晹偵偁傞婅朷傪傛偔昞偟偰偄傞偐傕偟傟側偄丅擇偮偺忦栺 JPEA 偲 WTO 偑堦偮偺忦栺僶乕僛儖偵斀懳偡傞廳傒傪棟夝偡傟偽丄幚嵺偵攑婞暔偼暔昳偱偁傝僶乕僛儖忦栺偼偦傟傜偺杅堈傪朩偘傞偙偲偼偱偒側偄偲偡傞 WTO 懁偺捠忢偺尒夝偑巟帩偝傟傞寢榑偲側傝丄僶乕僛儖忦栺傪姰慡偵懝側偄暍偡寢壥偲側傞壜擻偼廫暘偵偁傞丅 丂杅堈忦崁傪帩偮懠偺懡崙娫娐嫬嫤掕乮MEAs乯偲摨條偵僶乕僛儖忦栺偼憡屳偺媊柋偵晹暘揑側柕弬傪帩偭偰偄傞偙偲偼慜偐傜抦傜傟偰偄傞[23]丅偟偐偟丄崱擔傑偱丄傎偲傫偳偺崙偼懡崙娫娐嫬嫤掕偑WTO偺杅堈帺桼壔梫媮偵傛偭偰懝側傢傟傞偙偲傪朷傫偱偄側偄丅偟偐偟丄傾儊儕僇傗擔杮側偳崙偺惌晎偐傜側傞嫮偄椡傪傕偮僌儖乕僾偼攑婞暔偼戞堦偵暔昳偱偁傝攑婞暔偺杅堈惂尷偼崻嫆偑敄庛偱偁傞偲偄偆堄尒偱偁傞丅娐嫬惓媊偱偼側偔攑婞暔偺帺桼側杅堈傪嫋偡堦曽偱丄僶乕僛儖忦栺傪扨偵乭娐嫬偵揔惓側娗棟乭傪悇恑偡傞俁俼僞僀僾偵曄偊傞偲偄偆偙偲偼 擔杮傪娷傓僕儏乕僗僇儞僘僌儖乕僾乮擔杮丄傾儊儕僇丄娯崙丄僇僫僟丄僆乕僗僩儔儕傾丄僯儏乕僕儔儞僪乯偵偲偭偰旕忢偵搒崌偑椙偄丅JPEPA 偼僶乕僛儖忦栺偺娐嫬惓媊偺尨懃傪暍偡戞堦曕偱偁傞丅 媟拲18丗Manila Standard TodayThursday, October 26, 2006 / Official: Enough safeguards vs toxic waste http://www.manilastandardtoday.com/?page=politics6_oct26_2006 媟拲19丗Manila Standard TodayThursday, October 26, 2006 / Official: Enough safeguards vs toxic waste http://www.manilastandardtoday.com/?page=politics6_oct26_2006 媟拲20丗Philippine Daily Inquirer - 10/26/2006 / Senate indignant, CBCP sad over 'toxic' accord http://www.bilaterals.org/article.php3?id_article=6314 媟拲21丗Philippine Daily Inquirer - 10/26/2006 / DENR opposed waste dumping in trade deal but gave in to DTI http://www.bilaterals.org/article.php3?id_article=6315 媟拲22丗INQ7 Breaking News 10/25/2006 / Int'l trade expert says gov't claims on trade pact 'wrong' JPEPA to 'override existing laws' http://newsinfo.inq7.net/breakingnews/nation/view_article.php?article_id=28698 媟拲23丗BAN Report: When Trade is Toxic: The WTO Threat to Public and Planetary Health, 1999 http://www.ban.org/Library/when_trade.pdf 6. 寢榑 丂僼傿儕僺儞偲擔杮惌晎偼 JPEPA 偵攑婞暔杅堈偺帺桼壔傪娷傔傞偙偲偺堄枴偵偮偄偰惓捈偱偼側偐偭偨丅椉惌晎偼偙傟傜偺忦崁傪岎徛偺夁掱偵偍偗傞帠柋揑側堄枴偺側偄柤巆傝偱偁傞偲尵偄敳偗傛偆偲偟偨丅杮曬崘彂偼丄庡梫側寢榑偲偟偰壓婰傪嫇偘傞丅
丂椉崙偼丄1989擭僶乕僛儖忦栺傪斸弝偟偨偑丄1992擭丄1994擭丄媦傃1995擭偵嵦戰偝傟偨僶乕僛儖忦栺崌堄寛媍偱嬶懱壔偝傟偰偄傞攑婞暔杅堈偺嬛巭傪揔愗偵嫮屌偵偡傞偙偲傪懹偭偰偄傞丅偙偺攑婞暔杅堈帺桼壔忦崁偼丄尰嵼偺崙撪朄丄媦傃彨棃僼傿儕僺儞偑僶乕僛儖嬛巭廋惓忦崁傪斸弝偡傞帪偵丄枖偼 JPEPA 偺娭惻揚攑懳徾偲側傞攑婞暔傪嬛巭偡傞偙偲傪慖戰偟偨帪偵偦傟傜傪柍岠偵偡傞偨傔偵廫暘側椡偑偁傞丅偝傜偵丄偙偺 JPEPA 忦崁偼丄 僶乕僛儖忦栺拞偵尒偄偩偝傟傞攑婞暔偺帺崙張棟偲偄偆曪妵揑側悽奅惌嶔偵悈傪嵎偟丄偙傟傜悽奅偺婯斖偲懡崙娫帺桼杅堈嫤掕偱偁傞WTO偲偺娫偵懳棫傪惗傒偩偦偆偲巇慻傑傟偰偄傞傛偆偵尒偊傞丅 丂偙傟傜偺寢壥偼丄攑婞暔偼悽奅巗応偺宱嵪揑埑椡偺懳徾偲側傞尩枾側暔昳偱偼側偄偲怣偠傞慡偰偺恖乆偵偲偭偰旕忢偵婋尟偲側儕摼傞丅偟偐偟丄娭惻揚攑偼懡偔偺惢昳偵偲偭偰壙抣偑偁傞偐傕偟傟側偄偑丄椺偊偽丄怤擖惈偺偁傞惗暔庬丄愨柵偺嫲傟偺偁傞惗暔庬丄婋尟側壔妛暔幙丄杻栻丄晲婍側偳丄偁傞傕偺偵偮偄偰偺婯惂偲嬛巭偼嫮偄椣棟揑丄娐嫬揑丄偦偟偰宱嵪揑崌棟惈傪傕偮丅桳奞攑婞暔杅堈偼丄悽奅偺僐儈儏僯僥傿偑婯惂傪媮傔丄丄偦傟傜偺桝弌偑宱嵪揑庛幰偵僐僗僩傪墴偟晅偗傞偙偲偲摨摍偲側傞傛偆側応崌偵偼丄姰慡偵嬛巭偡傋偒傕偺偱偁傞丅攑婞暔偺帺桼杅堈傪婯惂偡傞偨傔偵偡偱偵惂掕偝傟偨傑偝偵偦傟傜偺朄偑偙傟傜偺娭惻嶍尭偺峌寕偵偝傜偝傟偰偄傞丅儕僗僩偝傟偰偄傞慡偰偺攑婞暔偑嫤掕偐傜嶍彍偝傟傞傑偱 JPEPA 偺斸弝傪捈偪偵慾巭偟側偔偰偼側傜側偄丅 7. 姪崘
Appendix
JPEPA 偺娭惻嶍尭栚昗偲側傞攑婞暔偺儕僗僩偲 偦偺傛偆側嶍尭偺婛懚偺朄棩偲偺愽嵼揑側柕弬
媟拲24丗http://www.bilaterals.org/article.php3?id_article=6323 栿拲7丗JPEPA偺娭惻昞 仭乽擔杮崙偺昞乿丂偲丂乽僼傿儕僺儞偺昞乿 丂娭惻昞偵偼丄乽擔杮崙偺昞乿丂偲丂乽僼傿儕僺儞偺昞乿丂偑偁傞丅乽擔杮崙偺昞乿丂偼僼傿儕僺儞嶻暔昳偺擔杮傊偺桝擖娭惻梡偱偁傝丄乽僼傿儕僺儞偺昞乿丂偼擔杮嶻暔昳偺僼傿儕僺儞傊偺桝擖娭惻梡偱偁傞丅 丂奜柋徣偺塸岅斉僥僉僗僩偵偼丂乽擔杮崙偺昞乿丂偲丂乽僼傿儕僺儞偺昞乿丂偺椉曽偑宖嵹偝傟偰偄傞偑丄擔杮岅斉僥僉僗僩偵偼丂乽擔杮崙偺昞乿丂偟偐婰嵹偝傟偰偍傜偢丄乽僼傿儕僺儞偺昞乿丂偼徣棯偲側偭偰偄傞丅 丂擔杮偐傜僼傿儕僺儞傊偺乮攑婞暔乯桝弌偵娭偟偰偼丂乽僼傿儕僺儞偺昞乿丂偑揔梡偝傟傞偺偱丄僼傿儕僺儞傊偺桝弌暔昳乮攑婞暔乯偺暘椶偲娭惻傪挷傋傞偨傔偵偼塸岅斉僥僉僗僩傪尒傞偟偐側偄丅偦偺偨傔偵丄JPEPA偵攑婞暔桝弌偑娷傑傟偰偄傞偙偲偑旕忢偵暘傝偵偔偔側偭偰偄傞丅 丂忋婰偺昞偼丂乽僼傿儕僺儞偺昞乿丂偵婎偯偄偰偄傞丅 丂擔杮岅僥僉僗僩偵偁傞乽擔杮崙偺昞乿偵偼丄忋婰偺昞偵帵偡昳栚偼帵偝傟偰偍傜偢丄師偺傛偆側戝暘椶崁栚偑帵偝傟偰偄傞偩偗偱偁傞丅 丒戞擇榋椶丂峼愇丄僗儔僌媦傃奃 丒戞嶰乑椶丂堛椕梡昳 丒戞嶰敧椶丂奺庬偺壔妛岺嬈惗嶻昳 丒戞榋嶰椶丂朼怐梡慇堐偺偦偺懠偺惢昳丄僙僢僩丄拞屆偺堖椶丄朼怐梡慇堐偺拞屆偺暔昳媦傃傏傠 丂擔杮偺廜嶲椉堾偱偺怰媍偑攑婞暔偺婰弎偺偁傞丂乽僼傿儕僺儞偺昞乿丂偺擔杮岅僥僉僗僩側偟偱丄廫暘側忣曬採嫙傪庴偗偢偵峴傢傟偰偄傞偲偟偨傜栤戣偱偁傞丅 仭娭惻昞
尨嶻昳 1 棯 2 1(a) 偺婯掕偺揔梡忋丄師偵宖偘傞嶻昳偼丄掲栺崙偵偍偄偰姰慡偵摼傜傟丄枖偼惗嶻偝傟傞嶻昳偲偡傞丅 (a)乣(h) 棯 (i)摉奩掲栺崙偵偍偄偰廂廤偝傟傞嶻昳偱偁偭偰丄摉奩掲栺崙偵偍偄偰杮棃偺栚揑傪壥偨偡偙偲偑偱偒偢丄夞暅枖偼廋棟偑晄壜擻偱偁傝丄偐偮丄張暘枖偼晹昳庒偟偔偼尨嵽椏偺夞廂偺傒偵揔偡傞傕偺 (j)摉奩掲栺崙偵偍偗傞惢憿庒偟偔偼壛岺嶌嬈枖偼徚旓偐傜惗偢傞偔偢媦傃攑昳偱偁偭偰丄張暘枖偼尨嵽椏偺夞廂偺傒偵揔偡傞傕偺 (k)杮棃偺栚揑傪壥偨偡偙偲偑偱偒偢丄偐偮丄夞暅枖偼廋棟偑晄壜擻側嶻昳偐傜丄摉奩掲栺崙偵偍偄偰夞廂偝傟傞晹昳枖偼尨嵽椏
|