|
|
|
|
![]()
メレンゲ(by LiSA)。 佐久間學
シンプソンは1988年にリヴァプールで生まれ、オクスフォード大学で管楽器、ギルドホール音楽院で作曲を学びました。神学は学んではいません(「神父さん」ではないので)。これまでに多くの作品を世に送り出していますが、その中には、2014年に初演された「The Immortal」というバリトン・ソロと合唱と大規模なオーケストラのためのオラトリオや、2016年にオペラ・ノースによって初演された室内オペラ「Pleasure」などといった作品も含まれます。さらに、2019年には、彼自身のソロで、クラリネット協奏曲も初演されています。 クラリネット奏者としても、特に現代の音楽のソリストや、室内楽のメンバーとして幅広く活躍しています。 この「Geysir」では、「グラン・パルティータ」で使われる13の楽器のうちの5種類の管楽器(オーボエ2本、クラリネット2本、バセット・ホルン2本、ファゴット2本、ホルン4本)を半分ずつ左右対称に配置して、その真ん中にコントラバスが入るという並び方で演奏されています。楽器編成だけではなく、作曲技法的にも「グラン・パルティータ」からの引用があるのだそうですが、そんなことは知らなくても、この曲を聴けばまさにアイスランド名物の間欠泉の姿が眼前に広がるような体験ができるはずです。 オープニングは、地中のマグマがうごめく様子でしょうか、そんな左右いっぱいに広がった様々な楽器によって、不気味な情景が描かれます。そのうちに、そんな滾るエネルギーが一つの「思い」となって収束してきます。それがクライマックスを迎えた時に訪れるの会心の「発射」、ほとばしり出るのは巨大な温水の柱です。それが終われば、萎える中で残るのは、なにかを成し遂げた後のすがすがしい満足感です(あっ、なにか別の事を想像したりしませんでした?)。 まあ、いまいち立ち位置のはっきりしない作風ですが、そんな感じで過不足なく伝わって来るものはありました。 そんな、スケールの大きな曲の後に続けて演奏された「グラン・パルティータ」からは、そんなエネルギーが乗り移ったかのような、とても大きく伸び伸びとした音楽が聴こえてきました。 まずは、1曲目の序奏では、そのラルゴのファンファーレにはすべての音にスラーが付けられていたのに驚かされます。もしかしたら、こんな演奏を聴いたのは初めてだったかも。それはまさに「コロンブスの卵」のように、これまで抱いていたこの曲のイメージをガラリと変えてしまうほどのものでした。ここでは、全ての音がしっかりと深いところでつながっているようです。 アレグロの主部に入っても、そのようなつながり感は続きます。とても緊密なアンサンブルとも相まって、全ての楽器が一つの方向に向かって進んでいることが実感されてしまいます。ここでの演奏家たちは、常設の団体ではなく、フリーランスの人たちが集まっているのでしょうが、このアンサンブルは驚異的です。 さらに、録音も素晴らしいので、今まで気づいたことがなかったようなそれぞれのパートのちょっとしたフレーズも、とてもくっきりと聴こえてきます。中でも、ファゴットは、いかにこの曲の中で楽しいことをやっているかが、如実に分かります。終楽章では、ソロの部分で見事なアドリブ・プレイを聴かせてくれましたね。 普段は全く目立たないコントラバスも、例えば4曲目のメヌエットの第2トリオでは、まるでエレキ・ベースのようなエッジのきいたベースラインを披露してましたし。 CD Artwork © Orchid Music Limited |
||||||
普通、「カヴァレリア」はレオンカヴァッロの「道化師」と一緒に演奏されますし、「外套」は、そもそもプッチーニの「三部作」の1曲目に該当し、他の2曲、「修道女アンジェリカ」と「ジャンニ・スキッキ」と一緒に上演するために作った曲ですので、今回のカップリングは本来の形ではありませんが、最近はこのように自由な組み合わせで上演されることも多くなっているようです。実際、仙台市では最近「カヴァレリア」と「修道女アンジェリカ」というカップリングの上演がありましたからね。  しかし、現在ではそのまとまった形で上演されることは、ほとんどありません。「単品」で最も人気があるのは、「私のお父さん」というヒットナンバーを持つ「ジャンニ・スキッキ」でしょうね。 ということで、初めて耳にする「外套」です。舞台はセーヌ川に浮かぶ艀(はしけ)の上、前奏曲はその川の流れを表すようなゆったりとしたリズムに乗って揺らめくような音楽で始まります。それはいかにもプッチーニらしい甘い曲調なのですが、その合間にほとんどSEと言った感じで船の汽笛の音が響き渡ります。それは、その場を凍り付かせるような暴力的なサウンド、おそらくこのあたりが悲劇的な結末の伏線となっているのでしょう。 メインの登場人物は、年老いた(50歳)艀の船長のミケーレと、なぜかその妻であるとても若い(25歳)ジョルジェッタ、そして沖仲仕のルイージ(20歳)の3人です。ご想像通り、すでにジョルジェッタの心は夫からは離れていて、年下のルイージとの不倫関係にあるという設定です。そんな分かりやすい物語を、まさに海外テレビドラマ1本分の尺で描くことになるのですが、それを支えるプッチーニの音楽の雄弁さによって、最後まで飽きることはありません。 それぞれのキャラクターが歌うアリアも、その心情をよく表していて、特に最後のミケーレのモノローグなどは涙さえ誘います。バックのオーケストラの、彼の心の中の渦巻くような感情を表したような音楽も、素晴らしいですね。 それだけではなく、その周りの様々な喧騒までが、しっかり音楽で表現されています。最初のあたりで聴こえてくるストリートオルガンを模した調子っぱずれの音楽はとてもインパクトがあります。 途中で、プッチーニの以前の作品「ラ・ボエーム」からの「わが名はミミ」の引用が聴こえてきます。これは、その中に出てくる、自分の外套を質屋に出すときに歌う「古い外套よ」に引っ掛けているのでしょうか。しかし、こちらの「外套」は、もっと壮絶な姿を最後にさらすのですね。 オーケストラのそれぞれのパートは、とてもくっきりと聴こえてきて、プッチーニの華麗なオーケストレーションを遺憾なく伝えてくれています。歌手たちの声は、適切な距離感をもって聴こえてきます。コンサート形式とは言っても、ある程度の所作や移動はあったのかもしれませんね。ルイージ役のテノール、ブライアン・ジャグデの伸びのある声が魅力的でした。 SACD Artwork © Pentatone Music B.V. |
||||||
ただ、もしかしたら、最初に書いてある「Eight Lines」というのも、この路線図に関係があるような気もします。「8本の線路」ですからね。それで、この路線図の色を数えてみたのですが、「8本」よりももっと多くて、どうも「14色」ぐらいあるような。ただ、この作品は、そもそもは1979年に「Octet」というタイトルで8人の演奏家(弦楽四重奏+ピアノ2台+フルート+クラリネット)のために作られ、レコーディングが行われたものを、1983年に各パートを増員して14人編成にし、タイトルも「Eight Lines」に変えていました。ですから、これもしっかり関係があるのではないでしょうか。「14人」が重要になってくるのです。 ここでは、そんな大人数のアンサンブルが、初期のライヒのアイデンティティであった「フェイズ・シフト」という、ちょっと感情を込めるには難しい様式から離れて、それぞれのプレーヤーのモティーフが微妙に変わっていく中でアンサンブル全体も変容を遂げるというある種の「ドラマ」を伴う音楽に変わった時期の作品を、いとも楽しげに演奏しているようです。 この中では最も新しい「City Life」では、その演奏メンバーは18人、その中には「サンプラー」も含まれていて、それこそラッパーの「チェケラ!」みたいな声が聴こえてきたりして、楽しさはより増すことになります。そこには、確かに大人数でなければなしえない音楽の喜びがあります。音楽自体がいくら重苦しいメッセージを持っていようと、演奏することに対する喜びは失われることはありません。 かと思うと、たった一人でもそんなアンサンブルの喜びを味わえるものも、この時期のライヒは作っています。それが「Counterpoint」というタイトルの一連の作品です。1982年にはフルーティストのランソム・ウィルソンのために作った「Vermont Counterpoint」、1984年にはクラリネットのリチャード・ストルツマンのために「New York Counterpoint」を、そして1987年にはギタリストのパット・メセニーのために「Electric Counterpoint」を作りました。もう一つオマケで、1986年に作った「Six Marimbas」を、2009年に加藤訓子が一人で録音した時には、ライヒ自身がそれを「Six Marimbas Counterpoint」と命名してくれたそうです。 ここでは、「Vermont」はフルート、ピッコロ、アルトフルートを2人で、「New York」はオリジナル通りクラリネットとバスクラリネットを1人で、それぞれ11のパートを録音しています。たまにしか出てこないアルトフルートなどは、ちょっと出損なっていたりして、いくら多重録音でも、やはり生身の暖かさを感じることができます。 このアルバムの最初に演奏されているのが、今回が世界初録音となる1964年に作られた「Music for 2 or More Pianos」です。この頃ライヒはルチアーノ・べリオの生徒でしたが、そこで学んでいた無調音楽にはほとほと嫌気をさしていました。そこでベリオが「ライヒ君、だったら、調性音楽を作ってみたまえ」と言ってくれたので、作った曲なのだそうです。なんでも、楽譜には9種類のコードが書いてあるだけで、演奏家はそれを自由なテンポで、コードに従えばどんなフレーズでも演奏できるのだそうです。それは、同じ年にやはりミニマルのもう一方の始祖、テリーライリーが作った「in C」と同じ発想ですね。 そんな、ちょっとジャズの即興演奏を聴いているような感じの曲ですが、かつてはそんなライヒもいたことだけは、しっかり伝わってきます。あ、「ホルスト」と言ってますが、このアンサンブルはドイツの団体です。 CD Artwork © Naxos Rights US, Inc. |
||||||
2018年からは、ここでの指揮者、リッカルド・ミナーシがアーティスト・イン・レジデンツを務めています。1978年生まれのこの指揮者は、最初はヴァイオリン奏者として、多くのピリオド・オーケストラの中での活躍を始めました。指揮者としても多くの団体との共演があり、CDも数多く作っています。手元にもそれと知らずに何枚かのCDがあったことに気づきました。彼の名前の日本語表記は「ミナーシ」、「ミナージ」、「ミナシ」などという多くの表記があって混乱していますが、とりあえず「ミナーシ」であるとみなしましょう。 というより、彼のフルネームには「マサヒデ」というなにか日本語っぽいミドルネームが含まれています。どこを調べても彼はイタリア人だということしか記されてはいないのですが、顔立ちがちょっと東洋人っぽいので、もしかしたら日本人の血が入っているのでは、と思っているのですが、どうなのでしょうか。  まずは、その「39番」の序奏で、そのあまりのテンポの速さに度肝を抜かれます。確かに、ピリオド系の指揮者では、ここはかなり早めに演奏することが多いようですが、これほどの速さはギネスものです。ですから、ヴァイオリンのパッセージなどはとてつもない超絶技巧になってしまいますが、彼らはそれを難なくクリアしています。 主部に入って気づかされるのは、極端なダイナミクスと自由なテンポ・ルバートを組み合わせた、自由自在な表現です。特にテンポの操作は時には全体の流れを中断させるほどの極端なところもありますから、そこで一瞬ハッとさせられる瞬間が頻繁に現れます。ただ、それは、そのことで音楽の持つ意味がしっかり伝わって来るという、とてもクレバーなやり方です。ですから、それに対してはさる大御所(物故者)のような嫌悪感を抱くことは全くありません。それよりも、今まで聴きなれた音楽の中に、まだまだこんな魅力があったことに気づかせてくれるのですから、もう楽しいのなんのって。 サウンド的には、トランペットとティンパニの派手さには圧倒されます。そして、その対極として、モダン楽器でなければ絶対に出来ないような究極のピアニシモが、例えば「40番」の第2楽章などで聴くことができます。ほとんど聴こえるか聴こえないほどのフルートの高音からの下降スケールが、そのまま他の楽器の受け継がれていくシーンは、まさに絶品です。 楽譜通りに、全ての繰り返しを、ダ・カーポのメヌエットでまでしっかり行っていますが、そこでは繰り返した時にも全く同じ表現で貫かれているというのも、一つの矜持なのでしょう。 マッコールのフルートは完璧でした。こういう正確なピッチは、ピリオド楽器では絶対に聴けないでしょうね。 CD Artwork © harmonia mundi musique s.a.s. |
||||||
今回は、二ルソンがプロデュースした、やはりスウェーデンの作曲家のレイフ・ストランドが作った「レクイエム」です。タイトルのように、彼の名前が頭に付いていますね。演奏しているのも、やはり彼の名前を冠した合唱団とオーケストラです。この「レイフ・ストランド女声合唱団」というのは、彼が1997年に作った団体で、この録音でも彼が指揮をしています。オーケストラの方は、おそらくレコーディングのために集められたスタジオ・ミュージシャンたちでしょう。こちらの指揮は別の人が行っています。 録音は、二ルソンのスタジオだけでなく、ベルリンのテルデックス・スタジオでも行われています。二ルソンのスタジオは手狭ですから、おそらくオーケストラだけはもっと豪華なところ(デラックス・スタジオ)で録音したのではないでしょうか。 ストランドという方は1942年生まれ、スウェーデンの王立音楽大学でクラリネットと指揮法を学び、これまでに、作曲家、編曲家、そして合唱指揮者としてかかわったアルバムを30枚ほど出しています。 彼の最新作「レクイエム」は、人が亡くなった後にまた甦るという信念を伝えるために作ったものなのだそうです。なんとも大層なコンセプトですが、その音楽自体は、いとも素朴で心が洗われるような優しさをふんだんに湛えていました。 曲全体は、「Introitus」、「Kyrie」、「Dies irae」、「Offertorium」、「Sanctus Benedictus」、「Libera me」、「Agnus Dei」、「In paradisum」の8つの楽章から出来ています。これを見る限りでは、現代の「レクイエム」にありがちな典礼文以外のテキストの使用はないようですね。ただ、後半の曲順がちょっと普通とは違うのと、細かいところでのテキストの変更が行われていました。 ここでの主役は、女声合唱です。彼女たちのあくまでピュアな、ほとんど稚拙とも思える歌い方は、時には全く無表情に感じられることもあります。しかし、彼女たちが作り出すハーモニーは、何か不思議な魅力で迫ってきます。 音楽もあくまでシンプルさに徹しています。たとえてみれば、同じ北欧のアーティスト「エンヤ」ととてもよく似たテイストを持っています。彼女が多重録音で作り上げた世界が、ここでは生身の合唱とオーケストラに置き換わっています。 そのオーケストラは、管楽器や打楽器もフルに加わった編成ですが、基本は弦楽器、あくまで淡白な音色で合唱をサポートします。 「Introitus」と「Kyrie」では、テキストは典礼文がそのまま使われています。しかし、次の「Dies irae」では、さすがに20節もあるテキストを全部使うことはなく、「Dies irae」で始まる最初の3行と、モーツァルトが「Lacrimosa」で使った、その言葉で始まる最後の3つの節だけが歌われています。ここではハープが加わって、流れるような三連符のリズムを弾き続けています。 「Offertorium」と「Sanctus Benedictus」は本来のテキスト通り、後者は3拍子の曲ですが、「Hosanna in excelsis」の部分でいきなりボレロのリズムになるのが和みます。 その後に、なぜか「Libera me」が入ります。チェンバロが入ってちょっとバロッキーなサウンドになりますが、曲調はシンコペーションを多用したジャジーなものです。ここでもテキストの最後の部分がカットされています。 「Agnus Dei」は、オーケストラがバーンスタインの「ウェストサイド・ストーリー」のメイン・モティーフそっくりのリフを奏でる中で歌われます。テキストは「Agnus Dei」だけではなく、その後の「Lux aeterna」で始まる「Commnio」の部分も歌われます。 「In paradisum」は、合唱が8分音符で3拍子のところに、オーケストラが4分音符で3拍子を取るという「ヘミオレ」のちょっとした浮遊感の中で進みます。後半には「Kyrie」や「Introitus」のテキストが繰り返されます。癒されますね。 CD Artwork © Nilento Records |
||||||
マーラーの「7番」はちょっと苦手な曲でした。そもそも「夜の歌」というようなわけのわからないサブタイトルが付いているのでなおさらです。でも、最近ではこれはあまり使われることはなくなっているようですね。そもそもこれはマーラー自身が付けたものではなく、マーラーは単に5つの楽章の中の2つに「Nactmusik」というタイトルを付けただけのことです。しかも、この言葉は直訳すれば「夜の音楽」ですが、本来は「セレナーデ」の意味ですからね。モーツァルトの「Eine kleine Nachtmusik」の「Nachtmusik」ですよ。 そんな、誰が付けたのかわからないようなタイトルに惑わされていたのと、さらに決定的だったのは柴田南雄という尊敬に値する明晰な頭脳の持ち主が、この曲を「他の曲よりも『第七交響曲』(の演奏頻度)が出遅れているのはなぜか。曲自体が魅力に乏しいからか。アイディアの枯渇による見劣りが感じられるのか。いや、そんなことはない、と力んで反論することは容易だが、まあ、それを完全に否定することも難しい」(「グスタフ・マーラー 現代音楽への道」1984年岩波新書)とディスっていたことでした。そこまで言われてしまえば、わざわざ聴きたいとは思えなくなってくるじゃないですか。 ですから、今まで単品でこの曲のCDを買うことは決してありませんでした。しかし、最近、なんとこの曲を実際に演奏しなければいけなくなってしまったのですよ。予定されている指揮者からは、「第7番を早く耳から覚えこんでください」という指令が出されたりしていますから、それに従わないわけにはいきません。 そこで、このハイブリッドSACDで入手できる最新のアルバムを聴いてみることにしました。このコンビによるマーラーは最初の「5番」を聴いて、ちょっと録音に問題があると思ったのですが、その後に「2番」を聴いた時には何の不満もありませんでしたからね。確かに、録音面ではいかにもBISらしいクリアなサウンドで、あくまでサラウンドはホールトーンを重視というスタンスでしたね。 そんな響きの中で聴こえてきた第1楽章は、テナーホルンによる物悲しいテーマが、とてもふくよかなものに感じられました。音楽自体はやはり暗さを持っていますが、それがひとしきりあった後に訪れる、まるでリヒャルト・シュトラウスかと思えるような甘美な世界には、ちょっと驚いてしまいました。このあたりは、おそらく「5番」の「アダージェット」の延長にあるのでしょう。 そして、第2楽章、最初の「セレナーデ」では、そのメインテーマがとことんキャッチーで、なんという素晴らしいメロディなのか、と思ってしまいます。無駄のない、それでいて変化に富んでいて心をわしづかみにされるメロディです。中間部の夢を見ているような華々しさにも惹かれます。 そして、曲全体の折り返し地点、スケルツォは、もろウィンナ・ワルツじゃないですか。ベースとなっているおどろおどろしい三連符の連続とのミスマッチがたまりません。 次の楽章は、本当の意味での「セレナーデ」でしょう。あいにく、この録音ではギターやマンドリンは聴こえてきませんが、とても穏やかな気持ちにさせられます。 そして、それまでの世界とまるで異なる、絢爛豪華な終楽章へと突入です。これはもう、四の五の言わずその目くるめくごった煮の世界に身を任せるしかありません。何回も出てくるロンド・テーマを飾る木管の超絶技巧のフレーズは、最初はまっとうにこてこての後期ロマン派だったものが、最後に出てくる時にはほとんど無調と化しているなんて、すごすぎます。 というわけで、ヴァンスカの目の覚めるような演奏で、すっかりこの曲が好きになってしまいました。あとは、本番がコロナが収まっている頃ならいいな、と祈るばかりです。 SACD Artwork © BIS Records AB |
||||||
そのオーケストラは、地元では、毎年シェーンブルン宮殿での野外コンサートを6月に行っていましたが、さすがにそれは無理だったのでしょう。しかし、それからたった3か月後には、お客さんの人数こそ限定したものの、例年と全く変わらないコンサートをやってのけたのですから、すごいものです。その模様を収めたBDです。 実は、このBDに収録されているものとほぼ同じものだと思われる映像が、先日BSでも放送されていました。その時には、やはり毎年恒例のBBCプロムス・ラストナイトが放送されていました。最初にこのBBCがあって、そのあとにウィーン・フィルが出てきたのですが、それぞれのイベントに対するスタンスが全く違っていたのが非常に印象的でした。BBCはロイヤル・アルバート・ホールでの「無観客」コンサート。広いステージでは総勢60名程のオーケストラはメンバー間の距離を大きく取っていますし、最後に登場する合唱団は客席、といってもアリーナ席ではなくまわりのスタンドで歌っていますから、どんだけ徹底された「ソーシャル・ディスタンス」なのかが分かります。 それに対してウィーン・フィルの方は、例年と全く変わらないコンディションでコンサートを行っていました。ステージは宮殿の前に作られた鳥かごのような狭苦しい空間、間口が狭いので、団員たちは奥の方までぎゅうぎゅう詰めになって座っています。これは彼らが演奏を再開した時からのスタイルで、そのような密集した配置でないと、このオーケストラならではの音楽は作れないという「信念」の元に行われていることのようです。メンバーは全員PCR検査を受けているのだそうですが、無謀としか思えません。きっと新年のコンサートも、こんな密集したところで行うのでしょう。 さすがに、お客さんはごく少人数が前の方に座っているだけで、いつものように庭園中が人で埋め尽くされるということはありません。庭園自体が入園禁止になっていたのですね。そのせいで、画面ではライトアップされた庭園の全景を楽しむことができますね。あれだけ広いところの照明をコントロールするために準備にはどれほどの手間がかかっているのか、気が遠くなるほどです。本当に、この映像は見事です。明るいころのショットでは、遠くに聖シュテファン大聖堂の尖塔が見えるようなアングルもありましたね。 指揮をしたのは、日本にも同行したゲルギエフです。この庭園コンサートが始まったのは2004年からですが、彼が登場したのはこれが4回目なのだそうです。もはや「常連」と言ってもいいのでしょうが、まだ「ニューイヤー・コンサート」からはお呼びがかかっていないようですね。今回もアンコールでヨハン・シュトラウスのワルツが演奏されていましたが、その時は団員は誰も指揮を見ていなかったようでした。というか、あの指揮に合わせていたら、とてもどんくさいウィンナ・ワルツになっていたことでしょうね。 プログラムの中でも、メンデルスゾーンの「真夏の夜の夢」の中の「スケルツォ」の時も、誰も指揮に合わせていなかったようで、その結果とても軽快な音楽を聴くことができたのではないでしょうか。今回のフルートの乗り番はシュッツ、彼のソロは完璧でした。 そして、なんと言ってもこのコンサートの主役はテノールのカウフマンでしょう。久しぶりにその姿を見たら、幾分丸みを帯びていたようですが、その声は全く変わっていませんでした。いや、その強靭さは、以前にも増していたような気もします。軽妙なオペレッタもいいでしょうが、やはり圧巻は重みのある「ネッスン・ドルマ」でしたね。最後の「Vincerò!」のハイB♭の輝きは、パヴァロッティを超えてます。 BD Artwork © Sony Music Entertainment |
||||||
これは、そこで、2019年に演奏された、「ウェストサイド・ストーリー」の室内楽バージョンです。この有名なミュージカルのナンバーを、ヴァイオリンと4本のサクソフォン(ソプラノ、アルト、テナー、バリトン)のための五重奏に編曲したのは、オランダのトロンボーン奏者で編曲家のヘンク・ハウジンガです。ヴァイオリンを演奏しているのはメシン自身、サクソフォンは全員が異なる国の出身で、2009年にアムステルダムで結成された「メリスマ・サクソフォン四重奏団」のメンバーです。 「ウェストサイド・ストーリー」と言えば、レナード・バーンスタインの最高傑作ですから、この作品のオリジナルは、ほぼ全ての録音は聴いています。 しかし、今回の陣容を見て、果たしてこんなものを聴く価値があるのだろうかと逡巡したことは事実です。ヴァイオリンはともかく、サクソフォンは、確かにオリジナルのオーケストレーションの一部にはなっていますが、果たしてその楽器が主役となって大丈夫なのか、という危惧があったのですね。なんせ、この粗野な楽器が他の楽器の邪魔をしていて非常に不快に感じた体験が何度かありますからね。 ということで、「怖いもの見たさ」で聴き始めたのですが、そんな心配は全く無用でした。ここでのサクソフォン達は、あの忌まわしいビブラートを完璧に封じ込めて、しっかりアンサンブルに奉仕していたのです。もちろん、ヴァイオリンとの相性もばっちり、サックス(サキソフォン)でも、やる気になれば「美しい」アンサンブルを作り出すことは出来ることを知って、目もぱっちり。 そもそもバーンスタインのこの作品は、決して「クラシック」ではありません。なんたって「ブロードウェイ・ミュージカル」ですから、その中にはジャズやラテン音楽の要素がてんこ盛り、そのような音楽にサックスはとても相性がいいのでしょう。 まず、オープニングとなる「Prologue」で聴こえてきたのは、バリトン・サックスによるパワフルでキレの良いリズムです。この楽器は、こんな役目を任されたら右に出るものはありませんから、まさにうってつけ、ダンスナンバーでのベースはこれで完璧になります。 その次には「Jet Song」ですが、そのメロディを歌うヴァイオリンは、ポルタメントをたっぷりかけて、この曲のブルーノートを強調し、いかにもブルージーなけだるさを演出しています。そして、そこに続くのが、かなり先のシーンである体育館でのダンスのナンバー「Blues」です。そして、その後にまた「Jet Song」が繰り返されます。 つまり、この編曲は、物語の進行をそのまま聴かせるのではなく、音楽的に関連のあるもの、あるいは、全く逆の性格を持つものなどを巧みに組み合わせて、全体を一つの起伏に富む組曲となるように再構成されているのです。ですから、このように何曲かをメドレーとして休みなく続けたりして、少し長めのセクションにしているのでしょう。 ですから、「Mambo」(ここでは、みんなで楽器を一瞬口から離して「マンボ!」と叫んでますね)の後にはオリジナル通り「Cha-Cha」が来ますが、その後には「I Feel Pretty」になりますからね。 面白いのは、「Tonight」になると、最初はヴァイオリンのソロなのですが、その後にアルト・サックスやソプラノ・サックスがソロをとると、ここぞとばかりにたっぷりのビブラートをかけて熱く歌い上げることです。こんなところで「地」がでてくるのですね。 いずれにしても、とても楽しめたアルバムでした。 CD Artwork © Orchid Music Limited |
||||||
ここで演奏しているのはラヴェルの「スペイン狂詩曲」とドビュッシーの「牧神の午後への前奏曲」と「海」の全3曲。それぞれ録音時期が異なっていて、「牧神」は2018年1月、「海」は2018年3月、この頃はまだ5.6MHzのDSDで録音されました。ラヴェルは2019年4月なので、11.2MHzになっています。この前のショスタコーヴィチではかなりその違いを聴きとることができましたが、ここではどうなのでしょう。 ロトはすでに自身のオーケストラでこの二人の作曲家の曲をいくつか録音していますが、今回のプログラムにあるドビュッシーの2曲もその中に入っていました。ただ、実際に聴いたことがあるのは「牧神」だけです。それとの比較も気になりますね。 まずは、ロトにとっては初録音となるラヴェルの「スペイン狂詩曲」です。実は、この曲はごく最近実際に演奏しているので、なにかと親近感があります。しかし、1曲目の「夜への前奏曲」がとてつもないピアニシモで始まった時に、それはもはやアマチュアとは全く別の世界の産物であることに気づかされます。この、トップクラスのモダン・オーケストラは、そんな途方もないダイナミクスを軽々と操ることができることをまざまざと見せつけてくれました。途中で、クラリネットやファゴットが2人ずつでカデンツァを演奏するところなどは、その2人の息が信じられないほどに合っていて、驚かされます。 そんな中で、非常にセンシティブな弦楽器のフレーズが現れると、それはやはり11.2MHz DSDならではの卓越した録音であることが分かります。ですから、全ての楽器がとても生々しい肌触りで聴こえてきます。コール・アングレのソロの音色の素晴らしいこと。 続く「マラゲーニャ」と「ハバネラ」の妖しい世界でもその繊細さをいかんなく発揮(ピッコロの煌めきは絶品)した後に、賑やかな「祭り」が続きますが、これはもうアンサンブルの極致です。ロトのドライブの下、オーケストラが一丸となって、踊りまくります。 次はドビュッシーの「牧神」です。これはもう、首席フルート奏者のギャレス・デイヴィスの独り舞台という感じですね。少し暗めの音色で、巧みなビブラートとダイナミクスのコントロールを行って、完璧なソロを聴かせてくれています。その周りに絡みつく他の楽器も、それぞれに自己を主張しつつ、緻密なアンサンブルを繰り広げています。 これを、同じロトが指揮をしたル・シエクルの演奏と比べてみると、これはもうソリストの差がもろに現れてしまっています。楽器は鳴っていないし、表現もなにか遠慮しているような感じですからね。パンチ力の違いでしょうか(それは「ボクシング」)。 そして最後は、大曲の「海」です。3つの楽章それぞれにその性格をきっちりととらえて、圧倒的な表現力で迫ります。ここで聴かれるフル・オーケストラのトゥッティ・サウンドは、11.2MHzのラヴェルを聴いてしまうとちょっと物足りない気もしますが、5.6MHzのスペックをフルに使いきった満足感のようなものはあるのではないでしょうか。 いずれにしても、これらの3曲はモダン・オーケストラのサウンドが最大限に生かされた聴きごたえのあるものでした。それに比べて、あくまで作曲された時代のサウンドを再現したとされる「レ・シエクル」には、なにか物足りなさがつきまといます。まあこれはこれでありがたみを感じる人もいるのでしょうが、そもそも、使い慣れない骨董品を修復した楽器を演奏した時に、そのプレーヤーの能力が100%発揮できているのか、という疑問が湧いてしまいます。 SACD Artwork © London Symphony Orchestra |
||||||
タイトルで「5番→1番」の順序になっていますが、これは1枚目が「5番」、2枚目が「1番」になっているからです。なぜそうなっているかというと、録音されたのがこの順番だったからなんです。「5番」が2016年、「1番」が2019年です。 ところが、そのデータが、ブックレットではこんな風にしか書かれていませんでした。 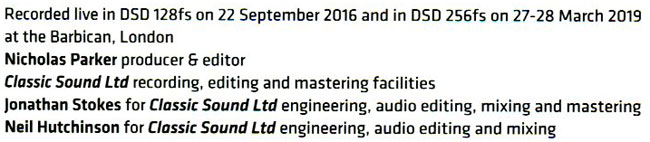 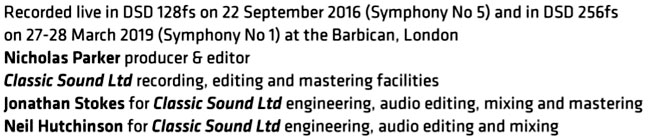 いずれにしても、この2曲は録音時期だけでなく、録音フォーマットも違っていることが分かりました。どちらも1ビットのDSDですが、2016年にはサンプリング周波数がCD(44.1kHz)の128倍(5.6MHz)だったものが、2019年にはそのさらに倍の256倍(11.2MHz)になっています。そもそもSACDでは64倍の2.8MHzなので、あまり意味はないだろうと思われるかもしれませんが、それを実際に聴いて確かめてみたくなりましたね。 「5番」の第1楽章は、あまりもったいぶらずメリハリのきいた、あっさりした演奏です、これが最近の演奏のトレンドなのでしょう。ちょっと気になるのが、フルートだけが他の木管よりオフに聴こえることです。ソロではもっと目立ってほしいのに。第2楽章はとても丁寧であまり軽さを前面には押し出してはいません。 第3楽章はかなり厚ぼったい表情が付けられています。フルートのソロは周りが薄い時は十分聴こえてくるのですが、例えばクラリネットのバックで演奏する時などはもっと聴こえてもいいのでは、と思ってしまいます。 第4楽章はゆっくり目で始まり、それほどのアッチェレランドはかけず、最終的に細かい音符でもしっかり演奏できるだけの適切なテンポに落ち着きます。静かな部分はかなりあっさりとした表現、最後の盛り上がりはじっくりと仕上げていっています。最後の音の残響がまだ消えないうちにカットされているのは、拍手を聴かせないためでしょうか。こんなのは、いくらでも細工できるのに。 録音は、十分満足できるクオリティ、というか、これまで聴いてきたものとは一線を画した、ハイレゾのサラウンドならではの素晴らしさでした。特に弦楽器の質感がとてもきれいに聴こえますし、ピアニシモになった時の雰囲気も素敵です。 しかし、その3年後、スペックがワンランクアップしたところで録音された「1番」では、さらにその上を行っていました。この曲はしっかり聴いたのは今回が初めてですが、もう各所にオーディオ的な難所があるのに、それらが全てクリアされています。 まず、第1楽章では、人を食ったような諧謔的な音楽が、室内楽のような編成で始まりますが、そこの楽器たちがそれぞれに透明感をもってとてもクリアに聴こえてきます。「5番」ではちょっと難があったフルートのバランスも、ここでは何の問題もありません。 そんなチマチマした音楽で、なかなかフルオーケストラが現れないのでストレスがたまったあたり、第3楽章になって、やっとトゥッティのフォルテシモが登場します。これはもうどこをとってもエネルギーの発散が感じられるというすごさです。金管楽器のリアル感がものすごく、圧倒されますし、弦楽器の質感も尋常ではありません。 第4楽章になって初めてチェレスタのソロが聴こえてきますが、そのクリアさも「5番」の時とは段違いです。ですから、この楽章の途中で出てくるティンパニのソロにはもう腰が抜けそうになってしまいました。それが、次の瞬間にはピアニシモで叩いているのですからね。そして、最後まで突き進んで行った先のバカっぽいエンディングも、こんな素晴らしいサウンドだったら、なにをやっても許されます。 SACD Artwork © London Symphony Orchestra |
||||||
さきおとといのおやぢに会える、か。
|
|
| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |
| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |