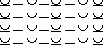
「詩の朗唱について」『言語文化研究』22(1996)153-170頁
(本文1)
原田裕司
そもそも言語とは、本来音声によって成り立つものであります。特に人間が言語を持つと同時に存在したであろう詩歌は、当然ながら本来歌われたり朗読されたりしたものであります。ところがそうした詩の朗読は、いつの頃からか、特に現代において、黙読に取って変わられるようになりました。これは詩が本来あるべき姿に背くものであり、そのことによって私達は詩や文学を学ぶうえで、また言語一般を学ぶうえで大きな不利益を蒙っているのではないか。そこで私達は、詩を歌い朗読することの意義を今一度見つめ直してみようではないか。これが本日の私の発表の基本認識であり、提言でもあります。1)
さてヨーロッパでは古来、読書とはすなわち朗読することであり、黙読がむしろ例外でありました。オットー・ボルストはその著『中世ヨーロッパ生活誌』において、一人きりの個人の読書においても、朗読が行われていたことを示す具体例をいくつか紹介しております。例えばエラスムスは自分の手紙の受取人に対して、秘密がもれないよう一人だけで手紙を読むことを依頼しております。つまり手紙を読む場合においても、朗読することが当時としては自明のことだったのであります。2)
散文でもそうでありますから、詩を鑑賞する場合では、朗読はいっそう重要であります。例えば古代ローマの詩人オウィディウスの記述を見れば、詩の公表とはすなわち人前での朗唱であったことがわかります。3) また近代ドイツの詩人ゲーテやシラーは、互いの詩作品を披露する時には、原稿を相手に見せるのではなく自ら朗読して聞かせていました。4) こうした例はヨーロッパの例ですが、日本においても和歌の朗詠や詩吟の例などを見ますと、詩を朗唱することそのものが、洋の東西を問わず重要な役割を帯びていたことは疑いありません。
しかしながら、表音文字であるアルファベットを用いて文書を記録するヨーロッパにおける方が、表意文字である漢字を用いる東アジアよりも、朗読の文化をさらに忠実に現代まで伝えていることは容易に推察できます。西洋の社会では弁論が伝統的に重視されることは言うに及ばず、今日でも詩を朗読して人に聞かせる機会は、日本などよりも多いように見受けられます。特にヨーロッパの古代・中世の文字表記では、文法的なシンタクスに従って句読点を配する現代のやり方とは異なり、朗読を行う際の間の開け方や声の上げ下げなどを示すことそのものが、句読点に課せられた何よりも重要な役割でありました。このことは、古来ヨーロッパにおいて、文字表記を行う際に朗読が如何に重要なものとして意識されていたかを示す一つの事例であります。5)
これに対して現代の日本においては、多くの場合詩は黙読で鑑賞されているように思います。すなわち、本来朗読されることによって完全な姿を現わす詩が、単にその内容面で解釈されるに留まってしまうことが、いかに多いことでしょうか。仮に詩について音声面の考察がなされる場合でも、それは単に解釈者の言葉による音韻の説明描写に留まるのみで、生き生きとした詩の音声そのものが直接私達に伝えられることはまれであります。私達はそこで自ら詩を朗読してその響きを確認しなければならないのです。そうすることによって初めて私達は、その詩が秘めている独自の魔術を体得できるのです。このことは例えば『万葉集』の朗唱によって人々の心を魅了した、犬養孝大阪大学名誉教授のいわゆる「犬養節」を聞けば、おのずと納得できるところでありましょう。すなわち、
[朗唱]いはばしる垂水の上のさわらびの萌えいづる春になりにけるかも 6)
といった具合いです。しかし、この「犬養節」は、黙読中心の現代日本の詩の鑑賞のあり方の中では、むしろ例外に属するものではないでしょうか。
詩の朗読をないがしろにするこの傾向の原因は、いったいどこにあるのでしょうか。その原因の一つは、学校の語学の授業において、美しい詩や散文を美しく朗読することの意味や喜びがあまりにもなおざりにされていることではないでしょうか。私達語学の教師が、美しい詩文を美しく朗読することによって学生達の心を魅了し、学生達自らがそのような詩文の朗読を心から楽しむようになる、そんな授業がもっとあってもよいのではないでしょうか。機械を使った授業がますますさかんになる今日では、逆に、教師と学生という生身の人間同士のぶつかりあいが、朗読という古くて新しい言語体験を通じて、いっそう求められるのではないでしょうか。また詩などの文学作品についての単なる研究発表だけではなく、詩そのものを朗読する会も、もっと催されてよいのではないでしょうか。
さて以下の発表は、具体的に詩を朗唱することによって、今述べた私の基本認識と提言を実証し、また実現しようと試みるものであります。私の専門柄、取り上げる詩をラテン語の作品に限定することを、お許し下さい。
まず、17世紀の中国で生まれた一つの詩を取り上げます。
[Ambrosianum]
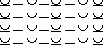
![]()
大園在上 Immensa caeli machina 巨大なる天の機構は
周廻不已 numquam rotando deficit, かたときもその回転をやめない
七精之動 planeta quisque proprium 各惑星は運行しつつ
經緯有理 eundo motum conficit. 固有の動きをなす
庶績百工 Hinc omne quod coelo subest 天の下にあるもの全ては
於焉終始 ortum exitumque postulat; ここから始まりと終わりを求める
有器有法 ars cuncta deinde machinis さらには学術が機具を用いて
爰觀爰紀 observat atque supputat. すべてを観察し計測する
惟此遠臣 Europa nobis hospitem ヨーロッパはわれらのもとへ
西國之良 submisit isthuc inclytum, 一人の高名な客人を遣わした
測天治歴 sunt astra et horum calculus 星辰とその計測方法は
克殫其長 statim reducta in integrum. すぐに正しく見直された
敬業奉神 Ut muneris sic Numinis 彼は自分の職をも神をも
篤守弗忘 oblitus haud unquam sui, かたときも忘れることはない
乃陳儀象 dum debitum signis sacris 聖なる天体に対して
乃構堂皇 temploque cultum praeparat. 教会に対して務めを果たす
事神盡虔 Dum sedulus servit DEO 熱心に神に仕え
事君盡職 et munus exaequat suum, 自らの職務を全うする
凡爾疇人 Chinensibus et Tartaris 漢人にも韃靼人にも
永斯矜式 tum forma vivit actuum. 7) 彼の生き方は行動の模範である
auファイル形式(各々120K)
Real Audio v.5形式(各々34K)
左の中国語の詩は、17世紀中頃の清の皇帝順治帝が、当時北京に滞在していたイエズス会のドイツ人宣教師アダム・シャル(Johann
Adam Schall von Bell, 1592-1666)の功績を称えるべく、彼の教会に与えたものであります。その右に掲げましたのは、中国語を解したシャル神父自身が、これをラテン語の詩に訳したものであります。これは私が知る限り、中国語の詩がラテン語の詩へ翻訳された事例
で、その両方のテキストが記録されている最も古いケースではないでしょうか。
さてシャル神父はこの詩を記録するにあたって、次のように述べています。
私はこれらの詩行を、それに当然ふさわしい手法ではなく、私に可能だった
手法で、ほとんど原文の言葉どおりこのようにラテン語訳した。8)
ここでシャル神父が「その詩に当然ふさわしい手法」および「私に可能だった手法」と呼んで区別した2つの訳詩の手法とは、具体的には、詩に用いる2つの異なった韻律の種類を指していたものと思われます。
ここで私達はこの2つの韻律の種類に言及する前に、詩そのものの種類すなわちジャンルの問題を考えてみましょう。先ほど私は、詩というものは本来朗唱によって鑑賞されるものであると申しました。しかし厳密に見ると、同じ詩でも、文字で筆記された形で人の目にふれることにより、その本来の役割を果たす、そのような類の詩もまた存在するのです。それはヨーロッパにおいては、本来物の上に書きつけられたところから名前をとる狭義での「エピグラム」というジャンルの詩であります。それは具体的には墓碑銘やその他の碑文に用いられる詩の類でありまして、ラテン語では古代以降おびただしい数で伝えられているものです。そしてそのようなジャンルの詩には、もっぱら特定の韻律が用いられるのです。それは、ヘクサメテル(dactylicus
hexameter 六脚詩行)またはディスティコン(distichon 二行詩句)と呼ばれる韻律であります。
[distichon]
hexameter:
pentameter:
Carmina qui quondam studio florente peregi,
flebilis, heu, maestos cogor inire modos! 9)
かつて勉学の熱意に燃えて歌を歌い通した私が
今では泣きながら ああ 悲しい旋律を奏でることを強いられる
ところで清の皇帝がシャル神父の教会に与えた中国語の詩は、清朝に対するシャルの天文学上の貢献を評価し、また彼自身の誠実な人柄を称えたものでした。それは彼の教会に永く飾られるべき記念碑的性格を持つ詩文でありました。それゆえこの詩をラテン語に訳すべき詩の韻律は、碑文に用いられることの多いヘクサメテルかディスティコンとなるはずであります。したがってシャル神父自身が「その詩に当然ふさわしい手法」と言ったとき、彼はおそらくはこれらの韻律のことを考えていたのではないかと想像できるのです。ところが実際に翻訳のために彼が用いた韻律とは、それらとは全然違ったものでした。
その韻律とは、イアンビクス・ディメテル(iambicus dimeter)という詩行4行から成るアンブロシウス詩節(Ambrosianum)であります。これは4世紀のミラノの司教アンブロシウス(Ambrosius)が自らの教会で歌う賛歌のために用いた叙情詩の韻律であったところから、その名を得ております。アダム・シャル神父が、「その詩に当然ふさわしい手法ではなく、私に可能だった手法で翻訳した」と述べたのは、碑文のための詩として当然ヘクサメテルかディスティコンで書かれるべきものを、本来崇高な賛歌の韻律であるアンブロシウス詩節で書いたことを指しているのです。ただしシャル神父は、ヘクサメテルやディスティコンの詩を書く力がなかったわけではなく、彼は、自分が洗礼を授けた中国人少年の墓に刻む詩をラテン語のディスティコンで自ら書いております。10) それならばなぜ彼はわざわざアンブロシウス詩節を、皇帝から賜わった詩の翻訳に用いたのでしょうか。一つには彼は、漢字4字からなる短い中国語の1詩行を、1行分が比較的長いラテン語のヘクサメテルやディスティコンに訳すことに無理を感じたのかも知れません。
しかし、どうもそれだけではなさそうです。なぜなら、アンブロシウス詩節は、本来カトリック教会の典礼歌であるグレゴリオ聖歌の中で、特にその賛歌の形式をなす非常に重要な韻律の一つでありました。そのような、本来教会で神や聖人を称えて歌われる賛歌の韻律を、自らを記念する詩のラテン語訳に用いることは、たいへん大胆な企てであるといわねばなりません。にもかかわらず、シャル神父がこの詩をこのような貴い韻律であえて翻訳したことは、自らの功績が愛する外国の詩で称えられたことに対する、彼のとてつもなく大きな喜びと誇りを暗示するものではなかったでしょうか。
私が以上のような考察に至りましたのは、私が1995年度、大阪大学大学院言語文化研究科で行っているグレゴリオ聖歌に関する授業と密接に関わっているのです。すなわち私はこの授業に参加している学生諸君と一緒に、これまで数曲のグレゴリオ聖歌を歌ってまいりました。その中の一曲に
Veni Creator Spiritus(来たれよ、創り主なる聖霊よ)という歌があります。この詩は実はさきほどのアダム・シャルのラテン語の訳詩と同じアンブロシウス詩節で書かれているのです。今ためしにシャルの詩とこの詩を続けて朗読いたします。その後で
Veni Creator を学生諸君とともに合唱いたします。11)
[シャルの詩と Veni Creator を朗読]
[Veni Creator を合唱]
[Ambrosianum]
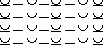
Veni, creator Spiritus, 来たれよ 創り主なる聖霊よ
mentes tuorum visita, 汝のしもべ達の心を訪れよ
imple superna gratia, 天上の恩寵もて
quae tu creasti, pectora. 汝が創りたる胸を満たせ
Qui Paracletus diceris, パラクレトスと呼ばれしもの
donum Dei altissimi, いと高き神のたまもの
fons vivus, ignis, caritas 生ける泉 火 慈愛
et spiritalis unctio. 霊の膏薬
Tu septiformis munere, 汝 七つの役目を帯びしもの
dextrae Dei tu digitus, 汝 神の右手の指
tu rite promisso Patris 汝 父の正しき約束なる言葉もて
sermone ditans guttura. われらの口喉を富ませるもの
Accende lumen sensibus, 五感に光を灯し
infunde amorem cordibus, 心に愛を注ぎたまえ
infirma nostri corporis われらの弱き肉体を
virtute firmans perpeti. 永遠の力で元気づけつつ
Hostem repellas longius 敵を遥かに蹴散らし
pacemque dones protinus, 平安を直ちに与えたまえ
ductore sic te praevio 汝をかくも導き手として
vitemus omne noxium. われらすべての災いを逃れん
Per te sciamus, da, Patrem 汝によりて父を知り
noscamus atque Filium, 息子をも認め奉らん
te utriusque Spiritum お二方の聖霊なる汝を
credamus omni tempore. 12) いかなる時も信じ奉らん
Gloria Patri Domino 主なる父に栄光あれ
Natoque, qui a mortuis 死者の中から蘇りたる
surrexit, ac Paraclito 息子と聖霊に栄光あれ
in saeculorum saecula. 13) いついつの世までも
Amen. アーメン
auファイル形式(各々120K)
Real Audio v.5形式(各々34K)
この Veni Creator という詩は、一説には9世紀のマインツ大司教ラバーヌス・マウルス(Hrabanus
Maurus)によって書かれたものと推察されております。聖霊を称えたこの歌は、キリスト教会での聖霊降臨祭に歌われるものですが、美しい旋律と一つに融けあったその詩は、宗教の違いを越えて人間の普遍的な心の願いを訴えるものであり、本当に素晴らしい歌であると私は思っております。アダム・シャルが、自らを記念する詩のラテン語訳に、このように美しい賛歌と全く同じ韻律を用いたことの意味は、この
Veni Creator の合唱を聞いていっそうよく理解できるのではないでしょうか。シャルは、自分を称える詩が単に碑文として記録されるにとどまらず、輝かしい思い出の歌として、自らこれを声に出して歌うことさえ欲したのではなかったでしょうか。