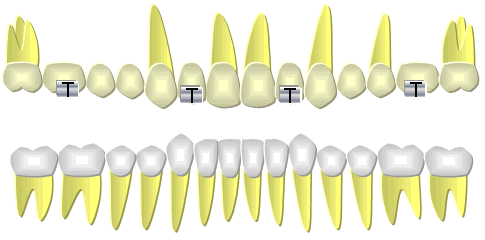
Laurell(1985)はクロスアーチブリッジでの咬合力と咀嚼能力について一連の研究を行ないました。
まず、習慣性咬合での歯列全体および局所の咬合力を記録可能な装置を製作し、硬い食物と軟らかい食物を用いた咀嚼プログラムを開発しました。これ らを用いて咬合力(咀嚼時、最大咬合時)や咬合様式、咬合力と残存歯根膜面積の関係、咀嚼能力(食物の粉砕能力)などを調査しました。
咬合力の研究に選択された被験者は、上顎にクロスアーチブリッジが装着され、両側性および対称性にtransducerを設置可能な人です。
カンチレバーではないクロスアーチブリッジ : 12人
片側に2ユニットのカンチレバーを有するクロスアーチブリッジ
: 12人
Transducerの設置(T)は下の図のようになります。それぞれ1部位ごとでの計測と、全体での計測が行なえます。
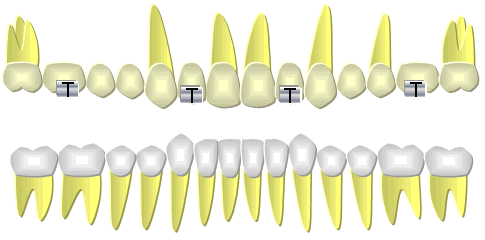

普段よく噛む側(好咀嚼側)と反対側(非好咀嚼側)、前歯部(A)と臼歯部(P)を比較しています。
咀嚼力 : 通常の咀嚼に用いる力
習慣性咬合での最大咬合力 : 全ての歯牙(transducer)が接触した状態で限界と感じるまで加えられた力
一部位のみの最大咬合力 : その部分だけに金属球を介在させて噛んだ時に限界と感じるまで加えられた力
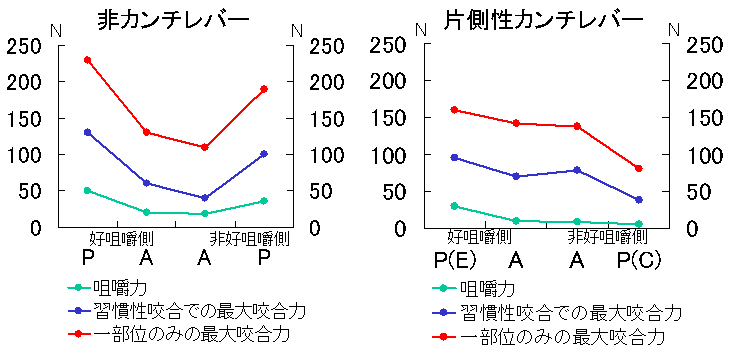
(Laurell 1985より改変)
結果をまとめると以下のようになります。
1. 好咀嚼側と非好咀嚼側 : 非カンチレバーブリッジでは人によって左右に好みが分かれるが、片側2ユニットのカンチレバーブリッジでは、常に臼歯部非カンチレバー側P(E)が好咀嚼側、臼歯部カンチレバー側P(C)が非好咀嚼側であった。
2. 左右差 : 非カンチレバーでは前歯部よりも臼歯部の咬合力が大きく、非好咀嚼側よりも咀嚼側で咬合力が大きいものの、大きな左右差は認められなかった。一方、カンチレバー部位に加わる咬合力は前歯部よりも小さかった。
一部位のみの最大咬合力を100%とみなした際の、臼歯部での咬合力の割合を示します。
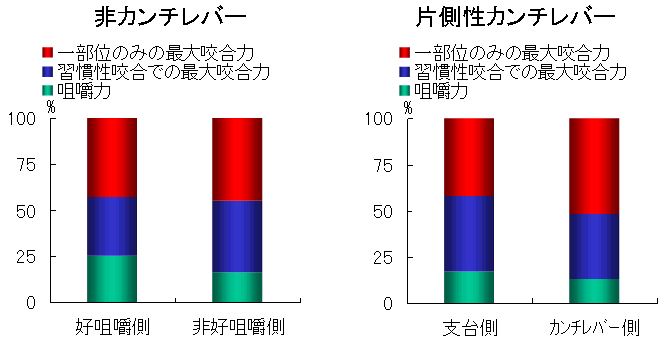
(Laurell 1985より改変)
通常の咀嚼に用いられる力は、非カンチレバーの好咀嚼側で25%、その他の部位はそれ以下の咬合力しか用いられていません。
硬い食べ物(ピーナッツ)と軟らかい食べ物(ローストビーフとポテトサラダ)を用いて、非カンチレバーとカンチレバーのクロスアーチブリッジの咀嚼力や咀嚼回数(飲み込めると感じられるまで)が比較されました。美味しい研究なので羨ましい。
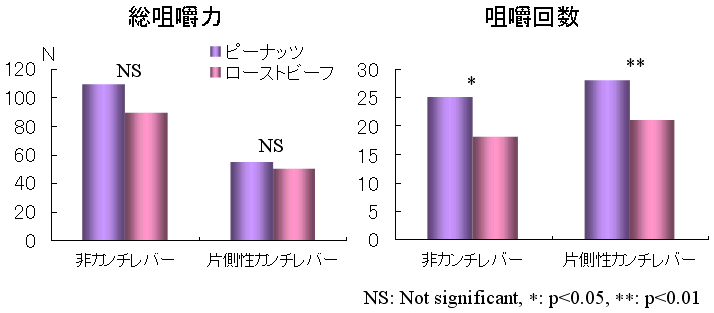
(Laurell 1985より改変)
カンチレバーの有無に関係なく、咀嚼力は硬い食べ物で多少大きいものの、むしろ咀嚼回数を多くすることで対応していることがわかります。
歯周組織が減少するに伴い、歯根膜面積も減少します。平均的な歯根の表面積と、エックス線写真上での骨吸収からブリッジの支台となっている歯根膜面積を算出し、咬合力との関係が調べられました。
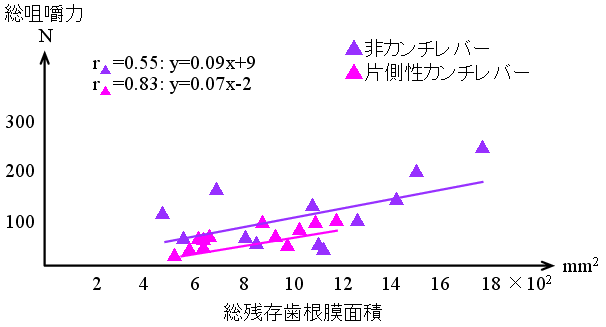
(Laurell 1985より改変)
残存歯根膜面積が小さくなると、総咀嚼力も小さくなることがわかります。片側性カンチレバーでは咀嚼力が小さくなるものの、比例関係は非カンチレバーと同様です。
最終更新2013.1.10