ショパン全作品を斬る
1841年(31才)
次は1842年(32才) ♪
前は1840年(30才) ♪
目次 ♪
音楽の間に戻る ♪
詠里庵ホームに戻る
- [191] バラード第3番 変イ長調 作品47
1841年出版。
ポーリーヌ・ドゥ・ノアイユ嬢に献呈。
4つのバラードの中では悲劇的要素が少なく、
バレエ音楽のような幸福感の支配するバラードである。
しかしこのバラードの作曲にあたってショパンが触発されたと言われているミキェヴィッツの詩「水の精」は必ずしもハッピーエンドのお話ではない。
ショパンは滅多に自分の音楽を文学と結びつけて説明しようとはしなかったので、
本当にこの詩が直接の動機になっているかは定かではないが、
とりあえず要旨は次のような叙事詩である。
「若者は森をさまよい、
湖のほとりで水の精に出会った。
二人は愛を語り合い、
心変わりしないことを水の精は若者に誓わせた。
若者はまた別の湖のほとりで若い女に出会った。
女は先ほどの水の精の化身であり、
若者を誘惑して試した。
若者が女の誘惑に負けたとき、
女は水の精の姿に戻り、
悔しそうに若者に抱きつくとそのまま湖の底に引きずりこんだ。
何もなかったかのような静寂だけが残った」
この詩はラベル「夜のガスパール」の第1曲「水の精」の話にも多少似たところがあるが、
全く同じというわけでもない。
それは次のような話である。
「湖の畔で水の精はあらゆる手練手管で若者を誘惑した。
しかし若者が『私は人間の女を愛しているのだ』と答えると水の精は悔しそうにめくるめく変化を見せ消えて行った」
ショパンのバラード3番に戻ろう。
冒頭、第1主題が前ぶれなく現れる。
ソプラノとテノールの対話のようだ。
主題は軽やかなステップを含んで変化するが、
ずっと変イ長調の回りにとどまる。
これ全体が序奏のような雰囲気も持っている。
一旦変イ長調終止のあと始まるヘ長調の第2主題(下の譜例1)は一層軽やかなバレエだ。
この主題は同主調のヘ短調の副次的主題に入り、
曲想は不安になり悲劇を予感させるが、
ほどなくヘ長調の第2主題に戻る。
変イ長調の推移部に入り印象的な舞踏的パッセージをいくつか経たあと終止変イ主和音はそのまま変ニ長調ドミナントの機能となり、
変二長調で第2主題となる。
副次主題はそこで当然同主調の嬰ハ短調となるが、左手の不安なざわめきに乗り、
右手の技巧的音型(下の譜例4)のクライマックスを迎えて最も激情的になる。
それがおさまるとそのまま第2主題を素材とする展開部的部分に入る。
ここでは左手の白熱した伴奏音型と右手第2主題を素材とする経過句の緊迫感が印象的。
時々現れる左手半音下降のサスペンス的効果が光る。
徐々に緊迫の度を増し、
予感されたクライマックスが第1主題の強奏で現れる。
最後は変イ長調の舞踏的パッセージを要素としてドラマチックに曲を締めくくる。
形式としてはいろいろに解釈できる面白い曲である。
たとえば (1) 全く自由なソナタ形式で、
本来の展開部にはエピソード3つが据えられ、
再現部は第2主題から始められ、
第1主題に戻る前に展開部のような緊迫した部分を挿入し、
最後の第1主題でコーダ代わりにクライマックスを迎えて終わる、
とも考えられる。
一方 (2) 基本的にABAの三部形式で、
Bが形を変えて二回繰り返される中間にいろいろなエピソードが入っていて、
最後のAはコーダの変わりにも使われているとも考えられる。
さらにもっと苦しい解釈かもしれないが、
(3) 変イ長調のAの部分は実は長い序奏で、
ヘ長調に始まるBが本体。
最後は序奏のテーマがファンファーレ的に現れてコーダの役目をして終わる、
という味わい方もあるのではないか。
この曲では第2主題のペダリングが版によって大きく異なる。
パデレフスキーやヘンレを含め多くの版では次のようになっている:
譜例1
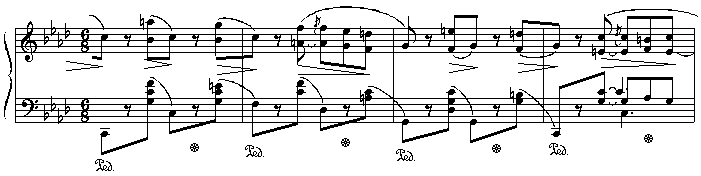
稀に次のようなペダリングも見られる:
譜例2
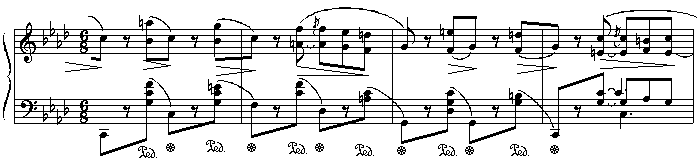
しかし実際には次のように演奏することが多いと思われる:
譜例3
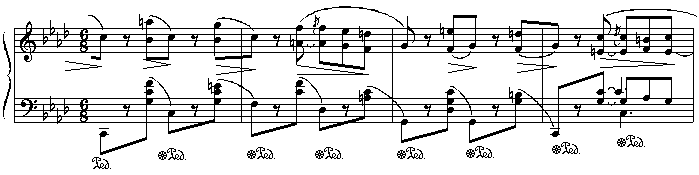
第176小節目、版による音型の違いがある。
パデレフスキーやヘンレを含め多くの版では
譜例4
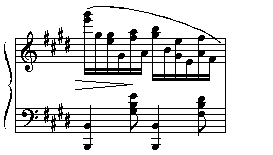
となっているが、
フランス初版およびイギリス初版を踏襲して
譜例5
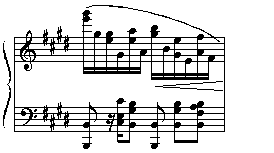
としている版もある。
エキエル版もこうなっている。
こちらの方がドラマチックであるが、
演奏の難しさのためここでテンポが落ちるようであれば、
譜例4で快調に演奏される方がすっきりする。
- [192] ノクターン第13番 ハ短調 作品48-1
作品48の二つのノクターンは1841年に出版、
いずれもロール・デュペレ嬢(ショパンの弟子)に献呈された。
傑作である。
しかしいかにも優美な変二長調のノクターンなどとはまた違った意味で。
この曲はあまりノクターンらしい曲想ではない。
主部はジャズトランペットがサックスのスローバラードを思わせる静かな感慨を湛えている。
ショパンの名旋律のほとんどは流れるように繋がっているが、
これはとぎれるように弱拍に据えられたGとA♭の二つの四分音符から始まる。
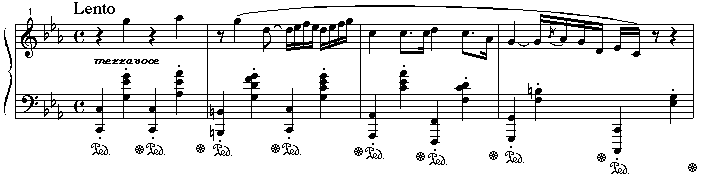
ショパンの弟子達の言(文献[11]p.185)によれば、
この冒頭数小節の演奏のニュアンスにショパンはなかなか満足せず、
弟子達に何度も弾き直させていたという。
葬送行進曲のようなリズムに乗る主部が終わると、
中間部はハ長調の荘重なコラール。
練習曲作品25-10のような両手オクターブによる三連16分音符の飾りが徐々に挿入され、
コラールは盛り上がる。
そのままffでクライマックスに達したあと、
同じ三連符のリズムで
−すなわち元の速度の倍でー
テーマに戻る。
しかしざわめく三連符の伴奏を伴い、
冒頭と違って不安げに奏される。
勝利のファンファーレ的な中間部の後だけに急に何かにおののくような再現は印象深い。
最後に6小節のコーダで静かに終わる。
- [193] ノクターン第14番 嬰へ短調 作品48-2
出版と献呈は前曲参照。
若き日のショパンを思わせるセンチメンタルな旋律。
若き日と少し違うのはいつ止まるとも知れずうねうねと旋律が続く。
中間部のコラール風3拍子は次の年に作曲する傑作「幻想曲」の中間部に似たリズム。
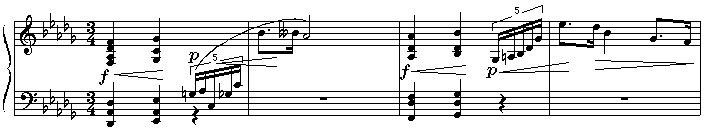
ここは文献[11]p.186によればショパン自身が弟子達に
「暴君が命令を下し(フォルテの二つの和音)相手は慈悲を乞うているのです」
とたとえた。
- [194] 前奏曲 嬰ハ短調 作品45
1841年出版。
エリザベート・チェルニシェフ公爵令嬢に献呈。
オーストリア版はベートーベン記念碑建立基金のための「ベートーベン・アルバム」に収められた。
まるでラフマニノフのような後期ロマン派的和声と息の長い動機が使われ、
感情に溺れない深々とした音楽になっている。
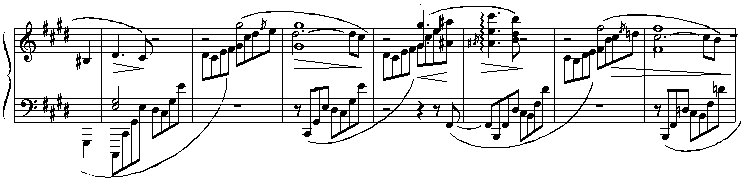
トニック、ドミナント、サブドミナント間の推移をほとんど使わない和声感が、
オルガンのような和声と相俟って、
時代を50年ほど先取りしたリリシズムを感じさせる。
作品28の前奏曲集とはまた違い、
単独の前奏曲としての重厚さを湛えた曲である。
- [195] ポロネーズ第5番 嬰ヘ短調 作品44
作曲年の1841年出版。シャルル・ド・ボーヴォ公爵夫人に献呈。
力感溢れる大規模なポロネーズ。
底からわき上がる疑問のようなショパン独特の始まり方はポロネーズ第2番やスケルツォ第2、3番を思わせる。
疑問が頂点に達するとすぐ決然的な主題が始まる。
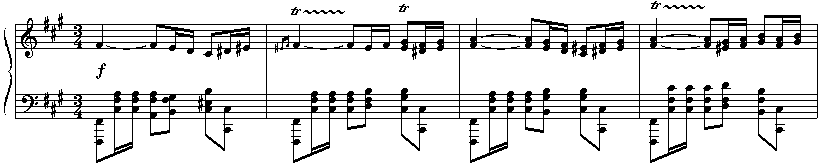
このポロネーズが大曲であることを予感させるような堂々たるテーマである。
短調であることもあり悲愴感も漂う主部だが、
この主題提示部は胸のすくような納得の行く構成なので、
それを楽しんだ後は心残りなく次の展開を期待することができる。
その新しい展開は第?小節から始まるが、
このイ長調のパッセージは特徴的である。
旋律がなく、ペダルを使わず乾いたリズムだけが刻まれるが、
各小節冒頭にしつこくAの音を刻み和声だけ変化して行く。
和声変化も感情に溺れるのでなく醒めたところがあり、
途中不意に現れる主部の経過句の叙事的な効果を演出している。
さらに進むと、
曲は何とマズルカになってしまう。
考えてみるとショパンお国自慢のポロネーズとマズルカをドッキングした大曲があってもおかしくないわけであるが、
そういう曲はこれしかない。
そして再現部では序奏も含め主部が大体忠実に再現される。
大曲には華々しいコーダがつきものだが、それとは逆に、
最後に付けられた短いコーダはドラマの後の回想のような諦観に満ちた素晴らしい中低音旋律による終結となっている。
- [196] マズルカ第43番(ヘンレ版第52番)イ短調(遺作)
1841年または1842年出版。
マインツのショット社刊行の「ノートル・タン」すなわち「現代作品名選集」の第2号に収められていたので現代でも「ノートル・タン」と呼ばれることがある。
献呈はなし。
ワルツ3番路線。
「ベース音付き和音伴奏+旋律」のパタ−ンでなく各声部が旋律になっている弦楽四重奏のような響きが心地よい。
寂しさが前面に出た目立たない曲だが、
心の琴線に触れる音楽である。
冒頭の増三和音を含む旋律も良いが、
中間部はワルツ3番路線にたがわずイ長調となり、
リズム的にはマズルで多少明るさを増すのだが、
明るくなりきらず感傷的でもある。
この曲で好きなのは次の譜例のところで、
ここはどうしてもギターかチェロの音色で聞こえてくる。
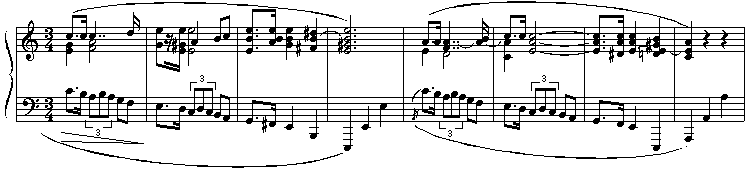
- [197] ワルツ第12番 ヘ短調 作品70-2
作品70-1、
70-3とともに1855年フォンタナ出版。
献呈はなし。
ショパンのヘ短調は哲学的悲愴感に満ちたものか冷静さを失った狂気を表すような曲が多いのであるが、
この曲はそのどちらでもなく、
成熟した旋律が淡々と歌われる。
その意味で絶筆となったマズルカヘ短調の先取りのようでもある。
ABABの形式。
ショパンのほとんどの曲がそうであるが、
どの小節をとってもよく考えられた無理のない音符運びである。
声で歌うとしたらオクターブの跳躍がそこかしこに見られる難しい旋律なのに、
全く自然で美しいヴォカリーズだ。中間部はワルツ3番路線にたがわずイ長調となり、
リズム的にはマズルで多少明るさを増すのだが、
明るくなりきらず感傷的でもある。
- [198] タランテラ 変イ長調 作品43
作曲年の1841年出版。献呈はなし。
ショパンは「『スイスの少年』による変奏曲(ドイツ/スイス)」「エコセーズ(イングランド/スコットランド)」「ボレロ(スペイン)」などエキゾチックな音楽を書く試みをいくつかしているが、
これはそのイタリア編である。
この種の試みでは一番成功しているが、それでも傑作の部類に入れるかと言えばそうでもない。
ショパン自身もあまり高く評価していなかったらしい。
使われている音域が狭いこともあって少し地味で単調ではある。
しかし同様に音域の狭いピアノソナタ第2番第4楽章の才気を思い出せば、
音域だけの問題でもなさそうである。
即興曲第1番が同じ調とリズムであるが、
即興曲の方が広範な音域を駆けめぐり中間部の対比もよいので、
聞き映えがする。
- [199] 演奏会用アレグロ イ長調 作品46
1830年作曲という説もある。
出版は1841年。
フリーデリケ・ミューラー嬢に献呈。
作品1路線はとうに卒業したはずのこの時期、
なぜまたこのような曲を書いたのか?
これを考えるために少しショパンの心境に関する想像を書いてみたい。
この年から2〜3年前の1838年、
リストは「パガニーニ大練習曲」と超絶技巧練習曲の前身である「12の練習曲集」を出版した。
これは現在残っている「パガニーニ大練習曲」と「超絶技巧練習曲」最終版よりさらに"超"超絶技巧で、
30才になり肉体的全盛期を誇る当時のリストの力を余すところなく示している。
これにはショパンも大いに刺激を受けた。
そして20才の頃ピアノ協奏曲第1、2番などの華麗な作品で果たした自分の華々しいデビューを思い出し、
ここはひとつ20才のころから構想していたピアノ協奏曲第3番イ長調を完成して巻き返しを図ることにした。
こうして第1楽章を書き始めてはみたものの、
「やっぱりそういうのはもういいや」と思うようになって、
その目論みは放棄することになった。
しかしせっかく途中まで作ったので、
とりあえずピアノ独奏曲にまとめることとした。
そうして生まれたのがこの曲である
・・・かどうかはわからない。
しかしこうでも考えないと、
なぜこの曲がこの時期に生まれたのか理解に苦しむのである。
まるでピアノ協奏曲の第1楽章を管弦楽パートもろともピアノ独奏用に編曲したかのような曲である。
以下、そのような曲として解説を試みよう(その方が曲想を適切に把握できるであろう)。
管弦楽による静かな序奏が威厳を持って始まる。
続いてロマンスのような主題が第41小節から始まり、
ひととおり主題提示されたのち、
ドミナントの持続音で独奏ピアノの登場を待つ(第87小節)。
そして独奏ピアノが登場し副次的主題を美しく奏でる。
管弦楽の静かな和声に乗り独奏ピアノの技巧的なパッセージが続き、
第125小節から第1主題がホ長調で現れる。
第2主題に相当するものはなく技巧の限りを尽くした展開部のような長い経過句を経て独奏ピアノが一旦締めくくると、
第183小節からは管弦楽のtuttiで楽想が展開される。
それが静まると第201小節からは第1主題がイ短調に変形されてピアノ独奏で奏される。
次第に盛り上がってピアノの技巧的パッセージが目も眩むばかりに続く。
まだ再現部ではないので、
このままでは膨大な規模の第1楽章が予感されてしまうのだが、
実は再現部は全く現れずそのまま終結へ向けての技巧的経過句に繋がり、
独奏ピアノがイ長調主和音で締めくくると同時に第269小節から管弦楽のtuttiによる終結となる。
最後はそれまでの伝統的ピアノ協奏曲と異なり、
最後8小節はピアノも参加してリストのような華々しさでもって曲を終わる。
この曲はショパンの曲ではピアノ技巧的に最難曲の部類と言われている。
深い感動をもたらすことはないかも知れないが、
聴き応えはあり楽しめる。
- [200] 幻想曲 ヘ短調 作品49
作曲年の1841年出版。
カトリーヌ・ド・スーゾ王女に献呈。
これはまた「演奏会用アレグロ」を完成した年に書いたとは思えない、
内容の深い大傑作である。
そう、
ショパンはこういう曲で音楽の方向性を世に問うべきなのである。
四楽章制ソナタの全要素を一曲に含むような一楽章制のソナタともいうべき作品だ。
もちろんその走りはバラードであるが、
バラードは物語性が前面に出ていすぎる。
物語性を排しもっと純粋音楽的なものは考えられないだろうか・・・それがこのファンタジーだ。
この方向をより拡大したのがリストのソナタロ短調と考えられないだろうか?
さらにそれを継承するのが1楽章制のスクリャービンのソナタ第5〜10番であり、
ピアノ以外ではその後リストが発明し現代でも作られ続けている交響詩である、
と考えてもいいのではないだろうか。
筆者が昔通っていたピアノ教室では、
生徒達はこの曲を「雪の降る街を」と呼んでいた。
その理由は冒頭のテーマ(の応答句)から明らかだろう:
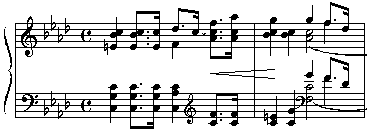
葬送行進曲風の導入を終わると三連符によるカデンツァ風のエピソードが深く静かなヘ短調で始まる。
この三連符エピソードはあとあとまで曲の主要部品を繋ぐ展開機構として頻繁に使われる。
その最初の提示が盛り上がって音域いっぱいの下降スケールで収拾されると、
主題提示部らしき部分が始まる。
「らしき」というのは、
これが通常のソナタの第1主題のような宣言的テーマではなく、
疑問の感情を持つドミナントを基調とし主調(ヘ短調)からすぐハ短調になったりまた変イ長調の明るく素晴らしいパッセージになったりと様相が移りゆき、
性格が定まらないからである。
しかし再現部で(移調されることを除き)ほぼ忠実に再現されているので、
主題としての重要な役割を持っている。
どれが第1主題でどれが第2主題かは古典的ソナタのようには判然とせず、
全く自由で自然に、
しかしまた練りに練られた構成で曲想が移り行き、
感嘆せずにはいられない。
まさに「幻想曲」の面目躍如である。
最後のレシタティーヴォとその後に来る麗しい分散和音のコーダは実にこの曲を締めくくるに相応しい。
長い曲であるにもかかわらず一瞬たりとも聞き手を飽かさず、
堂々とした全体構成と「幻想曲」的即興の要素を矛盾なく併せ持つ素晴らしい曲である。
なおこの曲にも音域の問題がある。それに関しては
「音域の話:ショパンの場合」を参照されたい。
- [201] 歌曲「美しき若者」ニ長調 作品74-8(遺作)
ザレスキ詩。1859年フォンタナ出版。
「どこをとっても好き」と、恋人を思う乙女の歌。
屈託なく明るいポップス歌謡のような歌で、
ショパンはマズルカのリズムで作曲した。
次は1842年(32才) ♪
前は1840年(30才) ♪
目次 ♪
音楽の間に戻る ♪
詠里庵ホームに戻る