[112] 練習曲変イ長調作品25-1のところでショパンの作曲時期を
(1) 作品1路線のワルシャワ習作時代、
(2) 若々しい絢爛な作品を発表して行ったワルシャワ出発直前からパリ時代の初期、
(3) 代表作・主要作品を次々と発表したジョルジュ・サンドとの蜜月時代、
それに (4) 円熟した晩年の1842年以降と分類したが、
それに従うとこの年から最後の(4)の段階に入る。
- [202] 即興曲第3番 変ト長調 作品51
1843年出版。
ジェーヌ・バッチアーニ・エステルハージ伯爵夫人(ショパンの弟子)に献呈。
熟成した赤ワインのような一曲。
即興曲第2番と同様、
表面的には地味だが複雑なコクに満ちていて、
後味もよい。
ショパン自身愛奏したというのもよくわかる。
変ト長調なので、
聴いている分には嬰ヘ長調の即興曲第2番と同じ調である。
この曲の右手の連続する速い3連符には3度、6度など重音が頻繁に出て来るので、
技巧的には簡単でない。
しかし難しさを感じさせるような派手な演奏は全く似合わない。
落ち着いた味わいに酔いしれたい曲である。
- [203] マズルカ第30番 ト長調 作品50-1
作品50の三つのマズルカは作曲年の1842年に出版され、
レオン・スミトコヴスキ氏に献呈された。
マズルカ第5番、
ワルツ第1番などと同様ドミナントから始まる元気のいい曲。
休みなく次々とエピソードが変わって行く舞踏的マズルカである。
ヴィヴァーチェということもあり一小節ごとに指揮棒を振るようにせわしなく弾かれることが多いが、
筆者としてはマズルカ第5番のように一拍ごとにしっかりリズムを刻む演奏の方が舞踏的で好みである。
- [204] マズルカ第31番 変イ長調 作品50-2
出版と献呈は前曲参照。
小船に揺られるような8小節の導入のあと始まる主題は4小節の単位で発展する息の長いもの。
この優雅な主題はどことなくシューベルトのイ長調ソナタのようなうららかな感じがする。
クヤヴィヤクに始まるが中間部はマズル的。
この中間部は弦楽四重奏のようで、
シューマン「子供の情景」の第2曲のような雰囲気である。
- [205] マズルカ第32番 嬰ハ短調 作品50-3
出版と献呈は前々曲参照。
これは大変興味深い造りに仕上がっているマズルカである。
冒頭カノン的クヤヴィヤクに始まるが、
よくカノンにできたと思わせるほど複雑な和声を内在する旋律である。
そのあとすぐオベレク風のせわしない動きとなるが、
ここはスケルツォ第2番のイ長調トリオに現れる嬰ハ短調レシタティーヴォを思い出させる。
上段(譜例1)はこのマズルカ、
下段(譜例2)はスケルツォ第2番:
譜例1
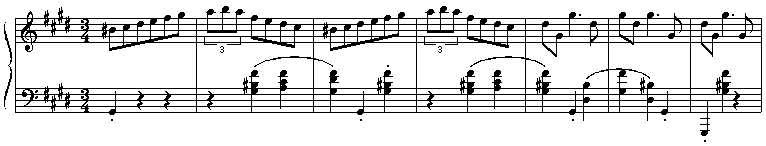
譜例2
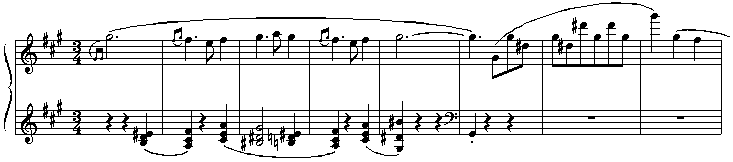
そのあと続く力強いイ長調の経過句も、
嬰ハ短調に戻るよう設計された対位法的嬰ト長調経過句も、
大変効果的で納得させられる。
そんな風に説得力のある音楽が5ページほど進むと、いよいよコーダに向けて対位法の極致が展開され、
第173小節目で慟哭するようなクライマックスを迎える。
この4小節はそれだけ取り出すと何ということはない単純で音域も1オクターブそこそこの音型なのだが、
高度に発展させられた対位法的盛り上がりの頂点で対位法を突然打ち切って現れるため、
非常に効果的である。
続くコーダは中低音に諦観を感じさせる旋律を歌わせる8小節である。
そしてさらに最後の4小節、
嬰ハ音と嬰ト音の二音のみが不規則に交代する終結。
ショパンの天才性と用意周到さが十分発揮された傑作マズルカである。