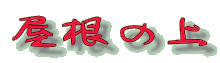
|
![]()
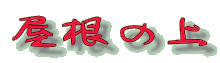
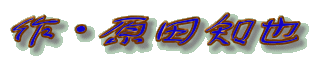
|
「私の背中には、十字架の印が刻まれている。 |
 |
「何だ、猫か。」 と、少女は言った。 少女は、小学6年生。屋根に登ったときに付いたらしく、長袖のシャツが黒く汚れていた。 「おまえも日向ぼっこかい?」 少女は汚れた袖をかくすようにたくし上げながら言った。 「ここはいいな。空に近いし、海だって見える。」 「ニャー。」 「お前、話し相手になってくれるのか?――たってどうせ答えは ニャーだけか。」 少女は、ひとつため息をついた。 「まあ、無視されるよりましかもね。学校じゃ誰もニャーとも言ってもらえないからな。・・・そりゃあ、あたしも悪いよ。運動ぐつで頭をぶったたいたり、け飛ばしたりもしちゃうからさ。」 「ニャー。(こいつは不良娘か?)」 少女は猫の背中を見て、急に笑い出した。 「何だぁ、お前の背中。ばってんの模様が付いてるじゃないか。おまえペケ猫か。」 「ニャー。(セイントキャットと呼びなさい)」 少女は猫のとなりに座り込んで、背中をなでた。 「ペケがついてるのは、あたしもおんなじ。でもさ、腹が立つんだよな。たとえば健介の父ちゃん。健介そっくりで、ひょろひょろっとしてて、青白くってさ。あれでも男かってんだ。 あたしの父ちゃんは色が黒くってさ。海の男だもんな、頑丈に出来てんだ。男だったら、あたしの父ちゃんみたいでなきゃね。」 「ニャー。(そんなんで腹立ててんのか?)」 「たけしんちの父ちゃんは、いつも同じ時間に、ほんとに一分も違わずに家に帰ってきやがる。 きっとたけしの母ちゃんが怖くって、頭あがんないんだぜ。情けないよな。」 「ニャー。」 「そうだ、お前にいいものやるよ。」 少女はランドセルの中から、チィッシュに包んだ魚のフライを出して、ペケ猫の前に置いた。 |
 |
「給食の残りだけどな。あたしは魚は食べないんだ。どうせこんなのまずいんだぜ。 あたしは 父ちゃんが捕ってきた新鮮な魚しか食べないんだ。あれはおいしいんだ、父ちゃんが捕ってきてくれた魚って・・・」 少女は下の道を通る洋一の父親を見つけて指をさした。 「見てよ、洋一の父親だ。ごますりおやじって有名なんだ。今度の町長選に立候補するんだって、笑わせるよな。笑顔でペコペコするだけで町長が勤まるかってんだ。」 ペケ猫は、魚のフライにむしゃぶりついていた。 「わかるだろ。あたしがあいつらの頭をくつでぶったたきたくなる気持ちが・・・。」 「ニャー。(分かるわけがない)」 「町長なんかになるより、船長の方がずっといいよな。うちの父ちゃんは船長だぞ。一番えらいんだ。どうだすごいだろう。」 「ニャー。(船長ったって二、三人乗りの漁船なんじゃないのか?)」 「あっ、一郎の弟のゆう太だ。あいつ三年にもなって父親に肩車なんかしてもらってやがる。――ふん、あたしの父ちゃんは、あいつの父ちゃんよりずっと背が高くって力持ちさ。 あたしが五年生のとき、軽々と肩車してくれたよ。父ちゃんが肩車するとあの海のずうっと向こうまで見ることが出来るんだぞ。」 「ニャー。(五年にもなって肩車か)」 ペケ猫は、最後の一切れをほおばった。 「そんなにその魚うまいか? あたしは魚は食べないことにしたんだ。 だって・・・そいつら、あたしの父ちゃんを食っちまったかもしれないんだ。」 「ニャー。」 「父ちゃんは。あの海の向こうの方に行ったきり帰ってこないんだ・・・今はあの雲の上かもね。」 少女は屋根の上で立ち上がり、背伸びして遠くの海と空を見つめた。 「だから、もう魚は食わない。」 雨が少女の顔にポツリポツリと落ちた。 「雨だ、もう帰らなくっちゃ。またこんど給食に魚が出たら持ってきてやるよ。」 少女は雨にぬれた顔を、たくし上げたそでで拭きながら、屋根から降りていった。 「屋根にひとりで登ってくるやつは、やっぱり猫族だ。」 そう言って、ペケ猫は少女と同じしぐさで、雨にぬれた顔を前足で拭った。 |
おわり |