|
中島飛行機製作所は更に陣容を拡大し、1931年(昭和6年)合資会社から中島飛行機株式会社に改組し、資本金600万円となった。そして1934年発祥の地の呑龍工場から、群馬県太田市の中心に新しい大規模工場を完成させ、本社を置いた。工場敷地は45,000坪(15万平方メートル)あり正面に近代的な3階建ての本館を設けた。(現在も富士重工業群馬製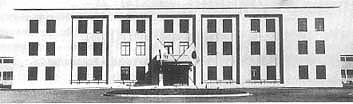 作所でそのまま使用されている。上空からこの建物を見ると飛行機の形をしているという:右の写真)この本館の3階に設計開発部門があった。 作所でそのまま使用されている。上空からこの建物を見ると飛行機の形をしているという:右の写真)この本館の3階に設計開発部門があった。
東側の入り口からはいると、左側が海軍機設計グループで三竹、明川、福田、井上、山本、松村、中村の各幹部技師が中央に陣取り、自分のアイディアを左右の作図設計者に指示を与えつつ仕事を進めた。さらに奥に入り中程をすぎると陸軍機の部隊で、小山、森、西村、松田、太田、青木、一丸、内田、百々(とど)の各幹部技師が居た。幹部技師とはいえ皆学校を卒業して間もない25〜35歳位の若者である。この頃は、試作機種毎にグループを結成するプロジェクトチーム方式で、各人が構造から電装、兵装など総てをこなしていた。ただ空力と重量は専門グループがあり、空力には戦後ロケットの研究で名を馳せた糸川英夫がいた。
この時代は若い技術者を中心として自由闊達な気風が溢れた最良の時ではあった。各技師はそうそうたる剛の者が揃っており、特に海軍機グループは東大航空出身の俊才で血の気が多く、個性あふれる豪傑ぞろいと言われた。之に対し陸軍機グループは小山悌、栗原甚吾を始め東北大出身が多く冷静沈着、質実剛健な気質であったが、悪く言うと地味で真面目な技術屋集団であったという。(糸川英夫氏は戦後の講演で「組織の三菱-パーソナリティの中島」と言われている)
これら技師たちは小山悌を技師長として連絡会を持ち横の技術交流を図るとともに、技師会を結成していた。この技師会は時には会社の役員会より権限が強く、役員会の決定さえひっくり返したこともあった。そんな事から回りからは何かと頼りにされた存在であったという。ただ陸軍と海軍の対抗意識があり、両設計グループは休み時間には紙と色鉛筆の囲碁に興じたりしたが、仕事の中身の話は敢えて避けていた。また、これらの技師を支える設計者たちは、関東、東北の高等学校や専門学校の出身者達であったが、皆、各学校での首席成績者ばかりで、大変優秀な人たちが集まっていた。
1938年航空機増産の政府方針に応え、太田製作所の大拡張と陸軍発動機専門工場の武蔵野製作所を建設した。ところが海軍は之に刺激され、海軍工場の独立拡充命令を 発し、発動機は多摩製作所、機体は1940年小泉製作所(現群馬県大泉町:左の写真)を建設した。小泉製作所は敷地132万平方メートルの東洋一の大工場で、中島のエンジン「栄」を搭載した「零戦」(三菱設計)を主として、その他に「月光」「銀河」「天山」「彩雲」等、約9千機の量産をした。従業員は最終的には何と6万人もの人々が働いていた。1機完成すると、工場の大扉(幅30m、高さ15m以上もある)が開かれ、その度に君が代と社歌が演奏され従業員みんなで見送る儀式が恒例であった。(後にスパイに生産能力が知れるといって軍から中止させられた) 設計部門も太田製作所の本館3階から出て、陸軍機グループは隣接する所に新たに建設した3階建ての設計新館に移り、また海軍機グループは小泉製作所に移ったのである。移動してからの開発体制は、従来の1機種1グループ方式から、専門グループ方式に変更され、空力班、重量班、構造班、動力班、降着装置班、操縦装置班、電装班、兵装班など、共通機能別体制となった。また標準化を進めるために統制班が設けられ、効率的な開発を目指した。中島からは何度も、陸軍機と海軍機の部品の共通標準化を提案したが、両方のエゴが出て歩み寄ることなく非効率な体制に泣かざるを得なかった。 (別頁:中島機体工場の変遷) 発し、発動機は多摩製作所、機体は1940年小泉製作所(現群馬県大泉町:左の写真)を建設した。小泉製作所は敷地132万平方メートルの東洋一の大工場で、中島のエンジン「栄」を搭載した「零戦」(三菱設計)を主として、その他に「月光」「銀河」「天山」「彩雲」等、約9千機の量産をした。従業員は最終的には何と6万人もの人々が働いていた。1機完成すると、工場の大扉(幅30m、高さ15m以上もある)が開かれ、その度に君が代と社歌が演奏され従業員みんなで見送る儀式が恒例であった。(後にスパイに生産能力が知れるといって軍から中止させられた) 設計部門も太田製作所の本館3階から出て、陸軍機グループは隣接する所に新たに建設した3階建ての設計新館に移り、また海軍機グループは小泉製作所に移ったのである。移動してからの開発体制は、従来の1機種1グループ方式から、専門グループ方式に変更され、空力班、重量班、構造班、動力班、降着装置班、操縦装置班、電装班、兵装班など、共通機能別体制となった。また標準化を進めるために統制班が設けられ、効率的な開発を目指した。中島からは何度も、陸軍機と海軍機の部品の共通標準化を提案したが、両方のエゴが出て歩み寄ることなく非効率な体制に泣かざるを得なかった。 (別頁:中島機体工場の変遷)
軍から新しい飛行機の試作要求が来ると、空力班が基本的な構想をたて、重量班が、目標値を定め、外観3面図が提示される。これが以下の各班に流れてくる。当然構造班は、「重量班の定めた重量では出来るわけがない」と議論が始まり、「出来るの、出来ないの」のすったもんだのあげく、何とか目標に入れてしまうのであった。当時の各種技術計算は、勿論コンピュータなど無く、計算尺一本であった。普通の物より相当長い5〜60cmのもので、「軍人は腰に刀を差すが、我々は計算尺だ!」という誇りがあった。どこへ行くにも胸ポケットには小さな計算尺を持っていた。一般計算は製作誤差を勘案すると丁度良かった。ただどうしてもと言うときは、朝から晩までタイガー計算機(手回しの機械式計算機。足し算と引き算を繰り返すことで積算と除算をする)を回し続けた。(青木技師談)
- 陸軍の制式化の評価試験は大体が立川飛行場で行われた。設計者たちは試験飛行を終えたパイロットがまず上官の前で敬礼をしつつ、結果を大声で報告する。之を脇で耳をそばだて、即座に対策案を立て、太田に電話をいれて必要な人員に待機するように指令を出し、クルマを飛ばして、熊谷から利根川をわたり太田に帰る。そして徹夜で改修部品を製作し、翌朝には自動車の屋根に水平尾翼をくくりつけ、とって返して翌日の試験に間に合わせたこともしばしばであった。しかし自分の作った飛行機が競合機に格闘戦試験や性能試験で「勝った、負けた」は実に楽しくやりがいのある仕事で燃えに燃えたという。ただ試験飛行には、特に初飛行には担当技師は絶対に搭乗してはならない決まりであったが、寒冷地試験で満州や、高温試験で南方へと飛び回っているなかでは一緒に搭乗して確認試験を行ったという。

- 太田製作所全景(中央が本館、その列の右端が設計新館。左端は強度実験室。)
中島飛行機は軍用機で名声をあげたものの、民間機は生産機数も微々たるものであり、そういった意味ではバランスに欠いていた。その中で特筆できるのはAT-2旅客輸送機である。基本は米国DC-2を参考にしてはいるが、極めて斬新な構造を採用しており、設計主務者である明川清技師の名を取ってAT(Akegawa
Transport)と称された。1号機は1936年尾島飛行場で初飛行に成功し、その後の改修は西村節朗技師に引き継がれ、操縦性、安定性に極めて優れた中型旅客機となった。戦前の日航の新鋭機として「浅間、鹿島、箱崎、熊野、出雲」等の景勝地の名がつけられた。また陸軍の制式輸送機としても採用された。


中島AT-2旅客輸送機
全幅:19.916m、全長:15.30m、
- 全備重量:5,250Kg
発動機:中島「寿」二型、最大速度:360Km/h
航続距離:1200Km、乗員3名、乗客8名
1935年の陸海軍の競作にたいし、中島戦闘機史の頂点に立つとも言える九七式戦闘機が採用された。当時、中島の中でも単葉にするか、複葉にするか会社を二分する論争が巻き起こっていた。海外でも同様であり、格闘性を重んじると必然的に複葉が常識であった。その中で主務者である小山悌技師は太田稔技師、糸川英夫技師らの若い新進技術者の協力により、初の全金属製片持式低翼単葉の軽戦闘機で革新的な機体構造や新しい翼理論による断面形状、前縁を直線としたユニークな桁構造を採用してキ-27を完成させた。そして三菱、川崎の機体に競り勝ち97戦として中島3番目の本格的制式機となったのである。
97戦は軽量化による運動性の良さだけではなく、整備性に優れており高い稼働率を誇りノモハン事件や初期の太平洋戦争で多くの戦果を挙げた。また主翼を1枚構造とし、後部胴体と別々に製作して組み立てる方式を採用して生産性も一段と優れていた。前線では次々と補給の機体が到着し、逆に操縦士が居なかったという逸話もあった。この97戦に採用された独特の翼理論は後の中島戦闘機の全てに引き継がれていった。
 九七式戦闘機 九七式戦闘機
この九七式戦闘機は1936年から42年まで中島で2,007機、立川飛行機や満州飛行機で1,379機、合計3,386機が生産された。
|
 九七式戦闘機
九七式戦闘機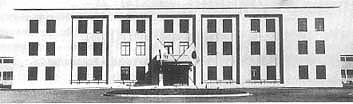 作所でそのまま使用されている。上空からこの建物を見ると飛行機の形をしているという:右の写真)この本館の3階に設計開発部門があった。
作所でそのまま使用されている。上空からこの建物を見ると飛行機の形をしているという:右の写真)この本館の3階に設計開発部門があった。 発し、発動機は多摩製作所、機体は1940年小泉製作所(現群馬県大泉町:左の写真)を建設した。小泉製作所は敷地132万平方メートルの東洋一の大工場で、中島のエンジン「栄」を搭載した「零戦」(三菱設計)を主として、その他に「月光」「銀河」「天山」「彩雲」等、約9千機の量産をした。従業員は最終的には何と6万人もの人々が働いていた。1機完成すると、工場の大扉(幅30m、高さ15m以上もある)が開かれ、その度に君が代と社歌が演奏され従業員みんなで見送る儀式が恒例であった。(後にスパイに生産能力が知れるといって軍から中止させられた) 設計部門も太田製作所の本館3階から出て、陸軍機グループは隣接する所に新たに建設した3階建ての設計新館に移り、また海軍機グループは小泉製作所に移ったのである。移動してからの開発体制は、従来の1機種1グループ方式から、専門グループ方式に変更され、空力班、重量班、構造班、動力班、降着装置班、操縦装置班、電装班、兵装班など、共通機能別体制となった。また標準化を進めるために統制班が設けられ、効率的な開発を目指した。中島からは何度も、陸軍機と海軍機の部品の共通標準化を提案したが、両方のエゴが出て歩み寄ることなく非効率な体制に泣かざるを得なかった。
発し、発動機は多摩製作所、機体は1940年小泉製作所(現群馬県大泉町:左の写真)を建設した。小泉製作所は敷地132万平方メートルの東洋一の大工場で、中島のエンジン「栄」を搭載した「零戦」(三菱設計)を主として、その他に「月光」「銀河」「天山」「彩雲」等、約9千機の量産をした。従業員は最終的には何と6万人もの人々が働いていた。1機完成すると、工場の大扉(幅30m、高さ15m以上もある)が開かれ、その度に君が代と社歌が演奏され従業員みんなで見送る儀式が恒例であった。(後にスパイに生産能力が知れるといって軍から中止させられた) 設計部門も太田製作所の本館3階から出て、陸軍機グループは隣接する所に新たに建設した3階建ての設計新館に移り、また海軍機グループは小泉製作所に移ったのである。移動してからの開発体制は、従来の1機種1グループ方式から、専門グループ方式に変更され、空力班、重量班、構造班、動力班、降着装置班、操縦装置班、電装班、兵装班など、共通機能別体制となった。また標準化を進めるために統制班が設けられ、効率的な開発を目指した。中島からは何度も、陸軍機と海軍機の部品の共通標準化を提案したが、両方のエゴが出て歩み寄ることなく非効率な体制に泣かざるを得なかった。 

