民衆を活気付ける踊りとして、藩政時代も踊り継がれてきたが、明治時代に藍商人が財政的援助を行ったために一層隆盛になった。大正期になると、踊り子の衣装は普段着の浴衣から、揃いの衣装へと次第に洗練された。一時、戦争のため中断した時期もあったが昭和21年に復活。その5年後からは演舞場も設けられ、今日に到っている。
・・・以上は高知新聞社の「四国まるごと自慢」と言う本から抜粋させていただきました。
今日では東京杉並の高円寺阿波おどり、埼玉では越谷阿波おどり、など日本各地にも広がっていますね。
わたしが初めて阿波おどりのことを意識したのは、作家・田辺聖子さんの、連を作って踊りに参加するお話を読んだことで、よその地域の人も巻き込むその魅力を書いておられたからですが、未だにテレビでしか見たことはありません。
左 2000.7.31発行 ふるさと切手徳島版「阿波踊り(女踊り)
右 ふみカード「阿波踊り(男踊り・女踊り)」
昭和40年から1枚も欠けることなく、説明書のついたフォルダーに収められた絵はがきは、どの絵もとても味があり、ぜひ全部を紹介させていただきたいと思いました。
また、当初10万枚もの発行があったものが、今年はついに2千枚と、数が落ち込んでいることも気にかかります。なんとしても、この灯を消さずに続けて発行されるように祈ります。
平成26年、ついに第50回で幕を閉じることになったそうです。
これまで楽しませていただいてほんとうにありがとうございました。
左 1989.4.18発行 切手趣味週間 北野恒富画「阿波踊」
下左 1994.8.1発行 ふるさと切手徳島版「阿波踊り」と徳島中央局の風景印(阿波踊り・徳島城鷲の門・眉山・サクラ)
下右 2008.8.1発行 ふるさと切手 ふるさとの祭 第1集(10連刷のうち2枚) 徳島県「阿波踊り」
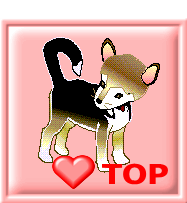 ページのトップへ
ページのトップへ トップページへ戻ります。
トップページへ戻ります。