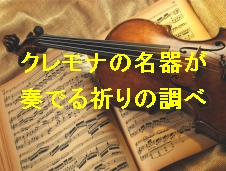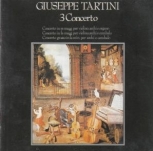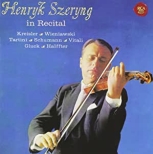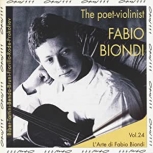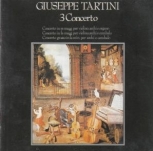
トリオレコード
PAC-2023
(1963年頃の録音) |
タルティーニは、この曲を作曲した頃、まさに油の乗り切っていた時期ですが、この第2楽章は、とくにヴァイオリンの音色の美しさを堪能させる名旋律です。
イタリアの名手フランコ・グッリが奏でるクレモナの名器、ストラディバリウスの美音でお聴きください。
↑(上の曲名をクリックすると曲目のページが開いて、自動的に演奏再生されます)
|
今年は、タルティーニの名曲をクレモナの名器で演奏するリサイタルが、日本でもいくつか予定されました。6月には、兵庫県芸術文化センターでも、実力派の米元響子さんが、タルティニの《悪魔のトリル》などを、1727年製のストラディバリウス(サントリー芸術財団より貸与)を駆使して演奏する予定でしたが、コロナ渦により、こちらは中止になってしまいました。
ぜひ鑑賞したい人気曲ですので、ここでは、ヘンリク・シェリングのグァルネリ・デル・ジェスによる名演をアップします。
|
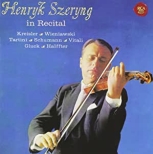
、 RCA BVCC-37334
(1959年1月録音) |
タルティニがまだ20歳の頃、夢の中に悪魔が現れてヴァイオリンを弾き、その美しさに目が覚めて、すぐに譜面に書き取ったという有名な伝説がある曲です。
この難曲を名手シェリングが、1743年製ガルネリ(「ル・デューク」の愛称)で演奏します。
楽器の魅力について、「ストラディヴァリは美しいがまだ若い女性の魅力、グァルネリは成熟した女性の艶やかさ」といった演奏家がいます。(ヤッシャ・ハイフェッツの言葉)
|
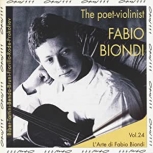
OPUS111 MOPS30-95
(1993年12月録音) |
最後に、タルティーニ晩年の作品を古楽器で鑑賞します。モダン楽器とは一味違います。
ストラディバリ、グァルネリ等の歴史的名器のほとんどは、現代の演奏用に改造されています。一方、製作された時代の姿で、改造なしの楽器を古楽器(ピリオド楽器)と呼びます。
ここでは、作品の時代に合わせた楽器にこだわるファビオ・ビオンディが、1740年製のイタリアの古楽器、ガリアーニのコピー楽器を、当時のガット弦とバロック弓を使用して演奏します。いずれにしろ、「作曲当時の本当の響きで聴く」というのは、じつに面白いことです。
|
*タルティーニの作曲年代には諸説ありますが、ここではジャケット記載どおりとしました。(選曲&文責:中野
哲男) |

|