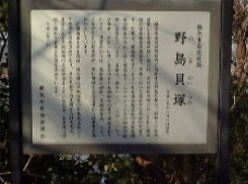| |
日 本 で は |
|
|
|||||||||||||||||
|
縄文時代はまだ農業による食糧生産がなかったので食糧としてよく貝をとったことと、この時代が1万年ものあいだ中断することなく続いたことから、縄文時代の貝塚は全国各地に多く発見されています。 貝塚は人々のゴミ捨て場だったのですが、貝がらや動物の骨、石器や土器のかけらなどが出てくるので、当時の人々の生活を知る貴重な手がかりとなっています。 日本考古学発祥の地と言われる大森貝塚は1877(明治10)年アメリカから東京大学へ招かれたエドワード・モースが舟で横浜に上陸し、新橋へ向かう途中発見、発掘調査したもので、貝塚が学問的に調査された初めてのものとされています。 千葉市にある加曽利貝塚は東西200m、南北400mという広大な遺跡の中に南北2つの貝塚が並びその規模は日本最大と言われています。 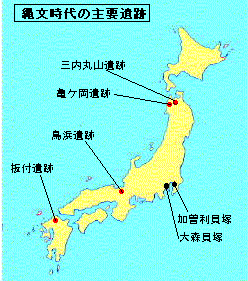 |
かねさはでも多くの貝塚が発見されており周辺では日本でも最古級の夏山貝塚などが発掘されています。 野島貝塚・・・太平洋戦争終了後間もなく山頂と北側斜面2ケ所に発見された貝塚は東西15m南北10m、貝層の厚さは2~3mほどでマガキ、アサリ、カリガネエガイなどの貝類がみられました。 同時に「野島式土器」や石器、クジラ製の骨斧なども出土されました。 青ケ台貝塚・・・1942年と67年の調査で住居跡や縄文人の人骨とともに多くの土器、石器、骨角器が発見されました。これらを覆っていた厚い貝層からはサザエ、アワビの貝殻やタイ、ボラなどの魚類、シカやイノシシのどの獣類の骨も見つかり当時の人々の海山の幸に恵まれた食生活をつたえています。 |
縄文時代 (BC10000頃~ BC400頃) BC
10000
|
|||||||||||||||||
| 土器の発明 |
土器を作り出したことは縄文文化の大きな特色です。 縄目の文様があると言う意味でこの時代の土器は縄文土器と呼ばれますが、放射性炭素による測定法では日本の縄文土器は世界最古に属するものといわれています。 縄文土器は主に食物の煮炊きに使われましたが、はじめのうちはまだ土器を焼く温度が低かったのでもろくて分厚く、色は黒みがかった褐色(こげ茶色)でした。 形ははじめ丸底でやがて底をとがらせたものが多くなり、だんだん平らな底になりました。 縄文中期から晩期には土器の上部に複雑な飾りをつけたり、土瓶や急須のような形のものもできました。 土器の表面には竹のへらや縄やひもを使って模様をつけていますが、当初は表面を平らにする目的だったものが次第に装飾のためにつけられるようになったようです。 縄文土器の変遷
|
野島貝塚からはこの貝塚の名にちなんでつけられた「野島式土器」といわれる砲弾型の尖底土器が出土されています。尖った底は主に炉に突き刺して煮炊きに使われたもので、移動して歩く生活に適したものだったようです。
六浦町の関東学園の敷地から発掘された室ノ木遺跡からは1970(昭和45年)多くの縄文土器が発見されましたが、この中には東関東、東北南部、北陸、中部、近畿地方のものも入っておりこの時代既にこれらの地域と活発な物や人の交流があったことを、うかがわせます。 |
||||||||||||||||||
石器の進歩 |
旧石器時代は単に岩石を打ち砕いただけの打製石器が主な道具でしたが縄文時代には土器の発明とともに、石器についてもよく磨いて鋭い刃を持った磨製石器が発達し、種類も石斧(せきふ、石のおの)、石鏃(せきぞく、石のやじり)、石槍、石匙(動物の皮をはぐ)などがあらわれます。 石器のほかに獣や魚の骨や角を利用した骨角器や釣針、もり、縫針などが出土しており、当時の生活が少しづづ進歩しているあとが見えます。 |
|
||||||||||||||||||
竪穴住居 |
縄文時代にはそれまでの移動生活から定住生活への変化に対応して住まいも洞穴から竪穴住居へと変わります。 竪穴住居の跡は日当たりの良い台地上などをはじめとして、いろいろなところで発見されていますが、方形または円形に地面を50cm~1mに掘りくぼめて住居の床をつくりそこに柱をたて屋根をふいたものです。 住居の中央部付近には火をたく炉もつくり暖房をとったり食物の煮炊きにも使われました。 竪穴住居は海岸と山に近い小高い丘の上に作られ、集団で生活したため数戸から10戸以上の住居跡がまとまって発掘されることがあります。 |
|
||||||||||||||||||
縄文人の生活 |
食生活 縄文時代の人々は食糧を海や山にもとめる狩猟・漁労・採集の生活で農耕などの生産は次の弥生時代の到来まで待たねばなりません。 山では獣をとらえることと、木の実の採集が主なもので、獣はシカやイノシシのほかタヌキ、キツネ、ウサギなどで、木の実はドングリ、シイの実をよくとったようです。 海ではシカの骨で作った釣り針やもりを使って魚をとったり網を使った漁もやっていたようです。 魚の種類はタイ、マグロ、イワシ、ヒラメなどのほかにクジラ、イルカなど多岐に亘っています。 風俗・信仰(関連サイト・日本の原始信仰) [土偶 ] 土偶と呼ばれる土でつくられた人形は縄文時代の代表的な遺物で、早期には顔や体の表現ははっきりしない粗雑なものでしたが、中期以降は目・鼻・口などもはっきりして妊娠した女性をあらわしたものなどがあらわれ、出産や動植物の繁殖などを願ったものとも考えられています。 土偶の殆どはこわれた形ででてきますが,これは土偶が病気やけがの身代わりとされたと考えられます。 [抜歯 ] 縄文時代から弥生時代にかけて健康な歯を抜く「抜歯」の風習がありました。 「抜歯」ははじめ成人の儀式などで抜かれ、その後結婚などを繰り返すうちに何回も抜歯されるようになったようです。 [埋葬] 地面に穴を掘り死者を埋葬する場合に一部には手足を伸ばしたままの伸展葬もありますが、死霊をおそれたためか殆どは手足を折り曲げる屈葬です。穴の上には石が積み上げられたり標石が立てられするものがあり、秋田県の大湯環状列石は共同墓地とも考えられています。 |
|