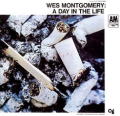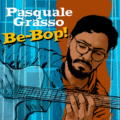ロック・ファンのためのジャズ案内のヘッダー
Rock Listner's Guide To Jazz Music
その他
| The Incredible Jazz Guitar / Wes Montgomery | ||
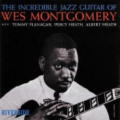 曲:★★★★ 演奏:★★★ ジャズ入門度:★★☆ 評価:★★☆ |
[Recording Date] 1960/1/26, 28 [1] Airgin [2] D-Natural Blues [3] Polka Dots And Monnbeams [4] Four On Six [5] West Coast Blues [6] In Your Own Sweet Way [7] Mr. Walker [8] Gone With The Wind |
Wes Montgomery (g) Tommy Flanagan (p) Percy Heath (b) Albert Heath (ds) |
| ウェス・モンゴメリーと言えば、このアルバムということになっている。ハーモニクスを駆使したテクニカルなギタープレイを堪能するには確かに最適。でも、個人的にはあまり面白くない。第一に、60年とは思えない録音の悪さ。クリアという言葉には縁遠いコモリ気味の音でピアノの音は歪み、テープの回転ムラで音がヨレている。次に、音楽的な観点でも60年という時代の中で特に進んでいるわけでもなく、実にオーソドックスな演奏と曲に終始しているところも物足りない。つまり、グループとしてのサウンドに面白みがない。パット・メセニーも賞賛するウェスのギターを純粋に楽しめるかどうか、それが問われるアルバムのように思える。ギタリスト的視点で見れないとその面白みがわからないのかも。(2011年6月19日) | ||
| Full House / Wes Montgomery | ||
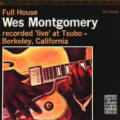 曲:★★★★ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1962/6/25 [1] Full House [2] I've Grown Accustomed To Her Face [3] Blue 'N' Boogie [4] Cariba [5] Come Rain Or Come Shine (take 2) [6] Come Rain Or Come Shine (take 1) [7] S.O.S (take 3) [8] S.O.S (take 2) [9] Born To Be Blue |
Wes Montgomery (g) Johnny Griffin (ts) Wynton Kelly (p) Paul Chambers (b) Jimmy Cobb (ds) |
| ライヴらしい雰囲気に溢れ、活気と適度なリラクゼーションに満ちたこのライヴ・アルバムはウェスの持ち味が良く出た代表作のひとつ。2曲目のソロ演奏(極控えめにベースとブラシがサポート)もいい雰囲気だし、他の曲で聴けるバッキングの柔らかいトーンも爽やかで気分がいい。もちろんアドリブも奔放で得意のオクターブ奏法を惜しげなく披露。グリフィンのテナーも気持ちよくブローしているし、リズム隊は元マイルス・グループの面々でコンビネーションもバッチリ。僕はトーンが明るすぎるケリーのピアノがあまり好きじゃないんだけれど、ここでは全体のムードにとてもよく合っていてケリーのベスト・プレイと言われるのも納得。この軽快で心地よいムードはケリーとジミー・コブのシャキシャキしたシンバルワークに負うところが大きい。「Incredible Jazz Guitar」の方が有名ながら、僕のように本質的にジャズ・ギターに熱心じゃない人にはこのアルバムの方がベターなのかもしれない。(2020年2月24日) | ||
| The Way Up / Pat Metheny Group | ||
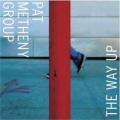 曲:★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★ 評価:★★★★★ |
[Recording Date] 2003/Apr [1] Opening [2] Part One [3] Part Two [4] Part Three |
Cuong Vu (tp, vo) Mat Metheny (g) Gegoire Maret (harmonica) Lyle Mays (p, Key) Steve Rodby (b, cello) Antonio Sanchez (ds) |
| 現代のジャズ・ギタリストとして圧倒的な支持を得ているのがこのパット・メセニー。もともとジャズ・ギターにあまり魅力を感じていないこと、所謂フュージョンも得意ではないこともあって、僕にとってパット・メセニーはあまりピンと来ない、というかむしろ苦手な人だった。この人もさまざまな形態で様々な音楽性を持ったアルバムをリリースしていて、ほとんど真面目に聴いたことがない僕が語るのは少々おこがましいけれど、門外漢の感想として以下レビュー。全体の印象としては耳当たりの良いサウンドでその点では従来の僕の印象と変わらない。それでも演奏のレベルは大変高度で内面から湧き出る熱さも確実にある。曲が長く(順に5分、26分、20分、15分)大作主義を打ち出しており、しかも作り込んであるために、ただの耳当たりの良い音楽に陥ることがなく聴き応え十分。一方で軽いBGMを期待する向きには重すぎる、あるいは難しすぎるかもしれない。でもその練られた音楽に僕は感服してしまった。時にフォー・ビート織り交ぜながら現代ジャズであることもしっかりと主張、いや現代のジャズの究極の形のひとつだと言われたら、「はい、おっしゃるとおりです」とひれ伏してしまう。録音状態、音の重ね方、細かい効果音、残響音の演出、すべてが完璧に作られていて、ギタリストとしてのメセニーというよりは音楽家としてのメセニーの凄さをまざまざと見せつけられる。(2008年9月15日) | ||
| Unity Band / Pat Metheny | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 2012/Feb [1] New Year [2] Roofdogs [3] Come And See [4] This Belongs To You [5] Leaving Town [6] Interval Waltz [7] Signals (Orchestrion Sketch) [8] Then And Now [9] Breakdealer |
Chris Potter (ts, bcl, ss) Pat Metheny (g) Benn Williams (b) Antonio Sanchez (ds) |
| サックスをメンバーに加えるのはかなり久しぶりだというメセニーの(2012年当時の)ニュー・グループによるアルバム。ジャズの持つスリルをオブラートに包んで表現するあたりはメセニーの音楽そのもので、従来のパット・メセニー・グループのファンなら安心して聴けるに違いない。クリス・ポッターは現代のサックス・プレイヤーとして標準以上の技量と表現の幅を持っていて不足はなく、3本のリード楽器を持ち替えてサウンドを多彩にしており、貢献度大。そのサウンドの色彩という点では、アコギ、エレキ・ギターにギターシンセ、更には自分で開発したという正体のよくわからないオーケストリオンという楽器までを駆使([7])し、ギタリストとしての、サウンド・クリエイターとしての技量を惜しみなく披露。録音が素晴らしく、各種ギターの響きや音場感をしっかり捉えているので、是非良いオーディオ環境で聴きたい。柔軟なリズムは現代のジャズでは当たり前のところとはいえ、ウィリアムスとサンチェスのリズム・セクションは柔軟なだけでなく、骨太かつ強靭。カルテットとしてのまとまり、力量は疑いなく現代ジャズの最高峰のひとつで音楽性も十分高い。それでいて「The Way Up」ほど難解でないところもこのアルバムのいいところ。じっくり聴いて噛み締め、スルメのように味わいを楽しめる。(2012年12月24日) | ||
| Spaces / Larry Coryell | ||
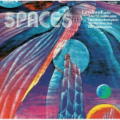 曲:★★★☆ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1969 [1] Spaces (Infinite) [2] Rene's Theme [3] Gloria's Step [4] Wrong Is Right [5] Chris [6] New Year's Day In Loa Angels - 1968 |
Larry Coryell (g) John McLaughlin (g) Chick Corea (elp) Miroslav Vitos (b) Billy Cobham (ds) |
| 顔ぶれを見ただけで胸躍るとはこのアルバムのことでしょう。サウンドは表面的にはソフトでフュージョンに分類される可能性すらあるものの、無味無臭の環境音楽と化した退屈なフュージョンと明らかに違うのは、ひとえに演奏が優れているから。リーダーだから当然コリエルのギターが中心、典型的なジャズ・ロック的なフレーズとサウンドで、テクニカルかつスリリングなプレイ全開。マクラフリンは一歩引きつつも出番は豊富でバッキングでもカッコいいフレーズを放つ。リズムは基本的にフォービートが多く、チックのエレピ(ただしここでは完全に脇役に回っている)が絡んでまさにこの時代的なエレクトリック・ジャズなサウンド。コブハムのプレイはジャズ・スタイルを貫いており、マハヴィシュヌ・オーケストラのようなパワフルなプレイとは趣を異にする。[1]ではロック調のリズムも組み込まれているけれど、ジャズとしての違和感がないのはヴィトウスがリズムの中心を支えているから。そのヴィトウスのベースが中心のときにコリエルとマクラフリンが絡みつくシーンが醸し出すムードは管楽器とは違う特質を持つギターならではのロック的アプローチだからこそ可能なもの。[5]で一瞬、ギター・サウンドがプログレッシヴ・ロック風に聴こえてくるのは、ジャズ・ギターからの影響が強いと個人的に思っているロバート・フリップを先に聴いていた僕の音楽歴のせいでしょう。全体的に、さすがこのメンツという納得のクオリティながら、実はアコースティック・ギター2本だけによる[2]がスリリングでこのアルバムのハイライトになっている。(2007年10月27日) | ||
| Cause And Effect / Larry Coryell, Tom Coster, Steve Smith |
||
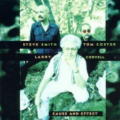 曲:★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1998/5/9-19 [1] These Are Odd Times [2] Plankton [3] Wrong Is Right [4] Bubba [5] Cause And Effect [6] Night Visitors [7] Miss Guided Missile [8] First Things First [9] Night Visitors Revisted [10] Finale: Wes And Jimi |
Larry Coryell (g) Tom Coster (key) Steve Smith (ds) Victor Wooten (b [1]) Benny Reitvelf (b) [2][6][10]) |
| ラリー・コリエルで何か良いものはないかなあと探していたところに目に入ったのがこのアルバム。ジャケットに映っているのは、中央にコリエル、左のスキンヘッドがあのジャーニーに在籍していたスティーヴ・スミス、右には、そのスミスと共にフュージョン・グループ、ヴァイタル・インフォメーションで活動しているトム・コスターという構成。一言で言ってしまえばバカテク系ハード・フュージョンで、この種の音楽が好きな人にはたまらないはず。曲は2つのパターンに大別できまる。ベースが入っていない曲ではコスターがジャジーなオルガンを響かせ、フォービートも多用。一方でベース入りの曲はかなりハードな演奏になる。スティーヴ・スミスはジャーニー全盛期でも、かなり凄腕と言われていたドラマーで、でも、その実力を聴く機会はなかったなんだけれども、このアルバムを聴いてようやく「なるほど」と納得できた。ただ、ジャジーな曲の演奏でも基本的な資質はロックにあることを感じてしまい(もっと言えばジャズ・ドラムのマインドに欠けていてスウィング感がない)、このアルバムをジャズの世界から遠ざけている最大の原因になっているように思える。だからスミスのハマリ曲(ベース入り)とコリエルのハマリ曲(ベースなし)が微妙に噛み合っていない。テクがあればこの程度のクオリティのアルバムは作れるのかもしれないけれど、うまくまとめられるかどうかはまた別の話ということか。それを逆手に楽しめるかどうかがポイント。(2008年4月26日) | ||
| Concierto / Jim Hall | ||
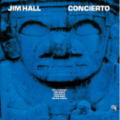 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1975/Apr [1] You'd Be So Nice To Come Home To [2] Two's Blues [3] The Answer Is Yes [4] Concierto De Aranjuez |
Chet Baker (tp) Paul Desmond (as) Jim Hall (g) Roland Hanna (p) Ron Carter (b) Steve Gadd (ds) Don Serbesky (arr) |
| このアルバムがどういう経緯で製作されたのかは知らないけれど、結論から言うと実によくできたアルバムと言うほかない。時代は75年、つまりフュージョンが完全に市民権を得た後ということもあり、ここでもその匂いがプンプン。原因はロン・カーターの電化ウッド・ベースのサウンドと、純粋なジャズ・ドラマーとは言い難い(後のエリック・クラプトンとの活動でも有名な)スティーヴ・ガッドのスタイルにある。そんな力感あるリズム・セクションに対する他のメンバーの演奏はソフィスティケイトされているという言葉が相応しい。ジム・ホールのクリーンなトーン、チェット・ベイカーとポール・デスモンドの柔らかいサウンド、小奇麗なローランド・ハナのピアノ、これらを融合させたドン・セベスキーのアレンジ、すべてが完璧に構築されている。20分弱の表題曲がなんといっても目玉だけれど、[1]の軽快感も素晴らしい。ジャズに熱さを求める向きには物足りないだろうけれど、ここまで完成度の高いアルバムもそうはなく、それ故にじっくりと聴きこむことができる作品。まさにクリード・テイラーのプロデュースの勝利。(2009年10月3日) | ||