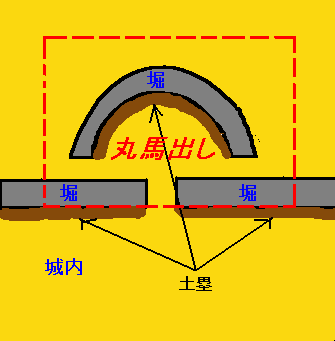 |
桝形と同様、虎口防御のための堅固な施設の一種。虎口の前に、小テラスの郭を設け、虎口を防御します。虎口付近に小テラスの郭を設けることは桝形と同じですが、桝形との違いは、馬出しの場合は、原則として虎口と小テラス間に図のように掘をもうけ、橋で結んで小テラスが出島のような形状になっているところなどがあげられると思います。馬出しから城内に架かる橋と馬出しから城外に架かる橋との方向は原則として直角にするか、または平行にならないように配置して、敵が馬出しに進入しようとしたとき、城内から弓、鉄砲で敵の側面を射撃できるようします。馬出しから城外へ向かう虎口のだいたいは、門や木戸などを設けられていないようで、そのため撃って出やすく、桝形より原則として攻撃性が強くなります。(木戸を設けた城もありますが)