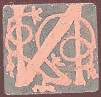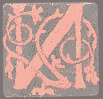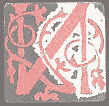お手軽度★☆☆
●石印材 ●印刀 ●紙やすり ●ラップ ●筆、鉛筆 ●墨、朱 ●歯ブラシ
本格的な篆刻はんこですが、遊び感覚で作成してみましょう。
はんこ用の石印材は、100円位から数万円の骨董品と呼べる物までさまざまです。
詳しくは”
なるほど解説”ページをご覧ください。
20ミリ角

ここでは比較的入手しやすい巴林石(バリンセキ)を使用しました。
どうも透明感のあるものが切れ味がいいようです。ご参考にしてください。
○まずはんこを彫る面(印面)を平らにします。
300番の紙やすりで文字を彫る面を整えて、今度は1000番で仕上げます。
平らに気を取られて、斜めになってしまう事がありますので十分注意してください。
ここで手を抜くと全てが水の泡になってしまいます。
平らかどうか確かめるには、はんこの表面をガラスや鏡に当ててみて、
グラグラしない様でしたら平らなのでOKです。
○鉛筆や筆でお好きな模様を描いてみましょう。
まず透明なトレーシングペーパーやラップにサインペンなどで下絵をデザインして、
左右裏返してはんこに画き写すといいでしょう。最終的には鏡に映して確認します。
ここでは石に墨を塗り、直接「N」字を朱で書き込みました。墨と朱を使って、
加筆修正していきます。 朱色の線を残して、黒の部分を削ります(朱文印)。
見本:イニシャル・N

これではちょっと面白くないので、もう少し遊んでみましょう。
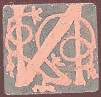
中世の”蔦模様”を自由にデザインしました。
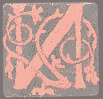
これに立体感をつけるため、修正を加えました。
鉛筆で描けば、消しゴムで何度でも修正できますが、
細かな修正には向かないので、その場合には単純なデザインがいいでしょう。
仕上がりをお楽しみに。↓
○さあ彫ってみましょう。
印刀見本 : 16センチ*12ミリ
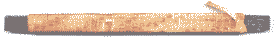
残念ながら、石のはんこは彫刻刀やカッターナイフでは彫れません。
必ず印刀をご用意ください。とはいえ店主は以前”平タガネ”を使っていた時期も
ありますし、そんなに悪くもありませんでした。
はじめてお買い求めでしたら、上図左のような平刀がオススメです。
詳しくは”
印刀(篆刻刀)のページ”へ。
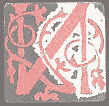
朱色の部分を残して、ゴリゴリ彫ってみました。

刀の持ち方は、手のひらで握ってしまうか、筆の持ち方で削って行きます。
店主は”引いて”彫っていますが、もちろん”押して”彫ってもOKです。
くれぐれもケガしないようご注意ください。
残りの部分も全部彫ったら出来上がりです。石の屑は歯ブラシで落としてください。
○きれいになったら、さあおしてみましょう。
さあ出来上がりです。西洋風の飾り文字のはんこが作成できました。
あまりテクニック(ギザギザの線をだしたり、わざと欠けさせたり)は使わず
シンプルなはんこに仕上げました。ここで気に入らないところは修正します。
右は黒い紙におしてから、全面にエンボス加工を施しました。いかがでしたか?
”
エンボス加工”もご覧ください。