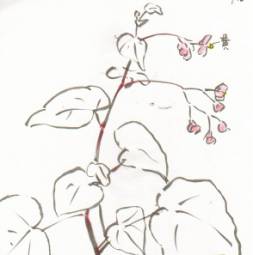●
▲
■
NO.1(1999.09)
|
|
● |
個人の「アウトソーシング」とは、「友達」のこと。
|
|
●
|
アイデアとは、「思いつき」。それを上手に温めたもの。
|
|
●
|
個性、個性と言い過ぎる。初心者にそんなものがあるものか。教わるうちに無くなってしまうような個性なら、そんなもの、もともと個性ですらなかったのだ。
|
|
●
|
魂の救済。法が救わなければ、大衆が救う。大衆が救わなければ、文学が救う。文学が救わなければ、神が救う。マスコミや文学や宗教の役割とは、そういうものではないか。
|
|
●
|
岡山の実家。深夜、すだく虫の音に包まれる。子供のころに聞いた虫たちの、きっと子孫に違いない。人のいのちのサイクルと虫たちのサイクル。輪廻の螺旋のなかに、ふるさとはある。
|
|
●
|
あなたなら、何と言うだろうと問いかける。その問いかけがあるかぎり、人は他者の中に生きている。
|
|
●
|
伝えたい感動があるなら、文章にしようが、やきものにしようが同じことではないのか。同根のものではないのかと思うようになりました。そしてその根は、おそらく「人格」というものに近いところに届いている・・・(出した手紙から)
|
|
●
|
「詩や文章を書くように織りをしたいと思った。私はスタートのところから、他の人とは方向が違っていた」(正確には覚えていないが、ラジオのインタビューで聞いた「織り」の志村ふくみさんの言葉。大きなヒントを頂いた。
|
|
●
|
人は失敗には学べないと思い始めています。人は成功にしか学べないのではないか。困難に出会うたび、自分の中の成功のパターンを思い出して立ち向かおうとする。失敗に学ぶためには、失敗するに至った根本の人格まで改造する必要があるように思います。(35歳年上のガールフレンドに出した手紙から)
|
|
●
|
「・・・私のような最晩年にふみ入った者には、失敗といい、成功というも、夫々が一つの「カタチ」なのではなく、失敗の中に成功を含み、成功も亦、失敗を内に蔵しつつ流動を続けてゆくのが、人生、人の世と思うようになっております。」(頂いた手紙から)
|
|
●
|
「美」は発見するものだ。そしてそれは、じつに個人的な発見だ。思いどおりに溶けず失敗だと思い込んでいた釉薬が、あとで見ると美しかったりする。そこに「美」を発見できるか、見過ごすか。400年の昔、溶けの悪い不透明な長石釉に「美」を発見した個人が確かにいた。「志野」は、そこから生まれてきた。
|
|
●
|
年齢のせいか、手続きとか、儀式とかを大事に思うようになった。封筒に入った手紙をもらうのが好きだ。これから、あなたの心の中に入りますよと、ハサミで封を切る一瞬の儀式。
|
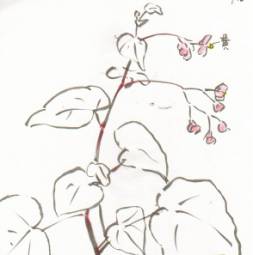
|
|
|
窯
変
「付録のおまけ」
|
|
|
●
▲
■
ここをクリック |

|