クララとノラとベルンハルト
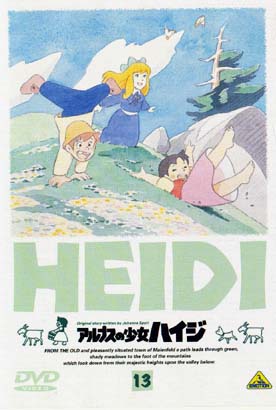
アルプスの少女ハイジ DVD13巻ジャケットより
原作「ハイジ」(1880-1881)は、第一部と第二部にわかれていました。
ハイジがフランクフルトから帰り、おじいさんが回心して村人と和解するまでが第一部で、第二部がクララがアルムにやってきて回復するお話になります。
当初、発表されたのは第一部だけで、好評だったので第二部が翌年になってから出版されたそうです。
題名も、第一部が「ハイジの修行時代と遍歴時代」で、これは前にも書きましたようにゲーテの「マイスター」になぞらえています。
「マイスター」は文豪の超大作で、「修行」と「遍歴」の二部構成です。
それを合成した名前で、ハイジ第一部の題名をなぞらえているからには、もともとハイジは、こんにち第一部とされている部分だけで完結していた。と考えるのが普通です。
ハイジ第二部は、第一部と比べると明らかに完成度が低く、つけたしの印象がぬぐいきれません。
しかし、第二部があって、病気の少女が大自然の中で治癒するという、最大の見せ場ができました。
強烈な感動を、読者に「強制」できるようになりました。
作品の整合性・完成度が高くても、それがヒットして、永久に記憶されるかどうかはまったく別の問題で、第二部の存在によってハイジは俗っぽい作品に転落した(のかもしれない)と同時に、永久に愛される作品になったのだと思います。
作者のもともとの思惑を超えた事態が発生したわけで、これを私は「天使がまいおりた」と表現したいです。(そうです特劇アプリオリのPEROさんのパクリです)
このサイトの表紙に、ハイジ第二部をずっと掲示してきたのは、このためでもあります。(そのうち変えます)
しかしけっきょく、第二部は予定外であり、好評だったからと続編を書いたことで、スピリは息子のベルンハルトより批判されたともされます。
さて、もし第二部がない場合、問題になるのはクララの扱いです。
第一部で物語が終わるならクララは悲惨な状況で放置されることになります。
ゼーゼマンさんの後悔もあって、クララの意向は無視されて、ハイジは故郷に帰っていきます。
せっかくできた友達を失ってしまいます。
クララは、アルムの山にいけるかもしれない。というばくぜんとした希望だけが残されて、歩けないまま取り残されます。
なんの救済もなされていません。
友達のいる楽しさを味わった後では、一人の寂しさはいっそうつのるでしょう。
だからこそ、第二部はクララの治癒のお話になったのですが・・
現実問題として、さまざまな病気で車椅子生活をする人々は、長期になればなるほど回復が難しいものです。
児童文学と障害の関係の評論「クララは歩かなくてはいけないの?」を書いたロイス・キースは脊椎損傷で、自分自身が少女時代からクララとおなじような車椅子生活で、ハイジを読んで自分もいつか歩けるようになれるものだと素直に信じ込んでいました。
成長した後、結局それが望みのないものだったと思い知らされて傷ついたと書いています。(追加あります)
クララは、なぜ歩けるようになったのか?。
これは、現実にありうることなのか?
ノーベル文学賞作家セルマ・ラーゲレーヴは「ニルスの不思議な旅」の作者として児童文学でも有名ですが、子供の頃、車椅子生活でした。
しかしある日突然、歩き出すことができたそうです。
100年以上の昔としては奇跡的なできごとであり、この例を考えるとクララのような回復は不可能とはいいがたいようです。
(ちなみに同じような治癒の物語として「秘密の花園」が有名ですが、これは1911年作ですから、1981年のハイジのずいぶん後です。ハイジを参考にしているのは間違いありません。)
しかしながら、すべての歩行障害が治癒するわけではないのは、残酷ですがあたりまえです。
この点、ハイジ第二部のクララの治癒は、相当に問題があります。
スピリは医者の娘ですから、車椅子で生活する人々の実際を知っていました。
そしてハイジ第二部を書いてしまい、回復しないままで終わるはずのクララが奇跡的に歩けるようになる物語になってしまったことで、スピリにはある種のうしろめたさ。
現実に種々の障害・困難に直面する人々に対して、絵空事を描いてしまったことへの、後悔が生じたのではないか?
と、私は推測しています。
アニメの歴代人気投票では、高畑ハイジの「クララが立った!」のシーンが必ずといっていいほど上位に入るようですが、実際はクララの場面よりハイジがフランクフルトより帰ってきて、おんじに迎えられる場面の方が感動するという意見が、あちらこちらのファンサイトで見られます。
これは、単純明快、素直に再会を喜べるハイジの帰郷にくらべて、クララの回復は人工的につくられた感動であり、少し考えればかなりの条件付でしか祝福できない、非現実的要素が含まれているのが一因ではないでしょうか?。
歩くのに不自由な生活をする少年少女は他のスピリ作品に3回(あくまでも私が確認できた中です)登場します。
そのいずれも結局、肉体は回復せずに物語が終わります。
クララのケースは、スピリにとっても例外なのです。
その中でも、もっともクララを意識して造型された、と思えるのが、ハイジの次に書かれた長編作品「グリトルの子供たち」(1883-4)に登場する金髪の少女・ノラです。
「グリトルの子供たち」は質・量ともハイジにつぐスピリの代表作とされます。
悲劇的色彩が強いためか、日本では「天使の歌」「僕たちの仲間」の題名で2回しか翻訳されていません。
ほとんど知られていないといっていいでしょう。
(絶版後40年以上もたった本を、読んでくださいとはとてもいえませんので、ネタばれご容赦ください)
ノラは裕福な家の一人娘で、父はすでにおりませんが、母と乳母の二人の女性に育てられています。(ロッテンマイヤーさんのような人は登場しません)
この少女は、生まれつき体が極めて弱く、歩けないわけではないですが、わずかな距離で体力がつきてしまうために、ほとんどの時間を安楽イスに座ってすごします。(心臓疾患でしょうか?)
ノラは大切に守られていて、負担をかけるようなことは、いっさいされませんが、それでも日々、少しずつ弱っていきます。
実母と乳母の、二人の母の手の中で、これから死んでいこうとする、小鳥のヒナなのです。
これは、たまったものではありません。クララをもっと極端にしたかのようです。
回復への最後の願いをかけて、ノラはスイスへ転地療養へむかいます。
そこで、ノラは二人の優しい少女と知り合います。
明るく元気なエミと、おだやかで華奢なエルスリです。
まるで、ハイジを二つに分けたかのような、この少女たちは、それぞれのやり方でノラと友達になろうとします。
でも活発なエミは、自分の楽しいことをノラにいろいろ提案するのですが、どれも体力を必要とすることで、結局二人はお互いに理解しあえません。
次にエルスリが、ノラの身近にいることになりますが、自分自身病弱で、辛抱強いエルスリは、ノラの語る「希望」の素直な聞き役となり、二人は友達になります。
なにもできないノラの、唯一の希望とは、
「もうすぐ、きれいな花のさく、ふたたび自由に動き回れる別の世界へ行けること」
なのです。
これはノラの乳母が実母の目から隠れて、何度も話して聞かせたことです。
こんな希望をいだいているノラに、エミが友達になれるはずはないのでした。
ある日、ノラとエルスリは窓際に座り、きれいな夕日をみつめます。
二人は長い間みうごきもせずによりそいあい、そしていつのまにか、かたわらのノラは静かに冷たくなっていくのです。
なげきかなしむノラの実母。
エルスリもエミも悲しみます。
しかし、やがてエルスリとノラの乳母の間には、ノラの思い出を仲立ちにして、強い結びつきができます。
ノラは目を閉じるまで、友達と一緒にいて幸せだった。
いまも別の世界で、幸せになっていないわけはない。
どんな人間も、永遠に生きられるものではないのです。
病弱であろうが健康であろうが、いずれ同じ問題につきあたります。
それでもノラの生涯は、けっきょく無意味だったのではないか?
スピリは「そうではない。すべてをゆだねきったあとに、思いがけない展開がある」ことを、描こうとします。
物語ではこれ以降、エルスリの心の中には常にノラの面影とノラの希望が残りつづけます。
グリトルという名前はエルスリの母親のものです。
貧しく若くして亡くなってしまったが、二人のこどもを素直に清潔に,優しい人間になるように育て上げた人です。
語感からすると、(よくわからないですが)なんとなく「優しい人間」という意味があるような気がします。
(脱線です。
ハイジという名前は、「高貴な」「野生」を裏側に秘めているようで、これはadelheidさまのご指摘です。
またアルムおんじの名前についての興味深い考察を、ねこばすちゃん様がされておられますが、私個人としてなかなかコメントできず、放置して申し訳ありませんでした。
私の印象では、なんとなく「アルムおんじ」の名には、新約聖書マタイ福音書のいわゆる「山上の垂訓」・・「心貧しきものは幸いなり」の意味が含まれているような気がしているのですが、結局確認できていません。)
その後、エルスリはノラの母から娘同然に扱われ、またエルスリの兄ファニーが画家志望であることを友達であるエミが知って、いろいろと奔走することになります。
その結果、グリトルの子供たち・兄妹二人はドイツのノラの家で暮らすことになります。
ここまでが「グリトル」第一部ですが、この作品も好評だったため、ハイジと同じように第二部が追加して書かれます。
二人はドイツで裕福に暮らすのですが、エルスリはふとしたことから困窮した漁師の家庭の子供たちと親しくなります。
ノラの母親の目を隠れて、その子供たちの面倒をみるようになり、優しく働き者の少女はその家庭を立ち直らせ、「天使のようなお姉さん」としてなくてはならない存在になります。
物語はいささかとりとめないエピソードもまじえて続きますが、このエルスリの活躍と、画家になりたいファニーとその希望を認めないノラの母との葛藤が後半の主題となります。
エルスリは全編通してのヒロインですが、彼女を内面で動かすものは第一部でいなくなってしまうノラの「希望」ですし、作品全体をメリハリあるものとして動かしていくのはエミです。トリプルヒロインです。
しかし最後に近くなって、体調が悪いことを自覚していたエルスリは大量に吐血し、その夜のうちに息をひきとります。
あんまりといえばあんまりの展開でした。
少女はもともと結核をわずらっていて、無理をして死期を早めてしまったのです。
この娘もノラのように真っ青な顔をしていて、スイスで働きづめの生活をしていたら命が危ないと医者に言われたからこそ、ノラの母は自分の子供の友達を家にひきとったはずでした。
ノラの母は再び悲しみを味わい、それが結果的にファニーとの対立を解消させます。
エルスリを慕っていた多くの人々も嘆き悲しみます。
しかしエルスリ自身は、最後までノラと同じように恐れもなく、おだやかに、でも優しく生き抜いたのです。
死にゆくノラは、少し遅れて、やはり死に行く運命であったエルスリに、精神的遺産をのこし、エルスリはファニーに未来を開きます。
エルスリの兄・ファニーは自分の進む道を求めて旅立ち、物語は終わります。
不幸も幸福も描くミニ大河小説といえるでしょう。
そしてハイジの変奏曲といえるようなお話です。
クララとハイジの幸せこそが、この悲しい物語を生み出したと私は思います。
アルムの山でも回復しないクララ。
フランクフルトでやせ細って、とうとう帰れなかったハイジ。
ハイジという物語で、すべてがうまくいかない最悪の事態になったとしたらどうなるのでしょう。
考えたくはないですが、そんなこともありうるのです。
絶望の淵にいるときに、どのようにしたら子供も大人も、希望をもつことができるのか?
それがこの物語のテーマの一つでしょう。究極の問題を扱ったともいえます。
また、「ハイジ」が作者にとって不本意な部分を持つ作品であったとしたら、これがスピリ流の「ハイジ」への決着のつけ方だったのでしょう。
もっとも、この作品の最後は、性急で配慮が欠けているようにも思えます。
おそらく、仕方のない事情があったのでしょう。
現実とは、まことにままならないものです。
「グリトルの子供たち」の完成した年、スピリの一人息子・ベルンハルトは亡くなります。
29歳の若さで、長年結核をわずらった末の衰弱死でした。
病気面ではエルスリのモデルであり、芸術的才能にめぐまれていたそうですからファニーのモデルでもあったはずです。(ベルンハルトは音楽です)
さらには同じ年に、心労も重なったのか人格者であった夫まで失い、スピリはたった一人とりのこされてしまいます。
自分の作品で、登場人物に悲惨な運命を用意した作家が、同じような状況によってさらにつらいかもしれない事態を迎えたのです。
自分の作品に足をすくわれてしまったかのようです。
真実を語るために、フィクションというウソをつかなければならない作家という仕事は、矛盾にみちたものです。
一人息子と夫の死から、ほぼ一年にわたってスピリの作品発表はなくなります。
でもその後、この作家は、前にもまして「自分自身で子供と青年のためになると考えるところの作品」を猛然と書きつづけます。
ただし、もう作中で幼い子供が悲惨な最期をむかえることはなくなってしまいます。
自分の息子のことを考えると、ノラやエルスリのような運命を描き出すことができなくなったのでしょう。
もともとスピリのデビュー作は、不幸な生涯を送った幼友達の思い出を書いた悲しい物語です。
悲劇はスピリの出発点でもあります。
それができなくなるのは、作家としての後退と見るのはたやすいですが、一人の人間、一人の母としてみた場合、これをとやかく言うつもりは私にはありません。
(例外はあります。「大岩」(1886)が少女の死を描きますが、これは再開後、第一冊目の短編集に収録された短い作品で、「グリトル第二部」と設定が似ていて原型のような作品ですので、それ以前に書かれたと考えることもできます。)
スピリ最晩年の作品に「レーザ家の一人」(1894)があります。
作品の内容に立ち入ることは今はしませんが、これは「グリトルの子供たち」で描ききれなかった、自分の才能を活かすために旅立っていく少年の軌跡をより丁寧に描いています。
少年が志すのはベルンハルトと同じ音楽ですし、この分野にすすむときに陥る問題点を容赦なく指摘してもいます。
この作品は、時としてスピリ作品に顕著だったご都合主義や構成の破綻が少なく、なるべく現実にありうる話として少年の自立を描いた作品です。
かなり完成度は高く、楽しい部分も悲しい部分も描いています。
ここで、スピリは「グリトル」で積み残した問題を終わらせているかのように思えます。
それは同時に、ノラやエルスリやクララへの最終回答かもしれません。
架空の存在であるノラ=クララのモデルがあるのかどうかはわかりません。
現実にそのような少女がいたのかもしれません。
ただ、内幕を知らない読者の一人としては、ノラの歌は一人の女性作家の最悪の時期をも、ささえたような気がします。
自分の作り出したキャラクターに、作者自身が語りかけられ、問いかけられたはずです。
「私たちを試練にあわせた作者のあなたは、自分が同じ立場になったときどうするの?」・・と。
徐々にやってくる最期でも、突然やってくる最期でもいいです。
「その時」を目前にしても恐れをもたず、いつもと変らずに優しくいられる人間はもっとも強い人間であり、自由な人間といえる。と私は思います。
なにしろ死という、現世の最高権力に脅迫されずにすむのです。
そして、スピリは絶望をのりこえ、自分の仕事を楽しみながら生涯をまっとうしたように、私には見えます。
2004/3/16
追記
さて、クララの病気についてはまだ書きたいことがありますので、別の機会にハイジの分とあわせて企画中です。それからノラの詩についてと例の「黄金色の・・」の詩との比較、その出典なども興味深いので調べたいです。 |