#040
明治史劇集、遠藤為春の聞書、「日本演劇」の劇評家研究、『一葉全集』の註釈を機に久保田万太郎と三宅周太郎を思う(31, August. 2004)
■ List【戸板康二・全著書リスト】に、『明治文学全集85 明治史劇集』(筑摩書房、昭和41年)[*] と『古典日本文学全集26 歌舞伎名作集』(筑摩書房、昭和36年)[*] の書誌データを追加。
■ 前々からの懸案、『明治史劇集』[*] は6月末に買った。岩波文庫の新刊で刊行されたばかりの三木竹二著『観劇偶評』を肌身離さず持ち歩いていた頃に買ったので、目次を眺めただけでなんとなく臨場感たっぷりで嬉しかった。月報には遠藤為春への聞き書きが「明治史劇の思い出」というタイトルで掲載されていて、このときの聞き書きがのち、芸能学会の雑誌「芸能」昭和45年3月号から5月号にかけて「明治・大正の芝居」というタイトルで全文収録された。この対談を載せるにあたっての附記として戸板さんは、
あれから4年目になるが、筑摩書房の「明治文学全集」の「明治史劇集」を編集した時、明治の名優の舞台をよく知っている遠藤為春さんの話を聞く機会を設けてもらった。というふうに書いている。この戸板さんによる遠藤為春への聞き書きは、去年図書館で「芸能」の記事を収集していた折にすでに読んでいたので、今回『明治史劇集』を買ったことでひさびさの再会と相成った。そして、『明治史劇集』の目次を眺めているときとおんなじように遠藤為春の聞き書きも、岩波文庫の三木竹二を手にしたあとであらためて眺めてみると、臨場感たっぷりだった。遠藤為春翁への聞き書きのなかで戸板さんは「遠藤さんが何げなくおっしゃることが、ぼくらにとってはたいへんな、いい資料です」と言う。明治の劇通への聞き書きというと、敗戦間近の明舟町のアパートでノートをとりながら川尻清潭の話に耳をかたむける戸板さんの姿がまっさきに頭に浮かぶ。川尻清潭との交流に関することは戸板康二を読み始めた頃からたいへん心に残っている挿話なので、遠藤為春の聞き書きを眺めることで、明舟町のアパートの川尻清潭に思いを馳せてみたりもした。明治の古老の話を聞き出す際の戸板さんの態度というか礼儀正しさのようなものがとてもいい感じで、そこに裏打ちされている戸板さんの側の博覧強記ぶりにも見とれてしまう。戸板さんのいろいろな意味での「教養」が遠藤為春への聞き書き全体にただよっていて、その独特の雰囲気がなんともいえず好きだ。
この速記は、昭和41年9月30日夜、銀座の岡田での対談で、遠藤さんはいつものように、機嫌よく、博覧強記の知識を語ってくださった。月報にその一部がのったが、枚数の制限があり、大部分を割愛した。そのままにしておくのは、あまりにももったいないので、筑摩書房の了解を得て、「芸能」にその全部をのせることにした。当然、一部は再録になるわけだが、本誌への掲載を快諾された筑摩書房の寛容に深くお礼を申し上げる。
遠藤さんの口調をいかし、その味い多い話術のふんい気を読者に知っていただきたいと思って、くり返して話された所なぞ、テープで聞くように、わざとそのままにしておいた。
2月6日は遠藤さんの一周忌である。この速記を読み返しながら、闊達な故人の人柄が、しきりになつかしまれる。
■ 遠藤為春への聞き書きを読んでとりわけ「おっ」となったのが、新蔵のくだり。『芸能めがねふき』[*] の現・富十郎の項で、戸板さんが《古老から話に聞いた市川新蔵という役者は、水際立った芸であたりを圧したといわれる。新蔵に関するデータを調べると、竹之丞(現・富十郎)が似た芸風のような気がしてならない。竹之丞に、新蔵研究をすすめておきたい。》というふうに書いているのを見て以来、長らく新蔵のことが気になっていたのだった。新蔵といえば、谷崎潤一郎『幼少時代』(岩波文庫)にも登場していて、鏑木清方が挿絵を描いている。と、新蔵のことが長らく気になっていたのを遠藤為春の聞き書きで新蔵が登場したあたりでふと思い出して「おっ」となってみると、遠藤為春は六代目菊五郎が新蔵に似ていると言い、さらに「もっと公平に言えば、六代目のいいんだな、新蔵という人は。」とまで言っていて、これを受けて戸板さんは「六代目のいいのというんだから、よほどたいへんな役者ですね。」というふうに返している。このくだりを見て、「え〜、六代目菊五郎のいいところ取り〜!」ととにかくびっくりだった。と、びっくりしただけで、その後、特に追求していないのであるが。
 ■ 前々回の制作ノート(実に2カ月以上前)で、戸板康二による三木竹二に関する文章を2つ挙げたのだけれども、このとき、うっかり書き忘れていたことがあったのだった。日本演劇社に入社して戸板康二がその編集に携わった最初の号、「日本演劇」昭和19年9月号でさっそく、戸板さんは「劇評家研究」として三木竹二のことを書いている。そして、よくよく見てみると、この「劇評家研究」なるシリーズは戸板さんの三木竹二が最初で、次号からさまざまな書き手によって「劇評家研究」が断続的に掲載されている。もしかしたら「劇評家研究」は、「日本演劇」の編集に携わったまなしの戸板さんによる企画だったのかもと思った。そのトップ選手として戸板さんが執筆対象として選んだのが三木竹二。それまでいろいろな媒体に劇評を書いていたものの、演劇ジャーナリズムの世界に入っていよいよ演劇人としての活動をスタートさせるにあたって、「劇評家研究」なる連載を企画して、自身は三木竹二について書いた。戸板さんの三木竹二に対する並々ならぬ思い入れが伺える。戸板さんは「劇評家研究」のなかで、
■ 前々回の制作ノート(実に2カ月以上前)で、戸板康二による三木竹二に関する文章を2つ挙げたのだけれども、このとき、うっかり書き忘れていたことがあったのだった。日本演劇社に入社して戸板康二がその編集に携わった最初の号、「日本演劇」昭和19年9月号でさっそく、戸板さんは「劇評家研究」として三木竹二のことを書いている。そして、よくよく見てみると、この「劇評家研究」なるシリーズは戸板さんの三木竹二が最初で、次号からさまざまな書き手によって「劇評家研究」が断続的に掲載されている。もしかしたら「劇評家研究」は、「日本演劇」の編集に携わったまなしの戸板さんによる企画だったのかもと思った。そのトップ選手として戸板さんが執筆対象として選んだのが三木竹二。それまでいろいろな媒体に劇評を書いていたものの、演劇ジャーナリズムの世界に入っていよいよ演劇人としての活動をスタートさせるにあたって、「劇評家研究」なる連載を企画して、自身は三木竹二について書いた。戸板さんの三木竹二に対する並々ならぬ思い入れが伺える。戸板さんは「劇評家研究」のなかで、
竹二の眼は、写真をみると、幅の広い禿げ上がった額の下に燦々とかがやいているが、あの眼がくい入るように新富座や歌舞伎座の座席の隅から、團十郎・菊五郎の圧倒的な演技を把え、一方、次の時代へ歩み出そうとする新進俳優のうえに暖かく注がれていたのを想い見れば、今日、尚吾々は心ゆたかになるのである。というふうに書いていて、戸板さんの三木竹二へのまなざしを見て、わたしもまさしく心ゆたかな気持ちになるのだった。最後は、
之は肝腎な事であるが、何といっても、まず、竹二は「芝居がすき」だったのである。その執心・熱意は、彼に端然たる態度があったから決して表面惑溺といった形を示さなかったし、逆に示さなかった丈に、案外吾々は、竹二があくまで客観的に冷静に、歌舞伎を処理している、と思い込むのである。が、どうしてどうして、三木竹二ほど夢中に、芝居にその精魂を打ち込んだ人は、その後もいく人もいないのである。というふうに締めている。戸板さんの企画だと勝手に決めてしまった「劇評家研究」は、三木竹二のあとも「日本演劇」に断続的に掲載されていて、目次を拾ってみたら、
- 戸板康二「三木竹二」昭和19年9月
- 水木京太「小山内薫」昭和19年10月
- 本山荻舟「根岸派の人々とその後」昭和19年11月
- 渥美清太郎「大正期のお社の人々」昭和20年1月
- 三宅三郎「劇評家岡鬼太郎氏について」昭和20年3月
- 利倉幸一「伊原青々園」昭和20年4・5月
- 山本二郎「坪内逍遥の劇評」昭和21年1月
- 加賀山直三「杉贋阿弥覚書」昭和21年2月
- 戸部銀作「六二連の事」昭和21年3・4月
■ 『古典日本文学全集26 歌舞伎名作集』(筑摩書房、昭和36年)[*] は、まずは庫田テツによる装幀がなかなか愛らしい。他の号も集めたくなってしまうけれども、西鶴集や浄瑠璃集を見たかぎりでは原文ではなく現代語訳での全集となっていて、わざわざ古典を現代語で読もうとは思わないから残念であった。浄瑠璃など原文で読んでこその楽しみのような気がする。この歌舞伎脚本集はさいわい「歌舞伎の特質を生かして脚本の原文をかかげました」とのこと。下欄に戸板さんによる注解がある。巻末のエッセイは戸板さん好みのセレクションなのかなあと思うと興味深い。
 ■ 戸板さんによる注釈というと、先月に鎌倉の木犀堂で、念願の新世社版『樋口一葉全集』を入手した。第2巻の「小説 二」は久保田万太郎の編集で、万太郎に頼まれて戸板さんが注釈を手伝って、予期しない稿料をもらって本を何冊か買った、ということを戸板さんの文章で知って以来ずっと気になっていた。昭和16年7月発行の第二巻のあとがきで、万太郎は
■ 戸板さんによる注釈というと、先月に鎌倉の木犀堂で、念願の新世社版『樋口一葉全集』を入手した。第2巻の「小説 二」は久保田万太郎の編集で、万太郎に頼まれて戸板さんが注釈を手伝って、予期しない稿料をもらって本を何冊か買った、ということを戸板さんの文章で知って以来ずっと気になっていた。昭和16年7月発行の第二巻のあとがきで、万太郎は
脚注に精粗のあったことは残念である。が、これは、この上とも月報「一葉ふね」で補足をつづけつつ同時に統一もし、漸次完全なものにして行くつもりである。しかし、この仕事は一人の力によくするところではない。げんに今度でも、慶應義塾大学文科出身の若い友人戸板康二君の助力をえた。後日のためにしるす。というふうに結んでいて、たしかに万太郎の言うとおり、脚注は精粗はありすぎ(のちに月報「一葉ふね」で補足されることもない)、おそらく万太郎が脚注を書いたのは自身が後年講義もした『たけくらべ』だけなのではないだろうか。『たけくらべ』の最初の方だけ詳細な脚注がついている。あとの小説は時々しか注釈がついていなくて、おそらく、適当にやっておいてくれたまえと、戸板青年が頼まれた結果なのだろう。戸板さんも当時明治製菓に勤める忙しい身であるし、国文科出身とはいえども研究者というわけではないのだし、かなり困惑したことだろうと思う。ちなみに、『わかれ道』の「かすりでも取って」のところの《かすりをとるとは上前をはねるということなり。黙阿弥の『梅雨小袖昔八丈』の台詞に「鬼といわれた源七がここで命を捨てるのも、餓鬼より弱い生業の地獄のかすりを取った報いだ」とあり。》という注釈はいかにも戸板さんかなあと思ってニンマリだった。しかし、きちんと稿料を戸板さんに渡している万太郎の誠実さには感激で、さらにあとがきにこうして「若い友人戸板康二君」というふうに書いてもらって、戸板さんはさぞ嬉しかったことだろうと思った。この「若い友人戸板康二君」の文字を見て、わたしもジンとなった。「後日のために」しるしてくれてありがとう、万太郎、と思った。
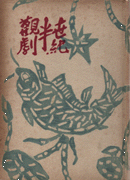 ■ と、ここで急に思い出したのが、三宅周太郎のこと。三宅周太郎について書く度に戸板さんが必ず言及するのが、和敬書店より昭和23年刊行の『観劇半世紀』に関する挿話ことで、『あの人この人』[*] の「三宅周太郎の宗教」では、
■ と、ここで急に思い出したのが、三宅周太郎のこと。三宅周太郎について書く度に戸板さんが必ず言及するのが、和敬書店より昭和23年刊行の『観劇半世紀』に関する挿話ことで、『あの人この人』[*] の「三宅周太郎の宗教」では、
三宅さんの自伝が書きおろしで刊行されることになった。関君が私に、どういう題にしたらいいだろうと相談して来たので、私は「観劇半世紀」という案を出した。幸いに賛同を得たのだが、本が届いたら「まへがき」に、私をよく知ってくれる厚意の現われと見なければならないと喜んでいる三宅さんが、題をつけてくれたのが「東京の若い友人T君」としてあるので、何となくガッカリした。「東京の若い友人」の「T」といえば、利倉さんだっているし、まだ他にいないわけではない。正直にいえば、戸板と明記していただきたかったという気がした。というふうに紹介している。と、わたしは、久保田万太郎の「若い友人戸板康二君」で三宅周太郎の「東京の若い友人T君」のことを思い出したわけだけれども、戸板さんも、上記の「三宅周太郎の宗教」の抜き書きのすぐあとに、
じつは三宅さんには、ストレートに書こうとしない癖があった。たとえば、はじめてこの役者について「某誌に書いた時」という風になっている場合がよくある。しかし、これは仮にその記事を知りたいと思う者がいるなら、まことに手数がかかるのである。久保田万太郎さんは、自分はこの小説を大正2年の「新小説」に書いたと正確におぼえていたし、某誌という表現を決してしなかった。人それぞれというわけであろう。というふうに、久保田万太郎を引き合いに出しているので、なるほどなあという感じだった。三宅周太郎の文章ではあと、『続文楽の研究』に「京橋の明治製菓に勤めているT君」が登場しているのを見たことがある。三宅周太郎の文章に登場する戸板康二はいつも「T君」なのだった。
■ 久保田万太郎と三宅周太郎で思い出すのが、久保田万太郎による『日記より』(「新演芸」大正13年連載)というシリーズのなかの「噂」という文章のこと。学生時代に三宅周太郎が電信柱にかじりついて柱巻の見得をやったという伝説について、万太郎は《もし、三宅君にうわさ通りの――電信柱に齧りつくだけの――熱情があったとしたら三宅君の劇評はいまどういうふうになっているのだろう?――うわさというものはつねに噂の主を裏切るものである。》というふうに結んで、柱巻の見得に関してはここではあくまで「うわさ」だと書いている。戸板さんが後年三宅本人に尋ねたところによると、その伝説は本当だったとのこと。なのだけれども、三宅周太郎が電信柱で柱巻の見得をしていたのが本当だった! ということの事の重大性がいまいちわたしには実感としてよくわからないのだった。これは三宅周太郎に関してまだまだよくわかっていないからなのだろう。
← PREV | NEXT →