#038
初山滋カヴァーの『わが歌舞伎』、ぜいたく列伝、岩波文庫の三木竹二(23, June. 2004)
■ List【戸板康二・全著書リスト】に、『ぜいたく列伝』(学陽書房人物文庫、平成16年)[*] と『わが歌舞伎』(河出文庫、昭和30年再版)[*] の書誌データを追加。
■ 今月の歌舞伎座昼の部の口上のあとの幕間に奥村書店で、河出文庫版の『わが歌舞伎』を買った。本書は、昭和28年に河出市民文庫として発売になったものが、昭和30年に再版になってカバーがついたもの。『暫』の挿画を全面にあしらった、初山滋によるカバーがまずはとても嬉しかった。戸板さんの著書のなかで、お気に入りの装幀を10選ぶとすれば、必ず入りそうな1冊。今までどんな本なのかまったく知らなかった本を、海老蔵襲名の幕間の奥村書店で買った、という巡り合わせもよかった。
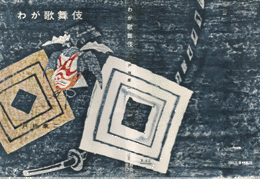
|
元版の、昭和23年に和敬書店より刊行の『わが歌舞伎』[*] は、翌年刊行の続篇 [*] とセットで、戸板康二の本を買い始めたまなしの、まだ蒐集とまでは行っていなかったころ、神保町の豊田書房で買った。そんなに高くはなかったけれども、安くもなかった。なんとなくペラペラ立ち読みして、『わが歌舞伎』のまえがきをちらっと読んで急に欲しくなって衝動買いして、買った直後は正続両方のまえがきとあとがきを何度も読んでいたものだった。《「わが歌舞伎」という標題は、歌舞伎に対する僕の気持を端的に表したものであるが、同時に「歌舞伎というものを、僕はこう見る」という含みも、あるわけである。》というふうに、『わが歌舞伎』のあとがきは結ばれているのであるが、昭和20年代の戸板さんの歌舞伎書に漂うムードみたいなものにたまらなく惹かれるきっかけになった本だったと、今にして思う。『わが歌舞伎』正続は、ふんだんに掲載されている鳥居清言の挿絵がとっても味わい深い。挿絵もそのままで復刻するとしたら、ちくま文庫がいかにもぴったり、かなりいい感じになるのでは、と前々から思っている。河出文庫の『わが歌舞伎』では鳥居清言の挿絵は掲載されていない。
■ 『わが歌舞伎』の初版は昭和23年1月、わたしの持っているのは昭和23年3月再版のもので、見返しに「昭和廿参年五月廿二日 京都より到着」という書き込みがある。版元の和敬書店は京都の出版社で、昭和21年5月より「幕間」という演劇雑誌を刊行していた。翌22年8月に戸板さんが戦後初めて京都を訪れたのは「幕間」誌上の企画がきっかけで、そのあたりのことは『回想の戦中戦後』[*] の「わが町になった京都」に詳しい。『続わが歌舞伎』は昭和24年12月に刊行。よく利用するとある図書館では「幕間」の所蔵は断片的で、先日適当に眺めていたら、昭和23年12月 の京都行きの際に和敬書店の2階で、昭和24年11月発行の『六代目尾上菊五郎舞台写真集』のもとになった木村伊兵衛撮影の菊五郎の写真を至福の思いで見た、という内容の戸板さんの文章があって、これがとてもよかった。戸板さんがその写真を見たときは菊五郎は存命だったんだなあと思った。
■ 昭和23年1月発行の『わが歌舞伎』に収められている文章は、島源四郎が編集していた雑誌「大衆文芸」での連載がもとになっている。『「ちょっといい話」で綴る戸板康二伝』[目次]巻末の犬丸治氏作成年譜によると、戸板康二が島源四郎と知り合ったのは、内田誠の指令で手伝うこととなった昭和16年10月資生堂にて開催の小村雪岱展がきっかけだったとのこと。翌17年10月より「大衆文芸」での連載が始まり、明治製菓在職時と退職後の女学校教師時代、同誌には「高島悠太郎」名義でも演劇時評風の文章も執筆している。と、敗戦直後に燦然と世に出た『わが歌舞伎』のもとの原稿は戦時下に書かれたもので、河出文庫として再び世に出たのはその約10年後。昭和28年3月に書かれた文庫版あとがきの書き出しは、
本文に収録した「役柄の話」「演技の話」の第一稿を書いたのは、昭和十七・八年で、その頃の歌舞伎には、まだひと世代前の古典的な雰囲気が残っていた。というふうになっている。河出文庫の『わが歌舞伎』を手にして、戦中戦後の戸板康二の十年、戦中戦後の歌舞伎の十年、みたいなことをちょっと思ったのだった。
しかし、すでに歌舞伎は知識人の趣味の対象としては、遠い所にあったし、反面、大衆との結着も弱まっていた。劇場の興行成績を数字面だけで見れば、決して悪くはなかったが、それが歌舞伎の繁栄と呼び得るかどうかは、軽々しく結論出来ない。この事情は、現在も同じことである。
ただ、歌舞伎が大衆の生活の中にとけ込まなくなった代りに、インテリゲンチャのあいだに、教養のひとつとして考えられるようになったのは、明治よりも、大正よりも、今日に於ける顕著な現象であろう。
■ 河出文庫の『わが歌舞伎』が戸板康二の最古の文庫本なら、今年4月の新刊文庫、人物文庫の『ぜいたく列伝』[*] は戸板康二の最新の文庫本。今年の1月と2月に岩波現代文庫で『歌舞伎への招待』正続が無事に発売になって一安心していたところで、今度は『ぜいたく列伝』がまさかの再文庫化と相成って、4月のとある土曜日、神保町へ出かけた折、豊田書房で武智鉄二の本をチェックしたりしたあと立ち寄った東京堂で人物文庫版『ぜいたく列伝』がデーンと地味に積んであるのに遭遇した。が、その日は、ほかのフロアを放浪しているうちに買うのを忘れて帰ってしまうという失態を仕出かしてしまって、結局、近所の本屋さんに地味に1冊だけひっそりと棚にささっているのを後日発見して買ったのだった。うーむ、真剣度が不足しているとしか言い様がない。人物文庫の『ぜいたく列伝』は、新たに解説が付されているということもなく、文春文庫版をそのまま、三井永一の挿絵もそのままに人物文庫になっている。が、パッと見たところですぐに誤植がいくつか目についてしまった。戸板さんの文庫本が新たに復刻したのはとても嬉しいけれども、もともと文春文庫で出ていたのを思うと、文春よ! せめて『ちょっといい話』だけでも復刊してくれないものかしらとも思う。車谷弘が企画した「銀座百点」が体現していた空気にいかにもぴったりだった戸板さん、といったふうな、往年の文藝春秋のよき雰囲気を今に伝える書き手の代表格だと思うのであるが……。
■ などとぼやきつつも、今回の『ぜいたく列伝』再刊を機に、この2ヵ月間、新たにいろいろな本読みの波及があって、極私的にはたいへん楽しかった。というわけで、やっぱり今回の学陽書房の再刊には感謝感謝。初めて『ぜいたく列伝』を手にしたのは4年前の2000年のちょうど同じ季節で、この4年間、いろいろな本読みがあったなあと思う。
■ 『ぜいたく列伝』の初版は1992年9月、小林信彦は、当時「週刊文春」で連載していた「私の読書日記」で以下のように書いている(『本は寝ころんで』文春文庫より)。
戸板康二の「ぜいたく列伝」は、さまざまな分野で〈ぜいたくを極めたいく人かの生涯〉を集めたものである。と、改行の多い文章をわざわざ長々とここに抜き書きしたのは、最後の一節がちょっと面白かったというのと、戸板さん最晩年の著書のリアルタイムの文章という臨場感というのもあるけれども、一番の理由は、『ぜいたく列伝』を初めて手にした人の第一印象がここに端的に示されているように思ったから。『ぜいたく列伝』の目次、戦前生まれの小林信彦ですら渋いと思ってしまうらしい……。
ここに集められた人々は、ぼくの年代からすると、すべて知っているとは言いがたいが、六十代後半から七十代の人たちにとっては親しい名前だと思う。
堀口大學は知っていても、光村利藻、益田太郎はぴんとこない。
とにかく、知っている名前からひろい読みすればいいわけで、まず、〈谷崎潤一郎の四季〉の章を読んだ。
谷崎の死は1965年(昭和40年)7月であり、その時の暑さをいまだに記憶している。ぼくは江戸川乱歩邸の応接間で、日影丈吉氏と話しながら出棺を待っていた。その時、谷崎の死が電話で伝えられたのだ。
その数年前、谷崎夫妻は PR 誌「銀座百点」の座談会に出席し、
〈久保田万太郎と歯切れのいい下町の言葉で話していた。〉
同席した戸板康二はさりげなく書いているが、ぼくはこのお二人の〈歯切れのいい〉会話をきいてみたい。そういうのが、今となっては(当時でも、だが)、〈ぜいたく〉というものである。
ある出版社の社長が、谷崎を招きたいが、万が一、食事が合わなかったらと考えて、ためらい、やめた、とある。
こういう〈ぜいたく〉は分り易いのだが、パリで豪遊する薩摩治郎八となると、なにかもう、ケタがちがってくる。
明治から昭和にかけての二十三人の名士の〈ぜいたく〉を集めたのは、戸板さんの強い好奇心である。
(「文藝春秋」10月号の戸板さんの「新ちょっといい話」には、太平洋戦争中、野球用語を日本語にしようとした時、巨人軍事務所の青年がいとこに相談して、ストライクはヨシ1本、アウトはだめ、と決める。そのいとこは堀田善衛氏とある。)
以下はぼくの冗談だが、今の日本でもっともぜいたくな人は長嶋一茂氏ではないかと思う。今年、アメリカに〈野球留学〉をするとき、彼は空港でこう語っていた。
――向うで、ハングリー精神とかいうものを、身につけられればいいのですけど……。
■ わたしも初めて手にしたときは、「ぴんとこない」名前は飛ばして、「知っている名前からひろい読み」していった。一気に読了ということはせずに、何度もめくっているうちに気のおもむくままに読んでいるうちに、いつのまにか全目次制覇という成りゆきだったかと思う。「ちょっといい話」に代表される戸板さんの人物エッセイの一貫として、その筆さばきをおいしいものを味わうように何度も楽しむというふうにしてめくっていた。と、そんな接し方でも十分すぎるくらい楽しかったけれども、『ぜいたく列伝』を初めて手にしてから約1年が過ぎて、2001年5月に月の輪書林の目録を初めて手にしたことで、わが『ぜいたく列伝』読書史(のようなもの)は第二段階に入ることとなった。とびっきりの愛読書、同時代の交遊記『あの人この人』[*] のあちこちの記述で読みたい本がどんどん増えていって、読みたい書き手がどんどん増えていって、いろいろつながっていくのと同じような接し方を『ぜいたく列伝』でもするようになったのだった。きっかけは、月の輪書林の目録に薩摩治郎八関係の本、雑誌「芸術新潮」の薩摩治郎八特集号(1998年12月号)と薩摩治郎八をモデルにした獅子文六の小説『但馬太郎治伝』と、戸板康二の『ぜいたく列伝』が並んで掲載されていたこと。これがいたく鮮烈だった。以来、『ぜいたく列伝』ではあちこちで「いもづる」が楽しくて楽しくて、読み直す頻度は、今や『あの人この人』以上かもしれない。
■ 『ぜいたく列伝』の芋づるをたどっていて、しみじみと感じるのは明治・大正、戦前昭和といった日本の近代のべらぼうな面白さ。大正4年に生まれて、青年期は昭和に入ってからという、震災後の東京で育った世代の戸板康二は、『ぜいたく列伝』で描かれているようないろいろな「ぜいたく」の余燼のなかで育った世代である、ということができるように思う。『ぜいたく列伝』の最初を飾る「光村利藻の愛妾」からしてとても象徴的。大学卒業後の戸板康二が明治製菓の PR 誌「スヰート」の編集者として何度も出入りしていた光村印刷の創業者の光村利藻、その愛妾の豆千代をのちに敗戦間近に、演劇記者として芸談を聞くため出入りしていた川尻清潭の芝明舟町のアパートで見かけることとなる。この距離感がいい。遠いような近いような、近いような遠いような、というような距離感をもって、『ぜいたく列伝』を彩る人物たちは戸板康二を魅了、あるいは戸板康二は彼らを目撃したり、彼らと接触したりしている。自分の編集している雑誌に載せるという念願がかなった、師の折口信夫が歌舞伎論の題材に選んだ十一代目仁左衛門、青年の頃から愛読していて戦後「銀座百点」の座談会で同席することになる谷崎、同じように愛読していて、「芸術新潮」の記事のため芝居見物の思い出をインタヴュウすることとなった志賀直哉、「スヰート」の編集者として原稿を取りにいった百間先生、三田の学生時代にアナトール・フランスの訳本を買いに麹町の社屋を訪れたこともある第一書房の長谷川巳之吉、子供の頃に家族で帝劇へ出かけて益田太郎の喜劇を見たり、同じく子供の頃、初めて五代目歌右衛門を大阪で見る、徳川義親の次男義龍と暁星の同級でクリスマスパーティーに呼ばれたことがある、などなど。
■ 2001年5月に月の輪書林の目録を手にしたことで第二段階に入った、わが『ぜいたく列伝』読書史、その3年間というもの、たまに局地的に『ぜいたく列伝』関係で大興奮、ということがあった。薩摩治郎八と並んで獅子文六が自らの小説の題材に選んだものの急逝して果たせなかった益田太郎がらみでは、高野正雄著 『喜劇の殿様 益田太郎冠者伝』(角川書店、2002年)が出た。なんとも素敵な1冊だった。著者の高野正雄氏は生前の獅子文六の担当記者だった人。太郎冠者がらみでは桂文楽所演の「かんしゃく」も大好き。最近教えていただいたのだけれども、「かんしゃく」をたまに高座にかける小三治さんは『喜劇の殿様』刊行当時、マクラでこの本のことを話していたとのこと。とても嬉しい話だった。『喜劇の殿様』の記憶がまだまだ鮮明なころに見学に出かけた、早稲田大学演劇博物館の帝劇展はたいへん鮮烈だった。演博といえば、五代目歌右衛門を見物したこともあって、ここでも『ぜいたく列伝』つながりになっている。円朝展もとても面白かった(と、ついでに『泣きどころ人物誌』[*] を思い出したり)。わりと最近では、鹿島清兵衛がとても面白くて、飯塚くに著『父・逍遥の背中』(中公文庫、解説は坪内祐三)のことを知り、あわてて取り寄せたりもしていた。この本はなかなかの大傑作で、戸板さんが読んだらさぞ喜んだことだろうと思う。近代日本の写真史みたいなことも気になる。そして、ごくごく最近ハマっているのが、第一書房の長谷川巳之吉。つい先日、念願の『第一書房長谷川巳之吉』(日本エディタースクール出版部、1984年)を入手してホクホクだった。長谷川巳之吉に関しては、元・小沢書店社主の長谷川郁夫さんが評伝を「図書新聞」に連載中なので、本になるのがとても待ち遠しい。長谷川郁夫さんは「三田文学」には堀口大學の評伝を連載中で、ここでも『ぜいたく列伝』つながりなのだった。それから、先月、3年ぶりに出た月の輪書林の目録を見ていたら、徳川義親に「おっ」となった。とかなんとか、『ぜいたく列伝』の芋づるはまだまだ尽きなさそう。戸板康二の『ぜいたく列伝』追跡記、みたいな文章をいつかまとめてみたいなあと思っている。
 ■ 最後に、今月の岩波文庫の新刊について。三木竹二の『観劇偶評』が渡辺保さんの編集で現代によみがえった。こんなに嬉しいことはない、の一言に尽きる。戸板さんが見たらさぞ喜んだことだろうと思う。三木竹二の名前を知ったのは、戸板康二を読み始めて間もない頃で、角川新書の『歌舞伎の話』[*] がきっかけだったかと思う(←この本は『歌舞伎への招待』の次に読んだ本。「その批評」で始まる「歌舞伎の話」)。戸板康二を読み始めると同時に、明治からの劇評史の系譜をたどる(真似事をする)というのが最大の関心事のひとつになった。以来、三木竹二の名前にはひときわ特別な響きがあった。と、戸板康二を読み始めて数年たって、まぼろしだった三木竹二の『月草』を手にすることができたわけで、本当にもうこんなに嬉しいことはない。たとえば中村雅楽シリーズが復刊されること以上に、戸板康二道的には朗報で、『歌舞伎への招待』の岩波現代文庫化に匹敵する大事件だとわたしは思っている(もちろん、雅楽シリーズの復刊も実現してほしいけど)。
■ 最後に、今月の岩波文庫の新刊について。三木竹二の『観劇偶評』が渡辺保さんの編集で現代によみがえった。こんなに嬉しいことはない、の一言に尽きる。戸板さんが見たらさぞ喜んだことだろうと思う。三木竹二の名前を知ったのは、戸板康二を読み始めて間もない頃で、角川新書の『歌舞伎の話』[*] がきっかけだったかと思う(←この本は『歌舞伎への招待』の次に読んだ本。「その批評」で始まる「歌舞伎の話」)。戸板康二を読み始めると同時に、明治からの劇評史の系譜をたどる(真似事をする)というのが最大の関心事のひとつになった。以来、三木竹二の名前にはひときわ特別な響きがあった。と、戸板康二を読み始めて数年たって、まぼろしだった三木竹二の『月草』を手にすることができたわけで、本当にもうこんなに嬉しいことはない。たとえば中村雅楽シリーズが復刊されること以上に、戸板康二道的には朗報で、『歌舞伎への招待』の岩波現代文庫化に匹敵する大事件だとわたしは思っている(もちろん、雅楽シリーズの復刊も実現してほしいけど)。■ 三木竹二に関する、戸板さんのまとまった文章としては、パッと思い出せるかぎりでは、
がある。ついでに、『夜ふけのカルタ』[*] には「鴎外とわが新劇史」という一文がある。この文章を読んだ頃にちょうど新潮文庫の新刊で、森まゆみさんの『鴎外の坂』が発売になって、三木竹二について一章がさかれてあったのがとても嬉しかったのをよく覚えている。思えば、戸板康二を読むようになって数年というもの、ますます森鴎外という存在が大きくのしかかってきていたのだった。つい最近、『木村荘八日記』(中央公論美術出版、2003年)を読んだことで、今まで文学史上の知識として知っていたつもりだった「スバル」「三田文学」やらの明治末期の反自然主義の流れとその周囲を初めて身を持って実感できたことが大収穫だった。戸板康二を考える上でも大収穫だった。というわけで、三木竹二の文庫化と期せずしてタイミングがあったことだし、これからさらに鴎外を追求していきたいところ。
■ 今回文庫化された『月草』という題名で知られた書物については、『見た芝居・読んだ本』[*] の「読書日記」(初出「小説新潮」昭和56年8月)に次のように書いている。
歌舞伎座の「髪結新三」の劇評を書くので、黙阿弥全集と、『月草』を机の上においている。『月草』は明治29年12月に春陽堂から刊行された本だ。森鴎外とその実弟三木竹二の評論集で、千ページ近い大冊である。前のほうに鴎外の坪内逍遥とのいわゆる没理想論争の時の論文がある。ぼくは竹二の劇評をよく読む。このとき戸板さんが書いた劇評はさいわい『戸板康二劇評集』[*] に「『髪結新三』細見」というタイトルで収録されているので、すぐに読むことができる。『観劇偶評』所収の五代目菊五郎に対する竹二の劇評を読んだあとで戸板さんの勘三郎の新三の劇評を読んでムラムラと、昔一度立ち読みしたことのある渡辺保著『中村勘三郎』(講談社、1989年)のことを思い出して、図書館で借りて読んでハマっていたところ。うーむ、やっぱり歌舞伎はおもしろい。そして、歌舞伎なくして戸板康二道なし、だなアとあらためて思うのだった。
ことに五代目菊五郎の芸風については、この『月草』の「牡丹燈籠」「安政三組盃」などの描写をていねいに読みながら、想像をたくましくするとよくわかるので、「髪結新三」のところも、六代目のよりももっとアクのつよい悪党で、そのくせ愛嬌があふれる舞台だったらしい。
この『月草』は、戦後間もなく大学の先輩からゆずり受けた本で、御礼はさしあげたはずだが、金額は忘れてしまった。いま古書店にたまにあるのか、あったとすれば時価どのくらいなのか、全然知らないが、珍本といっていいだろう。
「髪結新三」のところ以外も、ついでにまた、あちこち読んでたのしむ。五代目に限らず、明治の役者のおもかげが、何となくわかって来るのが、うれしい本である。
← PREV | NEXT →