#035
戸板康二と「銀座百点」(05, April. 2004)
■ List【戸板康二・全著書リスト】に、『続歌舞伎への招待』(岩波現代文庫、平成16年)[*] の書誌データを追加。
■ 世紀の大事件といっても過言ではない『歌舞伎への招待』正続の文庫化であったが、無事に刊行が済んでほっと一安心。岩波現代文庫として美しく完璧なかたちで、『歌舞伎への招待』が現代によみがえった。刊行直後にさっそく金子さんの「新・読前読後」にて、
- 事件としての文庫化(2004年1月22日付)
■ 書評の類でウェブ上で読めるものでは、毎日新聞の書評欄に、
- 今週の本棚・毎日新聞2004年2月29日付朝刊(高井有一氏)
- 坪内祐三「文庫本を狙え!」(「週刊文春」2004年3月5日号)
- 『歌舞伎への招待』 more info(岩波書店T・H氏)
- 『続歌舞伎への招待』 more info(犬丸治氏)
■ 何度も書いているように、本格的に戸板康二を追求するきっかけになったのが『歌舞伎への招待』だったので、あらためて美しい文庫本として『歌舞伎への招待』正続を手にすることで、なにかと初心に帰った思いで、2冊とも刊行直後に購入してずっと持ち歩いてのべつページを繰っていた。あらためてじっくり読みふけって、花森安治装幀の暮しの手帖社版でこれらの書物を手にしてから幾年月、いずれも初めて読んだときはそのあまりの鮮烈さに眩暈に似た感覚を覚えたものだったけれども、そんな初めて読んだ頃からあまりわたしの芝居見物も戸板康二読みも深まっていなくて、同じところをグルグル旋回しているだけだなあということを痛感して、むしろ嬉しかった。まだまだこれからなのだ。その意味でも、これら2冊の文庫本はまさしく戸板さんからの賀状という感じで、絶好の贈り物をもらったという気がしている。……と、半年ほど前から初心にもどってばかりいる「戸板康二道」なのだった。
■ 『続歌舞伎への招待』[*] の文庫解説は犬丸治さんだったのでなおのことたのしみだった。さっそくじっくりと読んで、なぜわたしは昭和20年代の戸板康二が一番好きなのかがよくわかった。このことに関してはまたいずれとっくり考えることにして、『続歌舞伎への招待』購入と連動するかのようなタイミングで、その犬丸さんのサイトに掲載の、 をもれなく印刷してファイルに綴じて悦に入って、ウキウキと眺めることとなったのだが、眺めてさっそくびっくりだったのが、第212号(昭和47年7月)の「銀座サロン」に戸板さんの実父・山口三郎氏が登場していること。しかもタイトルは《この父にして》ときた。
■ 戸板康二は書くことと書かないことの区別が厳格な人だった。ご家族のことなど私生活について自身の文章に直接綴ることは結構少なくて、多くの文章でちょろっと言及はあるけれども、お父さんに関しても直接記しているのは『五月のリサイタル』[*] 所収の「父の銀座」(初出は「銀座百点」昭和50年4月号)や『回想の戦中戦後』[*] ぐらいだと思う。しかし、戸板さんの文章に度々ちょろっと回想されるお父さんの姿が実にいい感じで、たまに垣間見るたびにスーッと残って、いろいろな断片が心のなかに蓄積されていった。久保田万太郎と慶應普通部で同級だったという時代にまず注目で、明治の東京育ちの芝居好きで、大正ベルエポックが始まったまなしに青春時代を過ごしていたりといった、戸板康二の父親世代の人物誌のようなものを組み立ててみたいものだといつも思っていた。芝居好きが嵩じて幼いわが子を劇場にのべつ連れていったことがのちの劇評家・戸板康二の素地になっていることは確実であるし、戸板康二の文章でお父さんの姿を垣間見るたびにしみじみ感じたのは、いろいろな意味でまさに「この父にして」ということだった。康二少年とその父、その東京のことを思うと、いつも織田一磨の版画の情景がパーッと頭のなかに広がる。
■ 資料・「銀座百点」と戸板康二を眺めているととにかく「おっ」の連続、いろいろと思うことがあって気持ちばかりがはやってしかたがないのだけれども、まずはさっそくびっくりだった《この父にして》の実物に対面したいッと、綴じたばかりのファイル片手に意気揚々と中央区立京橋図書館の地域資料室へ出かけた。その日は、昭和47年7月号の「銀座サロン」《この父にして》の確認が済んだら、歌舞伎座で吉右衛門の『毛谷村』をもう一回見ようという計画で早起きしたのだったけれども、結局は、ひとたび目にしてみると「銀座百点」に夢中になってしまって、時間を忘れてしまった。
■ 記念すべき、わたしの第1回「銀座百点」探検、ゲストが戸板康二の実父・山口三郎氏、戸板さん、円地文子、車谷弘が四方山話を繰り広げる《この父にして》、さっそく嬉しくてしょうがなかった。まずはお父さんの一人称が「あたし」というところがいいなア……。都筑道夫の『退職刑事』を読んだまなしというタイミングで目にすることとなったので、まさしく気分は一気に『退職刑事』だった。
■ 10歳のときに山の手から日本橋浜町へ引っ越したことから、明治座、真砂座、新富座といった劇場へ頻繁に芝居を見に行くようになる。明治座では左團次、真砂座では伊井蓉峰、河井武雄といった人々を見た。新富座へは、浜町から水天宮を通って八丁堀から桜橋というコース、慶応の学生になると、浜町から一銭蒸気に乗って、浅草の宮戸座、常盤座へ行き、沢村源之助、尾上菊四郎、浅尾工左衛門、嵐芳三郎といった役者を見て、この時分に同級の久保田万太郎と立見席でしじゅう一緒になる。歌舞伎、新派はもちろんのこと、松井須磨子といった新劇も熱心に見て、所帯を持ってからは康二少年を道連れにのべつ芝居見物、……といった感じに、以前から『回想の戦中戦後』[*] や『五月のリサイタル』[*] 所収の「父の銀座」で読んでいた通りの挿話が「銀座サロン」を舞台装置に活き活きとたのしそうに繰り広げられていて、前々から知っていた挿話のみならず初めて知ることもちょろっと何度か挿入されていて、「銀座サロン」を読むことで、何度も読み返しているお気に入りの「父の銀座」が別の方向から照らし出され、ますますヴィヴィッドに精彩を放つ感じで、とにかく頬が緩んだ。この「父の銀座」、初出は「銀座百点」昭和50年4月号、同年2月23日に82歳で他界したのを受けて書かれた文章であることは今回初めて知ったことだった。《自分の父のことを書くについてきまりの悪い思いがあるが》という一節が織り込まれていて、「銀座百点」が初出であるのに、「銀座サロン」に父が招かれたことにも一言も触れていない。戸板さんのそういう潔癖さがわたしは大好きだ。
■ 終生芝居を愛し、稽古事としては観世流の謡曲をやっていていたという。慶応理財科出身の典型的実業家として一生を過ごした、戸板さんのお父さん。息子の進路については、「銀座サロン」にて
あたしは電線業界におりましたから、よく周囲から、「いったい君、倅を慶応の文科なんかに入れて、学校の先生にでもするつもりか」なんて、言われたもんですよ。しかしあたしは、本人が文科をやりたいというんだから、やればいいと思っていました。そして、学校を出たらすぐに会社に入ったほうがいいだろうと思っていました。その頃、明治製菓の内田誠さんが随筆を書いたり、本を書いたりしていたでしょう。その内田さんのところへいきたいというんですね。それで明治製菓へやったわけなんです。というふうに回想している。「な、なぜ息子を文科なんかへ……」といった反応ばかりだった周囲の実業家のなかにあって、ひとり、藤木秀吉(→ click)なんていう人もいたわけで、ますます戸板康二と藤木秀吉のえにしのことが輝きを放ってくるのだった。
■ その、2月のある土曜日に、京橋図書館の地域資料室でまっさきに山口三郎氏登場の「銀座サロン」を探したあとも、しばし「銀座百点」探索が続いて、とりとめもなくペラペラとめくってあちこち読みふけった。第92号(昭和37年8月号)には、「水中亭の銀座」と題する永井龍男のエッセイがあった。いかにも単行本に収録されていそうだけども、この文章を読んだのはこのときが初めて、京橋図書館の地域資料室で「銀座百点」の本誌で直接読むというのがいかにも似つかわしくて、頬が緩みっぱなし。お父さんの回想で内田誠の名前が出たばかりというタイミングなのもよかった。その直後、突然思いついて、前々から気になっていた書物、内田誠著『銀座』(改造社、昭和15年)を閲覧したりの寄り道も。初めて見た《この父にして》でさっそく、今まで戸板康二の書物を通して知っていたことが別の方向から照らし出されて立体化したように、「銀座百点」バックナンバーをちょっと垣間見ただけでも戸板康二の文章のいろいろなこと、いろいろな人物がつながっている、ということの目白押しだった。これからもそうなのだろう。「戸板康二ダイジェスト」でも徐々に反映できるといいなと思っている。
■ 今回の更新箇所はあともう一つ、References【戸板康二を語る人びと・レファレンス】の古川ロッパの『劇書ノート』で、『続わが歌舞伎』[*] の抜き書きが漏れていたのが前々から気になりつつもそれっきりだったのをようやく訂正して追加。古川緑波著『劇書ノート』はあんまり語られていない本のような気がするけれども、こんなに面白い本、そうあるものではない、と思う。ひさびさにめくってみると、わたしの愛読書『唾玉集』が載っていたことに気づいて感激だった。愛読書と言いつつも、『唾玉集』(平凡社東洋文庫、1995年)、全部を通読しているわけではないのだけれども、ロッパの言う通りに「兎に角、たのしめる本」! なのだ。
■ ぼんやりしていたらいつのまにか新年度、2月に更新すべき内容が今ごろになってしまった。書きたいことが溜まっているので、新年度を機に、また仕切り直しということにしてしまおう。……と、仕切り直しばかりしている「戸板康二ダイジェスト」なのだった。とにもかくにも今年度もよい日々になりますよう。
#036
戸板康二と水木京太と丸善と(11, April. 2004)
■ Chronology【私製・戸板康二年譜 1915-1993】をファイルを分割して改訂。今まで4ページだったのを、昭和19年から昭和32年までをふたつに分けて、全5ページに。
■ 戸板康二の年譜というと、1995年1月の三回忌を記念して編まれた追悼文集『「ちょっといい話」で綴る戸板康二伝』[目次]の巻末に犬丸治さん作成の年譜が掲載されている。戸板さんのファンだったら誰もが感激するのは確実のすばらしい労作。『「ちょっといい話」で綴る戸板康二伝』はわりかし入手が難しいと思われるので、多くの人の目に触れる機会が少ないのがいかにも残念。矢野誠一さんによる評伝「戸板康二の歳月」が「別冊文藝春秋」にて始まったのが同じく三回忌の1995年1月で連載は翌年完結、1996年6月に単行本が発行された。わたしの個人的な体験でも戸板康二にますます夢中になるきっかけになったのは『戸板康二の歳月』を読んだことだったし、おんなじようにこの本に感銘を受けた人はたくさんいることだろう(文庫化が待ち遠しい!)。しかし、『戸板康二の歳月』でいくたびか犬丸さん作成の年譜を参考にしている箇所があるのをかんがみると、矢野誠一著『戸板康二の歳月』の背後には犬丸さんの仕事があるというわけなのだ。
■ 「戸板康二ダイジェスト」開設当初からわたしも年譜作成の真似事をしていて、入力の際は犬丸さん作成の年譜は見ないようにして、矢野誠一さんの『戸板康二の歳月』の記述から間接的に参照するようにして作り始めた。「戸板康二ダイジェスト」を公開するよりもずっと前から自宅の Mac にてチビチビと入力していて、いったん始めてみるとこれがもう楽しくて楽しくて、単なるわたしの道楽と化して、それが現在も続いているという次第。ちなみに、「私製・戸板康二年譜」を作ってみよう! などと思ったきっかけは、戸板康二とも密接に関係のあるとある年表を拝見して「これはスゴい!」と大変感激して何度も眺めているうちに、この体裁で戸板康二の年表を作ってみたらどうだろう? と突然思いついて、さっそく Mac の電源を入れたのが最初で、フォーマットはその年表を踏襲しているという、いわば完全な真似ッ子なのだった。作成者ご本人がご覧になったとしたら、ばれてしまうかな、かな、かな。
■ さて、『戸板康二の歳月』に、亡くなる前日の1993年1月22日、銀座のはち巻岡田で戸板さんを囲んだ会食があって、その会食の直前に矢野誠一さんが教文館から出てくる戸板さんの姿を目撃したというくだりがある。となると、戸板さんが生前最後に入った本屋さんは銀座の教文館ということになる。ということにあとで気づいて、あまりの因縁に震えつつもひとりで大喜びだったのだが、今年の1月22日、わたしは深い考えもなく教文館に足を踏み入れて、何の前ぶれもなく突然、洲之内徹の新刊『おいてけぼり』(世界文化社刊)を見つけてびっくり、さっそく購入して、その夜、長谷川りん二郎の《薔薇》という絵、洲之内徹の「気まぐれ美術館」最初の絵が「スヰート」の表紙絵だったということを知った。『歌舞伎への招待』(岩波現代文庫)[*] と「BOOKISH」第6号《戸板康二への招待》が発売になった今年1月、洲之内徹の新刊が発売になっただけでも事件だというのに、「スヰート」の表紙絵に遭遇するというさらなる大事件が待っていたという展開、天国の戸板さんの魔法の杖かしら、と、ついオカルトチックなことを思ってしまったくらい。
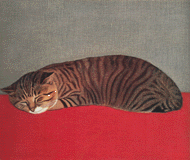 ■ 長谷川りん二郎のことを知ったのは洲之内徹の『絵のなかの散歩』所収の文章がきっかけで、たぶんこの文章を読めば誰でも長谷川りん二郎のことがくっきりと心に刻まれるであろう洲之内徹の筆致、長谷川りん二郎への洲之内徹のまなざし、洲之内徹の文章を通した長谷川りん二郎にとにかくうっとりだった。と、洲之内徹の文章で長谷川りん二郎のことを知って最初に見ることになったのが《猫》という絵、モデルのりん二郎の愛猫タローは長谷川四郎の家で誕生したのだという。長谷川四兄弟については『思い出す顔』[*] に、長男の海太郎(筆名:牧逸馬、林不忘、谷譲次)の夫人が、明治製菓宣伝部にて内田誠の脇に控えていた人物として登場している「長老で、相馬社長の自伝の編集をしたりする、おしゃれな香取任平氏」の妹だったというくだりがあったのが記憶にあったので、ワオ! と長谷川四兄弟のことでひとりでにわかに盛り上がることとなって、川崎賢子著『彼等の昭和―長谷川海太郎・りん二郎・濬・四郎』(白水社、1994年)や室謙二著『踊る地平線めりけんじゃっぷ長谷川海太郎伝』(晶文社、1985年)を読んだりと、思わぬ波及読書があってずいぶんたのしかった。この波及読書がまた別の方向へとつながっていった。
■ 長谷川りん二郎のことを知ったのは洲之内徹の『絵のなかの散歩』所収の文章がきっかけで、たぶんこの文章を読めば誰でも長谷川りん二郎のことがくっきりと心に刻まれるであろう洲之内徹の筆致、長谷川りん二郎への洲之内徹のまなざし、洲之内徹の文章を通した長谷川りん二郎にとにかくうっとりだった。と、洲之内徹の文章で長谷川りん二郎のことを知って最初に見ることになったのが《猫》という絵、モデルのりん二郎の愛猫タローは長谷川四郎の家で誕生したのだという。長谷川四兄弟については『思い出す顔』[*] に、長男の海太郎(筆名:牧逸馬、林不忘、谷譲次)の夫人が、明治製菓宣伝部にて内田誠の脇に控えていた人物として登場している「長老で、相馬社長の自伝の編集をしたりする、おしゃれな香取任平氏」の妹だったというくだりがあったのが記憶にあったので、ワオ! と長谷川四兄弟のことでひとりでにわかに盛り上がることとなって、川崎賢子著『彼等の昭和―長谷川海太郎・りん二郎・濬・四郎』(白水社、1994年)や室謙二著『踊る地平線めりけんじゃっぷ長谷川海太郎伝』(晶文社、1985年)を読んだりと、思わぬ波及読書があってずいぶんたのしかった。この波及読書がまた別の方向へとつながっていった。■ 室謙二さんの本でも引用されていたのだけれども、香取任平については和田芳恵著『ひとつの文壇史』(新潮社、昭和42年)に当時の証言があって、人気作家の義弟の事務いっさいを取り仕切るその姿は長谷川海太郎がかあいそうになってくるような SF 映画のようなシュールさ、その事務処理能力がのちに内田誠の片腕として「スヰート」編集部でいかんかく発揮されたかと思うとニヤニヤだった。戸板さんは《部長の脇にひかえ、一見部長のように見える香取任平氏》というふうにも書いている。若き日に内田誠の下で仕事をしていた明治製菓「スヰート」編集部のある種の空気について、『句会で会った人』[*] では《この部にいた人の多くは、コネで入ったらしく、男爵の長男とか、著名な画家のひとり息子とか、作家牧逸馬の義兄とか、みんな呑気な連中であった。》というふうに描写されていて、《宣伝部に毎日来る広告代理店や印刷会社の外交の人たち、「スヰート」の執筆者、表紙や口絵を描く画家といった、いわゆる文化人と知り合い、「スヰート」を主とした私の分担する仕事には、興味が尽きない、たのしさがあった。》というふうに記す、戸板康二をとりまく「スヰート」の人物誌、現時点では一度も現物を見たことのない戦前の雑誌「スヰート」、戸板さんの在籍していた昭和14年から昭和18年までのいろいろなことは戸板康二を読むようになって以来ずっと最大の関心事のひとつだ。
 ■ 「スヰート」編集部での同僚、香取任平について、繰り返しになるけれども「長老で、相馬社長の自伝の編集をしたりする、おしゃれな香取任平氏」というふうに記している戸板さん、この「おしゃれ」という言葉がきいているなアとしみじみとなってしまった。もし、ここに「おしゃれ」という単語ひとつが入っていなかったら、香取任平の印象はかなり薄くなる。なにげないようでいて、こういうちょっとした文章作法はまさしく天賦のもの。それから、室謙二氏の著書で描写されていた妹の長谷川和子のモダンガールぶりにも驚くばかりで、ほぼ同時に読みふけっていた都筑道夫著『推理作家の出来るまで』にもちょろっと鎌倉の未亡人宅を訪問するくだりがあった。と、その兄・香取任平がにわかに気になって、ちょいと調べてみたら、著書が1冊だけあった。数百円ということもあって、どんな本なのかも知らずに軽い気持ちで思わず注文。昭和33年発行の『花鳥亭日記』、「鎌倉風物誌」という副題がついている本が届いた。で、これが一目見ただけでもワオ! と、たいへん愛らしい本で、函の花の絵は著者自身によるもので、自らが手がけたという中身のレイアウト等も実に洒落ていて、かなりの「おしゃれ」さんであることは見た目にも明らかだった。(……が、中の著者の肖像写真では「おしゃれ」ぶりはあまり偲べず。)
■ 「スヰート」編集部での同僚、香取任平について、繰り返しになるけれども「長老で、相馬社長の自伝の編集をしたりする、おしゃれな香取任平氏」というふうに記している戸板さん、この「おしゃれ」という言葉がきいているなアとしみじみとなってしまった。もし、ここに「おしゃれ」という単語ひとつが入っていなかったら、香取任平の印象はかなり薄くなる。なにげないようでいて、こういうちょっとした文章作法はまさしく天賦のもの。それから、室謙二氏の著書で描写されていた妹の長谷川和子のモダンガールぶりにも驚くばかりで、ほぼ同時に読みふけっていた都筑道夫著『推理作家の出来るまで』にもちょろっと鎌倉の未亡人宅を訪問するくだりがあった。と、その兄・香取任平がにわかに気になって、ちょいと調べてみたら、著書が1冊だけあった。数百円ということもあって、どんな本なのかも知らずに軽い気持ちで思わず注文。昭和33年発行の『花鳥亭日記』、「鎌倉風物誌」という副題がついている本が届いた。で、これが一目見ただけでもワオ! と、たいへん愛らしい本で、函の花の絵は著者自身によるもので、自らが手がけたという中身のレイアウト等も実に洒落ていて、かなりの「おしゃれ」さんであることは見た目にも明らかだった。(……が、中の著者の肖像写真では「おしゃれ」ぶりはあまり偲べず。)■ 香取任平著『花鳥亭日記』は「鎌倉観光新聞」に連載していた随筆風日記が中心になっており、昭和20年代の鎌倉日記という体裁、発刊時には四谷若葉町に引っ越している。タイトルの「花鳥亭」というのは「香取」をモジった俳号で、『句会で会った人』によると、鎌倉文士の句会に出ていた香取氏を内田誠は自分の句会には誘わなかったそうなので、句会で戸板さんと同席することはなかったのだろう。文章そのものは正直いって内田誠の随筆に遠く及ばず、という感がして、実業家の手遊び以上のものではないように思うけれども、「スヰート」編集部の空気の一端が伺えるような『花鳥亭日記』の造本センスは一見の価値が大いにあった。明治製菓での勤務経験がいかにも似つかわしく「あまカラ」の原稿を執筆しているくだりがあり、その文章、戸板さんも「あまカラ」で見たに違いない。戸板さんの「あまカラ」掲載の文章を香取氏も見たことだろう。それから、久保田万太郎の「茶の間の会」のメンバーでもあった小道具の藤浪与兵衛の後ろ姿を描いた鏑木清方の挿画が添えられていたことに大感激だった。昭和27年2月10日という日付とともに「食へぬ菓子を作る藤浪さんを清方寫」という文字が添えられていて、ここでもお菓子つながり。
■ お菓子随筆と聞いてまっさきに思い出すのは内田百間の文章、戸板さんを取り巻く「スヰート」人物誌でもっとも心ときめくくだりのひとつは百間先生との交流だ。慶応予科時代の昭和8年、三笠書房『百鬼園随筆』を手にして以来の百間ファンだった戸板康二は、「スヰート」編集部の仕事を通して、直に接することになった喜びについて何度か文章にしている。『わが交遊記』[*] ではこんなふうに記している。
季刊の毎号、巻頭に内田百間先生(師ではないが百鬼園先生に倣って書く)の随筆が必ず載った。これは当時の中川蕃社長と岡山の中学が同級だったからで、今思うと、原稿がめったにいただけないという定評のあった作家の文章を、キチンキチンと掲載したのだから、贅沢な話であった。「牛」「シュークリーム」「漱石断片」「牛乳」「チース」「窮屈」「カステラ」「バナナの菓子」「蟻と砂糖」「紅茶」「砂糖袋」「小列車」「海苔」「茶柱」「罐詰」「喰意地」「爪哇迄も」「雛祭」「可否茶館」と、こんなに書いていただいている。明菓の雑誌だという事情を考えて、主題をえらび、独自の発想が、みごとな達意の随筆になっている。そのころ百間先生は、丸ビルの隣の日本郵船ビルの一室に、毎日出勤していた。電話がかかると、京橋から歩いて、原稿を頂戴しに行く。いい散歩の行程だった。と、『御馳走帖』で見覚えのあるタイトルがわりかしたくさん紹介されているわけで、この『わが交遊記』を読んで以来、中公文庫の『御馳走帖』を手にするたびにいつも、戸板さんと「スヰート」と百間先生のことを思い出して悦に入っていたものだった。と、その初出をきちんと調べようと思いつつ幾年月、先日、福武書店発行の『新輯内田百間全集』全33巻をもとにようやく懸案を片付けたのでここに書き留めておこう。まずは、「スヰート」初出の随筆を、先の文章で戸板さんが挙げていた「牛」から拾って一覧にしてみた。
|
「スヰ−ト」における内田百間 昭和13年
|
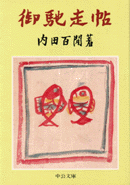 というふうになっていて、先の文章を書く際に戸板さんはおそらく書架の「スヰート」を参照してタイトルを書き留めていったに違いなく、だいたい順番は同じになっているものの「紅茶」と「蟻と砂糖」のところのみ入れかわっていたり、「可否茶館」からあとの3つの随筆に言及していなかったり、「季刊」でも「隔月刊」でもなく月が続いていたり、今回参考にした『新輯内田百間全集』でも初出の単行本の解題と最終巻の初出リストとで異なるところがいくつかあったりと、不明な点は多々ある。が、まずは一度調べてみた結果というわけで、二つの資料で「スヰート」初出の百間随筆のことが、まだまだ大まかではあるけれどもひとまずは判明して嬉しい。戸板康二が明治製菓に入社するのは昭和14年4月、それより以前の号に掲載の随筆をなぜ戸板さんは挙げているのだろうと思いを巡らせてみると、前年に久保田万太郎と対面したことで内田誠の下で働くことになり、配属先の資料として前年から「スヰート」を手にしていたのだろうと推測している。下線が引いてあるのは『御馳走帖』所収の文章、やっぱり『御馳走帖』には戸板康二在籍時代の「スヰート」がまんべんなく反映されているといえそうで、前々からの目論見があたっていたのも嬉しかった。右の矢印は収録されている単行本、初版本とは言わないからせめて旺文社文庫が欲しいなあと将来の古本買いの夢が広がるのだった。
というふうになっていて、先の文章を書く際に戸板さんはおそらく書架の「スヰート」を参照してタイトルを書き留めていったに違いなく、だいたい順番は同じになっているものの「紅茶」と「蟻と砂糖」のところのみ入れかわっていたり、「可否茶館」からあとの3つの随筆に言及していなかったり、「季刊」でも「隔月刊」でもなく月が続いていたり、今回参考にした『新輯内田百間全集』でも初出の単行本の解題と最終巻の初出リストとで異なるところがいくつかあったりと、不明な点は多々ある。が、まずは一度調べてみた結果というわけで、二つの資料で「スヰート」初出の百間随筆のことが、まだまだ大まかではあるけれどもひとまずは判明して嬉しい。戸板康二が明治製菓に入社するのは昭和14年4月、それより以前の号に掲載の随筆をなぜ戸板さんは挙げているのだろうと思いを巡らせてみると、前年に久保田万太郎と対面したことで内田誠の下で働くことになり、配属先の資料として前年から「スヰート」を手にしていたのだろうと推測している。下線が引いてあるのは『御馳走帖』所収の文章、やっぱり『御馳走帖』には戸板康二在籍時代の「スヰート」がまんべんなく反映されているといえそうで、前々からの目論見があたっていたのも嬉しかった。右の矢印は収録されている単行本、初版本とは言わないからせめて旺文社文庫が欲しいなあと将来の古本買いの夢が広がるのだった。■ 百間先生がらみで最後にもうひとつ、『新輯内田百間全集』をめくって、昭和14年9月20日に明治製菓講堂の「東京明治倶楽部講演会」にて内田百間の講演があったということを初めて知って胸が躍った。演題は「目と耳の境界」で、速記は『百間座談』(三省堂、昭和16年)に収録された。と、この講演、戸板さんも聴いていたに違いなく、年譜に追加した。昭和14年、戸板康二は明治製菓に入社して「スヰート」の編集に携わって、さまざまな人物と交流することになって、内田誠のもとで「いとう句会」にも初出席している。入社直後には藤木秀吉が急逝していて、その遺稿集の編集の仕事をしていたのもこの時期だ。……などなど、「私製・戸板康二年譜」制作でもっていろいろと思いをめぐらせている。多分に自己満足ではあるけれども。
#037
戸板康二文庫のデータベース化(18, April. 2004)
■ 戸板康二が「学恩の大先輩」と呼ぶ藤木秀吉(→ click)は戸板康二を読み始めた当初からずっと気になっていた人物で、去年にその遺稿集『武蔵屋本考』を手にしたことでますますヒートアップ、まだまだ追求したいところなのだったが、その藤木さんの「いもづる」で、このところちょこまかと興奮中。
■ きっかけは、「sumus」のサイトに掲載の林哲夫さんによる「daily sumus」に今年3月、藤木秀吉の名前が突然登場したこと。内容は、雑誌「読書感興」2号(双雅房、昭和11年4月号)に掲載の「丸屋善七失踪」というタイトルの藤木秀吉の文章がとても面白いというもので、この文章、『武蔵屋本考』にもしっかり収録されているので、あらためてじっくり読み返してみた。藤木秀吉が丸善のことに詳しくなったのは追求していた武蔵屋本の版元が丸善の傍流だからで、武蔵屋本研究の余滴だった。
■ と、あらためて読み返してみて、《筆者が知る限りに於て、武蔵屋本の刊行に関して記述された文献は、内田魯庵氏によって遺されたものがあるのみである。》というふうにして、藤木秀吉が内田魯庵の名前を出していることに初めてハッとなった。それから、『武蔵屋本考』に収録されているいくつかの古書随筆の初出は「学鐙」だったり「書物展望」だったり「読書感興」だったりで、内田魯庵がかつて編集長を勤めていた丸善の雑誌、斎藤昌三の書物展望、書物展望と袂を分かった双雅房の雑誌となっているということにもワクワクだった。と、まあそれだけのことなのだけれども、『武蔵屋本考』を手にした当初は、藤木さんの文章の初出まで気をつけて見ていなかったから、そのことに気付かされただけでも大収穫。
■ 藤木秀吉と戸板康二は昭和9年の春に阪神間で初対面しているのだが、その年の秋に早くも藤木さんは関西を引き払って東京に戻っている。なので、戸板青年が藤木さんの書斎を自由に使わせてもらった期間は昭和9年秋から藤木氏の急逝する昭和14年4月の間ということになる。翌年の昭和10年から、戸板康二は水木京太のすすめで「三田文学」で劇評を書くようになった。水木京太は昭和5年から21年まで、丸善の「学鐙」の編集長をしていた。戸板さんは時々日本橋の丸善の別館に遊びに行っていて、その際、水木京太は「この椅子は魯庵がすわっていた椅子なんだよ、いっぺんすわってごらんよ」と得意げに言っていたといたという。戸板さんはそのことを藤木秀吉に伝えていたに違いなく、水木京太も藤木秀吉のことを知っていたに違いないと思う。
■ 水木京太は戸板康二に「三田文学」に劇評を書かせた人物ということで長らくわたしの心に刻まれていたのだったが、水木京太が戸板康二の名前を知ったのは何がきっかけだったのだろうと思いを巡らせてみると、池田弥三郎の『わが戦後』によると戸板康二が予科3年のときに「三田歌舞伎」に連載していた原稿を池田大伍や高橋誠一郎も注目していたということだったから、「戸板康二」という名前が慶応人脈のなかで次第に聞こえていったということにあるのだと思う。が、もしかしたら、藤木秀吉と水木京太の間で戸板青年のことが話題になって、藤木秀吉が戸板青年を推薦したということもあったかもしれない。これは限りなく妄想に近い推測ではあるけれども。しかし、予科3年になる直前に藤木秀吉と出会って、藤木さんとおしゃべりに興じたり藤木さんの本を見せてもらったりしたことでますます鼓舞されて「演芸画報」の公募論文で菊五郎論が当選したり、「三田歌舞伎」(これは予科時代に所属していた歌舞伎研究会の機関誌?)に文章を連載したり、なんてことになったことは確実だと思う。ますます、藤木秀吉という存在がずっしりとのしかかってくる。予科3年だった昭和9年というと、この年の「鏡獅子」が菊五郎生涯の絶頂だった、というようなことを戸板さんが書いていたことを思い出す。18歳の戸板康二はこの「鏡獅子」を何回ぐらい見たのだろう。
■ いろいろと書き連ねてしまったけけれども、藤木秀吉とその若き書斎の友・戸板康二の交流のなかには「丸善」がある。まずは、このことにしみじみと感じ入ってしまうものがあって、藤木秀吉と戸板康二を取り巻くことがいろいろなことにつながってゆく。藤木秀吉という存在がますます輝きを放ってきて、『武蔵屋本考』という1冊の書物を手にちょっとクラクラしている。
■ 内田魯庵の周辺に集った多くの書物好きの一人、斎藤昌三が書物展望社を設立して、雑誌「書物展望」を創刊したのが昭和6年7月、そのメンバーのひとりだった岩本和三郎は在社中に双雅房の前身である文体社を設立、文体社の名での単行本刊行は横光利一著『花花』(昭和8年10月)以下全11冊、書物展望を離れてからは双雅房を名乗り、久保田万太郎『夜光虫』(昭和10年7月)が最初で以下、鏑木清方『絵具宮』(昭和19年4月)まで計31冊の書物を出版している(参考文献:今村秀太郎『双雅房本ほか』古通豆本47)。前々から双雅房に興味津々だったのだけれども、今までは、社主の岩本和三郎が内田誠と懇意で、久保田万太郎も内田誠の紹介で岩本和三郎と知り合って数々の美しい本が出版されることになったという事実に注目していたに過ぎず、ただ単に「いとう句会」つながり! とひとりで盛り上がっていたのだった。それから、岩本和三郎の名は、去年初めて手にとった岩佐東一郎の本にも登場していることにも胸が躍った。と、わたしの頭のなかでぼんやりと思いを巡らせていた双雅房と戸板康二をとりまく人物誌にあらたに藤木秀吉の名前を加えることができそうで、ますますワクワク。岩本和三郎はいよいよ空襲が激しくなったときに阿佐ヶ谷の自宅から疎開先へ荷物を運搬中に心臓麻痺で急逝したとのこと。ほぼ10年間の双雅房の活動は、そのまま戸板康二の青年期と重なる。
■ 『武蔵屋本考』の序文に、こんな一節がある。
故人は恐らく未定稿のノートを日々卓上に眺めながら、時々補筆して楽しんで居たのであろうから、未定稿の出版を喜ばぬかも知れぬが、一面には、藤木秀吉稿として古本随筆集とでも題された自著が上梓されることを密かに期待して居たかも知れぬ。否、居たと思われる点も戸板君の記憶に存する由である。たしかに、『武蔵屋本考』のいくつかの古書随筆の並びを見るにつけ、藤木さんがもっと長生きをしていたらきっといい感じの古書随筆集を出していたに違いないなアと思う。双雅房での出版がいかにも似つかわしい。そんな空想をするのもたのしい。
■ さてさて、藤木秀吉の『武蔵屋本考』のことで、もうひとつびっくりだったことがあった。図書館で借りた古本エッセイのアンソロジー、高橋輝次編『古本漁りの魅惑』(東京書籍、2000年)になんと! 『武蔵屋本考』所収の「『歌舞伎』の合本」が収められていたのだ。藤木秀吉の『武蔵屋本考』が貴重な古書随筆集として、きちんと認識されていたことがなんとも嬉しかった。装画が林哲夫さんのこのアンソロジー、戸板康二の「署名本」(『午後六時十五分』[*] 所収)も収録されている。このほかにもなにかと秀逸な構成になっていて、この本の編者の高橋輝次さんは、創元社のサイトの「こちら編集部」でとても面白い古書エッセイを連載されている。このサイトの存在は実は林哲夫さんの「daily sumus」で知った。やっぱり「sumus」周辺を眺めているといろいろとおもしろいなアと思う。藤木秀吉と戸板康二の初対面の舞台が関西だったことは、とても鮮烈なことだったとわたしはかねがね思っている。そんなわけで、関西初のリトルマガジンを機に、ますます藤木秀吉のことで盛り上がる、という成りゆきがとても嬉しい。
■ 『古本漁りの魅惑』に収録されている、藤木秀吉の「『歌舞伎』の合本」という文章はあらめためてじっくりと読み返してみると、やっぱりとても面白い。三木竹二が主宰、その死後は伊原青々園が引き継いだ「歌舞伎」全175号の合本はおよそ二十五、六巻、神保町のとある古本屋の高い棚にずらりと並んでいた。濃緑の総布のあっさりとした装幀もいい感じの金文字が眩しい美本を上京のたびに見に行くこと数年、昭和9年秋に東京に戻ったのを機に今こそ! と、神保町に馳せ参じてみると、なんということだ、棚から消えている! 店員に確認したところ一週間前に売れたのだという。そして、よくよく聞いてみると、買い取ったのはほかでもない新派の柳永二郎、のちに会う機会があって聞いたところ、柳永二郎も藤木秀吉と同じように、数年来神保町のK書店に通い詰めたあげく念願かなってやっと手に入れたのだという。……と、まあこんな感じの内容で、頬が緩む。ちなみに、本好きで学究肌でもあった柳永二郎は、『演芸画報・人物誌』[*] 刊行の折に長い手紙を送って戸板さんの仕事を評価したとのことで、とにかくもいろいろとつながる。
■ 昭和14年の藤木秀吉の死後、戸板康二は形見として「歌舞伎新報」と「歌舞伎」の合本を贈られたということだから、のちに藤木氏は宿願かなって「歌舞伎」の合本を入手したらしい。串田孫一の同人誌「冬夏」昭和16年3月号の鴎外特集号に早くも「森鴎外と三木竹二と」という論文を執筆している戸板康二、藤木さんの形見をそれこそ何度も何度もひもといたことだろう。この本が藤木さんの書斎にあった頃から何度も何度もひもといていたのだろう。というわけで、戸板康二を読むようになったまなしから気になっている三木竹二にもますます注目なのだった。
■ と、そんなことを思ううちにパッとひらめいたのが、戸板さんが所蔵していた「歌舞伎」の合本は、今どうなっているのかということ。矢野誠一さんの『戸板康二の歳月』のことを思い出した。1994年3月27日、当世子夫人より蔵書の整理をするので欲しいものがあったら取りにくるようにとのお話を受けて、洗足の戸板家を訪問した矢野誠一さん、結局、矢野さんは花柳章太郎の全著作と講談社の豪華本『中村勘三郎』等、同行の人々は歌右衛門の写真集と武智鉄二の全集、黙阿弥の全集などを引き取ったという。……と、なんともうらやましい話で、生前の戸板さんに尽くした方々への絶好の贈り物だったことだろう。なので、「歌舞伎新報」も「歌舞伎」も、このときの形見分けの際にどなたかの手にわたったに違いない。
■ というようなことを思っているうちに次にパッと思い出したのが、戸板女子短大図書館の「戸板康二文庫」のこと。祖母の戸板関子が始めた学校が規模を広げたものが現在の戸板学園で、膨大な蔵書整理の一貫として生前から戸板康二の蔵書が寄贈され、学生が自由に閲覧できる「戸板康二文庫」なるコーナーが設立されていた。この「戸板文庫」の存在はかなり前から注目していて、一度見学に行かねばと思いつつもずっと機会を逸していた。ちょっと前にウェブをチェックしてみたら、以前は八王子にあった雑誌類がすべて三田キャンパスへ移管されている最中で、移管は今年4月に完了するとのことだったので、「戸板文庫」に行くとしたら4月になるのを待った方が吉と思っていた矢先だった。…とまあ、「歌舞伎」の合本、もしかしたら戸板短大の図書館にあったりするのかも、どんな資料があるかの紹介文はあったかしらと軽い気持ちで、ひさびさに戸板女子短大の図書館のウェブを見てみることにした。そして、びっくり! 実は今まであまりきちんとチェックしていなかった戸板短大の図書館だったのだけれども、よくよく見てみると、OPAC で蔵書検索ができるのみならず「配架場所」別の検索もできるというたいへんすぐれた仕組みになっていて、戸板康二関係では、「戸板文庫」「戸板文庫署」「戸板康二著書」というふうに絞り込み検索ができるようになっている。要するに、「戸板文庫」はきちんとデータベース化されているのみならず、ウェブ検索も自由にできるということなのだった。つまり、生前に戸板康二の書庫にどんな本があったのかをウェブ検索でいつでもどこでも大まかに知ることができるということ。これはすごいことではないだろうか。説明書きがないので推測ではあるけれども、「戸板文庫署」という項目は、戸板文庫の蔵書のうち署名本に限って検索ができるということだと思う。戸板康二が直接署名をしてもらったということもあるだろうし、著者献呈本として戸板さんのもとに届いたということもあるだろう、ということは、「戸板文庫署」で限定することで戸板康二の生前の交流の一端もうかがえるというわけで、これはとにかくすごい! と、思わぬ大発見となってしまった。今まで気づかずにいたなんてとんだドジだったけれども、藤木秀吉の「歌舞伎」の合本を機にひょいと今回知ることになって、天国の藤木さんの魔法の杖かもしれない、とまたもやオカルトチックなことを思ってしまったくらい、興奮した。
■ で、ためしにいろいろと検索してみて、ひとたび検索を始めるとハマってしまって大変大変。たとえば、内田百間の署名本を検索してみると、前回の制作ノートに書いたような「スヰート」初出のエッセイが収録されてある単行本がヒットしたりする。明治製菓宣伝部勤務時代に刊行された百間先生の本がいくつかヒットして、これらの本、百間先生の原稿を受け取る際に署名をお願いしたのか、それとも百間先生からプレゼントされたのかと想像するのもたのしい。折口信夫、久保田万太郎、などなど、いろいろ検索して、徳川夢声の署名本も6冊所有している。獅子文六だと、昭和26年発行の『自由学校』だけなぜか署名本で、この『自由学校』、小穴隆一装幀のなかなか愛らしい本、ささま書店で裸本で見つけて安く買ったのがわたしの獅子文六読み始めだったなあと個人的な感慨にもひたったり。武智鉄二で検索すると、昭和44年発行の学芸書林版の『かりの翅』だけ署名本で、わたしもおんなじ本のおなじく署名本、ついこの間入手したばかり。序文に戸板さんの名前が登場するので、著者献呈本なのだと思うとニンマリ。そして、前回の制作ノートで言及した、「スヰート」編集部での同僚、香取任平の『花鳥亭日記』もきちんと戸板さん所蔵していた。自費出版らしいこの本、戸板さんのもとにも贈られていたのだ。意外な著者を探してみたりするのもたのしい。そして、涙が出るほど大感激だったのが、都筑道夫の著書を結構たくさん所蔵していたこと。『退職刑事』もあるわよ! と、大喜びだった。やっぱり戸板さんは都筑道夫のミステリーが大好きだったのだ、都筑道夫のかっこいい垢抜けした洒落たミステリーのファンだったのだ。……と、細かく書いていくとキリがないけれども、これから先、いろいろと検索することでまだまだ新発見はありそうな気がする。
■ 図書館に直接問い合わせたわけではないので、今のところ詳細は不確かだけれども、上記の矢野誠一さんの本にあったような形見分けが終わったあと、もしかしたら戸板さんの蔵書はすべて「戸板文庫」の方に寄贈されたのかなという気もする。どうなのだろう。それから、雑誌がまだデータベース化されていないようなのだけれども、もしかしたら「スヰート」もあるのかしら! などなど、夢はふくらむばかり。「戸板文庫」の目録冊子などは存在するのだろうか。これも気になるところ。それにしても、戸板さんの親戚が学校で、「戸板文庫」が設立されていたこと、これはかえすがえすも幸運なことだった。戸板さんはずいぶん前から蔵書を寄贈されていて、古本屋に処分ということはしていなかったようなので、その蔵書の様子がかなり鮮明に伺えるのは本当にすごいことだ。
■ 制作ノートがだらだらと長くなってしまった。今回書き連ねたいくつかのことに関しては、今後もっと追求していきたいところで、まずはその手始めとして。
■ 今回の更新は、Chronology【私製・戸板康二年譜 1915-1993】に、先日読み返した『ハンカチの鼠』[*] で「おっ」となったところをいくつか追加した。そして、今月、学陽書房の人物文庫として『ぜいたく列伝』が刊行されている。『ぜいたく列伝』のことは次回の制作ノートでちょっとだけ特集するつもり。今回のところは、Amazon.co.jp でこしらえている新刊書店に並んでいる戸板康二の著書を改訂。
← PREV | NEXT →