#034
長谷川四兄弟と戸板康二(17, February. 2004)
■ References【戸板康二を語る人びと・レファレンス】を更新。
■ 前回の制作ノートで、2003年のわが戸板康二道を一通り振り返ってみたものの、1番の大きな出来事はなんといっても、没後10年に際して、季刊誌「BOOKISH」第6号で戸板康二特集が制作されたことだった。前々からのお知り合い、金子拓氏が「BOOKISH」に創刊号から関わっていらして、次号はなななんと戸板康二の特集だてんで、「戸板康二ダイジェスト」を作っているよしみで、それまでは読者の一人だった「BOOKISH」の誌面のお仲間に入れていただいた次第だった。まったく世の中なにが起こるかわからない。……といったような、わたくし執筆のまとまらない紹介文を、「BOOKISH」のウェブサイトに現在載せていただいているので、詳細はこちらにて、ひとまず。 ウェブサイトで購入できますので、この機会に「BOOKISH」をぜひともお買い求め下さいませ。ぜひぜひ! そしてご意見・ご感想などをお寄せいただければこれにまさる喜びはございません。と、宣伝しつつ、「BOOKISH」第6号《特集・戸板康二への招待》を、References【戸板康二を語る人びと・レファレンス】に項目追加。きちんと詳細を記したいところであるが、今回のところは項目追加にとどめておいた。もうちょっと時間がたってから、もうちょっと客観的に見られるようになってから、少しずつ何かしていきたいなアと思う。うむ。
■ References【戸板康二を語る人びと・レファレンス】の更新はあともう1箇所。先月、『歌舞伎への招待』[*] が初版から50年以上の歳月を経て、岩波現代文庫として文字通り現代によみがえった。その岩波現代文庫の『歌舞伎への招待』[*] の感激にいつまでもひたっていた1月下旬のある日、とある図書館でなんとはなしに現在目下刊行中の『決定版三島由紀夫全集』の評論篇を繰っていたら、なんというグッドタイミング、三島による『歌舞伎への招待』の書評を発見! 今まで三島由紀夫の戸板康二への書評は『歌舞伎の周囲』[*] を知るのみだったので狂喜乱舞だった。さっそく、三島由紀夫の項に、今回あらたに見つけた『歌舞伎への招待』と『歌舞伎ダイジェスト』への書評を書き写し。これら3篇の書評を読んで、昭和20年代の戸板康二にあらためてグッとなった。
■ 戸板康二に急速に夢中になったのは『歌舞伎への招待』を読んだことがきっかけだった。『歌舞伎への招待』を初めて手にしたのは、歌舞伎座に通うようになって1年くらいたってからだった。歌舞伎座に毎月通うようになったのは、昭和23年の「暮しの手帖」の『歌舞伎ダイジェスト』で初めて戸板さんの名前を知って初めて戸板さんの文章を見て急に鼓舞されたのがそもそもの発端だった。『歌舞伎への招待』を手にしたのは六代目菊五郎没後50年の1999年の夏、それから急速に戸板康二に夢中になって、はじめは昭和20年代の歌舞伎書ばかり読んでいて、次第にエッセイ、人物誌などを知って、戸板康二の全仕事に夢中になっていった。……というようなことはこれまでしつこく何度も書いていることであるけれども、戸板康二道まっただ中の現在、戸板さんの本は全部好きだけれども、一番思い入れが強い戸板さんの仕事は何かというと、たくさんの著書を何度も読み返している今でもやっぱり昭和20年代の歌舞伎だし、昭和20年代の歌舞伎を知らずに他の多くの魅惑的な書物、「達意」の筆で綴られた文章に親しんでいたとしたらと仮定してみても、昭和20年代の仕事を知らなかったらこれほどまでに激しく戸板康二に夢中になることはなかったに違いないと確信している。と、昭和20年代の戸板康二には格別の思い入れがあり、そのきっかけとなった『歌舞伎への招待』はまさしく三島由紀夫が書くように「熱烈な愉しさをもつ誘惑の書」、そしてそれは歌舞伎だけではなくて、わたしにとっては、戸板康二そのものへの「招待の書である以上に誘惑の書」だった。
■ それにつけてもニンマリなのが、三島が『歌舞伎への招待』のことを《尤もこの本には、著者がお髭を生やして大先生に納れられた暁、自ら苦笑されるかもしれない個所がないではない》と書いているくだり。これほどの名著の『歌舞伎への招待』、多くの人が影響を受けたとしている『歌舞伎への招待』、戸板康二の著書でひとつ挙げるとすれば最初にくるであろう『歌舞伎への招待』、生前の戸板さんはずっと再刊を拒んでいたという。『あの人この人』[*] の「花森安治のスカート」では、《いま読むと、若い時なりの感傷や抱負を体した文章が気恥ずかしくもあるのだが、その前にこの本ばかりは、暮しの手帖社のために書き、その社のおかげだといつも恩に着ている心持を貫きたかったためだ。》というふうに書いている。その「若い時なりの感傷や抱負」が昭和20年代の戸板さんの文章のたまらない魅力なのであるけれども。
■ 戸板康二に夢中になったきっかけの書物ということで、『歌舞伎への招待』がもっとも思い入れの強い本なのであるが、これとは別に激しく偏愛しているのが『六代目菊五郎』(昭和30年)[*] 。ペラペラとめくって、ちょいと読み返してみるだけで、いつも胸がキューンとなり目頭がツーンとなる。『六代目菊五郎』に目頭がツーンとなるのは、書いてある内容やその文体のみならず、この著書が、昭和20年代の一連の仕事の総決算的なところがあって、それから先の戸板康二とのひとつの分岐点となっているからなのだろうとぼんやりと思っている。なので、本の内容や文章そのものにひたりきっているのと同時に、「昭和20年代の戸板康二」がひとまずここで終わっているのをひしひしと感じることで、昭和20年代の戸板康二を知って戸板康二に魅了されていった当時の甘美な日々のことを思い出すという個人的感慨がいつもどうしてもつきまとうのだった。講談社文庫版 [*] の解説は、この本の執筆を依頼した利倉幸一によるもの。戦後まもない時期、戸板康二、大江良太郎、安藤鶴夫の4人でよく会って、会えば必ず菊五郎の話をしていたというくだりがある。安藤鶴夫が「どうして、僕たちは会えば六代目のことばかり話し合うのだろう」と言ったという。みんな大好き菊五郎、「菊五郎歌舞伎」という語彙で歌舞伎評論の仕事をしていた戸板さんだって菊五郎が好きで好きでたまらなかった。利倉幸一はそのものズバリ、『六代目菊五郎』のことを《戸板康二の「青春の書」という感じもする。》というふうに書いている。その言葉をあえて借りると、『六代目菊五郎』の通奏低音は「青春との決別」というようなものであり、それが『六代目菊五郎』全体を覆うある種の感傷となっている、気がする。
■ あとがきによると、『六代目菊五郎』は書き下ろしとして執筆されたもので、利倉幸一が戸板さんに依頼したのが昭和30年8月、この間に中国を訪問したことで中断して、脱稿は12月下旬だったという。と、昭和30年に書かれたということもなにかと象徴的だ。やっぱりこのあたりが戸板康二の文筆生活のひとつの分岐点なのだ。昭和20年代の戸板康二に思い入れたっぷりである一方、昭和30年代以降の戸板康二の円熟と洗練のなんとまあ魅惑的であることだろうといつだって胸が躍る。昭和30年は「銀座百点」が創刊された年、戸板さんは早々にその誌面に登場することとなって、第7号では名篇「銀座の書割」(『ハンカチの鼠』 [*] 所収)を寄せ、次の第8号より「演劇合評会」が始まる。車谷弘が実質的な編集長だった「銀座百点」に戸板さんが登場したのは久保田万太郎人脈があったからこそなので、戸板康二の「銀座百点」はもちろんそれまでの文筆生活の延長線上に位置している。しかし、「BOOKISH」第6号の児玉竜一氏の文章の結びにある通りに、《戸板康二は、時に会い、それを活かす名人でもあった。》、とにもかくにも、希代の文人・戸板康二誕生の格好の舞台装置が「銀座百点」だった。そして、戸板さんの「銀座百点」登場は、戸板さんが書斎で『六代目菊五郎』を執筆しているのと同時期の出来事だった。
■ 「BOOKISH」の戸板康二特集号と岩波現代文庫の『歌舞伎への招待』にソワソワするあまり、またもや更新が1ヶ月以上も滞ってしまった戸板康二ダイジェストではあるけれども(本来は週刊を目指している、らしい)、「BOOKISH」と岩波現代文庫と三島由紀夫の書評のほかにも、嬉しいことがたくさんあった。収拾がつかないくらいに。一番嬉しかったことは、犬丸治さんのページにて資料・「銀座百点」と戸板康二が公開されたこと。
■ List【戸板康二・全著書リスト】に、『歌舞伎への招待』(岩波現代文庫、平成16年)[*] 、『奈落殺人事件』(文藝春秋新社、昭和35年)[*] 、『歌舞伎題名絵とき』(駸々堂、昭和60年)[*] の書誌データを追加。
■ Chronology【私製・戸板康二年譜 1915-1993】に追加と訂正をいくつか。
■ 2004年の初古本は、木山捷平の『酔いざめ日記』(講談社、昭和50年)だった。この本を手にとってまっさきにしたことは「文壇句会」さがし。と、『酔いざめ日記』を読んで急に鼓舞されて、『句会で会った人』[*] を読み返して、さる図書館へ出かけて、「別冊文藝春秋」よりせっせと「文壇句会」の記事を仕入れた。戸板さんの「文壇句会」初登場は昭和35年3月(「別冊文藝春秋」第71号)、昭和39年12月(「別冊文藝春秋」第90号)をもって「文壇句会」の記事は終了していて、これが最後の文壇句会なのかな、戸板さん見事1等賞。現時点では「別冊文藝春秋」第70号から第90号までの記事をせっせと収集したのみで、まだまだ「文壇句会」に関しては調査中の段階。とりあえず、今回のところは、年譜に「文壇句会」参加の記録を追加した。戸板さんが「文壇句会」に初参加した昭和35年は、直木賞を受賞した年。先月入手してさっそく読みふけった『奈落殺人事件』[*] に収録されているのは、昭和35年初頭の直木賞受賞をうけてこの年に断続的に発表された諸短篇だったので、昭和30年代の油が乗り切った戸板康二の活躍ぶりにあらためて心を躍らすこととなって、ますます昭和30年代の戸板康二に考えをめぐらすこととなった。
■ 『句会で会った人』では「文壇句会」の方が目次が先になっているけれども、参加そのものは「銀座百点忘年句会」の方が早い。「文壇句会」に参加したのは直木賞がひとつのきっかけなのだと思うけれども、車谷弘が活躍していた「銀座百点」での人脈もあったのだと思う。そして、「文壇句会」は昭和39年に終わってしまっているけれども、「銀座百点忘年句会」の方はは現在も続いていて、その伝統は今も健在。最新号(2004年2月号)に掲載の去年12月の句会でも矢野誠一、小沢昭一などなど、実に魅惑的面々であった。その「銀座百点忘年句会」、戸板さん最後の出席は死の1カ月前の平成4年12月であるので、終生関わっていたといってよい。とにもかくにも、昭和30年1月に創刊された「銀座百点」! と、「銀座百点」に本格的に取り組まねばならぬのだったが、犬丸治さんのページにて資料・「銀座百点」と戸板康二が公開されたことで、ますます大興奮なのだった。《「戸板康二・人物誌」の可能性》という一節を前に、わたしの2004年の戸板道も本格的にスタートさせたいなアと急に張り切ってしまった。
■ 先月、洲之内徹の新刊『芸術随想 おいてけぼり』(世界文化社)が発売になった。この本の冒頭に、長谷川りん次郎の《薔薇》というタイトルの絵があって、昭和13年に描かれたこの絵、もとは明治製菓の PR 誌「スヰート」の表紙画だったというからびっくりだった。洲之内徹の「気まぐれ美術館」の第1号は、「スヰート」の長谷川りん二郎の表紙画だった! 『思い出す顔』[*] によると、「スヰート」の表紙画はほとんど内田誠のポケットマネーで買い取られたとのことなので、この《薔薇》ももとは内田誠のもとにあった可能性大だ。洲之内はこの絵を《画商らしきものになって間もないころ、ある日、神田へ額縁を探しに行き、通りがかりの古道具屋へはいったら、のきの裏側の薄暗いところにこの絵がかかっていた。値段は私のほうでつけた。絵の値段としてではなく、額縁の値段だったが、主人は大喜びで、絵はおまけにしてくれた。》という経緯で入手することとなった。戸板康二が編集部に入る1年前の「スヰート」の表紙を飾った《薔薇》がめぐりめぐって洲之内の手元に来ることとなったなんて! と、胸が躍りまくりだった。「画商らしきものになって間もないころ」というから、それは昭和34年から35年頃のことだ。
■ それから、内田誠の著書、『浅黄裏』(文体社、昭和10年)と『喫茶卓』(双雅房、昭和11年)を手に入れることが出来た。この2冊に関しては、戸板さんが『思い出す顔』で《学生時代に自由に書斎へ出入りさせてもらったという意味で、いわば学恩をこうむった藤木秀吉氏の本棚にあった「浅黄裏」「喫茶卓」という随筆集を読み、著者の内田誠の名を知っていたのだが、……》と書いているので、藤木さんの書棚の本が一気に2冊もわたしの書棚に! と、嬉しさはひとしおだった。そして、その『浅黄裏』にも、長谷川りん二郎の絵画のカラー図版があった。長谷川4兄弟の次男のりん二郎、『思い出す顔』に、明治製菓宣伝部にて内田誠の脇に控えていた人物として登場している「長老で、相馬社長の自伝の編集をしたりする、おしゃれな香取任平氏」の妹が長谷川海太郎(筆名:牧逸馬、林不忘、谷譲次)の夫人だったというくだりがあるので、その人脈でもってりん二郎の絵が「スヰート」の表紙画になったのだろう。そして、自分の随筆集に載せているところを見ると内田誠お気に入りの画家だったに違いない。と、魅惑的なくだり目白押しの、「スヰート」や内田誠をとりまくあれこれに関しても、まだまだ調査中の段階。
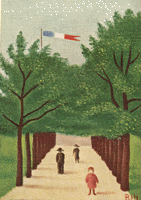
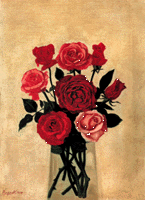
|
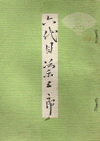 ■ 最後は、2004年初の奥村書店行きのことを。初芝居の約1週間後の3連休、チケットをお譲りいただいてわーいわーいと『九段目』再見に出かけた帰り道に奥村書店に寄った。そのときの買物が、昭和56年5月の六代目菊五郎33回忌追善興行の記念として歌舞伎座で制作された非売品の『六代目菊五郎』なる冊子。いかにも「配布された」という感じの粗末なナリではあるものの、内容は昭和25年に改造社より刊行の豪華写真集『六世尾上菊五郎』から「舞踊の極め付き」を抜粋して舞踊の解説と木村伊兵衛の写真を載せたもの、冒頭には戸板さんの「六代目菊五郎のおどり」という短文がある。タイトルが戸板さん直筆の文字はあしらってあるのが嬉しい。と、ペラペラと立ち読みして、『船弁慶』の後ジテの写真が目に入った瞬間、ふらふらっと衝動買いして、次なる目的地に向かう日比谷線の車中にてずっと眺めていた。
■ 最後は、2004年初の奥村書店行きのことを。初芝居の約1週間後の3連休、チケットをお譲りいただいてわーいわーいと『九段目』再見に出かけた帰り道に奥村書店に寄った。そのときの買物が、昭和56年5月の六代目菊五郎33回忌追善興行の記念として歌舞伎座で制作された非売品の『六代目菊五郎』なる冊子。いかにも「配布された」という感じの粗末なナリではあるものの、内容は昭和25年に改造社より刊行の豪華写真集『六世尾上菊五郎』から「舞踊の極め付き」を抜粋して舞踊の解説と木村伊兵衛の写真を載せたもの、冒頭には戸板さんの「六代目菊五郎のおどり」という短文がある。タイトルが戸板さん直筆の文字はあしらってあるのが嬉しい。と、ペラペラと立ち読みして、『船弁慶』の後ジテの写真が目に入った瞬間、ふらふらっと衝動買いして、次なる目的地に向かう日比谷線の車中にてずっと眺めていた。■ とかなんとか、「文壇句会」と『奈落殺人事件』、そして「銀座百点」とで、戸板康二の昭和30年代が今とっても熱い! それから「スヰート」や「いとう句会」をとりまくあれこれも気にかかり、その一方で、いつもたえず六代目菊五郎、そして昭和20年代の戸板康二のことが心にベタリと貼り付いている。……などと、あいかわらず焦点の定まらぬ戸板康二道であった。うむ。しかし、ひとつだけたしかなのは、戸板康二道はますます面白いということ。
← PREV | NEXT →