#030
『あの人この人』と『久保田万太郎』(02, December. 2003)
■ さる方から教えていただいて、今月号の「演劇界」、富十郎の『船弁慶』が表紙の「演劇界」の山川静夫さんの随筆に目を通して知ったところによると、来年1月に岩波現代文庫で『歌舞伎への招待』[*] が復刊されるという。山川さんも書いていた通りに、新年早々に手にすることになるであろう来月の岩波現代文庫は、まさしく戸板さんからの賀状。無事に今月を乗り切って、晴れ晴れと新年を迎えたいと切に思う。それにしても、夢のようだ。『歌舞伎への招待』はわたしにとっては戸板康二に夢中になるきっかけになったもっとも思い入れの強い書物。そのゆくたては、Special【「暮しの手帖」創刊号の戸板康二】に以前書いたことがあるけれども、またいずれ、『歌舞伎への招待』についてじっくり考え直したいと思っている。
■ ひさしぶりの更新になってしまった。この1ヶ月更新をさぼって何をしていたのかというと、まあ、いろいろ本を入手していたのだった。
■ List【戸板康二・全著書リスト】に、『あの人この人 昭和人物誌』(文藝春秋)[*] と『久保田万太郎』(文藝春秋)[*] の書誌データを追加。
■ いずれも文春文庫版をずっと前から持っていて、いずれもとびきりの愛読書。もう何度読み返したかわからないくらい。何度も文庫本棚から取り出していはいたものの、そのたびに本棚に文庫本が無計画に詰め込んであるため発見するのに時間がかかったり雪崩を起したりすることが多かった。単行本だったらすぐに取りだせるのに。というわけで、ふつふつと単行本も揃えておきたいという気運が盛り上がって久しかったのだった。
■ 『あの人この人 昭和人物誌』(文藝春秋)[*] は、思いもしなかった方から思いもしなかった場所で思いもしなかった展開でいただいたもの。ジーン。この本はわが戸板康二道において、きわめてエポックメイキングな本のような気がしている。
■ つい回顧モードになってしまう。ここでもう一度、わが戸板康二道を振り返ってみることにすると、わたしが戸板康二の名前を知ったのは、戸板康二没後5年の1998年、花森安治と「暮しの手帖」に興味を抱いて、昭和20年代の「暮しの手帖」を閲覧したときのこと(場所は暮しの手帖社別館、今はない)。歌舞伎にそんなには関心がなかった当時のわたしが読んでなぜだか心惹かれた「歌舞伎ダイジェスト」という連載が、「暮しの手帖」創刊号からあった。横で見ていた母が「あら、戸板康二」と言った。当時その名を知らなかった戸板康二、母によると、歌舞伎だとこの人という感じの大御所的な人だという。うーむ、そうであったか。そんな大御所的な人だって「暮しの手帖」創刊当時の昭和23年においてはまだまだ新進の人だったのだと思う。のちに大御所になる人物に早くも原稿を依頼しているという花森安治の編集者としての才覚! と、当時はそのことにまず感じ入ってしまうものがあった。
■ それにしても「歌舞伎ダイジェスト」になぜそうも心惹かれたのだろう。初めて目にしたのは『助六』について綴ったページだった。文末の《花川戸助六とシラノ・ド・ベルジュラックとは、東西あくたいの双璧ともいうべきである。》という一節に参ってしまったのか、各トピックを絶妙に交えてアトランダムに綴るいわゆる「螺旋階段方式」の軽やかな筆致に酔ってしまったのか、「歌舞伎!」という言葉から漂う紋切型イメージからどこまでも自由な新鮮さからなのか、今となってはよくわからないけれども。当時「歌舞伎ダイジェスト」を目にして急に鼓舞されて思わず歌舞伎座にまで行ってしまったくらい、「歌舞伎ダイジェスト」には心惹かれるものがあった。それで急速に歌舞伎に夢中になったのだから、わたしも単純といえば単純だった。その1年後、『歌舞伎への招待』を手にする。本誌の「歌舞伎ダイジェスト」とは別に花森安治の「暮しの手帖」から書き下ろされた本。こんな本があったなんて! と、嬉々と奥村書店で買った。六代目菊五郎没後50年の1999年夏のことだった。以来、詳細は覚えていないけれども、戸板康二の本を次々と読み漁るようになった。いずれも昭和20年代の本ばかりだった。その年の12月、ちくま文庫で『すばらしいセリフ』[*] が出た。翌2000年の初芝居は新之助の『助六』だった。ぺらぺらめくって、「キセルの雨が降るようだ」を目にしてクーッと興奮だった。『すばらしいセリフ』は見たことのある芝居でもない芝居でも、どこを読んでもその筆致がほんわかとしみじみと実によかった。
■ そんなこんなで、戸板康二を読み始めた当初は歌舞伎本、それもわりと初期のものばかりを読んでいた。『折口信夫坐談』[*] とか矢野誠一さんの『戸板康二の歳月』も読んでいたけれども、「ちょっといい話」をはじめとする歌舞伎以外の戸板康二を読むようになるまで、なぜだかわりと時間がかかった。それがある日、通りがかりの本屋さんで文春文庫の『あの人この人』[*] を買った。2000年春のことだったと思う。これを機に一気に戸板康二の人物誌に夢中、『ぜいたく列伝』[*] を次の日に同じ本屋さんで買ったのを覚えている。そのあと、古本屋で戸板康二の本を見つけると必ず買うようになった。旺文社文庫の3冊、『ハンカチの鼠』[*] 、『女優のいる食卓』[*] 、『夜ふけのカルタ』[*] を読んで、文人としての戸板康二にますます親しむようになった。というわけで、戸板康二道が新展開を迎えたのが2000年春のこと、その契機になったのが『あの人この人』 だったという次第。
■ 新たに知った書き手、戸板康二にますます惹かれたのは、矢野誠一さんの『戸板康二の歳月』のおかげだった。『歌舞伎への招待』を知ってわりとすぐ、1999年の残暑のころ、図書館で『折口信夫坐談』と一緒に借りたのを覚えている。その『戸板康二の歳月』の感激が、『あの人この人』を初めて読んだときじんわりと甦ってきた。文春文庫版の解説が矢野誠一さんだったということもあるかも。『あの人この人』は「オール読物」の連載を1冊にまとめたもので、1993年の死で連載は中断している。ということは、死がもっと先だったとしたらこの先どんな人物が登場したのだろうということをつい思ってしまう。矢野誠一さんの解説には、この連載、二ヶ月先の分まで書き溜めてあったという感動的なエピソードがある。とにもかくにも、旺盛な執筆活動のまっただ中で逝った戸板康二、まさしく「みごとな幕ぎれ」であった。『あの人この人』を機に読むようになった書き手、知った本など、芋づるが果てしなくあって、この本を読んだ頃から「戸板康二道」という言葉を心のなかで言い始めるようになったのは確かだ。その意味で、エポックメイキングな1冊なのだった。
■ さて、『久保田万太郎』[*]。久保田万太郎の名前をはっきりと知ったのは、戸板康二の『歌舞伎への招待』を手にしたあとで、すぐに読んだ矢野誠一さんの『戸板康二の歳月』がきっかけだった。それまで名前すらよく把握していなかった。『戸板康二の歳月』の眼目のひとつに、矢野誠一さんによる東京論がある。下町と山の手の対比。そこで語られていたのが久保田万太郎だった。これを読んで以来、なんとなく久保田万太郎のことを心にとめるようになったけれども、読みはじめるまでにはかなり時間がかかった。文春文庫の『久保田万太郎』[*] を買ったときのことはよく覚えている。『あの人この人』を手にして加速度的に戸板康二に夢中になっていった2000年夏のある日のこと、「戸板をさがせ!」と中央線沿い古本屋めぐりに繰り出したときのことだった。中央線古本屋めぐりといっても、根性なしのわたくしのこと、あまりに暑い日だったのですぐに挫折、吉祥寺のあと荻窪に出て、そこでおしまいになった。しかし、いい本を数冊仕入れた。『久保田万太郎』もそのときに買った。荻窪の岩森書店にて200円で売っているのを見つけて、とりあえず買っておいたのだった。
■ 久保田万太郎に親しむようになるのは翌2001年になってから。それまで戸板康二が唯一「親炙」という言葉を使っている久保田万太郎のことが気になってはいたけれども、当時は、そのガラス細工のようなデリケートな美しい東京言葉にかなり取っつきにくさを感じていたのだった。たとえば『大東京繁昌記 下町篇』「雷門以北」などを目にして。それが翌年になって急激に久保田万太郎に親しむようになったのはどういうわけだっただろう。そうそう、歳時記で散見される万太郎の俳句のどれもこれもが素敵だったからだった。まず俳句から入ったのだ。久保田万太郎の俳句について、小沢昭一は「わかりやすいし、共感はわくし、だいいちアカヌケている」というふうに書いている(『句あれば楽あり』朝日文庫)。この言葉に尽きると思う。俳句にほとんど親しんだことない無風流なわたしにとっても、久保田万太郎の俳句のよさはすぐにわかった。わかりやすい、共感しやすい、さらに垢抜けている。永井龍男曰く「繊細な都会句」、誰だってそのよさはすぐにわかる。というわけで、こうしてはいられないと戸板康二の『久保田万太郎』[*] を熟読して、胸がいっぱいになった。ちょいと俳句を垣間見ているだけで万太郎文学にはあまり親しんでいなかった当時のわたしが読んでも、思いっきり堪能した本だった。今でも、戸板康二の本で10冊選ぶとしたら必ず入る名著だと思っている。
■ そして、2001年年末に読んだ中篇小説『春泥』を機に、久保田万太郎に夢中になって現在に至っている。以来、久保田万太郎にイカれている。その間いったい何度、戸板康二の『久保田万太郎』を繰ったことだろう。それから、戸板康二のお父さんの世代の人物誌、たとえば「九九九会」の面々に興味津々になったりとか、本読みの歓びがさらに増殖していった。『あの人この人』と同じ意味で、『久保田万太郎』もわたしにとってはエポックメイキングな1冊なのだった。
■ 去年の12月に万太郎全集全15巻を入手して、本棚の一角は万太郎コーナーになっている。全集だけではなくて、古本屋で(安く)見つけた久保田万太郎の本とか、大江良太郎『家』とか後藤杜三『わが久保田万太郎』といった万太郎文献が並んでいる。『万太郎俳句評釈』[*] もここにある。ここに戸板康二の『久保田万太郎』も並べて、折に触れ参照したいものだなあとずっと思っていた。『久保田万太郎』[*] は文庫本棚に方に行ってしまっていた。と、単行本も欲しいという気運がにわかに高まったのが、ある日の神保町で手に取ったときのこと。とてもきれいな上に値段もお手ごろだった。函をはずしてページを開いてみると、見返しに万太郎直筆の原稿用紙があしらってあったりして、本全体がとても美しい。しかし、文庫本を持っているしなあとなかなか買うまでには至っていなかった。その念願の『久保田万太郎』[*] を先月入手した。
■ 戸板康二が「文学界」誌上に『久保田万太郎』の連載を開始したのが昭和41年、万太郎の三回忌の昭和40年、万太郎の誕生日11月7日における浅草神社の久保田万太郎句碑(竹馬やいろはにほへとちりぢりに)の除幕式から筆を起こしている。三回忌を過ぎてからすぐに書き始められた『久保田万太郎』、その死からわずかしか時間がたっていない。自ら「親炙」したと記す万太郎の評伝を書くということに対する並々ならぬ決意が伺える。そのことにもたいへん感動してしまうものがあった。『久保田万太郎』が文春文庫になったのは昭和58年8月のこと、万太郎没後20年に合わせて文庫化されたようだ。
■ 先月風邪で臥せっていた折に久保田万太郎の句集を眺めて、そのあとでじっくりと『万太郎俳句評釈』[*] を読みふけって、しみじみその名著ぶりに感激していた。この本のよさは一度読んだだけではわからない。折に触れ参照したい座右の書という感じ。そのなかで『青みどろ』に関する記述を見たとたんに、届いていたばかりの石神井書林の目録にあったことを思い出して、いてもたってもいられず思わず申込んでしまったのだった。というのはちょいとウソで、申込む前にどんな本なのか確認しようと図書館に見に行って、いざ現物を目にしてみると、あまりに美しくてとにかくうっとり、さらに巻末には戸板さんのあとがきと安住敦による懇切な解説が付されている、というわけで、わたしの決意は揺るぎないものとなってそのあとで申込んだのだった。いわば風邪で臥せったばっかりに買ってしまった『青みどろ』、思えば因果なことであった。そして同時に『久保田万太郎』初版 [*] を買ったわけで、久保田万太郎を読むようになってそろそろ2年、ますます久保田万太郎にイカれているのだった。
#031
戸板康二解説の文庫本(08, December. 2003)
■ Collection【戸板康二解説の文庫本を探せ!】を整理整頓しました。
■ 毎年年の瀬になると、いままでやり残していた諸々の懸案を片付けようという気運が盛り上がる。と言っても、気運が盛り上がるだけで実行に至ることなく新年を迎えてそのまま日々が過ぎてゆくことの方がずっと多いのだけれども。さて、今年も年の瀬がやって来た。しょうこりもなく今年も各方面の懸案を片付けようという気運が盛り上がっている。これに乗って、戸板康二ダイジェストでもいろいろな懸案を片付けていくとしよう。というわけで、今回の更新では、去年8月に「戸板康二ダイジェスト」が始まってから一度も更新されることなく今日まで来ていたコーナーのひとつ、戸板康二が解説を寄せている文庫本を紹介するページをやっと改訂。
■ 戸板康二に夢中になって、いつのまにか古本屋に足を踏み入れる度になんとはなしに、戸板康二が解説している文庫本を探すようになった。誰が解説を書いているかはページをめくるまでわからない(外に名前があることもあるが)。「もしや戸板康二の解説では?」とほのかに期待してページを繰って、ズバリ的中だったときのよろこびは大きい。と、そんな感じに古本屋で小躍りして購入した文庫本が現時点では17冊、わたしの本棚にある。このコーナーは、そんなわたしの本棚メモというかノートブック的な感じでこしらているもの。実はそんな本棚メモをもうひとつこしらえたいなというところで、これもかねてからの懸案、今年中に出来上がるかどうか。
■ 1年と数カ月ぶりの更新となって、このあいだに新たに見つかった戸板康二解説の文庫本は、関容子『中村勘三郎楽屋ばなし』(文春文庫)と巌谷大四『本のひとこと』(福武文庫)の2冊。いずれも荻窪のささま書店で見つけた。前から存在を知っていて、新たに入手したのは、徳川夢声の『夢声自伝』上中下(講談社文庫)のみ。前にもここに書いたことがあるけれども、その念願の『夢声自伝』を手に入れた直後に、夢声研究家の濱田研吾さんの私家版出版『徳川夢声百話』のことを知って、2冊セットで読みふけって、おかげでわたしにとっての夢声元年はなんとも幸福なひとときで、今年の本読みの白眉のひとつだった。その濱田研吾さんの著書『徳川夢声と出会った』が今月晶文社より刊行予定だという。今、刊行がひたすら待ち遠しい。
#032
濱田研吾さんの『徳川夢声と出会った』(28, December. 2003)
■ Chronology【私製・戸板康二年譜 1915-1993】に追加と訂正をいくつか。
■ 濱田研吾さんの『徳川夢声と出会った』(晶文社)を熟読した直後というタイミングで、長らく探していた、徳川夢声の『夢諦軒 句日誌二十年』(オリオン社、昭和27年)を西荻で発見、さっそく帰りの電車で読みふけった。「句日誌」というタイトル通りに、昭和9年からの自作の句を時系列に並べるのみならず、下欄に句作時の状況が日記風に綴られているので、日記本という趣きもして、たいへん秀逸なつくりになっている。序文で夢声は「いとう句会」のなりたちについて、
……妻の死を考えると、なんともやりきれないので、句作などをして気を紛らわしたのである。さて、こうなると俳句というものを、少しく本式に習いたくなった。で、或る日、内田水中亭宗匠に会った時、ひとつ運座というものを催してくれませんか、と依頼した。よろしい、そのうちやりましょう、と快く引き受けて下さった。それが大分のびて翌春、実現したのが、渋谷「いとう旅館」に於ける集りであった。そして計らずも、これが第一回「いとう句会」となった次第である。というふうに綴っている。戸板康二の明治製菓宣伝部勤務時の直属の上司・内田誠は夢声と府立一中で同級だったという間柄、そして、戸板康二が親炙していた久保田万太郎は昭和9年の「いとう句会」結成当初からの主要なメンバー。『句会で会った人』[*] で、戸板さんは「いとう句会」の成り立ちについて、《「いとう句会」という句会は、内田さんとごく親しかった大場白水郎という同世代の友人と、久保田万太郎先生をかこんではじめたものらしい。》というふうに書いている。成立当初の正確なところはよくわからないけれども、そもそもの発端はどうやら夢声だったようだ。このことを初めてくっきりと『夢諦軒 句日誌二十年』で心に刻むことができた。「俳句の天才」万太郎を中心にしつつ、夢声に高田保、秦豊吉、渋沢秀雄など、ユーモリストが集った運座の気分は、文藝春秋で車谷弘と永井龍男が中心になって催した「文壇句会」にも通じるものがあり、そして戦後、車谷弘の趣味性が色濃く反映した「銀座百点」へと受け継がれることとなる。現在の「東京やなぎ句会」の雰囲気に多分に通じるものがある「いとう句会」、『夢諦軒 句日誌二十年』には、夢声が俳句を始めるきっかけになった「いとう句会」の同人たちによって、寄書き風に文章や絵が寄せられていることで、この本全体がさながら「いとう句会」という感じもして、「いとう句会」研究を志して久しい(と言いつつ、特に何もせず)身としては、無類のよろこび及び刺激にあふれた書物であった。「いとう句会」には戸板康二道のルーツがひそんでいるような気がする。ちなみに、「いとう句会」文献というと、『じふろくささげ いとう句会随筆集』(黄楊書房、昭和23年)という本を、やはり『句会で会った人』で知って買って読んだ。久保田万太郎の前書きが実にいい。
■ さてさて、例によって、前置きが長い。このところ、図書館でいろいろなものを入手している。そのひとつが、久保田万太郎の七回忌の昭和44年5月に日本橋三越で開催された「久保田万太郎展」の図録のコピー。ここに、昭和16年12月の「いとう句会」のスナップがあって、戸板さんも写っていた。『夢諦軒 句日誌二十年』で句会の正確な日付が判明しているので年譜に追加したりした。さらに気になるのが、昭和19年初夏に「いとう句会」に向かう久保田万太郎と雨のなかを歩きながら、日本演劇社に入社を勧められて即答するくだり、この日の正確な日付けも知りたかったけれども『夢諦軒 句日誌二十年』では判明せず。『夢声戦争日記』ではどうなのだろう。後日、確認したい。
■ 中公文庫の『夢声戦争日記』は第1巻と第2巻だけ本棚にある。いずれも100円で見つけたものだ。今のところ手元にあるのは、2年前に刊行された「抄」と合わせて3冊なので、あとは図書館に行かなければならない。全7冊揃うのはいつになるのだろう。と、『夢声戦争日記』をめくっていたら、昭和17年2月のところに、戸板さんが内田誠の下で明治製菓宣伝部にて編集していた「スヰート」の原稿を書いているくだりがあった。「源氏巻」というタイトルの文章だそうで、夢声は《津和野のことを書くのはたのしい。》と日記に書いている。濱田さんの『徳川夢声と出会った』でも津和野のくだり、とても印象的だった。昭和16年12月8日の開戦の翌日に戸板康二は大政翼賛会の花森安治と初対面、どんどん戦時色が濃くなって内田誠の「スヰート」もやがて消えていくこととなるのだが、開戦から間がない頃の「スヰート」には夢声の文章が載っていたことを夢声の日記で知ることができた。わたしにとってはまだまだ幻の戸板さん編集時代の「スヰート」の様子が、きわめておぼろげではあるけれども、見えてくる気が少しした。開戦間がないころ、戸板さんは「いとう句会」に出席したり、夢声の原稿を受け取ったりしていた、と、ただそれだけのことだけれども。
■ このところ図書館でいろいろなものを入手している・その2は、雑誌記事いろいろ。もっとも重点的に収集したのが、芸能学会の機関誌「芸能」。芸能学会というのは、昭和18年に戸板さんの慶應国文科の師・折口信夫を中心に設立された学会。戸板さんによると、折口信夫は雑誌をつくるということに大変興味を持っていたという。昭和18年の創立当初からさっそく学会誌の刊行が始まった。明治製菓で「スヰート」に携わることで編集のいろはを知っていたので、戸板さんも請われて編集に参加することとなった。敗戦の昭和20年8月をもって活動を休止していた芸能学会が復活したのが昭和33年、翌34年に機関誌「芸能」が復刊し、刊行当初から戸板さんも参加している。「芸能」は1993年まで毎月刊行された。戸板さん参加の記事がたくさんあって、特に嬉しいのが奥野信太郎との対談記事「見たもの聞いたもの」、「銀座百点」の演劇合評会に似た雰囲気がある。それから書評も嬉しい。戸板さん執筆の書評も頻繁に登場するし、戸板さんの著書への書評もたくさんあるので、わたしにとってはお馴染みの本への書評を読むことで客観的なことをちょいと知ることができたりもする。折口信夫の遺産という側面がある「芸能」を見ることで、なんとなく「三田の戸板康二」という感覚も味わえるし、『折口信夫坐談』[*] の初出誌でもあるので、この本で垣間見た「垂教会」の記録の全文掲載をはじめとした幾多の記事によって、『折口信夫坐談』の追体験的な側面もある。「芸能」の表紙を担当したのが、『街の背番号』[*] の装幀者・岡村夫二。折口の題字である「芸能」とよくマッチした結構渋い仕上がりで、『街の背番号』をはじめとする装幀本とはだいぶ趣を異にしている。
■ 春先から少しずつ集めていた「芸能」の記事を、欠本以外は一通り見終わった。久保田万太郎の追悼座談会で万太郎を媒介にいろいろと本読みの刺激を得たり、筑摩書房の明治文学全集で戸板さんが編集した『明治史劇集』の月報用の遠藤為春との対談が全文収録されていて、明治の歌舞伎がますます気になったり(特に新蔵)、などなど、雑誌の戸板康二を探すことで戸板さんを媒介にいろいろなことが気になってくるのだった。特に大感激だったのが、戸板さんの書評を読んでぜひとも読んでみたい! と思った、仲田定之助の『明治商売往来』が今月と来月とでちくま学芸文庫として刊行ということ。なんというグッドタイミング! そして、「おっ」となったのが『明治商売往来』の初出誌が「新文明」だったということだった。
■ 戸板康二が生涯劇評家の道を歩む第一歩となったのが昭和10年代の「三田文学」、予科から国文学科に進学して折口信夫の教室に入った昭和10年に劇評の執筆を開始している。若き戸板青年を「三田文学」に推薦したのが水木京太、編集長の和木清三郎に紹介され、昭和10年5月号が初掲載だった。水木京太は三宅周太郎と慶應と同級で、永井荷風の時代の慶應文学部に居合わせた人だ。本郷菊富士ホテルに滞在していた三宅周太郎に丸善の「学鐙」の編集長だった水木京太、戸板さんよりちょっと上の世代の人たちを見回すと、一気に大正ベルエポックとなって何かと心躍るくだりが連発する。和木清三郎は「三田文学」の全盛時代の名編集長、「三田文学」の精神的支柱とよく称される水上瀧太郎が他界したのは昭和15年、その追悼号が「生涯の大事業」だったと戸板康二は『思い出す顔』[*] の「『スヰート』と『三田文学』」に書いている。「『スヰート』と『三田文学』」では、若き戸板さんと深いえにしのあるリトルマガジンの編集長、内田誠と和木清三郎を語って「スヰート」から「三田文学」のことへと話題をシフトさせていく際の筆の運びが実に見事、それにしても戸板さんの文章で伺うことのできる和木清三郎の人となりが実にいい感じ。和木清三郎編集長時代の「三田文学」が体現したある種の雰囲気は、当時の鈴木信太郎による表紙画を見るだけで鮮やかに感じることができる。その表紙を繰ると、青年時代の戸板康二がいるわけで、このあたりの人物誌に思いをめぐらすととにかく胸が躍る。戸板康二が初めて久保田万太郎と対面したのも「三田文学」だった。
 ■ そんなこんなで、和木清三郎は、戸板康二を語る際に絶対にはずすことのできない人物のひとり。「三田文学」和木清三郎追悼号、1970年7月号を今年7月に五反田の古書市で買った。戸板さんはもちろんだけど、野口冨士男も文章を寄せている。ある日、野口冨士男が紅野敏郎に「三田文学は和木さんの時代が最も充実していたんじゃありませんか。」と言うと、紅野敏郎も「荷風の時代よりも上だったと思います。」と言って同感したとのこと。訃報を聞いた直後のことを野口冨士男はこんなふうにも書いている。
■ そんなこんなで、和木清三郎は、戸板康二を語る際に絶対にはずすことのできない人物のひとり。「三田文学」和木清三郎追悼号、1970年7月号を今年7月に五反田の古書市で買った。戸板さんはもちろんだけど、野口冨士男も文章を寄せている。ある日、野口冨士男が紅野敏郎に「三田文学は和木さんの時代が最も充実していたんじゃありませんか。」と言うと、紅野敏郎も「荷風の時代よりも上だったと思います。」と言って同感したとのこと。訃報を聞いた直後のことを野口冨士男はこんなふうにも書いている。
私に前後する世代の人達は、今後も一代の名編集長として和木さんの名を心に刻んでいくだろうが、石坂さんの『若い人』は後代の読者につたえられても、和木さんの名前はやがて忘れられ、ついには消えてしまうだろうという予感より現実の前に、そのとき私は立たされたといってもいい。うーむ、たしかに、現在、和木清三郎の名前は忘れられているには違いない。しかーし、わたしは「三田文学」の名編集長としてくっきりとその名を心に刻んでいるし、戸板さんの心地よい文章によってその人となりにほんわかといい気分になっている。戸板さんのおかげで、いろいろなことを心に刻んでいるのだ。……などなど、仲田定之助の『明治商売往来』のことを書こうとしたら、思いっきり話題がそれてしまった。『明治商売往来』の初出誌「新文明」は戦後、和木清三郎が編集していた雑誌、多分に和木清三郎の趣味性が反映されているようだ。戸板さんもずいぶん誌面に参加しているとのことで、池田弥三郎と加藤守雄とで毎月鼎談をしていたという。ゲストを招いたりもして、ここでも「銀座百点」と似た雰囲気だったのかも。本誌を見ていないので想像だけれども。と、かねてから興味津々だった「新文明」に連載されていたのが『明治商売往来』だったわけで、ある魅惑的な本の初出誌をさぐってみるとある魅惑的な雑誌にたどりつくという愉悦の典型だった。「新文明」が初出の書物でわたしの本棚にある本に、阿部優蔵の『東京の小芝居』(演劇出版社、昭和45年)という本がある。著者は水上瀧太郎の子息で、刊行に戸板さんが一役買ったらしい。
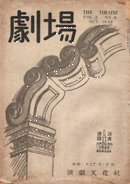 ■ 和木清三郎の追悼号を買った翌月、歌舞伎座へ『野田版鼠小僧』を見物に行く道すがらに奥村書店にて水木京太追悼号の「劇場」を買った。二十歳の戸板康二を「三田文学」編集長の和木清三郎に引き合わせた人物、水木京太。「三田文学」の戸板康二にまつわる人物の追悼号を立て続けに手にしたという次第だった。「劇場」に関しては、『回想の戦中戦後』[*] の「よその雑誌の出発」に詳しい。創刊は昭和21年1月で、請われて編集長に就任したのが水木京太だった。敗戦間際ということもあって紙は粗末だけれども、伊藤熹朔による表紙がなんとなく洒落ていて典雅な雰囲気。戸板康二はこの雑誌にさかんに劇評を執筆していて、戦後に惨然と演劇批評の書き手として出発した戸板康二の舞台装置のひとつだったといえよう。この追悼号は昭和23年9・10月号、編集長の水木京太の急逝でこの号をもっていったん休刊となっている。ちなみに、この号には、前号に掲載された戸板さんの劇評に対し、宇野信夫が怒りの一文を寄せている。戸板さんが親炙していた久保田万太郎に疎まれていた宇野信夫は当然万太郎にはよい感情を持っていなかった。水上瀧太郎に傾倒していたという。久保田万太郎をはさんでしばらく距離があった宇野信夫と交流を深めるくだりは、『あの人この人』[*] に詳しい。人形町でふぐを食べる宇野信夫と戸板康二、このエピソード、大好き。
■ 和木清三郎の追悼号を買った翌月、歌舞伎座へ『野田版鼠小僧』を見物に行く道すがらに奥村書店にて水木京太追悼号の「劇場」を買った。二十歳の戸板康二を「三田文学」編集長の和木清三郎に引き合わせた人物、水木京太。「三田文学」の戸板康二にまつわる人物の追悼号を立て続けに手にしたという次第だった。「劇場」に関しては、『回想の戦中戦後』[*] の「よその雑誌の出発」に詳しい。創刊は昭和21年1月で、請われて編集長に就任したのが水木京太だった。敗戦間際ということもあって紙は粗末だけれども、伊藤熹朔による表紙がなんとなく洒落ていて典雅な雰囲気。戸板康二はこの雑誌にさかんに劇評を執筆していて、戦後に惨然と演劇批評の書き手として出発した戸板康二の舞台装置のひとつだったといえよう。この追悼号は昭和23年9・10月号、編集長の水木京太の急逝でこの号をもっていったん休刊となっている。ちなみに、この号には、前号に掲載された戸板さんの劇評に対し、宇野信夫が怒りの一文を寄せている。戸板さんが親炙していた久保田万太郎に疎まれていた宇野信夫は当然万太郎にはよい感情を持っていなかった。水上瀧太郎に傾倒していたという。久保田万太郎をはさんでしばらく距離があった宇野信夫と交流を深めるくだりは、『あの人この人』[*] に詳しい。人形町でふぐを食べる宇野信夫と戸板康二、このエピソード、大好き。■ ところで、「劇場」の編集部にいたのが三國一朗。今月発売になった、濱田さんの『徳川夢声と出会った』の最終章は三國一朗のことが綴られていて、三國一朗と出会った、で締められている。今月は『徳川夢声と出会った』を読んで、とりわけ夢声のことを心に刻んだのはもちろんのこと、それに付随してわたしは相変わらずの戸板康二道、あっちをちをうろうろこっちをうろうろしていたのだった。
← PREV | NEXT →