#026
折口信夫没後五十年(02, October. 2003)
■ 串田孫一が尾を引いてしまうのだが、雑誌「論座」にて串田孫一の「忘れえぬ人々」が連載中で、戸板康二とのことが今年6月号の第3回「終戦の長閑さ」で綴られていたことをつい最近知った。「論座」は坪内祐三の「雑読系」を毎月立ち読みしたりし損ねたりなのだけれども、当の6月号では「風景」のことが取り上げられていて、その頃ちょうどわたしも坪内祐三のタイトル通りに「このところ、『風景』のバックナンバーを拾い読みしている」真っ最中だったから、あまりのタイミングのよさに狂喜乱舞。それでつい串田孫一の方を見逃してしまっていたらしい。(→「風景」のことは Magazines【戸板康二が通り過ぎた雑誌おぼえ帳】へ)。
……そんなごたごたの間でも、東京にいる戸板君とは手紙で連絡を取り合っていた。ひとまず、こんな具合に落ち着いたし、有難いことに戦争が終ったので、ここの部落の人達に、戦争は勝つか負けるかではなく、終ればこんなに有難いものはない、ということを私が言ったら、皆、そうだそうだと濁酒を酌み交して悦んだ。それを早速、戸板君に可なり長い手紙にして郵送すると、急に来てみたくなったらしく……この文章の書き出しは、「戸板康二君はもう亡くなって久しくなる。青山の葬儀場で式が行われたが、實に様々の種類の人達に挨拶をされ、私もその三日程前に文藝春秋からの依頼があって、短いものではあったが弔辞を書いた。」というふうになっている。平成5年2月6日土曜日、山口瞳の『年金老人奮戦日記』(新潮社、1994年)によると、2月だというのに20度の陽気、快晴だったという。青い青い空だったに違いない。
■ 戸板康二の没後10年である今年は折口信夫の没後50年の年でもあって、昭和28年9月3日に亡くなった折口、先月発売の雑誌「新潮」10月号では《折口信夫歿後五十年》として大変充実した特集が組まれていて大感激だった。さらに大感激なのが、渡辺保さんによる文章が収録されていたこと。あまり言及されることのなかった折口信夫の『かぶき讃』だけど、今まで川村二郎、高橋英夫、鈴木忠志によって論じられたことがあったという。読んでみたい。
■ さらに、折口歿後五十年の今年9月、上村以和於著『時代のなかの歌舞伎 近代歌舞伎批評家論』(慶應義塾大学出版会)が発売になった。これもしみじみ嬉しいことだった。上村さんの文章を読んだのはいつが最初だっただろうと思い起こしてみると、一度図書館で借りて読んだ『折口信夫坐談』[*] を神保町の古本屋で見つけて、文庫になっているのを知っていたから我慢しようと思ったが我慢しきれずえいっと買ってしまって、えいっと買ってしまってハイになっていたところで足を踏み入れた本屋さんの歌舞伎書コーナーにてなんとはなしに手に取った、歌舞伎学会の機関誌「歌舞伎 研究と批評」が最初だった。当時の最新号で上村以和於さんの連載「近代歌舞伎批評家論」で折口信夫が取り上げられていたのだ。なんという奇縁だろう。ますますハイになって衝動買い、コーヒーを飲むお金もなくなりスッカラカンになって家路についた。冬の澄んだ空気が頬に気持ちよい小春日和の日だったのを覚えている。以後、バックナンバーの上村さんの連載を当時の東京堂の4階の歌舞伎書コーナーで立ち読みするのが神保町のコースに組み込まれることになって、いつか本にまとまったらじっくり読みたいものだと心待ちにすること幾年月であった。それが折口歿後五十年の先月実現したのだった。
■ 『折口信夫坐談』[*] を初めて読んだのは、戸板康二に夢中になるきっかけになった『歌舞伎への招待』[*] にメロメロになった直後の残暑の厳しい頃。ただ字面を追ってなんとなくたのしんでいるという感じのちっとも内容が頭に入っていない、なんとなく気分を味わって、文章とは折口信夫の違った語り口といいそれを書き取る戸板さんの姿といい、なんだか妙に心に残った本だった。今でも、戸板康二の本で好きな本を挙げるとすると絶対にはずせない愛着ある本のひとつだ。その『折口信夫坐談』が出版されたのは昭和47年のこと、翌年の48年は折口信夫没後二十年にあたる。
■ その没後二十年を記念して編まれた書物がある。慶應義塾国文学研究会発行の非売品『三田の折口信夫』(昭和48年10月1日発行)という本を先日、さる方の御厚意で読むことができた。まず最初に思ったのは、戸板康二の「三田の芝居合評会」なる文章が収録されている、おそらく単行本未収録であろう、これはぜひとも読んでみたいということなのだったが、『三田の折口信夫』は当の戸板康二の文章はもちろんだけど、本全体が刺激に満ちている感じで、なんというか、上記の諸々で折口没後五十年に気もそぞろだったタイミングで『三田の折口信夫』を手にしたこと、このことが絶好のタイミングだったとしか言い様がない。
■ 『三田の折口信夫』は一度古本屋の店頭で手に取ったことがあった。5000円くらいだったか、目次に戸板康二の名前を見つけただけですぐに棚に戻したのだった。と、これはもう何年も前のこと、『三田の折口信夫』の存在は知ってはいたけれどもあまり深く考えることなく、折口没後五十年の今日まで来てしまっていたのだった。戸板さんの『折口信夫坐談』が出版されたのは翌年の折口没後二十年に先駆けるようなタイミングというわけで、おそらく連動している企画だったのではあるまいかと想像している『三田の折口信夫』、この書物を一度目を通したことで、戸板康二を読みはじめたまなしのあの頃に戻ったような感覚、もう一度初心に戻って戸板康二とその周辺に接していかねばならぬと思ったのだった。
■ 今回の更新では『三田の折口信夫』で知った諸々のことを、Chronology【私製・戸板康二年譜 1915-1993】に追加。
■ 折口信夫は従来からの国学院大学教授の役職と兼任するかたちで、昭和3年慶應義塾の国文科教授に就任し、昭和28年9月の死までその役職に就いていた。戸板康二が国文科に進学したのは昭和10年、前年に戸板さんを国文科に誘った池田弥三郎が進学している。『三田の折口信夫』をひもとくことで、今まで断片的に知識としてはあった色々なことを別の角度から見ることができたのが一番の収穫、『三田の折口信夫』は「三田の戸板康二」でもあったのだ。
■ 『折口信夫坐談』で知ってはいた、三田の国文学研究会で学生の前で折口が前月見た歌舞伎についての合評したということも、今回『三田の折口信夫』所収の戸板さんの「三田の芝居合評会」を読むことで、事の重大性が初めて実感としてつかめてきたというか、戸板さんの文章にはとりたてて新しい事実があったわけではなくて前年出版の『折口信夫坐談』の記述をさらっている感じなのだけれども、そんなあっさりした筆致だったからこそかえって、敗戦直後に折口が学生の前で歌舞伎のお話をすることになった背景、菊五郎が生きていた当時の歌舞伎界、のちの歌舞伎界を担うことになる若手の役者たち、戸板さんが「日本演劇」の編集に昭和19年に従事することで折口に歌舞伎に関する原稿を依頼し折口も書いてみる気になったこと、そしてそれが戸板康二という書き手が歌舞伎批評の世界に惨然と登場したのと同時代だったということ……、今まで知識としてはあった諸々の事実、それらの連関に「うーむ」としみじみ感じ入ってしまうものがあった。
■ というわけで、三田の国文学研究会にて芝居の合評会が敗戦後に催されたことについて、深く噛み締めようと『折口信夫坐談』より「三田の芝居合評会」の箇所を抜き書き、Extract【『折口信夫坐談』より・三田の芝居合評会】を作成、Chronology【私製・戸板康二年譜 1915-1993】の当該日付から飛べるようにリンクをはった。三田の芝居合評会での折口の話について、戸板さんは《その席で出石の茶の間や、先生のおともをして歩きながらの道で話されたのとは、表現が違う。学生にわかるように、きめこまかく解説されている点がちがうのである。》というふうに書いている。
■ さて、『三田の折口信夫』のよろこびは「三田の芝居合評会」だけにはとどまらない。いちいち挙げているとキリがなくなってしまうくらい。わたしのとっての今までの「三田の折口信夫」文献といえば、戸板康二の『折口信夫坐談』と池田弥三郎の『まれびとの座 折口信夫と私』のいずれも中公文庫で出ている、2冊のみだった。この二冊の折口の三田の愛弟子の残した書物で知っていた断片的なことを、『三田の折口信夫』であらためて目の当たりにできた興奮はまだまだある。
■ まずは口絵として『かぶき讃』の装幀(→click!)をしている、折口の門下生でもあった伊原宇三郎による折口の肖像画を初めて見ることができた。この肖像画が描かれたのは昭和24年8月15日のこと、池田弥三郎の記録によると伊原画伯は「先生は口元が複雑です」と言ったという。コカインのおかげで鼻の感覚が麻痺してしまっていた折口は「においは舌触りの記憶で嗅いでいる」とよく言っていたのを池田弥三郎は記憶していて、若き日にコカイン中毒だったことは戸板さんの『折口信夫坐談』でも語られている。折口のコカインのくだり、『戸板康二坐談』を初めて読んだときとても印象的で、ちょっとデカダンなところが忘れられない一種の香気と言ったらおかしいけど似たような気分を味わったものだった。その肖像画がこれかあと『三田の折口信夫』を開いてさっそく興奮した次第。この肖像画は今は慶應義塾の図書館の三田文学ライブラリーに保管されているという。三田文学ライブラリーには、「日本演劇」の編集者として戸板さんが受け取った折口の生原稿も 戸板さんの寄贈で保管されているのだそうだ。うーむ、折口没後五十年展のようなものは開催されないのだろうか。
■ それから、戸板・池田両方の書物に書かれてあったので前から知ってはいたこと、昭和22年に慶應義塾が創立90年を迎えるにあたって天皇陛下を招いて5月に記念式典が催された、国文学科でも何か記念行事をとの気運が高まって、折口の発案で学生によって演劇を上演しようではないかということになり、その劇は『九十年』というタイトル、折口の指示で戸板康二と池田弥三郎とが分担して脚本をこしらえ、上演会は無事に終了した……以上のくだり、とりたててそんなに気にも止めていなかった『九十年』なのだったが、なんと『三田の折口信夫』に脚本が収録されていてびっくり! 当日の式典にて配付のプログラムに戸板さんは「日本演劇」編集長の肩書きで「福沢先生の芝居」という一文を寄せていて、これも収録されている。そのタイトルにある通り、『九十年』は福沢諭吉を主人公の劇で、お能の『邯鄲』の段取りでそれぞれの時代の福沢諭吉を再現するという構成。
■ と、『三田の折口信夫』でそれまでそんなに気を止めていなかった『九十年』を戸板さんも参加していることだし、となんとはなしに読んでみたのだったが、これがまあなんとも嬉しい時間だった。第一景の分担は間違いなく戸板さん! ある箇所のト書きが《ト「新口村」忠三の女房の口調で》となっていたり、下座の馬子唄で舞台が変ったり、悪者(のち福沢諭吉によって改心)が少女をかどわかすくだりの台詞が思いっきり黙阿弥風の七五調、その台詞の中には《とんだお軽のくどきだが》という一節も! といった感じに、戸板さーん、かなり乗ってお書きですなあという様子が如実にうかがえてニヤニヤしっぱなしだった。最初の方の情景描写(舞台はどこかの峠の茶屋)で《あれが「幻の門」です。むこうに見える丘、あの丘の上に上ると、海が見えますよ》という台詞がある。これは三田の山を見立てている。さりげなくこんなくだりを織り込む手腕なんぞ、まさしく戸板康二の面目躍如たるものだ。などなど、思いもかけないところで大興奮だった。
■ 今回手にとった『三田の折口信夫』の巻末には、旧全集の補遺として未収録だった分の書簡の掲載もあり、そこに谷崎潤一郎宛の昭和20年5月1日付けのお手紙があって、折口は『細雪』を贈られて読んだことを綴っている。菊五郎が新橋演舞場で孤軍奮闘して毎日幕外で口上をしていた頃、折口はこんな手紙を谷崎に送っていたのだ。
■ ……などなど、『三田の折口信夫』のドキドキをあげようとするとキリがないのだけれども、最後に、昭和28年11月発行の「三田文学」折口信夫追悼号のことを。『三田の折口信夫』に折口追悼号の編集の仕事した田久保英夫による回想「追悼号前夜」という文章があって、これもとてもよかった。《表紙はかつての水上瀧太郎追悼号に倣ったデザインで、地色は折口先生が好まれた浅黄色を配した。》とある。ここにその2冊の表紙を並べてみよう。
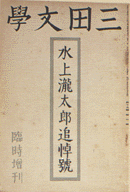
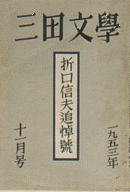
|
■ 「三田文学」の折口追悼号を図書館へ見に行ったのは古川ロッパが一番の目当て。わたしの愛読書『劇書ノート』(→click!)には未収録の「『かぶき讃』ノート」をロッパが書いてくれているのだ。冒頭を目にしてさっそく目がウルウル。
此の本を読みながら、ふと思ったのは、歌舞伎役者は幸せ者だな、といふことだった。歌舞伎役者以外に、誰が、その死後にまでこんな風に細々と、親切な批評などをして呉れるものぞ。そんなことをしきりに感じた。というふうになっていて、そんなことないよ、ロッパの天才ぶりはいくつかの文章を通してわたしもよーく知っているよ、それに残してくれた文章も大好きだよ、ロッパ! と思わずひとりで熱くなってしまったのだったが、今年生誕100年の古川ロッパ、小津安二郎をめぐる数々の狂騒、全集が復刊した森茉莉などを思うと、あまりにもロッパの登場頻度は少ないような気がする(わたしが気づいてないだけかもしれぬが)。うーむ、なにはともあれ、今年生誕100年の顔ぶれのなんと見事なこと。戸板康二よりちょうどひとまわり上のウサギ年の面々。しきりに田圃の太夫・源之助への偏愛をのぞかせるロッパ、彼と二人で源之助を来訪したことを久保田万太郎は源之助の追悼文で書いている。なんともなんとも素敵な文章で何度読み返したことだろう。そんな数々のすばらしい文章を多くの書き手に綴らせている源之助、あらためてその存在に興味津々だった。と、折口信夫の『かぶき讃』へ戻っていくのだった。
#027
続・折口信夫没後五十年(11, October. 2003)
■ 今年は折口信夫没後50年、先月発売の雑誌「新潮」10月号に大変充実した折口特集が組まれていて大感激していたばかりだったのに、今月発売の雑誌「三田文学」秋季号にて再び折口信夫の没後50年の特集に遭遇することになった。本家本元の「三田文学」でも折口特集! いろいろな意味でわたしにとっても折口信夫元年になりそう。
というわけで発売日の10月10日、さっそく東京堂へ買いに行った。まっさきに読んだのはもちろん渡辺保さんの「劇評家折口信夫」という文章。
すべてがわからなくとも『かぶき讃』は、わたしにとって忘れ難い書物であった。ことに忘れ難いのは、一つはそこに扱われた役者たちの芸風が眼前に髣髴として匂うようだったこと。もう一つはその文体の読む者を深淵に引き込むような不思議な力を持っていることであった。「匂いの濃密さ」と「文体のスタイル」。匂いの濃密さは読んですぐにわかるが、折口の文体の醸し出す独特の深淵はなかなかわからないかもしれない。だからこそ、折口の『かぶき讃』は何度読んでも面白い本だとも言えそうで、これからも折にふれて大事に読んでいこうと、それだけは強く思う。
■ 先月手にした『三田の折口信夫』のことが鮮烈に心に残っているときに、「三田文学」の折口特集にあたってみると、大久保房男の「戦時下の折口信夫」がとてもよかった。戸板康二も『女優のいる食卓』[*] や『折口信夫坐談』[*] に所収の「おもてに対す」で印象的に綴っている敗戦間近の昭和20年7月26日の情報局の会合における折口のことを、高見順も日記に記していることを初めて知ったりも。『高見順日記』もぜひとも読まないといけない。
■ その戸板康二の「おもてに対す」は昭和28年11月発行の「三田文学」折口追悼号が初出。『三田の折口信夫』には折口追悼号の編集部員のひとりである田久保英夫による文章があったが、今回の「三田文学」にも同じく編集部員だった桂芳久による「あさぎ色の記」というタイトルの回想を読むことができる。折口の死からわずか二ヶ月後に世に出ることになった「三田文学」の折口追悼号、あの表紙の浅黄色のなんと美しかったことだろう。
■ Chronology【私製・戸板康二年譜 1915-1993】に追加。訂正も大あり。
■ 今回の更新では、折口信夫がやたらと尾を引いているので、池田弥三郎の『まれびとの座』にある、池田が復員した昭和21年1月から死の昭和28年9月までを記録した「私製・折口信夫年譜」より、ちょっと追加した。
■ 今回「おっ」となったのが、昭和27年11月、難波治吉が荷風の偏奇館跡の住居を手放すと聞いて、池田弥三郎が折口の新宅にどうかと角川源義と一緒に偵察に行くというくだり。新橋南葩堂主人の難波治吉のことは『回想の戦中戦後』[*] にちょろっと登場する。戸板康二の勤務先の日本演劇社の末期に融資をして重役になった人物で、荷風を崇拝して偏奇館跡を購入し一時期住んでいたとのことで、川本三郎さんの『東京おもひで草』(ちくま文庫)では「もと文学座員で久保田万太郎の弟子」というふうに名前が登場していた。結局終生大井出石町に留まった折口であったが、偏奇館跡に引っ越す可能性もなきにしもあらずともいえないこともなかったというわけで、この挿話はなんだかよかった。
■ 荷風をとりまく人物誌のうち、やはり『回想の戦中戦後』でちょろっと登場するのが相磯凌霜で、戦中戦後に何度か催されていた岩佐東一郎らが集って本を交換する「交書会」に戸板さんも参加していて、大井出石町の岩佐家、久が原の相磯家のみならず、荏原の戸板家でも催されたことがったという。この「交書会」のくだり、串田孫一宛書簡(→click!)で戸板さんが何度か言及しているのを見てにわかに気になっていたのだった。戸板康二は永井荷風とは直接の面識はなく、『午後六時十五分』[*] 所収の「見た顔」によると、たった一度、邦楽座の客席でフランス映画が上映されているときにチラリと見ただけだったとのこと。
■ とかなんとか、どうも枝葉末節にばかり気をとられてしまうのだったが、戸板康二の同時代の人物のいろいろなつながりから立ちのぼる立体感のようなものにしょうこりもなく夢中なのだった。
#028
戸板康二書簡を買った、藤木秀吉のこと(21, October. 2003)
■ 反町の神奈川古書会館で戸板康二の戦前のお手紙を買った。鎌倉の游古洞さんの出品で、目録に出ているのを、古書目録界にその名をとどろかす「モクローくん」さんから教えていただいたのだった。うっ、涙が……。なんという親切であることだろう。相場はどうなのかよくわからないけれども、値段はとても安いように感じた。いてもたってもいられず、さっそく游古洞に電話してみたところ、その女店主さんの対応の気持ちいいこと気持ちいいこと、戸板康二のお手紙を見ることができる嬉しさのみならず、店主さんとの心地よいやりとりが嬉しくて、すっかりいい気分で、10月最初のよいお天気の土曜日、意気揚々と反町へ向かった。戸板康二のお手紙目当てでやってきた古書会館であったが、いい本をたくさん買うことができた。戸板書簡購入の折には游古洞さんとちょっとだけお話しすることができて、電話のときとまったくおんなじように、とても気持ちのよいひとときだった。それにしても、鎌倉の古本屋さんってどこもかしこも素晴らしい。来月鎌倉へ出かける予定があるので、今度はまっさきに游古洞さんへ出かけようと思っているところ。
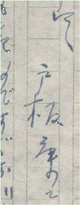 ■ わたしの買った戸板書簡は200字詰め原稿用紙一枚半の簡単な事務連絡、封筒もついている。わーいと大喜びで、購入以来、毎日毎日お手紙を眺めていた。戸板康二の草稿類を初めて手にして嬉しいあまりについ何度も何度も眺めずにはいられなかった、と言いたいところなのだけれども、修行が足りないせいで細かいところがどうもうまく解読できなくて、毎日毎日一生懸命目をこらしていたというのが本当のところだった。宛名は「三田文学」関係のとある人物だということがわかった。戸板さんの本では名前は見たことはない。とりあえず、ここに書いてあることは、3月26日に開催のさる会合には都合が悪くて参加できません、というようなことだということだけはわかった。うーむ、この書簡の正確な年号はいつだろうか。それだけはぜひとも知りたい。
■ わたしの買った戸板書簡は200字詰め原稿用紙一枚半の簡単な事務連絡、封筒もついている。わーいと大喜びで、購入以来、毎日毎日お手紙を眺めていた。戸板康二の草稿類を初めて手にして嬉しいあまりについ何度も何度も眺めずにはいられなかった、と言いたいところなのだけれども、修行が足りないせいで細かいところがどうもうまく解読できなくて、毎日毎日一生懸命目をこらしていたというのが本当のところだった。宛名は「三田文学」関係のとある人物だということがわかった。戸板さんの本では名前は見たことはない。とりあえず、ここに書いてあることは、3月26日に開催のさる会合には都合が悪くて参加できません、というようなことだということだけはわかった。うーむ、この書簡の正確な年号はいつだろうか。それだけはぜひとも知りたい。■ で、結局は、本読みの快楽の金子さんに解読をお願いしたり、それからなんという奇縁、そもそもの発端であった「モクローくん」さんのご学友であらせられるさる先生に教えていただいたりして、ようやく全文が明らかになったのだった。年号も判明、3月26日の会合に出席できないのは「つとめ先の女子校にて何うしても離せぬ用事」のため、戸板康二が女学校の教師をしていたのは昭和18年から昭和19年にかけてなので、この3月26日は間違いなく昭和19年だ。
■ 私製・戸板康二年譜(→click!)を参照してみると、昭和19年3月26日、戸板康二は串田孫一ら「冬夏」の同人らと会合に出席している。上のお手紙にあった「三田文学」の会合に出席できなかったのは「冬夏」の会合のためなのかそれとも本当に勤務先の女子校のためなのか、それは不明だけれども、思わぬえにしでわたしの手元にポンと転がりこんできた戸板康二のお手紙で言及されている日付けが他の書物でも言及されているというめぐりあわせがなんとも嬉しかった。この「冬夏」の会のことは、串田孫一の『日記』(実業之日本社、1982年)で知った。ここに全文書き抜いてみよう。
江東楽天地清昌閣にて、貞丈を囲んで冬夏の会を催す。出席者は戸板康二、大草実、中川幸永、酒井嘉七、今村信吉と私の六人。非常に面白く、珍らしい集りで成功した。冬夏の仲間だけで出て来ない話題が中心になったからだと思う。貞丈に対しては皆好感を抱いたし、幕末の話を先ず五十五分も話して貰って、それから雑談した。そして私たち一同が一斉に驚いたのは、清昌閣のおかみさんが、器にドロップを山盛りにして、しかも事もなげに出したことだった。夢を見ているのではないかと思った。こうなると、いろいろな日記で「昭和19年3月26日」を見てみたいという衝動にかられる。とりあえず、手元にある、荷風の『断腸亭日乗』より抜き書き。
三月廿六日日曜日 晴。風歇んで稍暖になりぬ。後庭に落葉を焚く。日暮五叟方より奈良漬を貰ふ。「昭和19年3月26日」というのはちょいと春めいてきた日曜日だったということがわかる。夢声日記にはどんなことが書いてあるかしら。
■ 夏に、串田孫一の『日記』を読んでいたとき、とりわけ心の残ったのは、串田孫一の叔父にあたる今村信吉(いまむら・のぶきち)のことだった。戸板康二も参加していた串田孫一が中心の戦前の同人誌「冬夏」は、串田孫一のお父さんが亡くなったときの通夜の席で、今村信吉の発案で始まった雑誌だった。今村信吉に関しては、『女優のいる食卓』[*] 所収の「雪」に次のような一節がある。大好きなくだりなので、ちょっと長くなるけどここの箇所全文抜き書き。
雪見といえば、七、八年前に、今村信吉氏に誘われて、雪を見に行ったことがある。串田孫一の『日記』では今村信吉の書簡も多数収録されていて、昭和21年の2月には国学院で折口信夫の源氏物語の講義があるから聞きにいかなくては、というようなくだりがあったり、昭和21年6月、菊五郎による『助六』の舞台稽古の様子を目の当たりにした戸板さんの絵入りハガキ(→ click !)のすぐあとで、東劇で『助六』を見ている今村さん、串田孫一から戸板さんのハガキを見せてもらっていたらしくて「戸板君のハガキのことを思い出した」というふうに串田孫一に手紙を書いていた。
今村さんは江東楽天地の社長で、串田孫一氏の叔父さんにあたる劇通だった。同級生だった串田君の縁で、ぼくはずいぶんかわいがってもらった。毎年大みそかになると、串田君と三人で町を歩いて一杯飲む習慣が長く続いていた。その今村さんのその日の趣向はおよそ昔の江戸の感じのある所へ行こうというのである。「だまって、ついて来たまえ」と今村さんはタクシーに乗りこむと、うれしそうにいった。
車は千住の方向に向った。そして回向院の前でとまった。小塚ッ原の刑場の跡にある維新の墓を掃い、それからその寺の回向院の裏手に当たる尾花屋という、うなぎ屋にはいった。
雪を見ながら食事をするという風情を堪能したのは、あとにも先にも、このときだけである。尾花屋の庭の雪は、歌舞伎の舞台そのままだった。低い石燈籠の笠の雪が、時々音を立てて落ち、池では鯉がはねていた。
午後、有楽町で今村さんと別れたが、何だか遠い旅から帰ってきたような気持がした。今村さんはもう亡くなったが、あの日のような雪も、東京には来なくなった。
■ 戸板康二の本を読んでいると、「文芸好きの実業家」のおじさんというのによく出会う(ような気がする)。何ヶ月か前の「銀座百点」で水村美苗さんが「『エリートサラリーマン』」というエッセイを書いていた。小津映画におけるおじさまたちについて、《主人公の男は丸の内のオフィスで働き、銀座で飲み食いする場面ほど、人が泰平の世で飲み食いできることの良さ、美しさ、ありがたさをつくづくと感じさせるものはないであろう。》なんていう一節があったけれども、なんだかこんな感じの都会の「おじさん文化」みたいなものがわたしはなんだか好きだ。
■ さて、戸板康二をとりまく「小父さん」たちのひとりに、藤木秀吉という人がいる。戸板康二を読むようになったまなしの頃から、藤木秀吉と戸板康二の交流にまつわるエピソードがずっと心に残っていた。藤木秀吉の遺稿集が一周忌の昭和15年に刊行され、若き戸板康二が編集を担当している。その『武蔵屋本考』という本を今年7月最初の土曜日に、目白の古本屋さんで買った。
■ Special【藤木秀吉遺稿集『武蔵屋本考』のこと】、記事追加。
■ 『武蔵屋本考』はとにかく嬉しい買い物だった。目白の古本屋さんで売っているのを知ったものの、値段は安いとはいえなかったので、ハテどうしたものやらと、とりあえずどんな本かよく確認してからゆっくり考えようと、6月のとある日曜日に早稲田大学演劇博物館の図書館へ出かけて、『武蔵屋本考』を閲覧したのだったが、いざページを開いてみると昭和15年5月14日という日付けとともに「戸板康二氏寄贈」という記入があって、ジーンとなった。この「ジーン」がいつまでも止まらなかった。
← PREV | NEXT →