#017
谷沢永一に興奮、『新東京百景』に興奮(02, June. 2003)
■ Index【日日雑記・戸板康二書名索引】に、2003年5月分までのデータを追加。どうもあんまり意味がないような気がしているこのコーナー、うーん、どうしよう。
■ Chronology【私製・戸板康二年譜 1915-1993】に追加修正。
■ 團菊祭が終了したところで、戸板康二年譜に大事なことを書き損ねていたことにふと気づいたのが、昭和24年4月に東劇で、戸板さんが六代目最後の舞台を見ていたというくだり。あと、このところかつての「文壇」を扱った本を何冊か立続けに読んで、そのたびにぶつかるのが十返肇だった。しばらく十返肇強化月間にしようと決意したところで、年譜にも十返に関するくだりをちょっとだけ追加。
■ 先月、神保町にて、折口信夫の『かぶき讃』(創元社、昭和28年)が安かったのでわーいと買った。その記念に、References【戸板康二を語る人びと・レファレンス】の折口信夫の項に『かぶき讃』の画像を貼り付けた。この本の巻末に池田弥三郎によるあとがきがある。昭和24年7月、池田や伊馬春部らが同行して旅行中だった折口信夫、その旅行中にもいよいよ菊五郎が絶望的らしいと話題になっていて、11日金沢に向かう途中の電車のなかで、新聞で菊五郎の訃を知ったとのこと。車中で戸板康二に宛てて寄書きの葉書を書いた折に、折口は「繊細(あえか)なる人 必ずも死なざらむ。青田にきゆる 白鷺ひとつ」と書いたという。
■ 密偵おまささんのページをたのしみに拝見している。
こちらで、谷沢永一の『紙つぶて 完本』に『演芸画報・人物誌』[*] のことが言及されていることを知ることができたことも嬉しかったことのひとつ。本当にもう『演芸画報・人物誌』は大変な名著なのだが、さすがは谷沢永一、見逃してはいなかった。
■ かなり以前に、ウェブ検索で、谷沢永一著『人生の叡智』(PHP 研究所、1994年)という本に戸板康二の書評が載っていることを知って、図書館へコピーに行ったことがある。読売新聞大阪版夕刊が初出の『すばらしいセリフ』[*] の書評で、戸板ファンうなずくことしきりの見事な文章だった。『ちょっといい話』をはじめとする一連の人物誌の系譜について語りつつ、「べとつかずに距離を保つ善意の視座と、既成の型にとらわれぬ見どころ探しの熱意が、書き下ろし『すばらしいセリフ』の興趣を貫く」としている。
■ そして、つい先日のこと、とある図書館で雑誌閲覧を済ませて、閉館までのわずかの時間に、書評本あたりの棚をうろうろしていた折に、谷沢永一の本が何冊か並んでいるのを見かけて、試みに戸板康二を探してみることにした。『人生を励ます100冊』(潮出版社、1994年)と、タイトルだけ見るとなにやら胡散臭いが(谷沢永一は「人生」が好きなのか?)、中身を見ると登場する本の並びが実にすばらしくて「うっ、できる」と唸ってしまう本があって、嬉しいことに戸板康二の『ちょっといい話』が登場していた。谷沢永一と山野博史による対談で、これまた戸板ファンうなずくことしきりの嬉しい対談だった。ちょいと長くなるけれども、この箇所全文抜き書き。
谷沢:戸板康二というのは、亡くなってみると、生涯ちっとも変わらず、芝居なつかしい、人なつかしい、何についてもなつかしいという、実にいい気分を与えた、まれな著作家やと思います。ことに文藝春秋から出た『ちょっといい話』[*] に始まるシリーズが4冊ありますけど、これは読ませますなあ。気分が重たいときにこの本を読んだらええと思うんですワ。人の世のたのしさというか、そういうものがふわーっとにじみ出ている。特に、「八分目ぐらいの力で調子をとりながら、九回完投型のピッチング」というくだりに、「なるほどッ!」と深く納得。この対談全体で言及されるいくつかの本のなかに上記折口信夫の『かぶき讃』があったのも嬉しかった。谷沢は《これは折口さんの語り口、文体の特徴が全部出ています。物好きで、歌舞伎にどれだけ思いをこめていたかがわかる。あの人は "思い" の人で、それがこり固まっている。しかも、ちょうど昭和の名優の最晩年に遭遇している。だから、時期といい、人といい、そらもう、歌舞伎についてこんな本は空前絶後でしょう》と言い、山野氏が《とくに大阪人が近づきやすいのはそのたおやめぶりです。文章、発想が色っぽい。肌あいがいい意味でほんとになよなよとしてはる。あの色気はやっぱり天性のものですかねえ》と語ったあとで、谷沢は《でしょう。つまり、前も後もないんだもの。系譜のつけようがない》と締めている。そんなこんなで、先月買った初版本でもって、『かぶき讃』をもう一度ゆっくり読み返してみようと思っているところ。
山野:戸板康二は、文豪と呼べるのは日本では谷崎潤一郎、海外ではバルザックだと言ってたんですね。それにちなんで申しますと、こぶりだけどあかぬけした「人間喜劇」の本邦よりすぐり集が『ちょっといい話』から『あの人この人 昭和人物誌』[*] へとつづく一連の人物誌ということになります。こがね色の鉱脈を掘り当てたんですね。あれで自分の書きたいものをぴたっと見つけた。
谷沢:ようあれだけのエピソードを記憶していたワと思うくらい、自分の周りの人を全部好意的に描いた。その人のよさがあらわれている話だけをピックアップした。
山野:好意の人ですね。胸がつかえる話とか、読んでつらくなる話は書かない。簡潔に書いてるんだけど、刈りこんだりはしていない。
谷沢:同じ慶応の久保田万太郎という難物を扱っても、戸板さんはしゃれている。そら、久保田万太郎についてはいためつけてる本が何冊かある。相当いやなやつだったらしい。それが戸板さんにかかると違いますなあ。
山野:他人のことをわるく書くことのできない人だったんですね。最後の十五年間をとっておきの人物素描集を書くことに専念してくれたおかげで、ほんま、われわれの大きな財産になりました。師匠の折口信夫ゆずりの、学殖も遊び心もたっぷりというのが嬉しいですね。
谷沢:そうそうそう。それから、私は若いころにまず『歌舞伎への招待』[*] を買うて、歌舞伎の一幕を見に行きましたよ。そういう、人を駆り立てるところがちゃんとありました。あれは、まだ本が十分出にくいときでしたが、戸板にほれたのが花森安治で、暮しの手帖社からあの花森安治の装丁で、A5判の粗末な本だけど、出したわけです。和紙のカバーで、なかへ折りこんである。
山野:私なんかはもうすこし遅れて、創元選書の『忠臣蔵』[*] ですね。もったいないくらい上手に書いてはります。
谷沢:あれはロングセラーで、創元選書のドル箱の一つです。
山野:『物語近代日本女優史』[*] なんかもよくできていますけど、要するに、ほめてはるわけです。太地喜和子が不運な死に方をしたら、すぐに新聞に寄せましたものね、情のあるしのび草を。注目している役者のことをいつも心にとめていたんでしょうな。それと、一番感心するのは、文章書くのに全力投球してはりませんわね。
谷沢:ああ、そうか、なるほど。
山野:八分目ぐらいの力で調子をとりながら、九回完投型のピッチングをしている。そうでないと、いくら好きな道でも、個性豊かな人物の横顔を十五年間も書きつづけられないでしょう。
谷沢:そらほんまにそうや。
山野:しかも毎回、読ませたですわねえ。晩年、喉頭ガンの手術で声が出なくなっても、つやのある筆さばきのほうは衰えを見せませんできた。
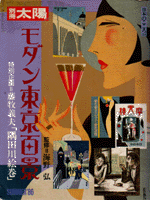 ■ 先月は戸板康二の本を1冊も購入することなく終わってしまったのだけれども、思わぬ発見があったので、最後にこのことを。左の画像の「別冊太陽」、海野弘監修『モダン東京百景』(平凡社、1986年)をなんとはなしに購入したのだったが、そのあとに喫茶店で眺めてびっくり、じっくり眺めてみると、一分の隙もないくらいに本全体がなんとも素晴らしい。日頃からこよなく慕うモダン都市・東京あれこれを豊富な図版でたどることができる、ぜいたくな一冊。洲之内徹による、藤牧義夫「隅田川絵巻」に関する文章があって、かつて『気まぐれ美術館』シリーズでじっくりと心に刻んだ「隅田川絵巻」にあらためてひたることとなった。2年前に東京都現代美術館で大堪能した展覧会《水辺のモダン》の追体験、というところが多々あった。
■ 先月は戸板康二の本を1冊も購入することなく終わってしまったのだけれども、思わぬ発見があったので、最後にこのことを。左の画像の「別冊太陽」、海野弘監修『モダン東京百景』(平凡社、1986年)をなんとはなしに購入したのだったが、そのあとに喫茶店で眺めてびっくり、じっくり眺めてみると、一分の隙もないくらいに本全体がなんとも素晴らしい。日頃からこよなく慕うモダン都市・東京あれこれを豊富な図版でたどることができる、ぜいたくな一冊。洲之内徹による、藤牧義夫「隅田川絵巻」に関する文章があって、かつて『気まぐれ美術館』シリーズでじっくりと心に刻んだ「隅田川絵巻」にあらためてひたることとなった。2年前に東京都現代美術館で大堪能した展覧会《水辺のモダン》の追体験、というところが多々あった。■ この本の巻頭は、海野弘による「1920年代のモダン都市『新東京百景』を歩く」という文章。「新東京百景」とは1928年から1932年にかけて「卓上社」同人、すなわち、恩地孝四郎、諏訪兼紀、平塚運一、川上澄生、深沢索一、藤森静雄、逸見享、前川千帆の8人によって次々と出品された版画シリーズ、《水辺のモダン》でも何枚か展示があった。海野弘は『新東京百景』で描かれた100の東京を紙上でたどる試みをしている。と、海野弘の文章とともに「新東京百景」のそれぞれの版画を見ながら、本で読んだり映画で見たりしたかつての東京に思いを馳せつつ、現在の知っている東京を頭に思い浮かべたりもして、そんな重層的ひとときがたいへんたのしくて、しばし遊んでしまうのだった。さて、この海野弘の文章の以下のくだりにびっくりびっくり、思わず声が出そうになってしまった。
『新東京百景』の100枚の版画は、もともとは番号がつけられていない。平凡社版では、戸板康二氏の文章に沿って、1「東京駅口」(恩地孝四郎)から100「井ノ頭池畔暮色」(恩地孝四郎)までの順に並べている。東京駅を起点として、そこから、ほぼ環状線に沿って、時計の針とは反対まわりにまわってゆくコースは都合がいいので、私もこの順番に従うことにする。と、思いがけないところで、戸板康二が登場しているのだから、大変大変。『新東京百景』の版画集が平凡社から出版されていて、そこには戸板康二の文章が収録されているらしい! ということがわかって、あわてて図書館へ走った。版画集『新東京百景』(平凡社)は昭和53年4月10日発行、定価は12000円。100枚の図版のあとに、戸板康二の「新東京百景」と題された文章があった。《この『新東京百景』という版画が作られていったのが、昭和3年から7年にかけてだとすると、それはぼくの生まれて育った都会が、大正12年9月の震災で受けた痛手からやっと復興できて、15区の旧東京が35区の大東京になるまでの、あいだに置かれた時期であった。》と、100枚の版画に描かれた東京を自身の回想を交えながらめぐっている。ここには桑原甲子雄と師岡宏次の写真も添えられていた。図書館でじっくりと『新東京百景』の一枚一枚を眺めた。
■ もともと魅惑的な一冊に戸板康二が登場していることでわたしにとってはさらに魅惑的な一冊となった、ということがなんとも嬉しかった。桑原甲子雄の写真集『夢の町』(晶文社)の巻末に戸板康二と桑原甲子雄の対談があるのを知ったときとおんなじように恍惚となった。その後、ちょいと気をつけてみると、『新東京百景』(平凡社)は古本屋でちょくちょく見かける本だということにわかった。古本屋で見るのは、たいてい恩地孝四郎の版画三枚付きの限定版、値段は4万円から6万円くらいだ。うーむ、いつか手にしたいなあと夢の本がまた一冊増えた。たくさんの東京随筆を書いている戸板康二は魅惑的な「東京本」に結構たくさん関わっている。部屋の本棚に並べたいなあと夢想しつつも、一方で、各エッセイ集に収録されている随筆を再編集して、戸板康二の東京エッセイ集を編むとしたらどんなふうになるだろう、と想像していたりもする。
#018
「風景」の戸板康二(10, June. 2003)
■ 新コーナー、スタートです。Magazines【戸板康二が通り過ぎた雑誌おぼえ帳】、戸板康二の初出誌を特集するコーナー、第一回目は「風景」です。
■ 戸板康二ダイジェスト始まって以来初の新コーナー設立! と、ひとりで大喜びしたいところなのだけれども、何の展望もなくダラダラと時の過ぎ行くままに書き連ねていたら異様なまでに長くなってしまって大失敗。戸板康二の初出誌のリストを作り始めようかなと思っているところで、その一貫として雑誌を紹介するコーナーとして、次回からはもっと手短にいこうと思います。勉強して出直してまいります。
■ 去年の夏以来そこはかとなく関心があった「風景」だったが、異様に長いファイルを作成してしまうくらい、憑かれたように「風景」に熱中しだしたのは、最近野口冨士男を読み始めたことが起爆剤だった。2003年新たに読むようになった書き手は野口冨士男と芝木好子さん。図書館で「風景」を眺めていたら、昭和38年2月号に芝木好子さんの「東京今昔」と題するエッセイがあって、その冒頭はこんな感じ。
友達からの電話で、大正時代の文献に良いものはないかと訊ねてきた。私の方は前に明治、大正、昭和にかけての連作を書いているので、そのとき役に立った本をあれこれ思いあわせてみた。明治と昭和にはそれぞれ編年史があるけれど、大正のは無かったように思う。私は最初に明治時代を書く時から、野口冨士男さんに相談して、参考になりそうなものをその都度七八冊挙げてもらった。野口さんは蔵書家で、得難い古書を揃えているから、私はいつも羨ましく眺めていた。と、ここを読んで、野口冨士男の挙げた本ってなんだろう、と気になってしょうがない。このあとの文章で『東京の今昔』という写真集のことが登場し、これに啓発されて東京のあちこちを歩いてみたとのことが綴られている。芝木好子さんも「歩く人」だ。とかなんとか、このところ芝木好子さんに夢中なのだけれども、芝木好子さんが登場する戸板康二のエッセイに「ひいき」という名の『ハンカチの鼠』[*] 所収のエッセイがあって、芝木好子さんは戸板康二の劇評をかなり熱心に読んでいたことが垣間見られる。この文章の初出が「風景」で、戸板康二初登場の号だった。……と、なにかと「風景」はおもしろい。
#019
東京やなぎ句会の戸板康二(21, June. 2003)
■ Chronology【私製・戸板康二年譜 1915-1993】に追加修正。
■ このところ、古本屋の軒先の100円コーナーで「こ、これは!」という買い物を立続けにしている。そのうちの一冊が、東京やなぎ句会編『友あり駄句あり三十年』(日本経済新聞社、1999年)。まあ! こんな本が出ていたなんて! と大喜びの、「東京やなぎ句会」の全貌を伝えるダイジェストという体裁の本なのだけれども、「東京やなぎ句会」というのは、戸板康二が何度もゲストとして参加している句会で、その様子は、『句会で会った人』[*] で詳しく読むことができるし、このほかにも戸板さんは何度もエッセイの題材にしている。思えば、戸板康二を読むようになったまなしの頃に読んだ、矢野誠一著『戸板康二の歳月』(文藝春秋、1996年)で知ったのが最初だったか。矢野誠一さんは「東京やなぎ句会」のメンバーのひとりなのだ。それにしても「東京やなぎ句会」のメンバーはなんと豪華なことだろう。
- 入船亭扇橋(俳号:光石)
- 永六輔(俳号:六丁目)
- 大西信行(俳号:獏十)
- 小沢昭一(俳号:変哲)
- 桂米朝(俳号:八十八)
- 加藤武(俳号:阿吽)
- 永井啓夫(俳号:余沙)
- 柳家小三治(俳号:土茶)
- 矢野誠一(俳号:徳三郎)
- 江國滋(滋酔郎/1997年没)
- 神吉拓郎(尊鬼のち拓郎/1994年没)
- 三田純市(道頓/1994年没)
■ それから、同じく100円コーナーで、谷沢永一著『完本 紙つぶて』(文藝春秋、1978年)を買った。文庫本で完全版が出ていることを考慮しても100円は安いッ。さっそく、目をランランと輝かせて読みふけって、あまりの面白さに釘付け。坪内祐三の『シブい本』(文藝春秋、1997年)のあとがきには《学生時代の私にとって忘れられない二冊の新刊があった。谷沢永一の『完本・紙つぶて』と開高健の『白昼の白想』である。その洒落た装丁も印象的だった。その二冊の本の編集者であった萬玉邦夫さんによって、この私の初めての書評集を作ってもらえた。夢のようである。》とある。文庫本ではなくて、初版の単行本でこのたび初めて『完本 紙つぶて』を読むことになったのもわたしにとっては縁というものなのかもしれない。
■ 前々回の制作ノートで書いたとおり、密偵おまささんのページで『紙つぶて』に戸板康二の『演芸画報・人物誌』[*] のことがチラリと登場していることを知ってとても嬉しかった。『完本 紙つぶて』読了記念に、わたしのページにもそのくだりを残しておこう。
浅野時一郎『私の築地小劇場』(秀英出版)は、大正13年6月から昭和3年12月25日小山内薫の死まで、現代演劇人が青春の夢をかけたアルト・ツキジ第一期の公演の全部を見て書きとめた貴重な記録。その解題を書いている戸板康二には、明治大正昭和劇評家論というべき好著『演芸画報・人物誌』(青蛙房)があって、本当の劇評の心意気を論じている。(45・11・20)それから、戸板康二が学生時代に、永井荷風が朝日新聞で岡鬼太郎の花柳小説を絶賛しているのを見てさっそく買いに行った、というくだりがとても印象的だったので、以前から年譜に加えてあったのだけれども、なんという機縁、『紙つぶて』に荷風が鬼太郎の花柳小説を激賞したことへの言及があったので、ここを年譜に抜き書き。正確な年月は昭和10年2月だった。
■ 谷沢永一の『完本 紙つぶて』に興奮のあまり、その続編『紙つぶて 二箇目』(文藝春秋、1981年)を図書館で借りて、またもや目をランランと輝かせて読みふけった。正・続を通じて、付箋紙をはさみたい衝動にかられる箇所が多すぎて大変大変! 完全版の文庫本(文春文庫か PHP 文庫)の発見が待ち遠しい。いつになるのかな。同じく、図書館で借りたのが、江國滋著『読書日記』(朝日新聞社、昭和54年)。「小説新潮」に連載の「読書日記」をまとめたもので、ここにも『完本 紙つぶて』のことが載っていて、なにかとシンクロしている。さらに、戸板康二の『ちょっといい話』[*] のことも登場していて、その間然するところのない論評に頬が緩みっぱなしだった。
昭和53年4月8日(土)晴本当にその通り、ちょっとした暇つぶしのつもりでほんの気まぐれだったとしても、いったん『ちょっといい話』をめくると、つい次から次へとページを繰って止まらなくなってしまう。江國滋みたいに、就寝時にほんの気散じにめくって結果的に睡眠不足に、という経験はわたしも一度や二度ではない。
旅先に携行した戸板康二氏の評判作『ちょっといい話』の続きを、帰宅後一献しながら読了。銀波荘での三夜、睡眠薬代りのつもりで拾い読むうちに、おもしろすぎて結果的に睡眠不足を招来したエスプリ・メモワール。各界知名の淑女紳士五百人の逸話、寸言、奇行、珍談のたぐいを一冊に満載した絢爛たるゴシップ集である。半世紀に及ぶという "戸板コレクション" の、量と質の両方に改めて舌を巻く。聞き流してしまえばそれっきりだし、保存が悪ければたちまち鮮度が落ちたり腐ったりしてしまうところがゴシップというものの厄介な通有性である。そいつを丹念に冷凍保存して、解凍と同時にさっと食卓に供したように見えてさに非ず、解凍後に火を通したり、裏ごしにかけたり、香辛料で味をととのえたりしたものをもう一度よく冷やした上で、食べやすいように一と口ずつきれいに盛りつけたといったぐあいの、なんとも贅沢なオードブルの饗宴。
「秦豊吉さんが、日劇のショウを演出する時、真木小太郎さんの前で、音楽家に、『あの曲を縮めろ、この曲はとってしまえ』といっている。『どんどん変えていいんだ。音楽は憲法じゃないんだ』」
この話、いちばん気に入った。
■ それから、『ちょっといい話』でよくあるのが、あの人物のあのエピソードが面白かったなあと追憶して、本文はどんなだったかしらと探し始めてみるとこれがなかなか見つからなくて、どんどんページを繰っていつのまにか違うところを読みふけって、結局当初の目的を忘れてしまうということ。そんなときの、強い味方が、本読みの快楽にてこのほど完成をみた『ちょっといい話』人名索引だ。これは本当にすばらしい! 今試みに、上記の江國滋お気に入りのエピソードを探すべく秦豊吉(別名:丸木砂土)をひいてみたら、すぐに発見。なんて便利だろう! このエピソードがほかのエピソードとどういうふうにつながっているかもわかって楽しみはどこまでも尽きない。そして、結局『ちょっといい話』をしばし読みふける時間となる。と、これだけにはとどまらず、『ちょっといい話』人名索引を眺めて、こんな人も載っていたっけ、とめくってしまうのもオツだ。現に今さっき、わたしは志ん朝さんで『ちょっといい話』をめくり始めて、まやもやしばし『ちょっといい話』のページを次々と繰っていたのだった。と、言ってるそばからこうなのだ。
■ と、『ちょっといい話』を256倍おもしろくするツール、『ちょっといい話』人名索引など、Links【戸板康二・関連ページへのリンク】も修正しています。全四冊の「ちょっといい話」シリーズ、今後続々と、その索引がアップされるそうでございますよ。
■ ついでに、アマゾンでこしらえている現在入手可能な戸板康二の著書リストを修正。三月書房の『戸板康二俳句集』が消えてしまった。当の『ちょっといい話』文春文庫版もまだ残っている本屋さんも多いけれども、版切れのようだ。
■ しかし、このほどの山口瞳ムーヴメントのように、戸板康二がちょいと読まれ始めることもこの先ないとは限らない。金子さんの『ちょっといい話』索引完成とあたかも連動するかのようなタイミングでさる方からいただいたメイルによると、雑誌「Quick Japan」の最新号に掲載の小西康陽&坪内祐三&赤田祐一の鼎談にて、戸板康二の名前がほんの一瞬登場しているという。えー、なんですってー! と、さっそく立ち読みに出かけてみたところ、鼎談の冒頭でさっそく戸板康二の名前が登場していた。立ち読みなので記憶はだいぶあいまいだが、永六輔があんまり好きじゃないと言う坪内祐三に、小西康陽が「でも戸板康二は好きでしょう」とたずね、坪内祐三が「戸板さんの本は好きですねえ」と答える、というやりとりがあり、その下欄の注釈に戸板康二のプロフィールが! ワオ! 担当編集者さんに感謝しないといけない。さて、その注によると、小西康陽はなんと矢野誠一著『戸板康二の歳月』を愛読書として挙げていて、その記事が「Quick Japan」のバックナンバーにあるとのこと。えー、なんですってー! と再びびっくり。すぐさま当該の号をチェックしようと思ったのだったが、わたしが立ち読みしていた三省堂書店神田本店のサブカルコーナーには狙ったかのようにその号だけ在庫がない。いてもたってもいられず、東京堂仮店舗の跡地に燦然と登場のふくろうブックステーション2階に移動し、「Quick Japan」のバックナンバーを立ち読みした。小西康陽が愛読書100冊を紹介している記事に矢野誠一著『戸板康二の歳月』があって、戸板康二の本が好きだが、『戸板康二の歳月』はたいへん感動的だった、いうようなことが書いてあった(立ち読みなので記憶はあいまい)。ここでもう一度「Quick Japan」最新号を立ち読み、小西康陽&坪内祐三&赤田祐一の鼎談を走り読みしてみると、花森安治のことも話題にのぼっていて、そこで坪内祐三が得意そうに語っているエピソードは戸板康二の『あの人この人』に載っているエピソードであった。……というわけで、来るべき戸板康二ムーヴメントの胎動が感じられなくもない気がする昨今である。気のせいかしら。情勢を見守ろう。
← PREV | NEXT →