#012
『丸本歌舞伎』あれこれ、モンブランのショートケーキ(03, March. 2003)
■ 書くことが溜まっていたはずなのに、ずいぶんひさしぶりの更新になってしまった。仕切り直しということで、また少しずつ作っていこうと思う。
■ 今回はまず、Chronology【私製・戸板康二年譜 1915-1993】に追加訂正。
■ 昭和24年3月発行の『丸本歌舞伎』[*] は戸板康二を読むようになったまなしの頃に買った本。戸板康二の本に夢中になったのは『歌舞伎への招待』[*] がきっかけで、これを機に戸板康二による昭和20年代発行の歌舞伎書を次々と読むようになった、そのまっただ中で古本屋さんで見つけて買ったのだった。たしか、荻窪の竹中書店だったと思う。そんなこんなで、『丸本歌舞伎』は特に愛着のある本のひとつで、去年の芝居見物では、10月に『忠臣蔵』の通し、11月は『新薄雪物語』、12月は『彦山権現誓助剣』というふうに、次々と丸本歌舞伎の代表作を見る機会に恵まれて、特に11月と12月は未見の演目だったから特に嬉しかった。これで『丸本歌舞伎』で取り上げられている演目をすべて見るころができたわけで、とりあえずは一巡することができた。この本に載っている演目を見るたんびに、読みふけっている『丸本歌舞伎』、今月は富十郎の『吃又』が楽しみ。
■ と、個人的にもとても思い入れの深い『丸本歌舞伎』なのだが、年表を作ってみると、ますます魅惑的になる。というのは、まず、久保田万太郎と折口信夫とが発起人となって、発行直後の3月11日に芝の美術倶楽部にて催された『丸本歌舞伎』出版記念会のくだり、折口信夫が作った「平気平三困切石」というタイトルの『石切梶原』のパロディが上演されただなんて、まあ! 三島由紀夫も見物しているこの舞台、先日、古本屋で中公文庫版『折口信夫全集第24巻 作品4 創作』にシナリオが収録されているのを見つけたばかり。ちなみに、折口は「三田文学」に書評も寄せていて、それは書評スクラップブックに抜き書き済み。
■ 『丸本歌舞伎』出版記念会のもうひとりの発起人、久保田万太郎は、その年の5月に『わが歌舞伎』と『丸本歌舞伎』の二冊で戸板康二が第一回戸川秋骨賞を受賞した折に俳句を寄せている。『久保田万太郎全句集』(中央公論社)を繰っていて、偶然見つけた。
戸板康二君、 "丸本歌舞伎" に戸川秋骨賞をうく
夏 逸 る 玉 菜 の い の ち 抱 き け り
季題が「玉菜」の、万太郎の唯一の句。5月になったら、また胸のなかで反芻してみたい。
■ 今回の更新はもうひとつ。List【戸板康二・全著書リスト】に、『團十郎切腹事件』(河出書房新社)[*] と『歌舞伎歳時記』(知性社)[*] と『家元の女弟子』(文藝春秋)[*] と『句会で会った人』(富士見書房)[*] と『物語近代日本女優史』(中公文庫)[*] と『演劇人の横顔』(白水社)[*] の書誌データを追加。
■ 以上6冊のうち、5冊は去年に買った本、これらのお買い物メモは後日にまわすことにして、新しい年になって初めて買った戸板本は『演劇人の横顔』[*] 、セロテープで補修されているせいか、値段がとても安かった。この本を買ったのは2月の祝日、早起きして、竹橋の東京国立近代美術館に出かけて、まず工芸館の《ヘルマン・ムテジウスとドイツ工作者連盟》を見て、本館でその続きと《ヴォルフガング・ライプ展》を見物したあとで、ゆっくりと所蔵作品展を巡って美術館をあとにして、そのあと神保町で遅い昼食を食べたあとで、少しだけ古本屋さんを見たときに買った本。日曜日の神保町の閑散とした街並が結構好きなのだが、祝日の神保町は日曜日とはまた違った雰囲気、開いているお店が日曜日より少しだけ多い。休日の神保町、なかなかいい雰囲気でたのしかった。
■ さて、夕方はあいにくの雨になってしまったけれども、今日は雛祭り。『女優のいる食卓』[*] 所収の「正月」から「クリスマス」までの12篇の歳時記的なエッセイが大のお気に入りでちょくちょく読み返している。3月のタイトルは「菓子春色」となんとも愛らしい。
洋菓子では、さっきちょっと書いたいちごを使ったショート・ケーキが、ガラス棚の中で、春から初夏にかけての季節感を高らかに歌うものである。そして、いちごの季節になってはじめて、そのショート・ケーキも、いちばんおいしくなるようだ。ショート・ケーキのクリームというのも、ぼくは春の触感だと思う。シュー・クリームも春の感覚だし、コーヒーにひと匙おとすクリームもまた、三月の香りと味を、たたえている。という一節があって、あんまり洋生菓子が得意でないのだけれども、ちょいと気まぐれにいちごのショートケーキをティーサロンで食べてみようかしら、という気にさせられる「菓子春色」の文章なのだった。さてさて、前にもこのページで少し書いたことがあるのだけれども、「菓子春色」には以下のような一節がある。
きのう、自由ヶ丘のモンブランにはいったら、女雛男雛の顔をのせた細長いケーキを売っていた。古来の年中行事に洋風の趣向がはいって、一般の嗜好に向くような工夫が施されているわけだが、チョコレートの台の上に、チェリーの実をのせて、内裏様の顔にし、クリームや冠や目鼻をつけたケーキは、めずらしかった。
 と、ここを読んで以来、自由ヶ丘のモンブランでは今でも、戸板さんの感興をそそった「古来の年中行事に洋風の趣向がはいって、一般の嗜好に向くような工夫が施され」ているケーキは今でも作られているのか、とても気になっていて、桃の節句が近づいたら自由が丘のモンブランへ偵察に行こうと思いつつも毎年果たせずにいた。その長年(でもない)の宿願を昨日ようやく果たすことができた。モンブランへ見に行ってみると、店内に入るまでもなく、店頭のウィンドウにひな祭りケーキが数種類並んでいるではありませんか。きっと、戸板さんが見たケーキもこんな感じのケーキだったのだと思う。わーいわーいとこっそり写真撮影。本当だったら記念に購入したいところなのだが、洋生菓子があまり得意でないので、断念した。でも、写真を見ているだけでも、上記の「菓子春色」のいちごのショート・ケーキのクリームのくだりが胸に浮かんで、なんとなく嬉しい気持ち。
と、ここを読んで以来、自由ヶ丘のモンブランでは今でも、戸板さんの感興をそそった「古来の年中行事に洋風の趣向がはいって、一般の嗜好に向くような工夫が施され」ているケーキは今でも作られているのか、とても気になっていて、桃の節句が近づいたら自由が丘のモンブランへ偵察に行こうと思いつつも毎年果たせずにいた。その長年(でもない)の宿願を昨日ようやく果たすことができた。モンブランへ見に行ってみると、店内に入るまでもなく、店頭のウィンドウにひな祭りケーキが数種類並んでいるではありませんか。きっと、戸板さんが見たケーキもこんな感じのケーキだったのだと思う。わーいわーいとこっそり写真撮影。本当だったら記念に購入したいところなのだが、洋生菓子があまり得意でないので、断念した。でも、写真を見ているだけでも、上記の「菓子春色」のいちごのショート・ケーキのクリームのくだりが胸に浮かんで、なんとなく嬉しい気持ち。#013
築地座のこと(10, March. 2003)
■ Index【日日雑記・戸板康二書名索引】に、2003年2月までのデータを追加。
■ Links【戸板康二・関連ページへのリンク】にて、中央区立図書館を勝手に「戸板康二ダイジェスト」公認図書館とさせていただきました。
■ それから、アマゾンでこしらえている現在入手可能な戸板康二の著書リストを修正し、1冊ごとに余計なコメントも追加。「ユーズドストア」は考慮に入れず、新刊書店の棚で目でできるはずの戸板康二リストとして作成しています。実際には、このほかにも本屋さんで見かける本はまだ少しはあるはず。とにかく、さらなる復刊および新刊を願うばかり。
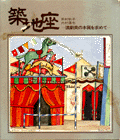 ■ 先日、年が明けて初めて、荻窪のささま書店に行った。今回は特に驚くような発見はなくて残念なような、でもちょっぴり安心なような、そんな気持ちになって、穏やかな心持ちで棚をめぐってお店をあとにした。と言いつつも、本を二冊購入。ふつうの古本屋でだいたい1000円くらいで売っていたら、まあ適正価格か少しお買得なくらいかなあという感じの本の値段をチェックすると、ささま書店ではそれはたいていいつも500円だ。という感じで、前から探していたというわけではなくて、棚でみかけてちょっといい感じだなあと思った本を二冊買って、計1050円のお買い物、というパターンがわりかし多い。先日のささま書店もそのパターンで、だいぶ表紙が汚れている『築地座』(丸ノ内出版、昭和51年)ともう一冊、とある落語関係の本を買った。表紙は伊藤熹朔の舞台装置図。
■ 先日、年が明けて初めて、荻窪のささま書店に行った。今回は特に驚くような発見はなくて残念なような、でもちょっぴり安心なような、そんな気持ちになって、穏やかな心持ちで棚をめぐってお店をあとにした。と言いつつも、本を二冊購入。ふつうの古本屋でだいたい1000円くらいで売っていたら、まあ適正価格か少しお買得なくらいかなあという感じの本の値段をチェックすると、ささま書店ではそれはたいていいつも500円だ。という感じで、前から探していたというわけではなくて、棚でみかけてちょっといい感じだなあと思った本を二冊買って、計1050円のお買い物、というパターンがわりかし多い。先日のささま書店もそのパターンで、だいぶ表紙が汚れている『築地座』(丸ノ内出版、昭和51年)ともう一冊、とある落語関係の本を買った。表紙は伊藤熹朔の舞台装置図。■ 築地小劇場の分裂後に友田恭助と田村秋子夫妻によって創設されたのが築地座で、顧問は久保田万太郎だった。同時代の「左翼」風な他の新劇集団とは異なり、あくまで「芸術的」だった築地座、その短い歴史における上演作品を時系列に紹介している。久保田万太郎の戯曲を読む際に、参照してみようと軽い気持ちで買った。戸板康二の数々の文章、たとえば『新劇史の人々』[*] といった本で鮮烈な印象を残している友田恭助、その姿を万太郎の『釣堀にて』を読みながら、頭に思い浮かべたりしている。《おもえば、この永い戦争は、友田恭助の死によりその初めを、丸山定夫の死によりそのおわりを、かなしくいろどられた。》(『演劇五十年』[*] より)。そんな戸板康二の書物を通じて興味津々の、日本の新劇史の副読本のひとつとして。
■ 戸板康二が初めて田村秋子の舞台を見たのが昭和9年、『あの人この人』[*] の「田村秋子の完全主義」冒頭に書かれている、そのあたりの情勢もこの『築地座』でヴィヴィッドに伺うことができる。それから、『演劇人の横顔』[*] によると、里見とんの『宮本洋子』という小説のモデルが田村秋子なのではないか、とのこと。ぜひとも読んでみたい!
■ ところで、この『築地座』の版元の丸ノ内出版は、戸板康二の『いろはかるた随筆』[*] の版元でもある。『築地座』巻末に、『いろはかるた随筆』の広告もあって、嬉しい。その隣には『歌舞伎いろはかるた』(戸板康二・吉田千秋作、解説付/700円)の案内があって、わたしの視線はそこに釘付け。おそらく『いろはかるた随筆』所収の「歌舞伎いろはかるた」を商品化したものと思われる。『いろはかるた随筆』に図版が収められている「歌舞伎いろはかるた」、カードの写真とカルタの文句とが見事に一致している素晴らしいカルタ。戸板さんがとある暮れに風邪で臥せっているときにこしらえたという伝説のカルタ。とっても欲しい!
#014
中村雅楽シリーズを思ふ(22, March. 2003)
■ まずは、Chronology【私製・戸板康二年譜 1915-1993】を追加修正。
■ Google で「戸板康二」を検索して、おおまかにではあるけれども、ひさしぶりに一通りチェックしてみた。そこから知った事実、ここでは主に受賞のことを少しだけ年譜に追加。今回のチェックで知って「おっ」と思ったことは、文化人類学者の船曳建夫氏が、影響を受けた本として『歌舞伎への招待』[*] を挙げていたこと。まあ! ぜひとももっと詳しい経緯を知りたい!
■ あと、もうひとつ。戸板康二の弟子筋の林えり子さんの日記ページを発見できて嬉しかった。戸板さんの亡くなった日は、今年の命日と同じような雪模様の寒い日だったとのこと、このくだりを目にしてちょっと胸がジンとなった。それから、去年の5月に戸板康二作の『ひとり息子――桜の園・その後のシャルロッタ』というお芝居の上演があったことを今になって初めて知った。ああ、なんということだろう。見逃してしまって残念無念……。
■ 「三田文学」1993年春季号の戸板康二追悼特集に寄せた文章の冒頭で、林えり子さんは《戸板さんは、昭和36年に塾の文学部へ特別講師として招かれ、……その教室に私はあまり優秀とはいえない学生として席に着いていた。》というふうに書いている。その林えり子さんは猿之助と同級だったようなのだが、もっとも猿之助の方は、戸板康二の『百人の舞台俳優』[*] によると《猿之助は、慶応義塾で、ぼくの演劇史の講義を単位にとって卒業した。もっとも、在学中、彼が教室に来ていることすら知らなかった。試験の季節に突然、喜熨斗政彦という名前で手紙が来た。テレビの仕事で講義をなまけました。申しわけありませんと書いてある。その手紙の来た時は、ぼくはもう猿之助のリポートを採点して、大学にまわしたあとであった。決してわるい点ではなかった。》とのこと、なかなか抜かりのない喜熨斗君なのだった。
■ 『見た芝居読んだ本』[*] の解説で、《芝居を見、劇評をし、読書に伴う書評を書き、推理小説や随筆の筆を執り、その合い間にかつてより少なくなったといわれるがそれでも結構な数にのぼるさまざまな会合に出席するという多忙さを、戸板さんは豪華客船が洋上を行くように折り目正しく優雅にやりおおしているのだ。》と、往年の戸板さんの姿が目に浮かぶような素敵な描写をしている林えり子さん、「三田文学」の追悼の文章で以下のように書いている。
戸板さんは、あるとき、ふと、こんなことを口にされた。「ぼくには、演劇評論という本職があるからね」。この一言は、私の裡でしだいに増殖されてゆき、やがて大きな意味を持つことになるのである。戸板さんの執筆分野の広さは、いまさらに私が言うまでもなく、また博識ぶりもつとに有名、そうした幅広さ、知識の豊富さというものは、何かひとつ分野で一家を成すことによって生じて来るものだということを、その一言にこめられていたのではないか、と私は思った。戸板さんにとって小説、推理小説、エッセイ、俳句、戯曲(演劇評論での本道とでもいえる歌舞伎の脚本は絶対に筆を執らなかった)、人物誌は、余技に属していたのだと思う。実際、たのしんで書かれていたように、私には見えた。この、「ぼくには、演劇評論という本職があるからね」という一言は、戸板康二読みにおいて重要なヒントになるような気がする。
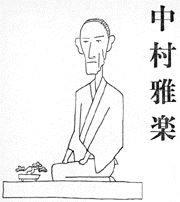 ■ ここから先は、中村雅楽特集。右の画像は、横溝正史編『別冊文芸読本 日本の名探偵』(河出書房新社、昭和55年)に掲載の、山下勇三氏による挿絵。この本には『車引殺人事件』が収録、新保博久氏による雅楽紹介が嬉しい。同じく著者紹介もあり、そこに《『宝石』の廃刊(昭39)とともに雅楽譚は休止されたが、その後も推理小説の執筆は続き、昭和46年頃より雅楽も再登場。》という一節がある。中村雅楽チェックリスト(謎宮会作成)を参照してみると、たしかに『淀君の謎』あたりで、一線を区切ることができそう。それにしても、謎宮会ホームページは素晴らしい。これで、雅楽シリーズ読み、鬼に金棒です。
■ ここから先は、中村雅楽特集。右の画像は、横溝正史編『別冊文芸読本 日本の名探偵』(河出書房新社、昭和55年)に掲載の、山下勇三氏による挿絵。この本には『車引殺人事件』が収録、新保博久氏による雅楽紹介が嬉しい。同じく著者紹介もあり、そこに《『宝石』の廃刊(昭39)とともに雅楽譚は休止されたが、その後も推理小説の執筆は続き、昭和46年頃より雅楽も再登場。》という一節がある。中村雅楽チェックリスト(謎宮会作成)を参照してみると、たしかに『淀君の謎』あたりで、一線を区切ることができそう。それにしても、謎宮会ホームページは素晴らしい。これで、雅楽シリーズ読み、鬼に金棒です。■ さて、本日2つ目の更新。List【戸板康二・全著書リスト】に『車引殺人事件』(河出書房新社)[*] と『劇場の迷子』(講談社)[*] と『美少年の死』(広論社)[*] の書誌データを追加。
■ わたしにとっては戸板康二の推理小説は高嶺の花で、半年に1冊購入する機会がめぐってくればいい方だったのだけれども、ああ、なんていうこと! この一週間で矢継ぎ早に3冊も購入することになるなんて! まずは、ひさしぶりに日本の古本屋をチェックしてみたところ、『車引殺人事件』(河出書房新社)[*] を発見、値段は今まで買った戸板康二の推理小説のどれよりも安い。何かの間違いではないかと思いつつも、わーいわーいと申し込んだ3日後、いつもチェックしているウェブ古本屋さんで『劇場の迷子』(講談社)[*] が売りに出ていたので即申し込んだ。この本は前はよく古本屋さんで見たのだけれども、最近は全然目にすることがなくて、見つけたらすぐに買おうと思っていたのだ。わーいわーい。そして、昨日、ふらりと荻窪のささま書店に行った。ささま書店は、ある日ふと行ってみると、大変なことになっていることがままあるのだが、昨日がまさしくそう、『美少年の死』(広論社)[*] だけでもびっくりだというのにこれ以外にもいろいろ欲しい本があって、ここまでくると困ってしまうくらい。今回断念した本を後日買いに行くと、今度はどれもこれも棚から消えていて心底がっかり、といういつもの展開が待っていそうな気がする。
■ 前に一度『車引殺人事件』を手にしたことがあって、それは都立中央図書館でのこと、江戸川乱歩の序文が目当てだった。いざ乱歩の文章を初めて目にしたときの胸の高まりは、今でもとても鮮明だ。さっそく複写申込みをして、帰り道でも何度も読みふけった。その序文は、書評スクラップブックに抜き書き済み。
■ しかし、この乱歩の文章を読んでもっとも嬉しかったのは戸板康二本人であったのは確実で、『わが交遊記』[*] の「江戸川乱歩」の項に、《初めて河出書房から出た単行本には、江戸川さんの序文を頂戴した。河出の坂本一亀君にコピーをとってもらい、もとの原稿を大切に保存しているが、ここでも江戸川さんは、ほめ上手で、何ともうれしくなってしまう序文を書いて下さった。》という一節がある。まあ! 伝説の辣腕編集者・坂本一亀の名前がここにも! 去年亡くなった坂本一亀と戸板康二の関わりは、おそらく昭和26年に河出より発行の『演劇講座』全5巻からのものと思われる。『演劇講座』全5巻にまつわることもいろいろ気になることがあるのだけれども(福田恆存のこととか)、ここではとりあえず、昭和の名編集者・坂本一亀に慎んで哀悼の意を。ところで、戸板家には、今でも乱歩の序文の生原稿が保存されているのかな、そんなことを思うとちょっとワクワク。戸板康二は編集者として折口信夫から歌舞伎に関する原稿を受け取った際、自分で書き写して元の原稿の方を手元に残して大切に保管したという。というと、折口信夫の生原稿もあるに違いない。それにしても、折口信夫の原稿を受け取った戸板康二の喜びが伝わってくるような、ちょっといい話だと思う。
■ 中村雅楽シリーズというと、去年の晩秋、『團十郎切腹事件』[*] を買った。黒の余白をいかした表紙が好きだ。『車引殺人事件』と同様、「宝石」に初めて掲載されたとき戸板康二の小説の挿絵を描いた、神保朋世によるもの。神保朋世の名前は『句会で会った人』[*] でも目にしたことがある。ちょっと気になって調べてみると、弥生美術館で《神保朋世展−芳年・年英・英朋・朋世の系譜をたどる−》という展覧会が平成9年4月から6月にかけて開催されていたそう。それから、去年の晩秋の買い物というと、『家元の女弟子』[*] をとある古書展で200円だったので無視できずに買った(おっと、今まで買った雅楽シリーズ、最安値はこれであった)。思い起こせば、わたしが初めて読んだ雅楽シリーズは文春文庫版『家元の女弟子』[*] なのだった。このことに関しては、さる方に感謝しないといけないのだ。
■ ……とまあ、そんなこんなで、全然まとまっていないけれども、初心にかえって、戸板康二の雅楽シリーズを熟読したいなあと思っているところ。
← PREV | NEXT →