#008
奥村でみた喜多村緑郎、奥村で買った「日本演劇」(12, October. 2002)
■ Index【日日雑記・戸板康二書名索引】に、2002年9月記入のデータを追加。
■ Amazon.co.jp を使ってこしらえている現在購入可能な戸板康二の著書リストを最新のものに変更。『最後のちょっといい話』が購入可能に変っていた。毎月10日くらいになると、いつも寄っている本屋さんに来月の新刊文庫一覧が貼り出されるので、その壁際にしばし立ちすくみじっと凝視、という怪しい人物と化すこととなる。いつもまっさきに探すのは戸板康二の名前なのだが、11月の新刊でも見つけることはできず。岩波文庫か平凡社ライブラリーか講談社文芸文庫にいつの日か戸板康二の本が入ってほしい。『すばらしいセリフ』につづいて、ちくま文庫でもぜひぜひ。どの文庫でもいいから、ぜひとも復刊させてほしい。……と、妄想は果てしなく続く。でも、講談社文芸文庫に久保田万太郎が入って欲しいッ、とひとりで勝手に念じていたら、あれよあれよと今年の8月に実現してしまったので、ひとりで勝手に念じていると本当に実現することだってあるかも。というわけで、しつこく、戸板康二の本が文庫本に入りますように!(かしわ手)
■ 少し前のことになるけれども、奥村書店の棚をひさしぶりにじっくりと眺めていたときのこと。喜多村緑郎著『わが芸談』久保田万太郎宛署名付き、というのが目に入ったとたんその背表紙に釘付け。うッ、猛烈に欲しい。そのときの心境はさながら「買ってー! 買ってー!」と街かどで駄々をこねるお子様。万太郎宛の喜多村緑郎の著書だなんて、まあ、なんて魅惑的なことだろう、なんと見事な組み合わせだろう。……しかし、越えてはならない一線というものがある(ような気がする)。決して高くはないと思ったけれども、さすがに購入はせず。万太郎と喜多村緑郎という組み合わせについて思いを巡らせるひとときとなって、悶々としつつも、思いがけなく楽しい時間だった。
■ 万太郎は喜多村へ宛てて句をいくつかこしらえていて、『万太郎俳句評釈』を参照すると、喜多村と万太郎の交流は大正4年、本郷座で万太郎が『日本橋』を演出したときにさかのぼるという。喜多村は万太郎より19歳も年長、戸板康二は万太郎が登場する喜多村の日記をいくつか引いて、ふたりの交流について《あまり愛想のよくない者同士の酔態は、どうであったろう》と思いを馳せている。喜多村の日記は二人の気のおけない交流が伺えて、とてもいい感じ。『万太郎俳句評釈』の見出しになっている句は「浪裡白跳河童の多見次ほとゝぎす」、喜多村の当り役、泉鏡花原作『風流線』を詠じたもの。
■ 戸板康二も喜多村のことはよく知っていた。『みごとな幕切れ』所収の「回想・新派十二人」を参照してみると、《喜多村の著作には『芸道礼讃』『わが芸談』があるが、じつにおもしろい》とのこと。まあ! 戸板さんのお墨付き! やっぱり『わが芸談』、欲しい……。喜多村について、戸板康二は《私生活も至ってハイカラなひとで、ナイトガウンを着て、ウィスキーや葉巻を愛用していたという。私の知っている喜多村は老年に達していたから背中もいく分曲っていたが、新派の役者というよりも、文人の風格が感じられた》と書く。そうそう、実のところ、わたしが喜多村に興味を持ったそもそものきっかけは、戸板康二が中村雅楽のイメージについて、《20年ほど前の喜多村緑郎の生活感覚を、歌舞伎役者の中にもちこんでいる》と書いていたから。その生活感覚について詳しく探ってみたい。
■ わが愛読書、古川緑波著『劇書ノート』(筑摩叢書)では、喜多村緑郎の本、昭和18年発行の『芸道礼讃』が取り上げられている。喜多村の文体は、ロッパによると《一寸久保田万太郎を思わせる江戸下町調、文字づかい仮名遣いに好みが強く、いっぱし理屈があって、動かせないという感じすらある。舞台同様一くせも二くせもある文章が、まず嬉しい》。そういう文体のよろこびだけではなく、内容も《いい話だなアと、うっとり読んでいた僕だ、しみじみといい芸談の連続だ》とのこと。まあ! こんなくだりを読んでしまうと、ぜひとも喜多村緑郎、読まねばッと思う。一くせも二くせもある文章でもって、その舞台についてもいろいろ思いを馳せることができそうな気もする。
■ ……などなど、奥村書店から帰って部屋で何冊か本をめくることで、心の整理を試みた次第であった。『わが芸談』の一節は、戸板康二編集『日本の名随筆「芝居」』で読むことができる。
■ その日の奥村書店では、「日本演劇」が何冊か売っているのを見た。1冊200円だった。喜多村緑郎に興奮の余波で、数冊買ってしまった。「日本演劇」を買ったのは、去年、月の輪書林の目録で1冊買って以来のこと。当時は深い考えもなく申し込んだのだったが、届いたのは昭和19年9月号、奇しくも戸板康二が編集に携わった最初の号だったのだ。「日本演劇」の最終号は昭和25年4月号。久保田万太郎の脚本『大つごもり』が掲載されているとのこと。戸板康二が編集に携わった「日本演劇」は全部で何冊になるのかな。古本屋で安価で売っているのを見つけたら、ひょいとたまに気まぐれで買うというスタンスで、少しずつ手元に集めていきたいなあと思っている。
■ 「日本演劇」を数冊まとめて眺めてみると、まず目に映る表紙がなかなか楽しい。ここでは三冊、並べてみた。
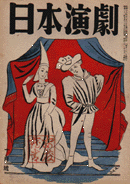

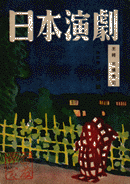
|
■ 戸板康二ダイジェストに追々、雑誌コーナーを設けようと思っている(いつになるかわからないけれども……)。編集者としての戸板康二、という観点にわたしはとても興味津々で、昭和19年から昭和25年までの戸板康二の仕事を具体的に探ってみたい。と、抱負だけはいつだってたっぷりとあるのだった。
#009
『演劇五十年』と『むかしの歌』(14, October. 2002)
■ List【戸板康二・全著書リスト】に、『演劇五十年』(時事通信社)[*] と『むかしの歌』(講談社)[*] の書誌データを追加。
■ ひさしぶりに吉祥寺に立ち寄った。せいぜい西荻どまりで最近はとんと御無沙汰だった。「ひさしぶりだなア」と上機嫌で、その帰り道、よみた屋という古本屋に行ってみた。ひさしぶりに来てみると、店内の様子が以前と変っている。整然とした棚が嬉しい。まず芝居や寄席関係のところをチェックすると、さっそく、戸板康二の『演劇五十年』を発見。この本は長らくの懸案だった。あらかた読み終えた昭和20年代の著作のなかでの唯一の未読、特に夏以来、演劇史的なことにあらためて興味津々なので、近くこの本を買いに行こうと思っていたところなのだ。奥村書店の奥の方の棚にいつも売っていたような気がする。たしか1500円か2000円くらいだったと思う。が、もっと安くどこかに売っていないかしらと、せこい了簡をおこしていたところでもあった。なので、今ここで、『演劇五十年』はいったい幾らで売られているかッ、値段チェックのその瞬間はなかなかスリリングだった。そして! 結果はなんと1000円未満の数百円。こんなに嬉しいことはない。わーいわーいと即購入を決意。ほかにもなにかないかしらといろいろ見てまわったのだけれども、『演劇五十年』を(安く)見つけて興奮のあまり、あまり落ち着いて探索できず、今日はこれ1冊のみのお買い物。『チェーホフ・クニッペル往復書簡』という本の存在を初めて知って、しばし立ち止まったりした。
■ 以前は、よみた屋ではやたらと本を買っていた、と同時に、やたらと売り払ってもいた。不思議と、戸板康二の本はここでは一度も買ったことがなかったのが、ひさしぶりに来てみると、買ったのは戸板康二1冊のみということになった。などなど、追憶にひたりつつ東西線に乗り込んで、さっそく『演劇五十年』のページをめくって、さっそく第三章まで読んだ。いろいろな本で垣間みている演劇史に関するいろいろなことをあらためて、戸板康二の文章でさらうことになって、さっそく面白い。《著者の見解によれば、二十世紀の初頭、この團・菊二人によって、歌舞伎は大成され、終止符を打たれたものとしたい。》という一節があった。あらためて、明治劇壇のこと、日本の近代のこと、いろいろなことに思いを馳せることができそうだ。團菊、新蔵のところでは、谷崎の『幼少時代』に載っていた鏑木清方の挿絵のことを思い出したり、芝の紅葉館のところでは、綺堂の『ランプの下にて』のことを思い出したり……。わりと新劇に重点がおかれているのも嬉しいこと、続きがたのしみたのしみ。
■ 一週間以上前のこと、これまたひさしぶりに、荻窪に行った。駅の近くの古本屋さんを少しめぐって、最後はささま書店へ。ささま書店は、しばらく行っていないと、それだけで損をした気になる古本屋さん。とりあえず、定期的に行っておかなくてはいけないような気がする。でもあまり頻繁に行くと、買い過ぎてしまうので節度が必要である。その兼ね合いが難しい。とても難しい。さてさて、その日のささま書店で買ったのが、上記の『むかしの歌』。これなら買ってもいいかなあという値段の半額くらい。『むかしの歌』はそれまでのエッセイ集から戸板さん自身が選んだ47本の文章が収録されているアンソロジー。なので、いずれも目にしたことのある文章ばかり。読む必要はないかというと決してそんなことはなくて、編集の妙というか、あらためて目にすることで、また新鮮な気持で読み返すことができる。その時間のなんと至福なこと、という感じで、なんとも嬉しい1冊だった。昭和17年の『俳優論』から40年近い年月にわたる文章が収録されている『むかしの歌』、あとがきには、《読み返して、それを書いた時の自分がなつかしく、その時代に対して、郷愁が湧いて来る》という一節があった。それはそのまま、戸板康二のエッセイ集を何度も読み返しているわたし自身にもあてはまること。『むかしの歌』であらためて読みかして、「おっ」という発見があったり、戸板康二に夢中の年月をいろいろ振り返った時間でもあった。
#010
森茉莉の「ドッキリチャンネル」(20, October. 2002)
■ Chronology【私製・戸板康二年譜 1915-1993】に追加訂正など。
■ 先日の演博の《よみがえる帝国劇場展》見物の余滴ということで、『思い出の劇場』からいくつかピックアップして追加。戸板家そろって帝劇へイタリアのカーピ・オペラの『椿姫』を観劇したくだりが印象的だったので、図書館で『帝劇の五十年』という本で正確な月を調べた、と、裏をとったのはここのみ。高野正雄著『喜劇の殿様 益田太郎冠者伝』によると、太郎冠者の「コロッケの唄」の歌詞は延々十番まで続くとのこと、歌詞全文がどうなっているのか非常に気になるッと思って、図書館で調べたが、どの本を見ても5番くらいまでしか載っておらずがっかり。こうなってくると、ますます十番までの歌詞が気になる。
■ 戸板康二の名前を知る以前から部屋の本棚にあった本を数年ぶりに繰って、思いがけない局面で戸板康二を発見する愉悦について、以前ここに書いたことがあった。つい最近も大興奮なことがあった。懸案だった部屋の本棚の整理整頓がやっとのことで完了して、すっきり。結構処分したので、本当に必要な本は何なのか、あらためてじっくりと心に刻むこともできたのがよかった。で、実に数年ぶりに、『森茉莉全集』を手にとって、なんとはなしに「ドッキリ・チャンネル」の収録されている巻(第五巻と第六巻)を読みはじめると、もう夢中。数年ぶりにめくってみると、芝居と寄席関係のところが、近年にこれらに夢中になっている身からすると、とりわけ面白い。森茉莉も宮戸座の源之助に心奪われていた人だった。森茉莉は1903年生まれ、古川ロッパと同年、戸板康二より一回り上のウサギ年だ。
■ なにかと心がスウィングの「ドッキリ・チャンネル」、以下の一節に「あっ」となった。
中村勘三郎の名推理を働かせる役者が出るドラマがあったのにうっかりしていて、終りに近いところから見た。残念だった。飯沢匡の、歌舞伎の世界を舞台にした推理小説と共に、秀でたものである。って、えー! きっとここで言う「中村勘三郎の名推理を働かせる役者が出るドラマ」って、戸板康二の中村雅楽シリーズが「土曜ワイド劇場」で3回ドラマ化されて、勘三郎が雅楽役を演じたものを指しているのよね? そして、「歌舞伎の世界を舞台にした推理小説」というのは、飯沢匡ではなくて戸板康二の雅楽シリーズのことよね! とかなんとか、大興奮だった。「ドッキリ・チャンネル」は週刊新潮に昭和54年から5年半連載されていた。その「中村勘三郎の名推理を働かせる役者が出るドラマ」のところは1981年末の執筆、 Chronology【私製・戸板康二年譜 (Page 4 of 4)】で確認すると、勘三郎の雅楽シリーズ放映日とは一致しない。なので、うーむ、森茉莉の言う「中村勘三郎の名推理を働かせる役者が出るドラマ」は中村雅楽ではないのかもしれない。でもでも、「歌舞伎の世界を舞台にした推理小説」は戸板康二の小説を指しているのは間違いないッ、と思う。……ということがあったりなんかもして、「ドッキリ・チャンネル」をさらに読み進めていくと、今度は以下の一節に「おっ」となった。1983年のところ。ちょっと長くなるけど、ここの箇所全文抜き書き。
「花ホテル」は、題名が、花ホテルというのにしては建物も客種にも、贅沢な雰囲気がなく、僅かに料理人の益田喜頓にそういうものが見られるに過ぎないのが、気に入らなかったので、見ぬようになったが、中村勘三郎の名が見えたので見てみると、勘三郎の客がホテルに入った日、無理やりに、入り込んで来ていた三人のチンピラが使用人を脅して金庫を開けさせて金品を奪い、その使用人を金庫に閉じこめる。そこへ勘三郎の客が来て雑作なく金庫を開ける。この勘三郎の客が、ルパンと言われている、巴里で堅牢な牢獄を何度も抜け出した怪盗とわかる。この勘三郎の役の設定がどうも私には、勘三郎の人(ニン)にないような気がする。昔、中村雅之丞(?)という歌舞伎役者が本職跣足の名探偵で、入り組んだ事件を難なく解いて犯人を御用にする、という小説があって、映画化も、テレビ化もされなかったが、面白かった。勘三郎の役もそういう設定だったら、面白く見られただろう。ですって! まあ! 「中村雅之丞(?)という歌舞伎役者が本職跣足の名探偵で、入り組んだ事件を難なく解いて犯人を御用にする、という小説」が、戸板康二の中村雅楽シリーズをのことを言っているのはもう間違いないだろう。雅楽と雪之丞とが混じって、森茉莉の記憶のなかで「中村雅之丞(?)」となったに違いない。中村雅楽シリーズは、舞台化もテレビ化もされていて、それ以前に3度も当の勘三郎が演じているのだが、森茉莉は見逃してしまったのか、それともそうとは知らずに見ていたのか。でもでも、なにはともあれ、森茉莉は、戸板康二の雅楽シリーズをとても面白く読んでいた、ということがわかったことは、なんともまあ嬉しいことで、愉悦の時間だった。そういえば、大岡昇平の『成城だより』には、森茉莉の長男のフランス文学者、山田爵(←に似た字)が雅楽シリーズの愛読者だというくだりがあったのだった。森茉莉も雅楽シリーズの愛読者だった! ということで、実のところ、雅楽シリーズの熱心な読者とは、あんまり言えなかったわたしなのだが、これからは心を入れ替えて、雅楽シリーズを追いかけることに決めた。
■ さきほど、名前の出た飯沢匡については、「ドッキリ・チャンネル」には以下のような一節があった。獅子文六が出てくるのが嬉しいので、さらに長くなるけど抜き書き。
浜っ子の方も会ったことがないが、港町なので、文明開化も東京っ子より一足先だったらしい。「帽子と鉢巻」の飯沢匡か、「大番」の獅子文六のどっちかがたしか浜っ子だったと思うが、飯沢匡が(獅子文六は亡くなったが)この頃ちっともああいう面白いのを書いてくれないことこそ憾みなれ、である。今も覚えているのは「帽子と鉢巻」で、能を遣る人々が巴里へ行って「能」を遣る箇所でシテが出てくる橋がかりの松がないというのでフランス人の関係者ともども巴里の郊外へ行く。それ、あったというと二人位車から下りて根ごと抜く。一人のフランス人が「en voiture」(車にのせろ)と叫んでそれをのっけるところである。獅子文六の「大番」という標題はこの頃では一寸意味が通じなくなった。現今(いま)ではL・M・Sサイズで言うが昔はシャツなぞのサイズを大番、中番、というように言ったのである。あそこの親父は大番でもちいさすぎるが○○なんかは小番でも余るんじゃないか? 経済でいいや、などと言ったものである。大番頭、中僧、小僧なんていう称号もなくなった。「帽子と鉢巻」の巴里で煙草を買うところも、面白かった。両方とももう一度読みたいのでS誌に探して貰うことにしよう。飯沢匡や獅子文六のああいう小説について「新潮」(文芸雑誌)に書いた時私は、飯沢匡や獅子文六が年中交る交るに、ああいう小説を書いて発表してくれたら、わが世は春、退屈しらずだろうと、書いたことがあった。ああいう小説が、毎日、新聞に出て、それを横になって読む、そこに丼に入れた柿の種か品川巻きがあれがこの世の幸福これにすぎるものはない。そうそう、まさしく、獅子文六の小説はそんな小説、これがあれば、わが世は春。そして、飯沢匡の『帽子と鉢巻』、森茉莉が戸板康二と混同した(と思われる)飯沢匡のお能が登場する小説、ぜひとも近いうちに読んでみようと思う。たのしみたのしみ。
#011
演劇博物館、「芸術新潮」(27, October. 2002)
■ List【戸板康二・全著書リスト】に、『六代目菊五郎』(演劇出版社)[*] の書誌データを追加。
■ まず、先日の演博の《よみがえる帝国劇場展》見物の余滴・その2。早稲田大学構内の演劇博物館に初めて行ったのは1999年初夏の《六代目菊五郎展》のときだった。菊五郎展以降、毎年のように演博に足を運んで、《三遊亭円朝展》《五代目歌右衛門展》などなど、それに今回の帝劇展、毎回大充実の時間だ。演劇博物館の存在を初めて知ったのは、歌舞伎に夢中になった直後の1998年10月の歌舞伎座で、坪内逍遥作の常磐津の舞踊劇『お夏狂乱』を観たときのこと、雀右衛門の踊りを堪能したのだったが、その公演は「早稲田大学演劇博物館創立70周年記念」と銘打った興行だった。ふむふむ、早稲田大学には演劇博物館というものがあるらしい、行ってみたいな、と思ったのだったが、なんやかやで行き損ねていて、1999年の《六代目菊五郎展》のときに初めて来訪することとなった。
■ 本格的に歌舞伎を見るようになってからまだ間がなく、当時は演劇史的なことには不案内だったが、今思うと、たいへん充実した展覧会だったことだろうと想像される。現段階で、あのときの展覧会を見てみたいと何度も思った。と、ときどき思い出しては、菊五郎展の目録を買っておかなったのが悔まれるッ、とずっと思っていた。去年の7月に六代目歌右衛門の追悼の展覧会に行ったときに図書室で目録を閲覧して、慶応の予科の学生のときに菊五郎論に投稿して採用された「歌舞伎を滅ぼす勿れ」と題された戸板康二の文章が掲載されている「演芸画報」の誌面、という、戸板ファン大喜びの展示もあって、号数を控えて、後日、奥村書店で購入したのも嬉しいことだった。展覧会で見物した当時は、まだ『歌舞伎への招待』を読んでいなくて、暮しの手帖連載の『歌舞伎ダイジェスト』を買ったのはその年の2月のこと、その後、戸板康二に夢中になって、そういえばあのときの菊五郎展には、と、ときどき「歌舞伎を滅ぼす勿れ」のことを思い出してはいた。
■ 先日の演博の《よみがえる帝国劇場展》見物のとき、今回の展覧会の図録は売っているのかしらと思って、図書室に足を踏み入れてみたところ、目当ての帝劇展の図録はまだ出ていなかったのだけれども、上記の菊五郎展の目録コピーが1部200円で売り出されていたので、「まあ!」と喜びいさんで購入することに決めた。実は、去年の7月に閲覧して以来、ずっとコピーをとらねばとらねばと思っていたのだけれども、なんやかやでそれっきりになっていたので、長年の宿願達成と相成った。いろいろ嬉しいことばかりの演劇博物館。
■ というわけで、先日の演博の《よみがえる帝国劇場展》見物の余滴は、1999年開催の《没後五十周年記念 六代目菊五郎》の目録のコピー冊子。これがもう、じっくり眺めていると、時間を忘れてしまい、気がつくと夜更けになってしまっていることがしばしば。「おっ」と思ったところを挙げようとするとキリがないので、ここではひとつだけ、谷崎の『細雪』のところ、昭和14年5月の歌舞伎座を観劇する場面があり、鶴子は初代鴈治郎の贔屓、幸子は菊五郎贔屓、贔屓役者でもって絶妙に描き分けられている人物描写。そういえば、菊五郎贔屓のママンに向かって「あれは歌舞伎じゃないわ、新歌舞伎よ」とあくたいをついていた森茉莉は、源之助贔屓だったという。 『細雪』を読んだのは、歌舞伎を見るようになったずっと以前だったせいか、このくだりはまったく記憶にない。ぜひともいつか再読せねばッ。なにはともあれ、歌舞伎を見るようになってから、さらに日本近代文学が楽しくなったことは、嬉しいことだ。
■ あと、戸板康二の「歌舞伎を滅ぼす勿れ」のことを。3年前に展覧会を見物したときも、去年7月に図録の閲覧をしたときも、戸板康二の名前しか目に入らなかったのだったが、今回よくよく見てみると、隣には、武智鉄二の個人雑誌の展示があり、これだけでも戸板康二と武智鉄二の対照性のようなものが見えてくる感じで、うーむと唸ったりも。
■ ……などなど、先日の演博の《よみがえる帝国劇場展》見物の余滴の《六代目菊五郎展》の目録のことでちょっと長くなってしまったけれども、ここから先は、最近のお買い物について。
■ 演博の図録で六代目菊五郎とその時代に思いを馳せていたところ、まあ、なんという因縁、ふとなんとはなしに足を踏み入れた古本屋さんで、戸板康二の『六代目菊五郎』の初版が売っていて、値段も手ごろだったので、わーいと買った。戸板さんの『六代目菊五郎』は、去年5月に講談社文庫で読んで、メロメロだった。初版の単行本では、口絵として写真を何枚か見ることができるので、いつか欲しいなあと思っていたのだ。この本は、戸板さんの歌舞伎書のなかで特に好きなもののひとつ。
■ その古本屋さんは、とある住宅街にあるお店で、定期的に訪れている場所なので、ちょくちょく通りかかるのだが、あまり中に入ったことはなかった。『六代目菊五郎』を買った日は、店頭に昭和20年代から30年代にかけての「芸術新潮」が三十冊ほど積んであったので、ふと立ち止まって手にとって目次を眺めていった。昭和20年代の「芸術新潮」というと、戸板康二が聞き手の志賀直哉の歌舞伎に関するインタヴュウ記事が昭和27年初頭あたりに掲載されていて、チェックせねばと思いつつそのままになっていたので、今、ここに売っていないかしらッ、と急にエキサイティング、そこにある限りでは志賀直哉の記事は見つけることができなったのだけれども、他の号でもちょくちょく戸板康二が登場しているので、まあ! と、全部買うわけにはいかないので吟味に吟味を重ねて、3冊ほど選んだ。1冊100円。この時代の「芸術新潮」はA5サイズ、絵画、デザインはもちろんのこと、クラシック音楽や演劇の記事も充実していて、なかなかいい感じの誌面で、一気にファンになった。「芸術新潮」は、書店ではほとんど買ったことがなくて、もっぱら古本屋さんで300円くらいで売っているのをちょくちょく買っている。とりわけ、1974年1月号から1987年11月号までの「芸術新潮」で、好みの特集が組まれていているのを古本屋で安く売っているのを見つけたらラッキー、洲之内徹の「気まぐれ美術館」が載っているので、カラー図版とともにあらためて洲之内の文章に触れることができるから。
 ■ この画像は、「芸術新潮」昭和28年11月号より。「わが渡欧作品」と題された文士たちによるスケッチや写真を載せた特集から、獅子文六による「巴里の街芸人」というタイトルのスケッチ。ほんわかと素敵、一目見て大好き。「わが渡欧作品」、川口松太郎の写真、ネロの遺跡を背景に溝口健二が写っていたり、小林秀雄によるイタリア写真は構図が凝りすぎなくらい凝っていて微笑ましいくらい、ほかもほんわかと面白かった。この号の目次には戸板康二の名前もある。「芸術祭を批判する」というタイトルの座談会で、出席者は、小宮豊隆、花森安治、文部省の寺中作雄、戸板康二の4人。この座談会に関しては、戸板さんは、『あの人この人』の「花森安治のスカート」でちょろっと書いてくれている。《寺中さんという人は、勘三郎とも親友だったそうで、役人らしからぬ性格だから、私も話しやすかったが、花森さんも、手ぐすねひいていたのが、拍子ぬけがしたような感じだった。かえりに新宿の酒亭五十鈴に寄り、寺中さんが即興にメモ用紙に、カウンターにいる客の顔をスケッチしているのをのそきこんで、ニコニコしていた》。この号は、ほかにも、秋田雨雀や山本安英の文章など、最近の関心事、新劇史あれこれに関する文献もあってなにかと楽しかった。
■ この画像は、「芸術新潮」昭和28年11月号より。「わが渡欧作品」と題された文士たちによるスケッチや写真を載せた特集から、獅子文六による「巴里の街芸人」というタイトルのスケッチ。ほんわかと素敵、一目見て大好き。「わが渡欧作品」、川口松太郎の写真、ネロの遺跡を背景に溝口健二が写っていたり、小林秀雄によるイタリア写真は構図が凝りすぎなくらい凝っていて微笑ましいくらい、ほかもほんわかと面白かった。この号の目次には戸板康二の名前もある。「芸術祭を批判する」というタイトルの座談会で、出席者は、小宮豊隆、花森安治、文部省の寺中作雄、戸板康二の4人。この座談会に関しては、戸板さんは、『あの人この人』の「花森安治のスカート」でちょろっと書いてくれている。《寺中さんという人は、勘三郎とも親友だったそうで、役人らしからぬ性格だから、私も話しやすかったが、花森さんも、手ぐすねひいていたのが、拍子ぬけがしたような感じだった。かえりに新宿の酒亭五十鈴に寄り、寺中さんが即興にメモ用紙に、カウンターにいる客の顔をスケッチしているのをのそきこんで、ニコニコしていた》。この号は、ほかにも、秋田雨雀や山本安英の文章など、最近の関心事、新劇史あれこれに関する文献もあってなにかと楽しかった。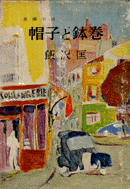 ■ と、戸板康二の『六代目菊五郎』とともに、昭和20年代後半の「芸術新潮」を3冊買って家に帰ってみると、ネットで注文した、飯沢匡の『帽子と鉢巻』(光文社、昭和33年)が届いていた。前回の制作ノートで書いたばかりなのだけれども、飯沢匡の『帽子と鉢巻』を急に読んでみたくなったのは、森茉莉の「ドッキリ・チャンネル」がきっかけ、さっそく申し込んでしまったのだ。梱包を解いてみると、なかなか可愛い本で、ひと昔前の児童書のような装幀でニンマリ。『帽子と鉢巻』は東京新聞朝刊の連載小説なのだそうで、装幀はその挿絵を描いていた桜井悦という人によるものだそう。スキャナに撮ってみると、あまり映えないのだけれども、本全体の手触りは獅子文六の単行本のようでなんとも愛らしい。あとがきによると、この小説はパリの日本人を描いているのだそうで、演劇人による巴里小説という中身も獅子文六を彷彿とさせる。実際に読んでみると、どんな感じなのだろう。ちなみに、飯沢匡というと、「悲劇喜劇」の戸板康二追悼特集に一文を寄せていて、ほかのひとがあまり書かないようなことを書いていた。
■ と、戸板康二の『六代目菊五郎』とともに、昭和20年代後半の「芸術新潮」を3冊買って家に帰ってみると、ネットで注文した、飯沢匡の『帽子と鉢巻』(光文社、昭和33年)が届いていた。前回の制作ノートで書いたばかりなのだけれども、飯沢匡の『帽子と鉢巻』を急に読んでみたくなったのは、森茉莉の「ドッキリ・チャンネル」がきっかけ、さっそく申し込んでしまったのだ。梱包を解いてみると、なかなか可愛い本で、ひと昔前の児童書のような装幀でニンマリ。『帽子と鉢巻』は東京新聞朝刊の連載小説なのだそうで、装幀はその挿絵を描いていた桜井悦という人によるものだそう。スキャナに撮ってみると、あまり映えないのだけれども、本全体の手触りは獅子文六の単行本のようでなんとも愛らしい。あとがきによると、この小説はパリの日本人を描いているのだそうで、演劇人による巴里小説という中身も獅子文六を彷彿とさせる。実際に読んでみると、どんな感じなのだろう。ちなみに、飯沢匡というと、「悲劇喜劇」の戸板康二追悼特集に一文を寄せていて、ほかのひとがあまり書かないようなことを書いていた。
← PREV | NEXT →