著作BOOKS
『認知症を生きるということ』(2009年 草思社)
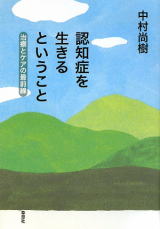
その人らしく暮らすために。
認知症についての誤解を解き、最新の治療薬や治療法の実態と効用、患者本人のためのケアの方法と問題点などをていねいに紹介します。
200万人近くの方が患っている認知症。高齢者ばかりか50歳そこそこで発症する若年性認知症も増えてきました。かつては「ボケ老人」「痴呆」などと呼ばれ、拘束などの手荒い対処も行われてきました。しかし、最新の研究成果と治療法の進歩は、「生活の質」を改善し、その人らしい穏やかな生活を送ることを可能にしつつあります。最新の薬物療法をはじめ、薬を用いない回想法や芸術療法などが実際にどう行われているか、治療の現場でたんねんに取材してきました。
○不安感から「家に帰りたい」との徘徊に
○認知症と診断されない「軽度認知障害」
○入院することで症状がどんどん悪化する
○状況に応じたケアプランで自宅で暮らす
○「グループホーム」で共同生活をおくる
○介護保険がかかえるさまざまな問題点
○経済的な負担をどうすればいいのか
○早期に発見するための診断法
○進行を止める効果がある薬の登場
○みずからの人生を振り返る「回想法」
○軽度の人も活用できる「地域回想法」
○「言葉」を使わない「芸術療法」
○右脳モードの「臨床美術」
○「家族カウンセリング」の重要性
(本書表紙・帯より)
治療法や介護法の改善によって、どのように生きていくかが重要になってきた
「認知症」と診断される高齢者がものすごい勢いで増加しています。厚生労働省の推計によると二〇〇五年の段階で約一七〇万人、二〇一五年には約二五〇万人にまで増加するとの予測です。しかも高齢者のみならず、五十歳前後で発症する「若年性認知症」の患者も増えているといいます。
かつて「ボケ老人」や「痴呆」と呼ばれ、徘徊や暴れるなどの行動をとることから、拘束などの手荒い対応を取られることも多かった認知症ですが、研究がすすみ治療法や介護法が発達してきたおかげで、患者の生活の質が改善され、守られるようになってきました。認知症のなかでも「アルツハイマー型」と呼ばれるものの場合、かつては診断後の平均余命が七年と言われていましたが、いまでは適切な治療と介護によって十五年から二十年以上と大幅にのびています。
ということは、重要なのはベッドに縛り付けるような自由を奪った「治療」を施すことではなく、いかにして患者さんがその人らしく、その人自身の暮らしを続けていくか、ということになるのではないでしょうか。
治療薬、薬をつかわない治療法、家族や地域社会とのつながりなどを紹介
前著で「脳機能障害」の実態を調査した著者は、本書では認知症の治療とケアの最新状況をたんねんに取材しています。認知症だから治療のしようがない、という誤解。あるいは、認知症と診断されて入院したら、急激に症状が悪化したというケース。病院から自宅に戻って生活をはじめたら、症状が良くなったというケースなどを具体的に取り上げます。また、病状の進行を止める薬の開発エピソードを紹介するとともに、「薬をつかわない治療」として「回想法」や芸術をつかった治療法の現場を紹介します。
患者を隔離し拘束するのではなく、暮らしのなかで、家族をはじめとするまわりの人々との交流のなかで治療し、生活の質を取り戻していく。それが最前の方法ではないかということが見えてきます。しかしその一方で著者は、介護する側の疲弊、苦しみ、あるいは経済的な問題など、現実に直面せねばならない数々の問題も取り上げています。
自分自身のみならず家族や近しい人が患う可能性のある認知症について、さまざまな角度からその実態を紹介する本書は、多くの方にぜひ知っておいていただきたい一冊です。
(草思社 書籍ニュースリリースより)