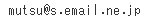HOME -> 城跡データ -> 福島県の城跡一覧(会津地方) -> 久川城
久川城 ひさがわじょう
- 別名
- -
- 時代
- 安土桃山時代~江戸時代
- 分類
- 中世山城
- 規模
- 面積:南北565m×東西250m、標高:628m、比高:約53m
- 現状
- 県指定文化財/公園・キャンプ場
- 場所
- 福島県南会津郡南会津町青柳字久川
- 最終訪城日
- 2010年11月21日
河原田盛次が築いた山城で河原田氏の居城。現在は公園とキャンプ場となっている。
城史
| 年代 | 出来事 |
|---|---|
| 1589年秋 | 河原田盛次は伊達政宗の勧告を拒否して伊達軍の襲撃に備えることにしたが、駒寄城では大軍を相手に出来ないために新たに久川城を築いてこれに備えた。そして長沼盛秀を先鋒とする伊達軍を篭城戦の末に撃退した。 |
| 1590年 | 「奥州仕置」により河原田氏は所領没収となり、伊南郷は新しく会津の領主となった蒲生氏郷に与えられることになった。これに伴い、久川城には蒲生郷可が城代として派遣された。 |
| 1591年 | 蒲生郷可は「九戸の乱」での戦功により長井郡の中山城の城代となり、久川城には替わって弟の蒲生郷治が配置された。 |
| 1598年 | 蒲生秀行が御家騒動で下野に転封されると、会津には替わって上杉景勝が移され、久川城には清野長範が配置された。 |
| 1602年 | 「関ヶ原の合戦」で東軍が勝つと、西軍に加担していた上杉家は減封されて米沢に移り、1601年には会津には再び蒲生秀行が入った。そして翌年に久川城には蒲生忠右衛門が配置された。 |
| 1611年 | 蒲生忠右衛門は失政により伊南郷を召し上げられ、この時に城は廃城となったという。 |
縄張り
城は伊南川と滝倉川の合流地点の丘陵に築かれており、丘陵の東西と北側は急斜面で特に西側は断崖絶壁となっている。南の丘陵続きの場所には堀切が設けられており、現在はその堀切を車道が通っている。
関連施設
アクセス
- 会津鉄道の会津田島駅から「山口内川」行きのバスに乗り、「古町温泉入口」で下車して徒歩10分。
- 会津鉄道の会津田島駅から「山口内川」行きのバスに乗り、「小塩」で下車して徒歩10分。
関連リンク情報
- 南会津町公式ウェブサイトの「教育・文化」の「町の文化財情報」から「久川城跡」の名称で確認できます。
- 本ページでは
 の地図リンクサービスを使用させていただいています。
の地図リンクサービスを使用させていただいています。