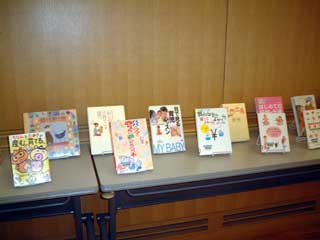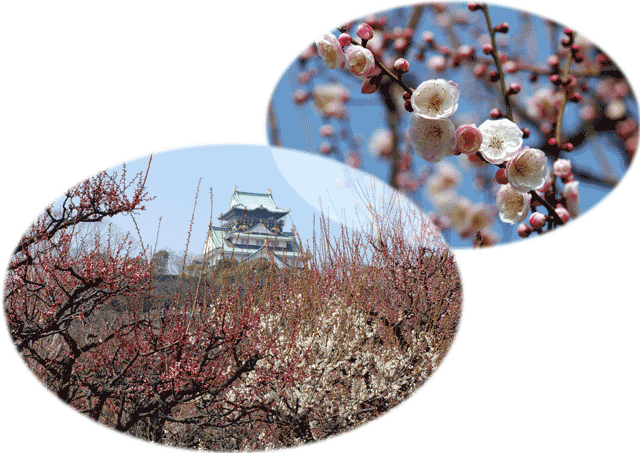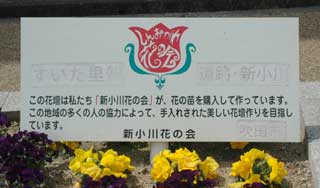<町長の2006年度施政方針等に対する会派代表の大綱質疑が行われました>
2月16日の日記にも書いていますが、今回の代表質問には新年度予算と共に8件もの条例制定及び改正に係る案件がくっついています。大変なボリュームですが、時間制限もあり質問に立った議員は(会派内での順番とはいえ)本当にお疲れ様でした。総ての施策・事業が対象になる予算質疑はどうしても総花的になってしまいますが、多くの会派が取り上げた項目に係り、町長・教育長の答弁からその一部をお伝えします。私自身としては反論もあり、ツッコミのひとつも入れたいところもありますが、先ずは町の考えをお伝えしておきたいと思います。
会派代表質問は3月1日に岡田議員(公明党)、伊集院議員(緑風純政会)が、翌2日には河野議員(共産党)、平野議員(人びとの新しい歩み=私の会派です)、菅議員(山吹民主クラブ)が行いました。なお今回初めて会派ごとに答弁書(1回目の質疑に対する答えが書いてある文書)が予め配布されました。お互い書いたことを読み上げるのですから当然の事です。以前から求めていたことがやっと実現しました。こういうところは川口町長になって改善された所だと思い、大いに歓迎しています。
ところがこれには続きがあって、私が全会派の答弁書を正式に委員会資料として要求したところ「資料提出は控えさせていただきます」と、なんとも意味不明な断り書きを出してきました。答弁書は町長が議場で読み上げているのですから堂々の存在を示す資料です。出せないわけはありません。多分議会関係から圧力があったのかも?と、これは私の推理ですが・・・。ほんとに変なの!私もそれならと直ちに情報公開請求を“させていただきました。”これなら提出を“控える”ことは不可能です。それにしても役場は全く余計な仕事を自分達で増やしているよね!
さて本題に戻ります。答弁の一部、しかも骨だけの概要ですがお知らせします。
* 島本町国民保護計画について
-
2006年度中に策定するが概案を委託で作成、その後町長の諮問により島本町国民保護協議会で審議をする。協議会の会議は原則公開とする。計画は議会にも意見を求め、報告も行う。住民へのパブリックコメントも実施。協議会の委員は、会長の町長を初め町職員・関係機関の職員・学識経験者で構成する。関係機関に自衛隊が含まれるかと言う点については、協議会委員は地域防災会議委員と同じで、防災に自衛隊の委員が含まれていることから可能性としては「ある」。まずは町の消防団や自主防災組織の代表者を任命する。
* JR新駅設置事業について
-
供用開始時期を諸般の事情から見直し、1年遅れの2008年(平成20年)春以降とした。西側道路(工事の目途も立っていない)、自由通路(工事はH19年度に完了)の供用開始については現時点で答弁できない状況にある。国の交付金対象事業であることから、H20年度末がタイムリミットである。新駅西側の利便性を考えると駅西側からのアクセスはぜひとも必要。用地買収はあくまでも任意買収が基本である。土地収用法の適用は最終手段であり、きわめて慎重な対応が必要と考えている。なお事業に伴う本町支出の負担金・委託料が適正か否かは第三者機関のチェックを受ける事は可能かもしれない。しかしその結果をもってJR西日本と交渉を行う事は困難であると考える。
* ごみ処理問題(清掃工場)について
-
一般廃棄物の適正処理は、市町村固有の事務である。当町清掃工場は竣工以来15年を経過し耐用年限(20年)もせまっているが、町単独の建替えは法律上不可能である。今後ともごみ処理の広域化を目指すが現状は困難である。従って多額の費用をかけ整備をしてきた現在の焼却炉等の適正な維持・補修を行いつつ、廃棄物処理事務を継続する努力をしていく。なお清掃工場の補修工事に係る積算チェックについては、前年度の保守点検結果をもとに必要箇所の選定、仕様書・設計書の作成をコンサルと共に行っているのでチェックは適正であると考える。(し尿処理を行う衛生化学処理場も施設の老朽化・近隣住民からの苦情もあり同様の問題をかかえています。解決策は広域化か中間処理施設を設けて下水に放流の選択肢しかありませんが、何れも困難な状況下にあります=これは私のコメントです)
* 介護保険制度について
-
昨年改定された施設の食費・居住費の負担増は、低所得者層にはむしろ軽減の状況にある。(改正前との比較において負担増は減の半数に満たない。むしろ負担減が総数の過半数を占めている)当見直しは施設側の収入減をもたらし、影響は施設に大だと考える。4月から始動する地域包括支援センターが行う新予防給付に関するサービスは、保険給付の抑制も目的ではあるが要介護者の残存能力を維持、改善する為のケアマネジメントが重要であると考えている。センターに配置される専門職員が、要介護者の地域・家庭での生活継続に対する一助になるよう努力する。
* 障害者自立支援法に基づくサービスについて
-
法の施行が4月より始まる。説明会については今後も地域に出向いて行いたい。現行の福祉サービス利用者には、個別通知・対応を行い具体的な利用料軽減策への周知を図り理解に努めたい。障害程度の区分認定に当っては既に研修等を受講させ、現在大阪府の認定調査員研修受講の調整も行なっているところである。当事者の立場を考えた調査が出来るよう万全の体制を整備していく。また障害程度区分審査会委員の選任については身体・知的・精神障害者の均衡に配慮し、中立・公正な審査を行うため各分野の学識経験者を任命する。10月から始まる地域生活支援事業は相談支援・コミュニケーション支援・日常生活用具・移動支援・地域活動支援センターの5事業が市町村の必須事業となる。当町の具体事業としては手話通訳派遣・通学通所者支援・ガイドヘルパー派遣(支援費制度適応)等の事業がある。現在経費等について国からの提示がない為、情報収集に努めている。
* 子育て・教育問題について
-
「幼保一元化」については、保育所の定員超過と幼稚園の定数割れ状況のもと、民生部と教育委員会で勉強会をスタートしている。現在審議中の行財政改革推進検討委員会の審議内容にも含まれているため、第三次行財政改革実施計画への答申を踏まえ更なる検討をしていく。「小中一貫教育」については、新年度から2年間、第一中学校・第一小及び第四小学校を指定し、各校に一貫教育の推進者をおき研究を進めていく。「学童保育の延長保育」については、保護者のアンケートによると32%が希望している。4月からの実施に際して、延長保育料の減免は要領の一部改正で対応する(私のコメント=私が2月15日の日記で書いている通り、生活保護世帯と町民税非課税世帯は0円となる事を確認しています)。「少人数学級の推進」については、法では40人の学級編成が基本原則であるが法律の緩和に伴い、大阪府の判断による1年生35人学級、2年生38人学級が新年度から実施される。30人以下の少人数学級の実現には、構造改革の教育特区を取得するなど町単独の事業とする事が必要であり、そのためには教員を町雇用とするなど財政的に非常に厳しいと考える。
5つの会派代表質疑への答弁書をあちこち見ながら、できるだけ公平に書き出したつもりです。まだまだたくさんの質疑がありますが、これだけでも読んでくださる人は少ないのではないかと思っています。大体こういった内容のものは面白くありません。「だからどうなん?」に答えていないからです。私も頻繁に突っ込みを入れ、ブツブツ言いながらキーを叩いています。一つひとつが大きな課題でありますから、今後の報告は日記に掲載の折には、また続きを読んでください。
ひとつ気づいた事がありました。総ての答弁書を見ていると、新しい提案をしているのは「共産党」や「人びとの新しい歩み」(私の会派)以外の3会派のほうだと言う事です(ただし提案の中身を云々してはいませんが)。どちらかと言えば前述の2会派は追求型なので、過去や現状を見るほうに重点をおいているのかもしれません。これは私自身も馴染んだ視点の据え所でしたから、気付かずに過ごしてきたのかもしれません。今回他会派と比較する事で、予算に対する姿勢の一端を今更ながら学んだような気がします。
今回は長文でしたのでお疲れになったと思います。「春の使者」をお届けします。
 |
 |
|
|
|