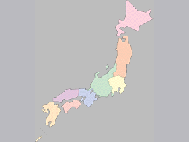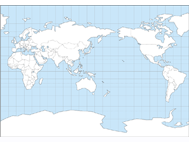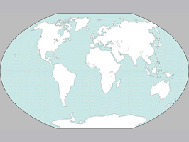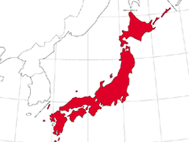ISO認証とシステム構築ポイント解説
マネジメントシステムの構築について
規格の要求事項に基づきその企業でどういうシステムにするかは要求事項さえ満たせば自由である。したがって良くも悪しくもシステム構築に携わる人たちの力量によるところが大きい。 もっとも大切なのは要求事項を満たすことにばかり捉われて実際の日常業務のなかで負担ばかりかかるシステムにしていないかということである。 この対処として
①システムを構築する前に、現に今ある仕事のノウハウや帳票や標準といったものがどこの会社でもあるはずであるから、それを先ず活用することで、新たな文書を二重に作ってしまわないことである。
②実際にシステムのサイクルを回し維持管理する現場の人たちの日常業務が極力負担にならないように話し合い相談してシステムを作り上げていくことである。
③システムも文書も簡単明瞭にしてスリムにを念頭において、システム間の矛盾や責任権限などが二重三重の明記になっていないか組織の構成員でチェックすることも大切である。
本来の業務フローにISOのマネジメントシステムをどれだけ如何に組み込むかが((統合)重要であり、このことによって日常の本来の業務をきちんとやればISOも必然的にできているということになるりようになる。。
ISO認証取得について
認証取得の目的や理由は経営者のそれぞれの考え方で様々であろう。しかし取得に当たって此処のところが極めて大切であって、親会社に云われたとか、仕事が来なくなるとか後ろ向きの姿勢で取り組むと、認証が取れたとしてもその後の維持で大きな重荷になってしまいかねない。
認証審査や更新審査などの費用、日常業務の中でのシステムの維持管理の負担を考えると経済的負担もそう軽くはない。認証を維持し続ける間は経営上固定費的に発生し続ける。 従って経営者は取得に当たり『何故、何のために取得し会社をどのようにしたいのか』を明確にしておくと同時に会社の方針に沿うようにマネジメントシステムを大いに活用し、体質改善・強化にも大いに役立てたい。
また認証の費用負担、維持更新の負担が大きければ認証をあえて急いで取らず自己宣言型で実施し効果を実感できるようになってから認証審査を受けてもよいし認証をとらずにそのまま継続するのもよいと思う。
要はISOのマネジメントシステムが経営に寄与するか否かである。