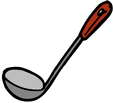うどんの打ち方教室
私が子供の頃家庭でうどんを打っていた。町には多くの麺打ち名人がいた。いつの頃からか麺は買ってくるものになった。本来うどんは手軽に打てるものなのだ。
うどんの打ち方はいろいろなところで紹介されているが、香川県の生活改良普及員の発見したビニール袋とハトロン紙を使う方法が手軽と思われるのでお勧めする。
材料
材料は次のとおりだが、ひとつ注意を。中力粉がなければ、強力粉と薄力粉を混ぜるとよい、と書いてある本がたくさんある。確かにグルテンに関してはそうなんだろうが、デンプンの特性が違うので多分うまくいかないはず。だってうどんはグルテンを食べるのではなくデンプンを食べるものだから。
|
麺の素
|
麺づくりの道具 |
| うどん専用小麦粉(中力粉)1キロ |
麺棒 |
| 塩 冬30グラム〜夏50グラム |
ビニール袋 |
| ぬるま湯(40℃) 400㏄〜450㏄ |
打ち板(ハトロン紙で代用可能) |
| コーンスターチ(打ち粉) 少々 |
包丁 |
 |
紙の箱 |
| 大きな鍋 |
| ざる |
| だしの素 |
だし作りの道具 |
| 水 |
鍋 |
| 昆布 |
お玉 |
| いりこ |
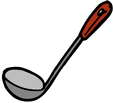 |
| 味醂 |
| 醤油 |
麺の作り方
- ビニール袋に粉を全部入れ、塩30グラム〜50グラム(夏が多め)を溶いた、ぬるま湯400㏄〜450㏄(小麦粉の水分量で変えるのがベスト平均夏が少なめ)を加える。塩、水加減は季節天候によって変える。
- ビニール袋の上から全体がボロボロになるように混ぜ、押しながら団子に丸める。
- それを袋のまま上から踏み延ばしては丸め、を数回以上繰り返す。このビニール袋に入れた塊を2〜3時間以上ねかす。
- ねかした塊を打ち板の上で延ばす。本格的にうどんを打つ人以外はハトロン紙または米袋で充分。まず2回くらい踏み返した麺をハトロン紙の上に出しコーンスターチを振ってくっつかないようにする。塊を四方から麺棒で延ばすのだ。縦横に延ばすとグルテンのつながりがよくなり腰が強くなる。だいたい3〜4ミリくらいに延ばすこと。
- 延ばしたものを折り畳み、菜切り包丁のような刃がまっすぐな包丁で切っていく。そのままほぐして、紙箱のなかに30分くらい置く。凍らせると冷凍うどんとしても活用できる。
- 切った麺をたたきほぐし、充分沸騰した大きな鍋に入れ10〜12分くらいゆでる。ゆで時間もポイントだ。細目だと短めに。また釜上げも短めに。ゆでた麺を冷水にさらしてできあがり、冷水もかなりのポイント、井戸水が理想的だがO−157の心配もある、街中の店では氷水を使っている。
注意する点
- 塩、水加減は最初はきちっと計算する。
- 踏みすぎてはいけない、堅くなりすぎる。
- コーンスターチは片栗粉に比べてゆで汁が粘らない。
- ゆでるときはできるだけ大きな鍋で。それでも切れたり煮崩れするときは酢を2〜3滴落としてみてください。
だしの作り方
材料を信ずるままに利用し美味しいだしを作ってください。あなたの舌にかかっています。
うどん教室
ここまで読んできて、うどんが打ちたくなった人には、体験型うどん教室もあります。(有料、要予約)
- さぬきうどん中野学校 仲多度郡琴平町(0877)75-0001
- 綾南町うどん会館 綾歌郡綾南町 (087)876-5018
- 休暇村五色台(宿泊施設) 坂出市大屋富町 (0877)47-0231 等など