丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂
壠栦偼壠偺徾挜偲偄傢傟偰偄傑偡丅挿偄揱摑偲晽廗偵傛偮偰堢偰傜傟偨壠栦偼丄
偦偺扨弮柧夣側恾幃壔偼恄旈姶傪偝偊屇傃婲偙偝傟丄婔惎憵傪宱偨恖乆偺垽忣偵傛偭偰惗傑傟偨傕偺偱偁傝傑偡丅
壠栦傪昤偔偙偲傪惗奤偺巇帠偲慖傫偱嶰廫梋擭丄偦偺娫偱摼偨抦幆偐傜
壠栦偺偙偲傪彮偟偱傕
抦偭偰栣偊偨傜偲巚偄偙傫側儁乕僕傪嶌偭偰傒傑偟偨丅丂丂丂丂丂嵟廔峏怴擔:
13/05/03
栚丂丂師
|
摿慖俆侽庬堦 棗
|
擔杮偺拞偱堦斣傛偔巊傢傟偰偄傞壠栦傪敳悎偟偰偄傑偡丅 |
|
怉暔宯 |
怉暔偐傜恾埬壔偝傟偨壠栦偱偡 |
|
摦暔宯偦偺懠 |
摦暔傗丄挷搙昳丄晲嬶側偳偐傜恾埬壔偝傟偨壠栦偱偡 |
|
楌巎忋偺恖暔 |
愴崙帪戙偺戝柤偲偐楌巎忋偺恖暔偺壠栦偱偡並 |
|
恄幮暓妕栦偐傜 |
嫗搒偺庡側幮帥偺栦復傪慖傫偱傒傑偟偨 |
|
儕儞僋 |
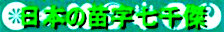 |
|
帺屓徯夘 |
侾俋俁俆擭嫗搒巗惗傑傟丄栦奊巘楋4俇擭丄僱僢僩楋18擭 |
丂丂丂丂丂丂
壠栦偺庬椶偲暘椶
壠栦偺慺嵽偵偼偙偺悽偵懚嵼偡傞丄偁傜備傞傕偺偑巊傢傟偰偄傑偡丅
巗斕偝傟偰偄傞丄昗弨栦挔偵偼栺俆侽侽侽庬椶偑宖嵹偝傟偰偄傑偡偑丄幚嵺偵偼丄偙偺係丆俆攞偼偁傞傛偆偱偡丅
偦傟傜傪戝偒偔暘偗傞偲壓婰偺傛偆偵暘椶偡傞偙偲偑弌棃傑偡丅
嘆丂帺慠丄揤暥宯丂丂丂擔丄寧丄惎丄愥丄嶳丄攇丂
嘇丂怉暔丂宯丂丂丂丂丂丂埁丄嬧埱丄堫丄攡丄徏丄抾丄悪丄攼丄摗丄媖丄曅嬺丄嬎丄媕峓丄嶚丄旳丄
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂塟丄嬧埱丄捰丄媏丄嶗丄晱巕丄棾抇丄洫壸丄壊扥
嘊丂摦暔丂宯丂丂丂丂丂丂棿丄掃丄婽丄挶丄揺丄攏丄數丄婂丄奀榁丄悵丂
嘋丂婍暔丂宯丂丂丂丂丂丂慘丄屰丄娺嬶丄愵丄妢丄姌丄姇丄寱丄栴丄抍愵丄揃敳偒丄幵丄
嘍丂婔壗妛宯丂丂丂丂丂妏丄娵丄婽峛丄旽丄堜寘丄堫嵢丄椮丄攂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂
嘐丂暥帤宯丂丂丂丂丂丂忋丄堦丄擇丄嶰丄廫丄栘丄丂
壠栦偺梡搑
尰嵼偱偼丄晽楥晘丄傆偔偝丄峀奧丄栦晅塇怐丄嵳楃採摂丄枊丄壠栦妟丄壆崻姠丄暓抎丄愇旇側偳偵尒傜傟傑偡偑丄
僱僋僞僀僺儞丄僇僼僗丄僱僢僋儗僗丄僐儞僷僋僩丄僶僢僋儖丄懷棷傔摍偵傕憰忺偲偟偰偮偐傢傟偰偄傑偡丅
傕偲傕偲壠栦偼丄岞壠偱偼梎幵偵丄偦傟偐傜堖暈傗挷搙昳偵巊傢傟傑偟偨丅
峕屗帪戙偐傜偼弾柉偵傕晛媦偟偰丄壩徚憰懇堖丄抔楘丄恮妢丄暥屔丄庤嬀丄採摂敔丄庰攗側偳偵晅偗傜傟傞傛偆
偵側傝傑偟偨丅
堦曽丄晲壠偱偼涱丄婙丄枊丄弢丄奪姇偺晲嬶偵梡偄傜傟偰偄傑偟偨丅
壠栦偺婲偙傝
壠栦偺楌巎偼屆偔丄夝柧偝傟側偄晹暘偑懡乆偁傝傑偡偑丄婱懓暥壔偺塰偊偨摗尨帪戙偵堖暈傗挷搙昳偵
巊傢傟偩偟傑偟偨丅岞壠偱偼庡偵怉暔傪暥條壔偟偨傕偺偑懡偄傛偆偱偡丅
堦曽晲壠偱偼愴応偵偍偄偰揋枴曽傪幆暿偡傞栚揑偱婙傗晲嬶偵梡偄傜傟偨傎偐丄壠栧偺抍寢傪婇偰傞偨傔偺
徾挜偲偟偰梡偄傜傟偨偲巚傢傟傑偡丅
愴崙帪戙偺晲巑偲壠栦偺娭學偼嫽枴怺偔丄偙傟偩偗偱堦嶜偺杮偑弌棃忋偑傝偦偆偱偡丅
丂 丂丂丂
乽價儕乕偺晹壆乿傊