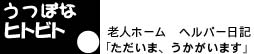

わたしの仕事は老人ホームの介護職である。
老人ホームといってもマンションである。したがって健常者(ほんとに変な言い方だ)が多い。かれらは、人との接点を求めている。いや、渇望している。
うつぼとは、部屋の中でヘルパーの来訪や、隣近所の人間が通りかかるのを待ち構えているといったイメージなのだ。さてさて、それは真実かどうか――。
|日記4(最近の出来事 2004.Janu--)|
|日記3(夜勤痛と最悪のクリスマスイブ夜勤 2003.Oct--Dec)|
|日記2(初夜勤・退職者続出の謎 2003.July--Sept)|
日記1
6月30日
しばらく入院していた人(わたしが入院に付き添った人)が帰ってきた。2週間足らずの入院なのに、仙骨部に「じょくそう」を作ってきた。
病院は「入院の原因となった病気は治すが、そのためにはほかが犠牲になる」を目の当たりに見る思いだ。
退院後は生活動作レベルが明らかに下がっている。
6月28日
ようやく気安く口がきけるようになった先輩2人が相次いで辞める。
なんだか、がっかりである。いかに定着率の悪い業界とは、職場に長い人が抜けるのは利用者にとっても組織にとっても痛手に違いない。
ところがこの業界(といってもあちこち知っているわけじゃないが)、定着率を高めようという努力をあまりにしていないのではないか。
そのたびに利用者は「一からの人」と刷り合わせをしなくてはならない。そうならないように「マニュアル化」されているかというと、これまたそうでもない。
職員も利用者も右往左往する。
人が減るため、また、シフト内容が変更になるようだ。楽をおぼえたのだから、それを維持するように努力すればいいのに、と思うが。
職場はメンバーの力量でも変化するが、やはり、リーダーの影響力が大きい。
定着率が悪いといえば、近所のグループホームは毎週の様に新聞の折りこみで求人している。大丈夫なんだろうか? 利用者が痴呆だから、関係ない?
6月22日
「長生きをするもんじゃない」という人が多いのはなぜだろう。まさか、勤務先の老人ホームの「特長」と言うわけではあるまい。
たぶんホームには、「年下の老人」と「年上の老人」しかいないからだと思う。
6月20日
勤務先の老人ホームには、家政婦さんを採用している入居者が何人かいる。家政婦さんはの話を聞くと、病院での経験が長い人のようだ。料理も得意な人たちがおおい。
家政婦さんがいれば、まさに24時間の介護である。利用者にとっては心強いことだろう。
資金に余裕のある人は、これでいいのかもしれない。介護保険など利用する必要もない。
もともと介護保険は24時間の献身的介護など前提にしていないのだから。家族を介護地獄からほんのすこし解放するだけのこと。さらには、他人を家に入れることの世間体や心理的な抵抗感を介護保険という仕組みで和らげるためのものに過ぎないのだろう。
とうぜん家政婦さんのほうが稼ぎは良いに決まっている。鞍替えしようかな?
ところで、家政婦さんて、自宅の電気料金を「別荘」扱いにしてもらっているんだって。
6月18日
人の育て方――にもいろいろある。
かつて小さいながらも組織に属していた時、後輩が何人か入ってきて、結局は全員が辞めていった。辞めていった理由は様々だ。組織に魅力がなかったということもあろうが、先輩としての指導法が間違っていなかったか、思い出すこのごろである。
今の職場に先輩のPさんとQさんがいる。両者とも「プロの介護者」として立派な人たちだ。だが、後輩に対する処仕方は微妙に違う。
Pさんは「あなたにできるだけ早く、私と同じプロになってもらわなければ困るから、注意もし、教えもする」という立場で、「指導」のときも「それがなぜ必要なのか」を示しつつおこなう。
Qさんは「早くプロになってね」という立場で、「指導」は意表を突く質問をしてくる。本人にその意思はないのだろうが「こういうところをちゃんと見ている?」「知っていた?」という攻め方なのだ。
どちらも受け取る側には「メッセージはきちんと届く」のだが、組織としての未来を考えた時、どちらが良いのか? 答えは明らかだ。
6月15日
疲れるなァ。
ただ、それだけ。
6月14日
ノンビリと見守り入浴に付き合っていたら、携帯で呼び出されて、入院に付き添いを命じられた。
玄関を出るわたしに上司は「入院できるかどうかはあなたの腕次第」とつぶやく。
どういうことなのさ!?
たしかに、ヘルパー泣かせの人ではある。
病院に到着して無事に入院が決まる。個室しかないという。この点について指示を受けていないので、あわてて電話する。
「大部屋が空いたら移してもらうように一言いっておいてね」
でも、結局、家族がこの点に納得しなければ、付き添いが新人だったからと言いそうな気がする。
6月10日
美容院へのお迎えが急に入った。ホームから歩いていけるところ。店に入って探していると鏡の中で手を振っているPさんと目が合った。
いつもは蛇行する会話で私をイラツカセル「アーダコーダ姫」のPさんだが、鏡の中のPさんは、ちょいと凄みのある「女」だった。
支払いの時にはいつもの「アーダコーダ姫」に戻っていたけど。
6月8日
ホームには食堂がある。入居者の全員が利用しているわけじゃないが、そこそこ利用者がある。
食堂の手伝いにはいってフトおもたんだけど、夕食の時に「晩酌」している人がいないんだ。女性が多いからとはいえ、かなり異様な光景ではないか?
食堂の人(外部の業者)に聞いてみたら「ここは禁酒禁煙なんじゃないの?」とのこと。でもなぁー。泥酔するほど飲むわけもないでしょう。
もっとも、外が明るい五時すぎに夕飯じゃね。晩酌する気にもならないか?
6月3日
病院からターミナルで帰ってきたQさんがいる。
帰ってきた当初は、かなりレベルの低い状況だったが、ここ数日は呼びかけに反応を示すようになった。今朝などは、私の顔をまじまじとみて、あんた誰? という表情をされた。それもそのはず、はじめてお目にかかるのだから。
元気になったとはいえ、薄皮を一枚一枚はがすように「死」というものに向かっていく状況に変わりはない。
この方とほぼ同時に病院から帰ってきたPさんがいた。やはり末期だった。帰ってきてからは、入院前に見られたヘルパーへの拒絶感もなかった。しかし、それはどうやら、二度と入院したくないというPさんなりの意志表示だったようだ。だが、願いむなしく1週間ほどで、病院に再入院され、その日の午後にあっけなく亡くなられた。
この仕事のつらさはここにあるのだと思う。結局は、みんな死んじゃうんだ。決して、元気なって、現役に復帰するなどということはありえない。
押川真喜子さんの『在宅で死ぬということ』(文藝春秋)を読んだ。涙が止まらない。
死に際して自分の接し方は良かったのか? という自問はこの仕事を続ける限り続く。でも、良かったんだと自分に言い聞かせて、騙せるだけのことは日々の刹那的な接触の中でもしなくてはと思う。
だが末期の生活の質を充実するお手伝いをするには、日々の時間が少なすぎる。そして、時間の短さを質でカバーできるだけの技量もない。
5月31日
Xさんには「おまえさんは、会社の落ちこぼれ」と切って捨てられ、
Yさんには「がんばるのよぉー」と励ましの言葉とともにヤクルトをいただき、
Zさんには「テレビで指名手配の殺人者」よばわりされた。
浮き沈みの激しい一日だった。
5月29日
全介助の人や病人が多発したたため、早番の人数を臨時に増やすことになったのだが、課長が先輩と交わした言葉を聞いて上司としての資質を疑いたくなった。
曰く――
「利用者の健康状態が平常に戻ったらすぐにでも止めたい。だって、新人さんに楽だと思ってもらっては困るから。私たちだってそれなりに大変な思いをして苦労してやってきているわけでしょう」。
上司としては、自分が大変な思いをしたからこそ、スタッフが楽な体制を考えるというのが本来だと思うのだが。
だいたい「新人」のぼくがいるところで、聞こえよがし(?)にこそこそ話をする見識も疑う。
5月27日
夕食の配膳の途中、あるお宅に配膳を終えてドアを開けた途端、通路を挟んだ反対側のドアから出てきたAさんに声をかけられた。
わたしの顔をまじまじと見て
「何ヶ月もつかねぇ」。
Aさんは老人ホームの体制に批判的な意見の持ち主らしい。Aさんには入社して間もない頃も同じことを言われた。そのときは一緒にいた先輩に「向こうから話しかけてくるなんて珍しいことだよ」といわれた。認識してもらうのはありがたいことだが、しばらく話につきあったあとで、「辞めるなら早いほうがいいよ」とは、これいかに!?
どうにも複雑な職場に来てしまったらしい。
5月19日
1週間の入浴介助の後に、普通のシフトにもどったのは良いのだが、そこは、別世界?
高齢者の七日間は天地創造の七日間にも等しいのだ!!
おまけにわたしの脳みそも湯気ですっかりふやけたか、仕事の内容をボロボロ忘れている。
5月17日
今日は、入浴介助研修の最終日だった。
午後に、一般浴室で介助浴の予定の入ってたAさんの部屋に迎えに行ったところ「あんたは、介助しなくていいから、さっさと着替えて、介護室にいって手伝いなさい」と、まるで上司のように命令する。先輩が「勉強だから」と口添えしてくれても、「そんな必要はないんだよ」とにべもない。逆らってもはじまらないので、退散!!
男はいやだという理由で拒否する人はいるけど、Aさんのような人は珍しい。
ふだんから「自分理論」のある人だけに、なにか理由があるのだろう。男に眺められながら入浴するのが嫌なのか、なんなのか。
いずれ巡回で部屋に行けば、本人の口から真相は明らかになるであろう。部屋に行きたくもないし、真相を聞きたくもないけどね。
5月15日
今日は6時半出勤の超早番。変なシフトだよ、まったく。必要があって作られたんだろうけどね。
早番との違いは、新聞を配膳に載せるとか、インシュリンの●○をするとか、居室にいる人を介護室に連れて行くとかが、早番よりも早い一時間でおこなうだけ。あとは風呂風呂風呂。
今日は、あまり人数もなかったので、助かった。
でも、めちゃ眠い。特に昼休みが眠い。午前中いっぱいの入浴介助で温まった体が冷えていく、その過程で睡魔に襲われる。
5月14日
職場の懇親会から流れて2次会へ、前々から声をかけてくれ、約束していたひとたちと出かけた。ところが、どうやら、これは、派閥のオルグだったようだ。
かたや、課長を頂点するグループ。こなたは、古株の介護職員をコアにする自称「改革」派。なにを改革するのかは、いまひとつわからないのだが、どうやら、老人ホームであるにもかかわらず、特養化している現状(どこがどうしてそうなるのかは不明)に対して、改善を求めるグループらしい。
ぼくは、前者からはお呼びが掛からない――いつかは辞めると履歴書に書いたわたしは、面接官でもあった課長からはなから員数外と思われているらしい――ので、自然と後者に落ちついた。下宿屋構想をチロリと披露すると、のって来てくれる。
まさに好感触!!
しかし、なんで、こんな歳のわたしが採用されたのか。単純な理由で、人が集まらなかったからだという。
喜びも哀愁も相半ばの2次会だった。
5月11日
来週は1週間、早番シフトの研修に入る。7時半と6時半からの勤務。
いよいよ、我が家の子どもたちの「試練」が始まる。この試練を乗り越えても、次は夜勤が控えている。
早番は朝起きるだけのことだが、夜勤は「寝て」「起きる」という、重要な作業を自律的に行わなくてはならない。これがうまくいかなければ、正職員からバイトに変更を願いでることになるだろう。
5月10日
わー、こわい。
インシュリン●○、やるんだって。●○なんて、昆虫採集以来だぞ!! ペンシル型(カートリッジ)と注射型がある。前者は、後者よりも恐怖感はないが、それでも、人様の体に針を刺すのは怖い。まずは座布団で練習だ(苦笑)。
介護課長は「大根と思ってさせば怖くない」などと暴言? を吐いていたが、個人的にはどちらかというと「ボンレスハムだろう」と思った。
看護婦さんに立ち会ってもらって「人体」にやらせてもらったけど、怖かったよー。
5月8日
男性ヘルパーにも制服が導入された。
今日はシフトの関係で、わたし一人しか着るものがいなかったので、品評会の格好の的になった。
「床屋さん」「ばーばー●●」が、女性ヘルパーのみなさんの結論です。
ま、そんなもんです。それにしても似合わない。へこむ。
5月3日
ゴールデンウィークも、老人ホームには余り関係ない。
いつもの日曜日よりも来客が少ないぐらいだ。連休は家族サービスなのだろう。
4月30日
数日前から、高層階に担当が移った。仕事の内容に変更があるわけじゃないが、キャラクターの濃い人々が多いといわれていた。新人をてぐすね引いて待っているという噂の人もおり、戦々恐々の出だしだった。
こちらの身上をことこまかに取り調べ、血液型から干支まで聞いて、「そうだと思ったよ」とひとり得心している人に出会ったが、他にはウンコを踏んだり、ありがたーいお説教を受けることもなく1日目は終わった。
ところが2日目は――。
台所の洗い物のあとが水はねだらけでうんぬんかんぬんで、お説教をいただきました。すみません。ほんとうにごめんなさい。
何回も部屋に出入りして、水飲んでくださいねとか、オムツは交換しなくても良いですか? といってゴメンナサイ。ほんとうにすみません。
血圧が高くて、何回計っても高くて楽しみにしていた入浴をキャンセルしたのに、ぼくが計りにいったときには平常値でごめんなさい。
家に帰ってきてから食器洗いをしているときおもわず「ごめんなさい」と独白するような終わり方だった。
4月29日
利用者に理不尽なことを言われれば、ぼくも人間ですから、頭に来ます。でも、そのとき思うんです。ぼくには家族がいる(幻想かもしれませんけど)。当たり散らしたり(サイテーの親だ)、愚痴ったりする家族がいる。
でもこの人にはいないんだなぁ。そう思うとちょっぴりコゴトも楽になる。
4月28日
仕事をはじめて1ヶ月弱。はじめて一人看取った。朝から具合が悪く、職場には言い知れぬ緊張感があった。
夕方、ヘルパーが見守る中で、徐々に脈も呼吸も弱くなり、亡くなられた。
静かな死だった。――合掌
4月27日
生活支援者、全介護のシフトが終わり、要介護度1以上の人たちの居室巡りが始まった。高層マンションを低層階、高層階に分けて担当する。まずは低層階から。
わがままが多いかと思いきや、意外とみなさん穏やか。愛すべき人々。少し安心。
でも仕事は余るほどある。食堂への送迎やうんぬんカンヌン。コールボタンで呼ばれればすっ飛んで行く。おぼえる頃には、次の場所の実習に入るから、忘れてしまう。
困ったもんだ。
でも、今日も先輩に教えられた。肝心なことは、ごく当たり前のことに注意を払うこと。ウンコが出ていない、おしっこが出ていない。熱がある。食事が進まない等々。オムツ換えのスピードは問題じゃない!!
だけど、スピードがないと、TO-DOリストに追われて見落としてしまう。まだまだ修業が足りない。
4月25日
「家族が来てくれると良く眠れる」
●ヘルパーってなんだろう。お手伝いさん以上家族未満。
「死ぬまでに1度で良いから、イカの塩辛が食いたい」
●死んじゃうと困るから、食べさてあげなさい(看護婦の指示)。死ぬまで健康って、理想だろうか?
「自殺を幾度も考えるけれど、ここの名前が出るとおまえさんたちに迷惑がかかると思ってやめるんだ」
●死にたくなるような場所で暮らしていていいのだろうか?
4月24日
今日は休みだった。夜、友人の建築人類学者の講演会にでかける。
日本人は家にこだわりすぎる。カルト的犯罪者の部屋が公開されると、部屋が犯罪者を作り出したかのように指摘する。家が家族を作るような考えを持っている。私にとっての家族の原点は、インドネシアで出会った、壁のないダンボール屋根の小屋で暮らす、類縁関係も不明な10名近い老若男女――等々の話に、心揺さぶられる。
自分で作りたいと夢想している下宿屋構想でも、「形」をはじめに考えていた自分を反省。
4月20日
老人ホームの一隅にある「介護室」。
利用者はホーム内に居宅があるが、基本的にこの部屋で24時間生活する。
つまり痴呆や全介助が必要なため、居宅での生活が困難なヒトビトの場所である。
本人の希望というよりも、家族・親族の希望でこの空間へ来ることが多いようだ。
老人ホームにこういう場所があるのは、ヨイコトなんだろうか? 利用者は安心するのだろうか?
老人ホームに「終の棲家」をもとめたのに、買い求めた居室で「最期」を迎えられない。
老いを若い時から、考えておくことはよいことだとおもう。どういうところで老いたいのか、いざそのときなって、家族との関係がギクシャクする前に、宣言しておくことが肝要だ。
老いとは死に向かう不可逆的な過程だ。普通はかなり長い時間をかけて人は行く。だからこそ、その時間をどのように生きたいのか、考えておくことは大切だと思う。
死んだらどうする(たとえば葬式を自分でプロデュースするとか、埋葬法を指示することなどより、よっぽど重要だ。
4月18日
今日は休み。
NPOの設立講座にでかけてきた。いつかは、自分で老人下宿を――こうした現実逃避をしないとやってられない仕事でもある。私だけのことかもしれないが。
ところで、制服がないはずだったのに、突如、採用された。ブルーのスタンドカラーの制服。医者や検査技師が着ているものといったら、想像してもらえるか? その上に、エプロンをするのだから、なんとも珍妙な格好だ。
女性はいまでも看護士スタイルの制服を着ている。みんなで、コスプレでもやるか――とは、男性更衣室の与太話。
通常、ヘルパーは、利用者に威圧的もしくは権威的な感じを与えないために、医者もどきの服は着けないのが常識となっている。それなのに――。大丈夫か、この施設は?
4月17日
今日はさほどへこまんかった。事件がなかったこともあったし、怖い? 先輩もぼくのシフト現場にあまり顔を出さなかったこともある。
明日は休み。帰りがけにあがなったビールをぐび。ぷっはー!!?? くっせー。
鼻を突くクレゾールの臭い。
そういえば、帰りがけに、部屋で失禁した人の床を消毒したんだっけ。グローブを忘れた報い。
この人、配膳に行ったら、下半身を剥き出しにして、放心状態で部屋に倒れていた。
「まるで犯されたみたい」とは、一緒にいった先輩の弁。
明日は休み。クレゾールくさいビールをグビグビ。
4月15日
へこむなぁ。通りすがりに、「時間かかりすぎるんだよ」と先輩の一言。
介護室で、夕食後の排泄介助をしていたときのことだ。排泄が終わって、ベッドへ移し、パジャマに着替えていただいていた。そこへ……!!
時間をかけるのが悪いといっているわけじゃない――と思う。むだな動きが多いということなのだろう。
この先輩、どうやら「トロイ」やつが大嫌いな性格のようだ。申し訳ない、いらいらさせて。
以前の仕事で、ぼくもそうだった「トロイ」やつは癇に障るんだ。わかるよ。
でも、急いでやって、利用者にいらぬ苦しみを与えることのほうがまだ怖い。もう少し待ってくれ!! 待ってどうなるものでもないが。
4月14日
これを絶対矛盾といわずして、なんとよべばいいのだろう。
介護者として、赤の他人に寄り添ういっぽうで、自らの家族にたいしては疎遠になる。
ヘルパーとして、他人の家を掃除して磨きあげる一方で、汚い部屋に帰る。
なんとも矛盾に満ちた仕事だ。
看護と介護の境界はこのへんにあるのかもしれない。看護者は、被看護者の外に存在する。かたや、介護者は、被介護者に限りなく同化しつつ、介護者よりも視野を広くしなければならない。いったん憑依し、幽体離脱する――といった、オカルティックなモノなのかもしれない。
介護者に対して、愚痴をこぼす。一見、人格として認められているようだが、どうだろう。壁よりはマシ――程度かもしれない。だからといって、あきらめているわけではない。
くだらんことを考えるのも疲れているせいだ。
4月11日
勤務をはじめて10日が過ぎた。最初のお勉強は「生活支援レベル」のお宅巡り。
ホームの1階から6階までに暮らす十数名を対象に走りまわっている。午前と午後の2回の巡回だ。
体調のチェック、ゴミ回収、水汲み、洗濯、布団干し、買い物聞き、入浴見守り……。
午前中は申し送りの終わった9時半から11時過ぎまで、午後は2時から4時過ぎ間の間にまわる。昼は、介護室での介助補助や、配膳、4時以降も6時まで、配下膳など目いっぱい。
1ヵ所で「コケル」とすべてが崩れる、なかなかにきわどいスケジュール。玄関を出るとダッシュ!!
帰りがけに声をかけて引きとめる人、厳しい人、優しい人……実社会と同様に多様なヒトビトが扉の向こうで待っている。開けるまで何が起こるかわからない。
介護というより家政婦(現代的には家政士?)的な仕事が必要な人たちだけに頭脳明晰、細かいところにも目が行き届いている!! ちょっとしたミスも許されない。緊張とダッシュで、確実に瘠せた。
来週からは、24時間介護が必要な人々が暮らす「介護室」に移る。移動のないぶん体は楽そうだが、命に関わる部分も多いので、精神的な緊張が多そうだ。また、オムツ交換もあるので、腰に負担がかかるのは間違いない。トホホはまだつづく。
4月7日
足を踏むは、パジャマの着替えを忘れるは、失禁用のサブパンツを二枚にするのを忘れるは――。踏んだり蹴ったり。はーーーー。
働き始めて四か月ほどの若い人たちがテキパキやっているのに――。
大丈夫だろうか? やっていけるのだろうか?
久しぶりに感じるこの焦燥感。でも、20年前は若かった――(遠い目)。
弱気なことを言っている場合ではない。
老人にとってマンションは良くないのではないだろうか――というのが1週間足らず働いただけですが正直な感想。せめてホテルにしないとだめだ。ヘルパーがおとずれるのではなくて、本人が出てこないとなにもできない世界というのが良いように思う。
自活できる人にも、自室の台所ではなくて、厨房を使ってもらう。
もちろん、一人で食べたい時は一人で食べれば良い。
でも、嫌な人とも接点を持つ。そうしたことで、心に小波を立てることが良いように思う。
自室にこもっていると、老若に関係なく辛い。
3月27日
仕事開始まで1週間を切ったある日、勤務先に電話をかけた。内定通知から1ヶ月以上なんの連絡もないから、ちょっと不安になっていた。
介護課長に初日の指示をもらう。
●「9時15分前までに出勤」
よかった、いきなり早出とかじゃなくて。なにせ、この業界、だいたいが「現場研修」だから、いきなりとんでもない時間の勤務があったりするから、ちょっとびくびくだった。電話の口ぶりだといきなり夜勤体験もなさそうだ。一週間くらいは「日勤」かな。甘い?
●「動きやすい上履き用靴を持ってくること」
これは、ヘルパーの経験でわかる。紐靴はダメだ。
●「ズボンはGパンはダメ。チノか綿パン、上はポロかトレーナーね」
あれ? 制服はないのかな。二次面接で施設にいったときには、あったような気がする。コムスンの時は、コーラルピンク? のトレーナーと、チェック柄のパンツが支給されたけど、パンツはほとんど着なかった。それにしてもなんで、あういうパステルカラーの制服が多いんだろうかね。相手は幼稚園児じゃないんだから、もうすこし落ちついた色やフォーマルなデザインでもでもいいんではないの? 今度はどんな色だろうか……不安。
●「手帳と筆記用具」
ま、常識ね。
●「当日休みの希望を聞きますが、新人は基本的に希望はなしにしてもらいたい」
なら、言わないで。ぼくは当然だろうと思うけど、いまの若い人はそう思わないでしょうね、きっと。
●「ロッカー用意してありますから」
自前のロッカーがある職場なんてはじめて。わーい(^O^)。でも何いれるの? 着替えか?
さてと、普段、ポロとかトレーナーなんて着ないから、ユニクロ行かなくちゃ。
3月26日
仕事をはじめるのは2003年4月1日(火曜日)午前九時からだ。
当初は疲労困憊で記録を書いている暇などないだろうから、つなぎにまずは「前史」を書いておこう。
97年の晩秋というか初冬にそれまで14年近く務めた組織を辞めた。なぜ辞めたのか――などいうことは、この際どうでもよいこと(関係者も多数生存しているし(^^ゞ)。
翌年の初夏、失業保険をいただきながら、某編集プロダクションでバイトをさせていただいている時に「介護」に出会った。といっても、その編集プロダクションがジジババ集団で、その介護をした――というわけではなく、資料整理をやっている時に、ヘルパーという仕事はもしかしたら、将来有望かもしれないと思っただけのこと。ちょうど、介護保険導入を1年半後にひかえた時期のことだった。
せっかく組織を辞めたんだから、他の仕事(編集以外)をしたい――というのが正直な気持ちだった。
で、職業訓練校の介護ヘルパーコースを「お受験」したけど、落ちた。結構ショックだった。で、一時は気分が萎えた、相当に。
そして結局、2000年の初夏から冬にかけて、首都圏コープで開催していたヘルパー講習を受けて2級資格を獲得した。
講習で何があったかオムツをはいて実際に排尿してみたり、機械式の入浴装置を体験したり、特養研修で老婆に殴られたり……それはそれはメクルメクような体験でした――長くなるので、止めておこう。その一部は、「湾岸通り敬老会」「老人ホーム西行苑」とかに昇華してますので、詳しくはそちらをどうぞ。
資格を取って早速、コムスンに非常勤で就職した。半年近く「こんにちは、コムスンです」を体験した。いろいろと批判のあった(いまもあるのか?)コムスンだが、仕事場としては「普通の会社」で違和感がなかった。かえって、家政婦紹介所が成りあがった? ようなところに就職していたら、そうとうな違和感をもっていたとおもう。
楽しかったよー。
たとえば、最初は家事援助だけだったユーザーさんのスケジュールに入浴介助が入った日、背中に綺麗な模様があって……とか。別のユーザーさんのお宅では、やはり入浴介助が終わって部屋に入ると(オートロックマンションなのに!!)見知らぬ人が5、6人(一人は茶髪の女子高生)いて……(翌週行くとこの家族が同居しいて、女子高生のパンティーとか干してあってユーザーのおじさんと顔を見合わせてニヤリ)、とか。1人分のカレーを1食分だけつくってくれといわれたときには心の中で「レトルトじゃだめなのかーーーーぁ」と叫んだ……とか。
結局、採算が取れないからという理由で勤務していたステーションが廃止になったので辞めました。
その後はしばらく、WEB周辺のお仕事などをやらせて戴いて、これはこれで楽しかった。でも、そのプロジェクトが終わったとき、今度こそちゃんと仕事探そうと思った。
東京都福祉人材センターに登録して職探し、新聞折り込みの求人情報紙で職探し、何度か面接を受けたけど「ダメ」「ダメ」「ダメ」……で腐った。大学の就職の時だってここまで、真剣に活動しなかったので、腐敗しかけた。
で、“ダメモト”で出かけた「福祉関係合同就職説明会」でただひとつ面接を受けたのが、今度勤務することになったホームです。
自宅から自転車で10分ぐらい、歩いても行けるところ。
|日記4(最近の出来事 2004.Janu--)|
|日記3(夜勤痛と最悪のクリスマスイブ夜勤 2003.Oct--Dec)|
|日記2(初夜勤・退職者続出の謎 2003.July--Sept)|
copy-right reseved [Bunroku's Factory] 2003
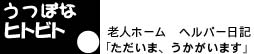
![]()