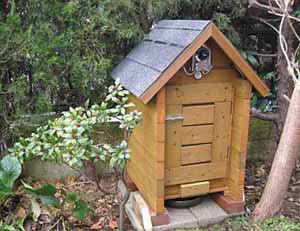簡単な燻製鍋
なべ底にチップを入れ、カセットコンロに載せて使う、熱燻専用器。
容量が小さくて火力が強いので、燻煙の付きがとても良いし、とにかく早い。
一気に温度が上がるので、外側が良く焼けて中身がジューシーな熱燻も作れる。
一握りのチップを入れて、中火で6〜10分、煙が止まるまで燻せば完了だ。
真冬のデータだが、1分で50℃、2分で100℃、5分で170℃まで上がる。

鍋の縁に、曲げたアルミ板をひっかけ、これに金網を載せている。
アルミ板の長さは2種類作ってあり、金網は2段にして使える。
鍋にフタをすると、アルミが挟まって、適度なスキマが出来る。
金網は25センチものが入手しやすいので、これが入るサイズの鍋を選べば便利だ。
簡易なのに高性能な燻製器だが、欠点は汁受け皿が置けないこと。
汁垂れを少なくしないと、垂れた汁が焦げて、その臭いがつく。