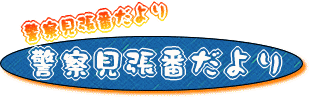去る10月10日、福島県郡山市民文化センターにおいて、日弁連第45回人権擁護大会が開催され、その3つの分科会の一つとして「だいじょうぶ?日本の警察-市民が求める改革とは-」シンポジウムが行われた。
日弁連(日本弁護士連合会)とは、日本で活動する弁護士が全員所属する団体であり、人権擁護大会とは、年に一度日弁連の人権擁護活動を集約・点検して当面する重要な人権課題を明らかにし、これまでの蓄積を生かしたより高度な人権擁護活動を目指すため、全会員の英知を結集することを目的として、持ち回りで開催される大会である。今回はたまたま警察問題が取り上げられたことで、警察見張番の今後の活動にも参考になると思い、役員7人が参加した。
シンポジウムの内容は以下のとおり。
第1部 「警察不祥事の実態とその要因をさぐる」
基調報告 「警察不祥事の実態と分析」
平 哲也(新潟県弁護士会)
基調報告 「神奈川県警の組織的隠蔽はなぜ起こったのか」
山田 泰(神奈川県警見張番、横浜弁護士会)
特別報告 「警察社会の実態と不祥事の原因」
黒木昭雄(元警視庁警察官、ジャーナリスト)
第2部 パネルディスカッション
「情報公開と不整経理ーはじまった警察情報公開」
パネリスト 庫山恒輔(仙台市民オンブズマン事務局長)
大内 顕(元警視庁職員、ジャーナリスト)
大沢理尋(新潟県弁護士会)
第3部 パネルディスカッション
「市民の生活の安全と警察の役割
-警察をどのように民主的にコントロールできるか」
パネリスト 渡名喜庸安(愛知学泉大学)
黒木昭雄(前出)
高井康行(第一東京弁護士会、元検察官)
新垣 勉(沖縄弁護士会)
特別報告「警察は市民を守っているのか
-桶川ストーカー殺人事件」狩野憲一(被害者の父)
特別報告「弁護士である公安委員として
-山口県公安委員の立場から」末永汎本(山口県弁護士会)
第1部の山田弁護士の基調報告は、いうまでもなくわれわれ警察見張番がこれまでのメインイベントとして取り組んできた、渡辺元県警本部長他による覚せい剤もみ消し事件の刑事確定記録閲覧・まとめ作業の結果がベースとなっている。われわれの活動が、日弁連の人権活動にも貢献することとなっていることは、大いに自負してよい。
第2部のパネルディスカッションでは、元警視庁で経理業務に関わっていた大内さんによる暴露話が非常に印象的であった。すなわち、「警察組織において経理業務に携わる者は、裏金作り(捜査費や旅費の名目で支給された金を、実際には別の用途に使うのに、捜査費用や交通費として使ったという体裁を装うため、領収書を偽造するなどの作業)を日常業務としてやらされており、作られた裏金は、幹部のヤミ給与として配分されるほか、広く末端の職員にも飲食代等として配分されている。最初は罪悪感を感じる職員も次第に慣れていき、自分も恩恵に預かっているため内部告発がしづらく、しようとしても徹底的な反撃が予想されるため怖くてできない(大坂高検の三井検事がいい例ではないか)」とのこと。大内さんは、講談社より『警視庁裏ガネ担当』という著書を出版されているので、興味のある方は、是非お求めあれ。
情報公開法および都道府県の情報公開条令が整備される中で、公開情報の時期制限や文書の保存期間などの点でまだまだ不備はあるものの、カラ出張が激減するなど将来に向けての一定の威嚇効果はあり、(警察が内部から変わることはほぼ期待できないことを考えれば)現時点では警察を改善するのに最も有用な方法であることが確認された。
第3部のパネルディスカッションは、
(1)検挙率が下がっている原因は何か
(2)なぜ、警察は告訴事件の処理に腰が重いのか
(3)公安警察部門の権限が拡大していることをどう考えるか
の3つの議題を柱として、各パネリストがそれぞれの立場や経験から意見を述べた。(2)の関係では、桶川ストーカー事件の被害者である女子大生のお父さんが、上尾暑の警察官からいかにやる気のない杜撰かつぞんざいな対応をされたか、被害者が殺害された後で、そのような対応をしていた事実を上尾暑が隠蔽しようとした有様などを、赤裸々に涙ながらに話された。
上記3点に重畳的に関わってくる問題点として、
・過度の成績主義や採用試験の難化により、本当に捜査実務に優れている人材が適性に配置されなくなっていること
・やはり成績主義・点数制がはびこっていることにより、警察官は解決困難と思われる事件の告訴を受理しないことで、検挙率の低下を防ごうとすること
・キャリアシステムによる士気低下
・警察は刑事警察活動よりも公安警察活動の方に重点を置く政治的傾向を持っており、したがって刑事畑の警察官は大変である半面出世につながらず、やる気が失せていること
・事件が解決しないと問題になるが、事件を受け付けないなどの怠慢があっても、それに対する制裁規定がないこと
・警察にはいまだに「組織の威信偏重主義」体質があること(黒木さんは、自分でも刑事裁判で偽証をしたことがあるし、警察官の証言の8~9割は偽証ではないかと述べられていた)
・警察を外部からチェックすべき公安委員会や警察署協議会が形骸的に運用され、チェックの機能を果たしていないこと、特に委員の選任が多く警察側の推薦などにより行われていること
などが指摘された。このシンポジウムで議論された内容がいまの警察問題の縮図なのであろうと思いながら興味深く聞き入っているうちに、あっという間に5時間が過ぎてしまった。
最後の点に関しては、実際に山口県の公安委員を務めている末永弁護士から「自分が委員になる前と比べて、少しずつではあるがよくなってきている。全国で175人いる公安委員のうち弁護士委員は現在わずか10人だが、これが50人になれば随分変わるではないか」と述べられていた。確かに、今回のシンポジウム開催に先立って、シンポジウム実行委員会が18の都道府県に対して行った警察情報の「いっせい公開請求」により開示された資料をつぶさに見ると、山口県の公安委員会議事録は他の県のものに比べ、墨塗の箇所も少ないし、議事録自体も、発言者の顕名を含め詳しく作成されている。今後われわれは積極的に情報公開請求・訴訟活動を行っていく予定であるが、それとは別に、神奈川県公安委員会の委員にも、弁護士委員が継続的に任用されるよう、神奈川県の弁護士会でも組織的に働きかけを行っていかねばならない、などと思いながら会場を後にした。
帰ってから、300数十頁にわたるシンポジウムの配付資料をぱらぱらとめくっていたところ、実は1989年に島根県松江市で行われた第32回人権大会においても警察問題が取り上げられ、上記とほぼ同様の問題点が議論されていたことが分かった。もちろん、この間に情報公開の面では格段の進歩があったのであるが、13年の時を経てほぼ同様の議論がなされていることを知って、警察問題の根深さ・改善の困難さを改めて思い知ったような気がした。
|
![]()