![]()
![]()
(99/11/16掲載)
■概要
モーツァルト、ベートーヴェンなどの協奏曲をフォルテピアノで演奏し、そのCDが高い評価を受けているピアニスト、作曲家ロバート・D・レヴィンは、1987年に国際バッハアカデミーより、1991年のレクイエム200年記念演奏会に向けての、新しい楽譜の改訂を依頼されます。その要請にこたえて完成されたのが、この「レヴィン版」なのです。彼は、ここでジュスマイヤー版の楽器法、楽典上の間違いや構成上の問題点を明らかにし、改訂を施しました。この版の刊行、初演にあたっては、バッハのカンタータなどの演奏で有名な、国際バッハアカデミーの主宰者ヘルムート・リリンクの助力が欠かせませんでした。
ちなみに、この版の初演は1991年8月24日、シュトゥットガルトの国際バッハアカデミーヨーロッパコンサートにおいて、リリンクの指揮によっておこなわれました。
■詳細
Lacrimosa
後半で、ほんの少し手直しがなされています。例えば14小節(譜例)など。また、19小節からの間奏が1小節少なくなり、間奏が終わったあとの3小節目のd-cという入りが、ソプラノ→テノール→アルトの順になります。そして、もちろんアーメン・フーガが続きます。
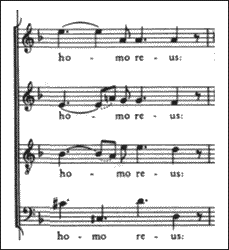 |
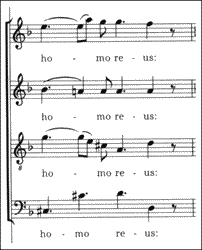 |
| ジュスマイヤー版 | レヴィン版 |
Sanctus
後半、"Plenisunt caeli et terra"という歌詞の部分が大幅に手直しされ、1小節増えています。オブリガートも全く別のものになっています。
続くOsannaは28小節から58小節に拡大されています。これはハ短調ミサ(K.417a)などにおけるモーツァルトの教会音楽での曲の長さのバランスを参考にしています。
Benedictus
やはり後半が手直しされています。続くOsannaは、従来の変ロ長調ではなく、Sanctusの後と同じニ長調に変わり、フーガの入りも短くなる別の形になっています。
Agnus Dei
構成は元のままですが、ハーモニーや声部が変わっています。
たとえば、17から24までのコード進行は
従来のF→C7→F/Dmin→G7→C →C#dim7/Dmin →D#dim7→E から、
F→C7→F→G#dim7→C6→Dmin6 →D#dim7→E
に変わっています。
| ジュスマイヤー版 | レヴィン版 |
Cum sanctis
テキストの割り振りが変わっています。
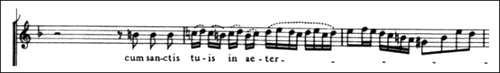 |
| 上段:ジュスマイヤー版 下段:レヴィン版 |