![]()
(99/8/3掲載)

ドヴォルジャークの批判校訂、つまり、自筆稿や客観的な資料と照らし合わせて作曲当初に出版された現行版の楽譜のまちがいを取り除き、作曲者の本来の意図を伝える原典版を出版するという作業は、1951年に、当時のチェコ国営の出版社であったスプラフォンで始められました。交響曲第9番「新世界から」の原典版も、1955年に出版されています。さらに、そのリプリント版が1988年にジェスク音楽文化振興会から発行されました。
今回、指揮者の岩村さんの意向で私たちが用いることになった「プラハ版」というのは、まさにこの原典版のことなのです。出版元のスプラフォンは、1989年に国の体制の変化にともない、私企業として再スタートを切りますが、1998年には社名を"EDITIO PRAGA"と変更して、引き続きドヴォルジャークを始めとして、スメタナ、ヤナーチェク、マルティヌーなどの自国の作曲家の原典版の校訂、出版を行っています。
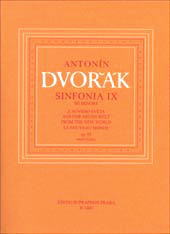 |
| プラハ版の表紙 |
現行版とプラハ版との違いは、曲が始まって20秒もすれば明らかになります。第1楽章の4小節目に出てくるホルンのタイミングが、まるまる1拍違っているのです。
譜例1 現行版
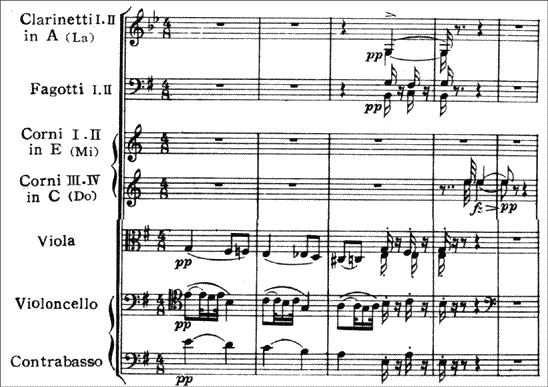 |
ホルンの入りは3拍目のアウフタクト、三十二分音符。
譜例2 プラハ版
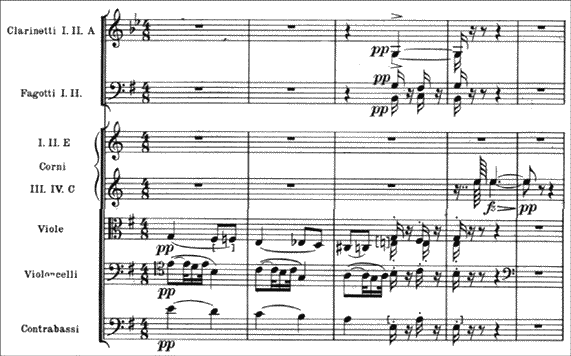 |
ホルンの入りは2拍目のアウフタクト、六十四分音符。
さらにもう1点、分かりやすいところは、フルートソロで出てきてヴァイオリンに受け継がれる第2主題の後半のリズムです。
余談ですが、このテーマは黒人霊歌の"Swing Low, Sweet Chariot"そのままです。それについてはこちらを。
譜例3 第2主題後半のリズムの違い
| 八分+八分 | 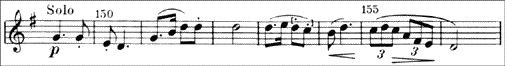 |
|
| 付点八分+十六分 | 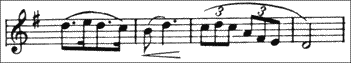 |
表1 現行版
|
表2 プラハ版
|
ただ、この点については、現行版があまりに不自然な形ですので、使っている版には関係なく、指揮者の裁量で変更されることは多いようですね。(私も実際に吹いてみて、現行版には不自然さを感じます。)
以上2点のチェックポイントをもとに、手元にある最近のライブビデオをかたっぱしから調べてみました。その結果が、つぎの表です。
表3
|
実を言えば、まだまだ現行版の方がはばをきかせていると思っていましたので、この結果は、私にとってはかなり意外なものでした。知らないうちに、時代はとっくに「プラハ版」になってしまっていたのですよ。そのことに目覚めるきっかけを与えてくれた岩村さんには、ぜひとも感謝をしなければいけません。
ところで、プラハ版があたりまえになり始めていた92年11月の時点で、版については何の言及もなかった國分誠って、いったい……。
ちなみに、世界最高のフルーティスト、ジェームズ・ゴールウェイは、ロンドン交響楽団時代にはケルテスとオーマンディと、そしてベルリン・フィル時代にはクーベリックと、合計3種類の「新世界」を録音しています。あいにく、手元にオーマンディ盤(66年12月録音/SONY)はないのですが、ケルテス盤では現行版、クーベリック盤ではプラハ版を吹いています。
 |
イシュトバン・ケルテス指揮 ロンドン交響楽団 DECCA:417 724-2 (rec.66/12) |
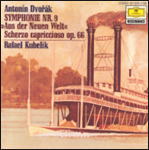 |
ラファエル・クーベリック指揮 ベルリン・フィル DG:427 202-2 (rec.72/6) |
その他の録音について、掲示板で調査をお願いしたところ、次のような回答がありました。
|